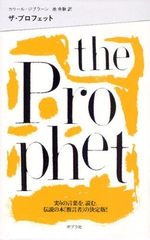副題に「詭弁・逃げ・だましの倫理なき菅政治は日本を滅ぼす」とある。斬れている。
鳩山・菅両氏が小沢幹事長を非礼きわまりない斬り方をした「人情紙よりも薄い民主党人間関係」から始まる。どこにも人間哲学がある。
「巧言令色鮮し仁」「君子は本を務む。本立ちて道生ず。(本とは基本)」「利して利する勿れ(国民の利益のためにのみ働き、自分の利益をはかるな)」「選挙至上主義と自分さえよければ主義の執行部」――。
そして、後半は労働組合についてだ。「労働組合は政治権力の番犬になってはならない。あくまで独立自尊を貫くべし」とし、「君子の交わりは淡きこと水の若し。小人の交わりは甘きこと醴(れい)の若し。君子は淡くして以て親しみ、小人は甘くして以て絶つ」を示す。
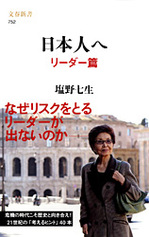 「文藝春秋」に毎月、連載されたものをまとめたもの。歴史・哲学を踏まえ、しかも現場を見ての確立された視点からの塩野さんの発言は、カミソリというよりオノで真正面から叩ききる強さがある。
「文藝春秋」に毎月、連載されたものをまとめたもの。歴史・哲学を踏まえ、しかも現場を見ての確立された視点からの塩野さんの発言は、カミソリというよりオノで真正面から叩ききる強さがある。
イラク戦争から本書は始まるが
「人間ならば誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。多くの人は、見たいと思う現実しか見ていない」(ユリウス・カエサル)
「危機打開に妙薬はない。ということは人は代えたとしても目ざましい効果は期待できないということである。やらねばならないことはわかっているのだから、当事者が誰になろうと、それをやりつづけるしかないのだ」(「継続は力なり」の項)
「ドイツの敗戦処理を見習えと言ってくるがあれも見習わない方がよい。・・・・・・戦前戦中の悪のすべてをヒットラーとナチにのみ転嫁したこのドイツのやり方は、ドイツ人自身の自己批判能力を衰えさせてしまった」(「負けたくなければ」の項)
――各篇に全てといっていい。考えさせられることが詰まっている。
 リーマン・ショック前後の時期に専門家が分析している格差問題をまとめた本書。短い論考だけに角度がそれぞれあって、論点が整理されている。
リーマン・ショック前後の時期に専門家が分析している格差問題をまとめた本書。短い論考だけに角度がそれぞれあって、論点が整理されている。
所得格差、教育格差、地域間格差、若者世代内・老齢世代内の格差。そして、グローバリゼーションが世界の貧困を緩和するにしても、世界の国家間格差を是正するか否か、それも分析している。しかし、いずれにしても、先進国・途上国とも所得格差は拡大する(技術革新が単純労働の雇用機会を奪っているし、世界規模のアウトソーシングで先進国の賃金格差が拡大している)。
格差問題と貧困問題は別。ワーキングプアは、未熟練労働への需要減少(グローバリゼーションとIT)にもかなり起因する。
1990年代前半、地域格差は縮まった。バブルのはじけた都会と引き続き伸びた地方。そこの公共事業との関係。その後、高齢化の進展、企業規模間の賃金格差拡大、非正規社員の比率増加などが顕在化する。
若者への教育・訓練投資の重要性。「ゆとり」教育の失敗も「ゆるみ」「たるみ」になったというよりも、それを可能にするカネと人の資源不足、教育のインフラ(それを支える人とカネ)が崩壊しているという構造を見ない甘美な教育論。それがまかり通ってしまった。
このように、本書では専門家が次から次へと問題を提起している。
- 1