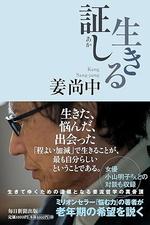 姜尚中さんのエッセー集「生きるコツ」「生きる意味」に続く「生きる」シリーズ第3弾。人生における折々の人や場所、風物との「出会い」を味わいながら生きる。優しさと深さが穏やかに伝わってくる。喧騒の中を周りを見ることもなく突っ走ってきた者として、本書のおかげで道端に咲くツツジに感動し、思わず写真に収めた。
姜尚中さんのエッセー集「生きるコツ」「生きる意味」に続く「生きる」シリーズ第3弾。人生における折々の人や場所、風物との「出会い」を味わいながら生きる。優しさと深さが穏やかに伝わってくる。喧騒の中を周りを見ることもなく突っ走ってきた者として、本書のおかげで道端に咲くツツジに感動し、思わず写真に収めた。
スタンダールの「生きた、書いた、愛した」を思えば、姜尚中さんは「生きた、悩んだ、出会った」が、人生を要約する言葉だと言う。「出会い」は歓びであり、「『出会い』の多くは、人生の折々に予期せず訪れては『生きる』力を分け与えてくれたように思える」と言う。良き師匠に出会ことができ、良き友に出会えることほど幸せなことはない。良き仕事もそこから得られる。「生きる証し」である。
「『薫陶』という言葉(私を政治思想史研究に導いてくれた藤原保信先生)」「『先生』としての伊集院静氏」「街中の高原」「現代のシャーマン(ノーベル文学賞ハン・ガン、歴史の痛みとそのトラウマに寄り添い続ける語り)」「犬・猫との共生(蒲島熊本県知事の強い意向の『アニマルフレンズ熊本』)」「写真嫌い(泥に埋もれた写真、立谷相馬市長の『籠城宣言』)」「飲み込む力(ハシカベ体操)」「世界の不幸と小さな幸せ(ジョナサン・グレイザー監督の映画『関心領域』)」・・・・・・。静かに心に染み込んでくる。
「テレビよ、さらば(テレビは『生もの』を扱うメディアだが、ネットの定かでない情報や、過激な論調に押され、その場限りの『生もの』に飛びつく傾向がますます強くなってるように思える。古希を節目に『活字の世界』に専念したい)」「スマホを捨てよ、田園に出よう(寺山修司に倣って)」「息苦しさの正体(夏目漱石の『草枕』、息の詰まるような時代の到来を漱石は100年も前に見抜いていた)」「生と死の近さと遠さ」「檸檬(梶井基次郎の「えたいの知れない不吉な塊が、私の心を始終押さえつけていた」)」・・・・・・。
「『程良い加減』で生きることが最も自分らしいということである」――「朝生!」で知り合った大島渚さんの妻で女優の小山明子さんとの対談が収録されている。
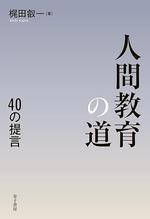 「人間教育」に全てを注ぎ「教育の本道」を示し続けてきた梶田叡一先生の教育哲学、人間哲学の書。教育に携わる教師、教育行政関係者はもちろんのこと、すべての人に必読の書。
「人間教育」に全てを注ぎ「教育の本道」を示し続けてきた梶田叡一先生の教育哲学、人間哲学の書。教育に携わる教師、教育行政関係者はもちろんのこと、すべての人に必読の書。
「教育の最終的な目標は、一人の人間として自立し、世の中を生きる力と、自らの人生を生きる力を身に付けることです。そしてその成果は、主体的に、深く豊かに生きることができるかどうかで確認されることになる。まさに人間教育こそが、教育の歩むべき本道と言ってよい」と言う。「教育の深さが日本の未来を決定する」と私は教育基本法改正案の衆議院本会議で発言したが、喧騒の時代、SNS時代、言葉も軽く攻撃性に満ちた時代であればこそ、「人間教育」「教育の本道」が重要だと思う。
「我の世界と我々の世界」「我の世界を生きる力を」「生きる力の土台となる健全な自信とプライド」「我々の世界(社会)を生きる力も大切だが、我の世界を生きる力こそ」・・・・・・。
「子供たちの目がキラキラ、みんなイキイキ、ではどうにもならない(そうした外的現れのレベルでなく、内的世界へのこだわりを(実感・納得・本音に基づいたものを)」「素直さを越えて知的な『渇き』を」「没頭体験、良い本との出会いを。達成感・効力感を持たせたい」・・・・・・。
「基盤となる言葉の力を」「聴く力、書き表す力を」「直感と共感を超えた言語論理教育への注目と理解を(P I SAショック直後の文科省の言語力育成協力者会議の座長が梶田先生)」「概念・根拠・論理へのこだわりを(最近の「やばっ!」「可愛い!」などの単純表現の多用は嘆かわしい)」・・・・・・。特に学習指導において、「開示悟入」を提唱する。仏法でいう開示悟入の四仏知見だがよくわかる。
「真の道徳教育を実現していきたい」「生命の重さの実感を」「学校でも宗教的な伝統や文化の教育を」「日本の伝統・文化を学ぶ」――。教育基本法で正確にうたってている通りである。また「空と他力を学ぶ」「無常だからこそ」を取り上げ、「はかない世界ではあるが、それを前提に私はグィッと前進していくぞ」の姿勢を訴えている。
豊かさ故の精神的弛緩と慎みのなさを指摘、「品格ある日本人の育成を」と提唱する。「人間力」が重要だが、OECDの「コンピテンシー(脂質・能力)」について、「『我々の世界を生きる力』だけでなく、『我の世界を生きる力』に関わる点が、『人生設計や個人的計画を作り実行できる力』という形で注目されていることは評価できる。しかし、ここにも『総合的な人間力』の基盤となるべき『人間としての育ち』を実現する上で大事な点の見落としが残っている」と重要な指摘をしている。そして「人間としての育ち(人間力)」として本質的に重要なものとして、「強靭な主体性の確立」「深い共感協働性」「本源的自己への立脚」の3つが不可欠であると結論している。まさに「人間教育」は「人間哲学」であり、今こそ「人間教育」だとつくづく思う。
7月3日に公示を迎える参院選(7月20日投票)――。暑い日差しとなった6月28日(土)、公明党の川村ゆうだい党青年局次長(参院選予定候補=東京選挙区)が街頭演説。赤羽駅東口、池袋駅西口に私も参加、多くの方に参加いただきました。
川村ゆうだい氏は、外科医、医学博士、党青年局次長、ちょうど今日(29日)が誕生日の41歳。「心に青空が広がっているような好青年」と会う人がみんな好感を持つ情熱溢れる若き力。山口那津男元代表(参議院議員)の後継者として、東京選挙へ初挑戦。
「山から川へ、川から雄大な海へ」「政治にメス」「いのちを守る力、無限大」「若き世代の希望を形に」――。川村ゆうだい氏の医療改革への叫びは心揺さぶられるものでした。私も、コロナ禍の医療現場で戦い抜いた実績と爽快な人柄を紹介。直面する人口減少・少子高齢社会では、「新しい医食住」への改革・挑戦が重要。介護・医療とその担い手はますます大切になると強調、川村ゆうだい氏に力を与えてほしいと訴えました。
「山から川へ、川から雄大な海へ」――川村ゆうだい氏への期待は大です。
 「なぜそうなるのか」を意識して、YouTubeに数学動画を連日投稿して人気の著者。「私が数学動画を投稿するようになったのは、40歳を過ぎてからオイラーの公式が理解できたのが嬉しくて・・・・・・」と語る。私も「因数分解すると」「微分すれば」「積分量で言えば」など日常的に使用するが、本書は、「なるほど、そういうことだったのか」とのめり込むほど面白い。
「なぜそうなるのか」を意識して、YouTubeに数学動画を連日投稿して人気の著者。「私が数学動画を投稿するようになったのは、40歳を過ぎてからオイラーの公式が理解できたのが嬉しくて・・・・・・」と語る。私も「因数分解すると」「微分すれば」「積分量で言えば」など日常的に使用するが、本書は、「なるほど、そういうことだったのか」とのめり込むほど面白い。
「なぜ三角形の面積は、(底辺) × (高さ) ÷ 2で求められるのか?」「なぜ錐の体積は3分の1をかけるのか?」から始まる。「細かく分ける」という考え方だ。「なぜ球の面積は(4/3)πr³なのか」「なぜ円の面積はπr²なのか?」・・・・・・。微分も積分も薄く切って並べる、積み重ねる考え方が示される。
「なぜ分数の割り算はひっくり返してかけるのか」・・・・・・。「0乗するとなぜ1になるのか? 」は「a³ = a×a×a a² = a×a a¹ = a そこでa⁰ = a÷a = 1」となるわけだ。それでは「0!はなぜ1なのか」・・・・・・。
「マイナス×マイナスはなぜプラスになるのか?」――「複素数の掛け算は、それぞれの複素数の絶対値をかけた値。それぞれの偏角は足しているということになる」・・・・・・。
「なぜ二進法が使われるのか?」・・・・・・。そもそも十進法が使われているのは、人間の指が10本だからという生物学的なもので、数学的な合理性はないと言う。つまり「十進法というのは言わばローカル言語のようなもの。コンピュータの世界のニ進法は数学的に最も合理的だから」と言い、ニ進法が合理的な理由を説明している(ONかOFFだけでいいので便利)(桁数が多いのが不便となるが、コンピュータはいくら多くても問題ない)。
「ふしぎな数[e](ネイピア数)」――。不思議な数「72の法則」は本当に便利な近似値。72を年利で割れば2倍になるまでの年数。年数で割れば2倍になるのが必要な年利がパッと出てくる。年利5%なら、72 ÷ 5 = 14.4年で2倍。GDPが年3%増なら72 ÷ 3 = 24年で2倍になるわけだ。
「直感に反する確率」――。「平均を平均してはいけない」。2地点を往復するのに行きは時速4キロ、帰りは時速6キロなら平均は「時速5キロ」ではない。速さは、距離/時間で、分母が違う。「直感は裏切られる」のだ。「ギャンブラーの誤謬」もそうで、パチンコでも「そろそろ当たるだろう」とはならない。常に初期状況からスタートだ。
「素数の神秘」――。素数とは「1と自分自身でしか割り切ることができない2以上の自然数(1を含めないのは素因数分解の一意性を担保するため)」。素数は無限にあることは証明されているが、現時点で人類が知っている素数は有限。「連続する3つの奇数が全て素数となるのは3、5、7だけであることを証明せよ(早稲田大学入試)」「9991を素因数分解せよ(慶應義塾女子高校入試問題)」など面白いし、よく入試に出るようだ。ちなみに動画再生回数では「伝説の東大入試問題 π>3.05を証明せよ」の240万回が1位だと言う。
見ているのは女性より圧倒的に男性、年齢で言うと若者より高齢者、65歳以上が51.8%だと言う。なぜだろう? 「公式を使い、この解き方をすれば答えが出るという『やり方』だけを説明する動画は高校生に喜ばれる」のもわかるが・・・・・・。「テクニック」では必ず行き詰まるし、何よりも面白くないはずだが・・・・・・。
 「紀伊国は、見渡す限りどこもかしこも美しい」――紀州藩士の息子・十兵衛(後の本草学者・畔田翠山)は、幼いころから草花と話していると癒され楽しい。草花とは、自在に話すことができるのに、人と接するのは苦手。学問、文化・工芸、草木にも力を注いだ賢侯の藩主・徳川治宝、藩の本草局に籍を置く藩医・小原桃洞の愛情と信頼の下で、十兵衛は塾にも御薬園にも通い成長していく。
「紀伊国は、見渡す限りどこもかしこも美しい」――紀州藩士の息子・十兵衛(後の本草学者・畔田翠山)は、幼いころから草花と話していると癒され楽しい。草花とは、自在に話すことができるのに、人と接するのは苦手。学問、文化・工芸、草木にも力を注いだ賢侯の藩主・徳川治宝、藩の本草局に籍を置く藩医・小原桃洞の愛情と信頼の下で、十兵衛は塾にも御薬園にも通い成長していく。
紀伊国は草木が茂り花が咲く「美っつい国」だ。「天狗」「卯木」「蜜柑」「雪の舌」「伊佐木」「藤袴」「仙蓼」「譲葉」「山桃」「白山人参」「黒百合」・・・・・・。15の章立てで、人や草木との出会いを温かく、穏やかに、みずみずしく描く。草木に触れ合うなか、突然、天狗に出会い、また亡くなった父が現れたり、村の娘や姫君の怨霊と出会う。自然の中からの声だ。
「海と向き合うのは、相応に力がいる。・・・・・・その点、山はいつでも力を与えてくれる。草木の香りに満たされて、体の隅々まで癒されるようなのだ」「天狗は軽妙な笑い声を立てた。『草木相手の務めをしておるのに、お前はずっと頭で考えとる。・・・・・・己の物差しで勝手に種族を分けようとしている。・・・・・・お前は種別することで腑に落ちるかもしれんが、それは人に限ってのことぞ」「獣と人。樹木と蔓植物。山のものと海のもの。紀州の者と他国の者。男と女。その線引きにどんな意味があるのか」「十兵衛は夜とも朝ともいえぬ、そのあわいをたゆたいながら、『分け隔て』という行いに思いを致す」・・・・・・。
「根と根が地中で触れ合っている草木は、意思をかわすことができるのだと、翠山もかつて、桃洞から聞かされている。空模様や、虫がついて難儀だということ、霜害や冷害、酷暑を乗り越える術についても、木々も草も絶えず話をしているのだという。『吉野人参はとりわけ繊細でございますから、己の好まぬところではうまく育たぬかと』 翠山は、手の上の吉野人参をしばし見つめた。己にとって、居心地の悪い場所に居続けねばならぬ辛さは、翠山もよく知っている」「この紀伊国がいかに美っつい地ぃか、広う知らせたいのぅ。それに、他国で生きておる本草にも触れてみたいのぅ」・・・・・・。
若き本草学者の成長物語だが、自然と人間、自然の中の人間の原点を呼び起こす秀逸の作品。





