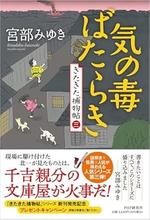 富勘長屋に住む北一、相棒の長命湯の釜焚き・喜多次のコンビが事件を解決するシリーズ第3弾。人情が通い、助け合う長屋や湯屋、文庫屋、文庫作業場、棒手振、そして岡っ引きの親分、おかみさん・・・・・・。江戸の町が浮かび出てくる宮部みゆきの世界が心地良い。
富勘長屋に住む北一、相棒の長命湯の釜焚き・喜多次のコンビが事件を解決するシリーズ第3弾。人情が通い、助け合う長屋や湯屋、文庫屋、文庫作業場、棒手振、そして岡っ引きの親分、おかみさん・・・・・・。江戸の町が浮かび出てくる宮部みゆきの世界が心地良い。
第1話「気の毒ばたらき」――。年明け、おかっ引きの千吉親分が、河豚に中毒って頓死してしまう。岡っ引きの跡目はおらず、北一はその真似事をしている。そんな時、万作・おたまが継いだ千吉親分の文庫屋から火が出て焼失。下手人は、台所女中のお染だというが、北一は信じられない。疑いを晴らそうと北一は奔走する。
一方、火事で焼け出された人々が集まる仮住まいでも、"切り餅" 4つ(百両)がなくなるという事件が起きる。
目は見えないが、おかみさんはすごい。世の中、人の心の動きが見えている。「お染はどこにいるんだろうね。なぜ放火なんかしたんだろう。それ以前に、なぜお店の金に手をつけようとして、見咎められるような羽目になったんだろうか」「女が善悪を忘れて、何かをしでかすのは、自分のためじゃない。想う男か、子どもの命がかかっているときさ」・・・・・・。
北一、喜多次は動く。「気の毒ばたらき。気の毒だねえ、大変だったねぇと同情しながら、火事で焼け出された人たちの間に立ち交じり、その人たちが命からがら持ち出してきた家財道具のなかの金品を漁って盗み出す。卑怯な手口だ」・・・・・・。
第二話「化け物屋敷」――。前の話の続き。江戸の正月の風景や日常が浮かんでくる。深川佐賀町の村田屋という貸本屋。28年前、その店主・治兵衛さんのおかみさん(おとよ)が、行方知れずになり、半月も経ってから、千駄ヶ谷の森の薮の中で亡き骸になって見つかる事件があった。下手人が捕まるどころか、なぜそうなったかの事情もわからないままになっていた。北一は、町奉行所の文書係・おでこ(三太郎)の力を借り、同じような事件があったのではないかと調べ始める。そして「化け物屋敷」の<大旦那様>の存在とお社、後始末に働く八助の気狂いに行き着いていく。
江戸の街の人情、生活、風習、災害と恐怖が、キャラが立つ人物を通じて、生き生きと立体的に情緒深く描かれる。
 「データで読み解く所得・家族形成・格差」が副題。1990年代半ばから2000年代初頭にかけ、バブル崩壊後の不況の中で未曾有の就職難にぶつかった世代。この1993~2004年に高校や大学などを卒業した世代が就職氷河期世代。1970年(昭和45年)生まれから1986年生まれ(2005年に高校卒業)が該当する。約2000万人。現在30代の終わりから50代前半となる。著者は93~98年卒を「氷河期前期世代」、99~0 4年卒を「氷河期後期世代」とする。団塊ジュニア世代は1970年代前半生まれを指し、氷河期前期世代と重なる。人口のボリュームの多いこの世代の人生のスタートが、バブル崩壊後の不況に直面したことは、日本にとって極めて痛いことだ。本書は、この世代を数々の統計から精緻に分析し、今後の動向と行うべきセーフティーネットの拡充などを提言する。しっかりした学術論文。
「データで読み解く所得・家族形成・格差」が副題。1990年代半ばから2000年代初頭にかけ、バブル崩壊後の不況の中で未曾有の就職難にぶつかった世代。この1993~2004年に高校や大学などを卒業した世代が就職氷河期世代。1970年(昭和45年)生まれから1986年生まれ(2005年に高校卒業)が該当する。約2000万人。現在30代の終わりから50代前半となる。著者は93~98年卒を「氷河期前期世代」、99~0 4年卒を「氷河期後期世代」とする。団塊ジュニア世代は1970年代前半生まれを指し、氷河期前期世代と重なる。人口のボリュームの多いこの世代の人生のスタートが、バブル崩壊後の不況に直面したことは、日本にとって極めて痛いことだ。本書は、この世代を数々の統計から精緻に分析し、今後の動向と行うべきセーフティーネットの拡充などを提言する。しっかりした学術論文。
この世代は「上の世代に比べて給与の低さと不安定就業の多さ」が目立つ。長期にわたる無業者が多く、求職活動をしないニートも多い。低い収入・不安定就業が続くと、年金も低く、老後不安、生活保護の高齢者が大量に出てくることが懸念される。すぐ上の「バブル世代」とは年収など大きく異なる。
しかし、極めて大事なことだが、その後の「ポスト氷河期世代も、年収などを見ると、氷河期後期世代とあまり変わらず、氷河期前期世代よりも低い水準にとどまっている」とデータ分析する。続く世代も雇用が不安定で、年収が低く、格差が解消しないというわけだ。そして、「就職氷河期世代を境に、就職した年の景気の長期的な影響(瑕疵効果)が弱まった」とデータ分析している。労働市場の流動性が高まったからなのか、デフレの長期化なのか、注目すべき分析だ。
「氷河期世代の家族形成」――。「就職氷河期世代は、家族形成期に入っても経済的に安定せず子供を持てない」と見られがちだが、違うと言う。「氷河期後期世代は実は団塊ジュニアの世代よりも、40歳までに産む子供の数は多かった」と指摘している。出生率はより幅広い要因によるようだ。
「新卒時点では、女性の方が、男性よりも就職氷河期の影響が強かったが、就業率や正規雇用率の世代差は数年で解消した」「晩婚化や既婚女性の就業継続率上昇が就職氷河期の影響を打ち消していた面が大きい」と言う。
また「就職氷河期世代以降、所得分布の下位層の所得がさらに下がることによって、世代内の所得格差が拡大する傾向にある」「ニートや、親と同居する無業者・非正規雇用者、孤立無業者など、特に厳しい状況に置かれている人の割合は、若い世代ほど増えており、年齢が上がっても減っていない」と言う。
「セーフティネット拡充と雇用政策の必要性」――。将来、雇用が不安定で、年収が低いままの就職氷河期世代、それと同様のその後の若い世代も、「親世代の高齢化による生活の困窮」「低年金・低貯蓄からくる老後の困窮」は重大問題であり、雇用政策・就労支援で若年のうちに挽回をするべく、様々な取り組みがさら必要であることを提唱する。手をこまねいていると大変な時代が迫って来ている。
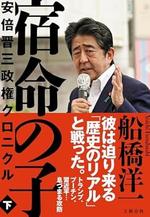 読みながら思うことが溢れた。しかし改めて安倍晋三総理が、いかに戦略的に戦い続けたか。多くの仕事をしたか。安倍政権に関わった人が、激変する世界と社会の中で結束して戦い仕事をしたか。そして各テーマを設定し、船橋さんが徹底取材し、それを立体的に組み上げて、熱が伝わるドキュメントに仕上げた力量に感心する。「彼は迫り来る『歴史のリアル』と戦った」と言う。
読みながら思うことが溢れた。しかし改めて安倍晋三総理が、いかに戦略的に戦い続けたか。多くの仕事をしたか。安倍政権に関わった人が、激変する世界と社会の中で結束して戦い仕事をしたか。そして各テーマを設定し、船橋さんが徹底取材し、それを立体的に組み上げて、熱が伝わるドキュメントに仕上げた力量に感心する。「彼は迫り来る『歴史のリアル』と戦った」と言う。
「母の洋子は、安倍を『宿命の子』と呼んだ。安倍自らも、心の底に、そのような使命感と歴史観を秘めていた。・・・・・・『その先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を負わせてはなりません』戦後70年首相談話に込めたあの一言は、安倍の心の叫びでもあった」とあるが、「宿命を、日本を背負う使命に転換して戦おうとした」のだと思う。
<下>は「外交」が生々しく描かれる。「プーチン」「習近平」「トランプ」「金正恩」「アメリカ・ファースト(トランプなど)」「自由で開かれたインド太平洋(モディ、ターンブルなど)」「G7 vs.ユーラシア(メルケル、マクロン、キャメロン、オバマ、トランプ・・・・・・)」の各章は、いずれも息づまる攻防。冷静な国際会議や外交交渉というよりまるで格闘技のような攻防だ。その中で安倍晋三総理が躍動する。日本の総理でかつてない存在感を勝ち取ったのだ。あの有名なトランプにメルケルが迫り安倍晋三総理がその真ん中で腕組みをする写真。その真実の意味も・・・・・・。
その後に「天皇退位と改元」「パンデミックと退陣」などが描かれている。「戦略性」と「リアリズム」で新たな日本の未来を切り開こうとした安倍晋三政権のエネルギッシュな姿が掘り起こされている。とてつもない船橋さんの力の著作。
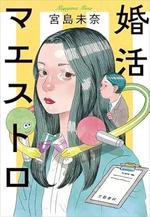 「成瀬は天下を取りに行く」は大津市だが、今回は浜松市。学生時代からずっと同じマンションに住み、Webライターとして生計を立てている40歳、独身の猪名川健人。婚活事業を営む「ドリーム・ハピネス・プランニング」の紹介記事を引き受ける。雑居ビルに小さな事務所を置く零細婚活会社だ。手作り感溢れる地味なパーティーに取材に出かけると、そこに現れたのは、張りのある声で見事にパーティーを仕切る美しい司会者・鏡原奈緒子。彼女は、脅威のカップル成立率を誇る伝説の司会者(婚活マエストロ)と言われていた。
「成瀬は天下を取りに行く」は大津市だが、今回は浜松市。学生時代からずっと同じマンションに住み、Webライターとして生計を立てている40歳、独身の猪名川健人。婚活事業を営む「ドリーム・ハピネス・プランニング」の紹介記事を引き受ける。雑居ビルに小さな事務所を置く零細婚活会社だ。手作り感溢れる地味なパーティーに取材に出かけると、そこに現れたのは、張りのある声で見事にパーティーを仕切る美しい司会者・鏡原奈緒子。彼女は、脅威のカップル成立率を誇る伝説の司会者(婚活マエストロ)と言われていた。
いつの間にか巻き込まれ、ドリーム・ハピネス・プランニングを手伝うようになってしまい、婚活パーティー、シニア向け婚活パーティー、婚活バスツアー、そして市が主催する大きな婚活パーティーにも参加することになる。そこで出会いや結婚を求める高齢者も含めた多くの人がいることを改めて知る。そこでの会話はマンションに閉じこもってばかりいた猪名川にとって、新鮮であり、新たな生活への窓が開くことになる。そして、伝説の婚活マエストロ・鏡原奈緒子に惹かれていく。
現在の婚活事情、出会いを作る婚活事業の現場が、伝説の婚活マエストロを通じて、生き生きと紹介される。そして40歳独身男の心が動き始める。
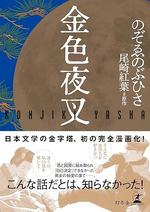 尾崎紅葉「金色夜叉」の初の完全漫画化!「金色夜叉」が書かれたのは、日清戦争後の明治30年1月1日から明治35年5月1日まで讀賣新聞連載。1900年前後の欧米化の波が押し寄せている時代だ。37歳で亡くなった尾崎紅葉の30代前半の作品。映画、ドラマ、舞台と数限りなく演じられた作品だが、漫画化は初めてと言う。新潮文庫では「前編」「中編」「後編」「続金色夜叉」「続読金色夜叉」「新続金色夜叉」と700ページにも及んでいる長編。
尾崎紅葉「金色夜叉」の初の完全漫画化!「金色夜叉」が書かれたのは、日清戦争後の明治30年1月1日から明治35年5月1日まで讀賣新聞連載。1900年前後の欧米化の波が押し寄せている時代だ。37歳で亡くなった尾崎紅葉の30代前半の作品。映画、ドラマ、舞台と数限りなく演じられた作品だが、漫画化は初めてと言う。新潮文庫では「前編」「中編」「後編」「続金色夜叉」「続読金色夜叉」「新続金色夜叉」と700ページにも及んでいる長編。
一高の学生・間貫一は、孤児であったが、鴫沢家で育てられ、娘の宮と将来を誓い合う。しかしお金持ちの息子、富山に宮を奪われ、ふられた憤怒と悲嘆から、学士どころか社会の嫌われ者「高利貸し」となって、拝金主義の社会と自分を捨てた宮への復讐を誓う。当時の家制度の重さで、宮は貫一を心から愛しながらも違う行動を取る。家制度、悪辣な高利貸し、妾を何人も持つ金持ちの男たち・・・・・・。当時の社会に押し潰された貫一と宮。そこに貫一を求める美人アイス(高利貸し=氷菓子)の赤樫満枝、友人の荒尾などが絡む。
貫一は、人間であることをやめ、あえて人でなしの人生を選ぶ。宮は富山と結婚したが魂をなくしたように生き身体を壊す。そして、2人は偶然再会するのだが、貫一は許さない。
数年後、高利貸しを止めて弁護士となった貫一は、栃木県、塩原旅館で若い訳あり男女に会い、心中から救う。ここからの結末を、のぞゑのぶひささんが付け加えている。

