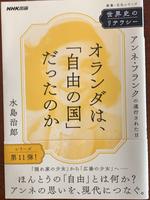 「アンネ・フランクの連行された日」が副題。「アンネの日記」は、1942年6月12日から1944年8月1日まで、ドイツ占領下のオランダの首都アムステルダムの隠れ家時代の記録が綴られている。その3日後の1944年8月4日、隠れ家に潜伏していた15歳の少女アンネ・フランクたち8名のユダヤ人が、ナチ親衛隊率いるドイツ当局に連行された。1930年代初め、ユダヤ人たちが相次いで目指した「自由の国」オランダに、まさに「自由」を求めて、ドイツから移り住んでいたのだったが・・・・・・。
「アンネ・フランクの連行された日」が副題。「アンネの日記」は、1942年6月12日から1944年8月1日まで、ドイツ占領下のオランダの首都アムステルダムの隠れ家時代の記録が綴られている。その3日後の1944年8月4日、隠れ家に潜伏していた15歳の少女アンネ・フランクたち8名のユダヤ人が、ナチ親衛隊率いるドイツ当局に連行された。1930年代初め、ユダヤ人たちが相次いで目指した「自由の国」オランダに、まさに「自由」を求めて、ドイツから移り住んでいたのだったが・・・・・・。
「アンネ・フランク一家は、なぜオランダで捕まったのか(事件の全容)」――。「広場の青春(アンネは一人じゃなかった) (広場の3人娘、アンネ、ハンネ、サンネ)」・・・・・・。オランダでは歴史的にユダヤ人が住民として受け入れられ、自主的に難民支援を開始していたが、1940年5月、ドイツ軍がオランダに侵攻、ユダヤ人の生活は一気に暗転した。
「ドイツ占領下のオランダで、ユダヤ人はいかに追い詰められたのか (事件の背景と結末)」――。華やかなオランダ劇場は接収され、収容所への移送拠点になってしまった。その向かい側に保育園があった。これがレジスタンスの有数の拠点となり、「闘う保育園」として子供たちを脱出(滞在した子供の1割の600人)させた。アンネは、ベルゲン・ベルゼン強制収容所の劣悪な待遇に苦しめられ弱っていったが、親友ハンネとのうれしい再会もあった。
「アンネつながった"ほんとうの"友だち(同時代へのインパクト)」――。オランダにアンネと同年の少女オードリー・ヘプバーンがおり、「魂の姉妹としての交歓」は衝撃的だ。1945年5月、父親のオットーが帰還、「アンネの日記」が刊行される。著者はここで「隠れ家での日記」を深掘りする。小川洋子とアンネの「閉じられた空間」「静かな孤独な空間のように見えて、この閉鎖空間の中にある人々は実に自由に、自分独自の方法で、語り、文章を綴り、他者と関わり、痕跡を残す。不自由に見える閉鎖空間が自由で創造的な空間に転化する」ことを語っている。「小川洋子さんの中に、どこかの時点で閉鎖空間を出て外の世界に出ること、そこで本当の自由に出会うことへの憧憬を感じる」と言っている。深いし納得する。
「自由な国オランダはなぜ、ホロコーストの犠牲者がユダヤ人住民の73%に達したのだろうか。他の国より格段に高い比率だ」――。それはオランダの行政機構や公営企業、民間団体が、占領当局の指示に忠実にし従い、「従順」に実行してしまった。そしてその背景には、オランダがユダヤ人を受け入れ、市民として平穏に暮らすことができる自由で寛容な国であったからでもある。
2020年1月、アウシュヴィッツ解放75周年でルッテ首相は謝罪演説。2023年7月オランダ国王は「奴隷制・奴隷貿易に対する国王の謝罪」が行われている。「アムステルダムの自由と寛容の背後には、大勢の他者の『不自由』があったのだ」と水島さんは言い、「この『他者の不自由の上に成り立つ自由』という問題は、難民が世界的に増加する現代の各国が向き合うべき重要な課題であり、日本も無縁ではない」と問題を提起している。
かなり人間の本質に関わる問題の根の深さを考える重い著作だ。
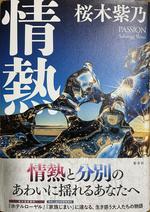 人生をたっぷり経験した熟年男女が織りなす6短編集。分別もあり、互いに相手を尊重、恋もあるが抑制的、プライドもチラッと覗かせつつ、これまでたどった人生の節を心に思い出しつつ、今を生きる。「情熱と分別のあわいに揺れるあなたへ」「あなたはもう、大人ですか」と帯にある。老けゆく男の心情が、実に穏やかな筆致で描かれる味わい深い大人の短編集。
人生をたっぷり経験した熟年男女が織りなす6短編集。分別もあり、互いに相手を尊重、恋もあるが抑制的、プライドもチラッと覗かせつつ、これまでたどった人生の節を心に思い出しつつ、今を生きる。「情熱と分別のあわいに揺れるあなたへ」「あなたはもう、大人ですか」と帯にある。老けゆく男の心情が、実に穏やかな筆致で描かれる味わい深い大人の短編集。
「兎に角」――。同級生だったカメラマンとスタイリスト。40年ぶりに片思いだった女性に会う。早期退職と離婚を同時期に体験した後、北海道に戻ってきた男。人生も円熟期だが、ふと蘇る40年前の記憶。半月に一度の撮影ペースで一緒に仕事をする。同性カップルの記念撮影、遺体を囲んでの家族写真・・・・・・。「淡々と降り注ぐ雪のように、人の幸福をひとつずつ心に溜めてゆく。兎に角----とにかく今日は、壁のジャッカロープが牧村を見て、微笑んだのを見逃さなかった」・・・・・・。
「スターダスト」――。とうを過ぎたサックス奏者と作曲家。若いディレクターに曲の作り直しをさせられる。「お互い時代を捉える瞬発力が落ちているのは明らかなのだ。『得意なところ抑えてほしい』などと若造に指摘されては、わかっているぶん憤慨もする」・・・・・・。「追い詰められた作曲家が、噛み付くように出してきた曲は、糸井を狂気させた」。老いの哀しみと意地が滲み出る。
「ひも」――。「ボケたら関係解消」が条件の70代ホストと美容室店長の中年女性。「体でお返しできないヒモ、江里子が言うところの『得がたい知恵袋』は、今日も女のために時間を使う」・・・・・・。ヒモという弱い立場の老人の気の使いようは尋常ではないが、哀れではなく人生が上品に見える。この2人、すっかり「寸借詐欺」に会うのはコメディー。
「グレーでいいじゃない」――。ジャズピアニストのトニー漆原が死んだ。ピアニストの母は、息子を本格的なピアニストにしたかった。「グレーでいいじゃない、突き詰めんなよ。どこからか、トニーの声が聞こえてくる」・・・・・・。
「らっきょうとクロッカス」――。順調に出世街道を歩いていたはずの札幌の裁判所職員の女性。突然、釧路に転勤させられる。小説家の妻を亡くした60歳を過ぎた弁護士と交流するうちに、次第に心が惹かれてメールのやりとりをする。「わたしずっと、百点を取り続けてきたんです。今までずっと、百点を取っていないと安心できなかったんです」「百点を手放した日々には、悔しさもなかった----この気楽さはなんだろうか。釧路に来てから、ほとんど、損得の計算をしなくなった」・・・・・・。
「情熱」――。60になる遅咲きの小説家が、同年代の女性大学教授と出会い、彼女のふるさと下関を案内してもらう。過去を明かさぬ彼女だったが、昔の恋人の話を聞く。「14で出会い、15のときには約束した場所で、5時間待つほど焦がれ、20歳を過ぎてから再び学ぶことを勧めた男は、彼女を置いて死んだ」「女の生きてきた60年を思うと、これ以上立ち入ってはいけない気がした」・・・・・・。
「なにが足りなかったのか。あのときどうかすれば、人生の潮目は変わったのか」――。人生の夕暮れの男には、それぞれの円熟と諦念があるものだ。
 「学問の常識を揺るがした思考実験」が副題。ガリレオ、デカルト、ニュートン、アインシュタイン、シュレディンガー、そして2022年のノーベル物理学賞は「量子もつれ」・・・・・・。人類は、それまでの「常識」「概念」を次々と打ち破る「思考実験」を繰り返し、新たな地平を切り開いてきた。ガリレオから量子力学まで、一冊の中に興味深く集結させる力技に感心した。「シュレディンガーの猫」についても、これだけわかりやすく解説されるのは有難い。
「学問の常識を揺るがした思考実験」が副題。ガリレオ、デカルト、ニュートン、アインシュタイン、シュレディンガー、そして2022年のノーベル物理学賞は「量子もつれ」・・・・・・。人類は、それまでの「常識」「概念」を次々と打ち破る「思考実験」を繰り返し、新たな地平を切り開いてきた。ガリレオから量子力学まで、一冊の中に興味深く集結させる力技に感心した。「シュレディンガーの猫」についても、これだけわかりやすく解説されるのは有難い。
思考実験は科学にとどまらない。「トロッコ問題」「臓器を分ける臓器くじ」「野戦病院でのトリアージ」・・・・・・。
「ガリレオの連続物体の落下(重いものも軽いものも同じ速さで落下する)」「アキレスと亀(到着までの過程の再分割、時間空間は無限に分割できない)」「サンクトペテルブルクの賭け」・・・・・・。
「クオリア」――「マリーの部屋(白黒の世界に住んだマリーが外に出た時)」「哲学的ゾンビはクオリア(感じ)を持たない」。
「コンピュータは考えているのか――チューリング・テスト」――当然、意味はわかっていない。「宇宙のファイン・チューニングから眠り姫問題へ」――宇宙は、奇跡的に人類誕生に都合が良かったのか、事あるごとに生ずる問題。
「ギャンブラーの誤謬」――9回連続で赤が出たのだから、さすがに次は黒か。これは錯覚。「モンティホール・ジレンマと3囚人問題。心理学でよく用いられる教材。「囚人のジレンマ」の心理実験をすると、裏切り戦略を取る人がほとんどと言う。「ケインズの美人投票ゲーム」は株式投資でも見られる話。
「マックスウェルの悪魔――取り返しがつかないことを元に戻せるか!?」。「ニュートンのバケツとマッハのバケツ――どちらが回っているのか」・・・・・・。
「光速度のパラドックス――光速度で、光を追いかければ」「通過する列車上での同時性の思考実験」「自由落下する瓦職人、自由落下するエレベーター」――落下する人から見ると、重力が消えている。アインシュタインは、屋根から落ちる瓦職人の思考実験からヒントを得て、重力と加速度は区別がつかないというアイディアを原理にして、重力の理論である一般相対性理論を構築した。アインシュタインーード・ブロイの関係式」・・・・・・。
「シュレディンガーの猫」――量子力学が、古典力学と根本的に違うのは「重ね合わせ状態」という概念。「量子力学は不完全か?――アインシュタインVSボーア(光子箱の中の時計の論争)」・・・・・・。
歴史に残る思考実験を20 選び興味深いが、難解な課題をわかりやすいイラストを使って説明してくれる。これがまたありがたい。
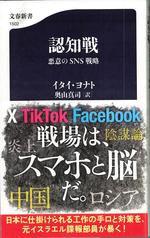 「悪意のSNS戦略」が副題。「ロシアや中国を中心とした権威主義国家による、日本を始めする西側諸国への工作は、ハッキングのようなサイバー・ネットワークを通じたものだけではなく、我々が普段から触れているSNSを通じた宣伝戦のような形で行われている。認知戦とは、相手の認知領域、つまり思考や感情などの心理的な部分を揺さぶって、行動を情報操作によって変化させようとする戦いの形のことである」「本書で明かされるのは、主に民主国家に対して平時から行われている『影響力工作』や『認知戦』『ソフト戦』と呼ばれているものの実態である」・・・・・・。著者はイスラエル軍に入隊し、諜報部員として「心理戦」「経済戦」「サイバー戦」など様々な作戦に従事。世界に広がる「悪意のSNS戦略」「認知戦」「影響力工作」の実態と工作の手口、その対抗策を示している。
「悪意のSNS戦略」が副題。「ロシアや中国を中心とした権威主義国家による、日本を始めする西側諸国への工作は、ハッキングのようなサイバー・ネットワークを通じたものだけではなく、我々が普段から触れているSNSを通じた宣伝戦のような形で行われている。認知戦とは、相手の認知領域、つまり思考や感情などの心理的な部分を揺さぶって、行動を情報操作によって変化させようとする戦いの形のことである」「本書で明かされるのは、主に民主国家に対して平時から行われている『影響力工作』や『認知戦』『ソフト戦』と呼ばれているものの実態である」・・・・・・。著者はイスラエル軍に入隊し、諜報部員として「心理戦」「経済戦」「サイバー戦」など様々な作戦に従事。世界に広がる「悪意のSNS戦略」「認知戦」「影響力工作」の実態と工作の手口、その対抗策を示している。
「ルーマニア大統領選で、ロシアが影響力工作(憲法裁判所が選挙無効と判断)」「ディスインフォメーションの3つの領域(影響力工作、虚偽情報などディスインフォメーション、詐欺・フィッシング行為)」「中ロが拡散した『汚染水』」「日本人への憎しみを喚起する作戦」「沖縄での影響力工作」「イスラエルは認知戦で負け続けている」など具体的事例を挙げ警告する。
著者自身の「イスラエル軍の『経済戦争プロジェクト』の責任者に」「イランの核武装を防ぐために、モサドが行った秘密工作」・・・・・・。
そして「中国が行っている影響力工作(悪い日本のイメージ、電気自動車の自動車業界でもキャンペーン)」「ロシアが行った影響力工作(ウクライナ、原発反対運動、第三世界の政権転覆工作)」などを例示する。
そこで、「認知戦への対抗措置」を示す。まず「影響力工作への対抗を可能にする法整備」。法律が整備されなければ動けない。次に「データ収集及び分析」――Xの改悪。「いいね」が非公開となり分析能力が落ちた。偽ユーザーがボットかどうかを見分けることも重要。そして「敵を潰す」の手順で行う。
そこでどう対処するか。「テイクダウン(フェイクユーザーを見つけアカウントを削除させる)」「大量通報して『シャドウバン』(他の人々とグループを作って報告する)」「暴露(影響力工作の実態やユーザーを公表)」「攻撃者に心理戦を仕掛ける」「カウンター・オペレーション(積極的にこちらも影響力工作を用いて反撃)」「ハッシュタグ・クリーニング(こちらも同じハッシュタグを使い、ボットを活用し、ポジティブメッセージを注入する)」の6つを示している。
日本は影響力工作が行われているにかかわらず、気づいていない。「戦いが始まる前に負けてしまっている。そのことを自覚し、一刻も早く準備を始めよう」「日本は『マインドセット』の入れ替えを」と著者・訳者が強く警告する。
 欧米などの世界は、移民と格差を背景にしてポピュリズムが広がり、それにSNSが加わり不安定な政治が続いている。「アウトサイダーポリティクス」とか、「デジタルポピュリズムの時代」と言う人もいる。本書のキーワードは、「右派ポピュリズム」の潮流だ。
欧米などの世界は、移民と格差を背景にしてポピュリズムが広がり、それにSNSが加わり不安定な政治が続いている。「アウトサイダーポリティクス」とか、「デジタルポピュリズムの時代」と言う人もいる。本書のキーワードは、「右派ポピュリズム」の潮流だ。
「参政党の集会に見られる熱狂と対立の風景はそうした危うさを如実に物語っている」「主張の実証的な裏付けがなければ、それらの言葉は独り歩きし、結果として排外的な感情や差別意識、あるいは根拠の乏しい迷信を助長する可能性が高い」と危機感を抱く。そして、「この悲劇の歴史(第二次世界大戦)が教えるのは、孤立よりも協調、迷信よりも科学、武力よりも経済、そして過剰な精神主義よりも、物質的な豊かさの追求であるという明確な教訓である」・・・・・・。そこに日本では、「反戦」と「協調」、そして「経済重視」の吉田茂以来の「保守本流」があったとする。しかし今やこれとは本格的に異なる「異形の保守」、つまり「右派ポピュリズムの潮流」が形成・拡大してきたとする。それは、「小沢一郎による政治改革」、「小泉純一郎による構造改革」、「安倍晋三による初期政権」を経て、「日本の政治を支配し続けている」と指摘する。
「安倍晋三の『遺産』」「『新たな保守』の正体」「戦後レジームと岸信介」「保守本流の崩壊」「アベノミクスと奇跡の復活」「歪められた言語空間」「保守の終焉」を現場記者の目で論述し、終章として「戦争実感の喪失と警鐘」で、「勇ましく、強くあれと叫ぶ『右派ポピュリズム』に煽られ、平和主義や反戦を『卑怯』と貶める勢力が台頭することに、なかにし礼や野中広務は抗った。戦争の醜さを知る彼らは、生き残ろうとする人間は、時に等しく『卑怯』となることを知っていた世代だ」と言う。また一方で、「左派ポピュリズム」が支持を失う現実、また「バラマキポピュリズム」に堕すことを批判する。

