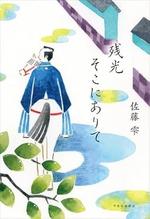 動乱の幕末、家禄2500石の旗本としての矜持と4度にわたる勘定奉行を任せられた小栗上野介忠順の生涯を描く力作。幕末の歴史を徳川幕府の側から描くと、徳川慶喜や勝海舟らがどうしても表に出るが、破綻寸前の幕府財政を支え、列強に負けない近代日本の産業化を目指した聡明、厳格、信念の男であり、徳川家に忠義を尽くした直参旗本。それが小栗上野介忠順だった。時流をつかみ、数字にも強い。ズケズケと慶喜であろうが、老中であろうが直言する。それゆえに、敵は多く、職を辞すことも何度も。「自己顕示の塊のような勝麟太郎」と合うはずがなかった。
動乱の幕末、家禄2500石の旗本としての矜持と4度にわたる勘定奉行を任せられた小栗上野介忠順の生涯を描く力作。幕末の歴史を徳川幕府の側から描くと、徳川慶喜や勝海舟らがどうしても表に出るが、破綻寸前の幕府財政を支え、列強に負けない近代日本の産業化を目指した聡明、厳格、信念の男であり、徳川家に忠義を尽くした直参旗本。それが小栗上野介忠順だった。時流をつかみ、数字にも強い。ズケズケと慶喜であろうが、老中であろうが直言する。それゆえに、敵は多く、職を辞すことも何度も。「自己顕示の塊のような勝麟太郎」と合うはずがなかった。
1860年(万延元年)、遣米使節団として訪米。金銀流出問題の解決での通貨の交換比率の見直し交渉に辣腕。先進技術に圧倒され、日本での造船所建設を志し、鉄による一本のネジを大切に持ち帰った。
帰国して外国奉行に就任、ロシア軍艦が対馬に居座る事件に対処。この交渉の辣腕ぶりも見事。1864年(元治元年)に、軍艦奉行に就任すると、造船所の建設に本格的着手。多くの借金をしてまでとの反対論に、フランスとの借款という日本人の誰も考えつかない方法を使ってまとめあげてしまう。
最も苦しんだのは攘夷思想の跋扈。生麦事件を始め、列強への賠償は、結局は幕府の負うこととなり、財政のみならず、兵庫の開港など外交要求は右往左往する老中のなか、小栗忠順が奮闘するしかなかった。長州征伐も将軍の入洛も、すべては財政負担に帰着する。「攘夷によって、この国が背負った代償は、あまりに大きい。諸外国への莫大な賠償金、改悪された関税、不利な条件のまま迫る兵庫開港、ニ度にわたる長州征伐に垂れ流された軍費」・・・・・・。それを工面するのも、結局は小栗忠順に委ねられた。
時代の趨勢を予見し、正論・ 直言の忠順は、憎まれても、裏切られても、「この国の100年後の希望」のために、信念を貫こうとする。武士の誇り、旗本の忠義、無責任な者たちへの怒りと慨嘆が伝わってくる。
大政奉還、王政復古、そして戊辰戦争・・・・・・。自ら手がけたカンパニーや造船所の行くえを見ることなく斬首となる。「最期に思うことは、ただ一つ。それは、この世に生きた一人のネジとしての、切なる祈り。百年後に生きる人たちへと続く航路に、どうか、消えない光が残っていることを」と結んでいる。読んだ後も、小栗忠順の「残光」がある。

