 世界はますます流動化、不安定化している。戦争、内戦、民族対立、サイバー攻撃、AIの悪用、インフレ、格差の拡大、気候変動や災害の多発、政治の不安定とポピュリズムの跋扈。まさに著者の指摘する危機と不確実性に満ちた「複合危機」だ。なぜ世界経済は停滞し、国家政策は機能していないのか――。その理由は、動体視力を持たない硬直的思考停止と思うが、「政策の世界で覇権を握っている主流派経済学の似非科学的なドグマにある」と中野さんは言う。そして社会の実在を無視した経済学に振り回されない「公共政策の実在的理論」を論理的に展開する。
世界はますます流動化、不安定化している。戦争、内戦、民族対立、サイバー攻撃、AIの悪用、インフレ、格差の拡大、気候変動や災害の多発、政治の不安定とポピュリズムの跋扈。まさに著者の指摘する危機と不確実性に満ちた「複合危機」だ。なぜ世界経済は停滞し、国家政策は機能していないのか――。その理由は、動体視力を持たない硬直的思考停止と思うが、「政策の世界で覇権を握っている主流派経済学の似非科学的なドグマにある」と中野さんは言う。そして社会の実在を無視した経済学に振り回されない「公共政策の実在的理論」を論理的に展開する。
「現場と地図が違ったら、現場が正しい」――「地図が正しい」と言いがちな学者を厳しく諫めた著名な社会学者を思い出す。政治家や官僚、民主政治においては、有権者全員が広い意味では「責任ある政策担当者」。その責任ある政策担当者は、「政策の根拠となる現実的な真の社会科学を追求すべきであり、その根底の社会科学哲学を探求しなければならないはずだ」と言う。
その筋道で各章を立て、「実証経済学とは何か(主流派経済学が使う非現実的な『合理的経済人』という仮定)」「科学とは何か(古典的経験論は、経験の領域にとどまり、超越論的実在論にとって科学的発見とは実際の領域にまで深く到達し、生成メカニズムを見出すこと)」「社会科学は可能なのか(マクロ経済学とミクロ経済学は並び立つのか)」「国家とは何か(国家は構造であって行為主体ではない)」「政策とは何か(存在論と政策手法)」「ポスト批判的実在論(バスカーの批判的実在論とポランニーの科学哲学)」「政策はどのように実行されるのか(ポランニーのポスト批判哲学を基礎としたロウの道具的推論・政治経済学)」が展開される。
さらに「複雑系の世界における政策(アジャイルな政策形成)」「財政哲学(インフレーションの実在論的分析) (科学としての現代貨幣理論)」「政治とは何か(人間と裁量、裁量の限界)」が詳述される。
「財政金融政策だけではインフレーションは起きない」――。「主流派経済学者は、財政赤字の拡大が高インフレーションを起こすと主張するが、政府が財政支出を拡大しても、需要が供給制約を大きく超過しない限りは高インフレーションにはならない。財政赤字それ自体がインフレーションを起こすわけではない。財政支出が実物資源をその供給制約以上に動員した場合にのみインフレーションになるのである」「インフレーションという現象は実物資源の需給関係の問題であって、貨幣供給量や財政赤字の規模の問題ではない。逆に言えば、自国通貨を発行する政府に歳出抑制や課税が必要になるのは、財源を確保するためではなく、例えばインフレーションを抑制するためなのである」----。さらに、「『公共政策の実在論的理論』は、政策の対象は事象ではなく、事象を生成するメカニズムであるべきだとする。機能的財政で言えば、完全雇用と物価の安定を実現するメカニズムを作動させるために、政策担当者は、政府支出、課税、国債の発行、金利の調節といった政策手段を講ずるのである」「ミンスキーによる修正機能的財政は、インフレーションや失業をもたらすメカニズムをより厳密に特定し、適確に政策効果を上げるため、政府の支出先を特定の分野で限定しようとするものである。インフレーションや格差の拡大を引き起こさずに、完全雇用を達成するためには、どのような政策プログラムが必要になるか。金融システムの安定化、長期的な生産性向上のためにはどうするかだ」。まさにメカニズムを厳密に捕まえ対処する「高度な裁量」が必要なのだ。特に現実の経済が開放系・複雑系である以上、不確実性は逃れられない。加えて「人間は可謬的」と指摘する。だからこそ、ドグマではなく実在論ということだろう。
「『公共政策の実在的理論』は、有効な国家政策を生み出す上において不可欠な役割を果たすものだ」「政策担当者たちの注意を、目の前の問題からその問題を生み出している構造やメカニズムへと向けさせる」――。デフレ→総需要不足→不確実性の高まり→不確実性を低減し需要創出へ。メカニズムを掘り当て解決策を編み出す。それができるのは、政府による財政出動であって、主軸を民間に委ねるのではない。
常に構造変化、メカニズムを凝視し、その転換を思考し続ける。ドグマを打ち破り解を求め続ける知恵のダイナミズム。現実を直視した臨機応変の知恵のダイナミズム。それが「中道」であることを、この難解な力業の著作に触れながら想起した。
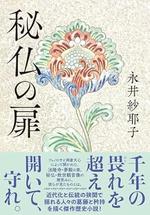 明治政府の発した神仏判然令、廃仏毀釈とは何であったか。天皇制の確立にあることは間違いないが、「寺はかつて、江戸幕府との繋がりが強かった。その故にこそ、その力を削ぐことは新政府の思惑でもあった。そのため、法隆寺のような古刹でさえも、廃寺のように零落れていくのを、手柄顔で語るものも少なくない。だが、町田久成は、それを喜ぶことなどできなかった。それは久成なりの中に、あの夢殿の救世観音像の姿が厳然と立っているからだ。千年以上の歳月を超えるものが、この国にどれだけあるというのだろう。そして、その幾つかが既に壊され、異国へ渡り、失われているのは明白である」・・・・・・。
明治政府の発した神仏判然令、廃仏毀釈とは何であったか。天皇制の確立にあることは間違いないが、「寺はかつて、江戸幕府との繋がりが強かった。その故にこそ、その力を削ぐことは新政府の思惑でもあった。そのため、法隆寺のような古刹でさえも、廃寺のように零落れていくのを、手柄顔で語るものも少なくない。だが、町田久成は、それを喜ぶことなどできなかった。それは久成なりの中に、あの夢殿の救世観音像の姿が厳然と立っているからだ。千年以上の歳月を超えるものが、この国にどれだけあるというのだろう。そして、その幾つかが既に壊され、異国へ渡り、失われているのは明白である」・・・・・・。
飛鳥時代に聖徳太子の姿を模して造られたといわれる法隆寺夢殿の救世観音像。その厨子に納められた仏像は鎌倉時代以降、固く閉ざされ、扉を開けば、ただちに仏罰が下ると信じられていた秘仏であった。それを開けたのは、明治19年、日本の美術研究の第一人者、帝国大学教授アーネスト・フェノロサと岡倉覚三が住職・千早定朝を説得してのもの。2年後の明治21年、「近畿宝物調査」として、宮内省図書頭であり、臨時全国宝物取調局の委員長・九鬼隆一が岡倉覚三、フェノロサと友人の外国人資産家ビゲロー、写真家・小川一眞などを伴って訪れ秘仏を見る。本書はその歴史的ドラマを、そこに参加した各人の思い、そこに至るまでの壮絶な人生から描く。
それこそ一筋の道を求めて戦う男たちの感動的な人生ドラマだ。近代化と伝統の狭間で揺れ呻吟する人々の葛藤と矜持を描いている。さらにそれら男に忍従を強いられ翻弄される波津子(九鬼の妻の立場から逃れ岡倉覚三に走る)など、明治の女性の生々しい姿が加わり、この物語は深みを増す。光にはいい知れぬ陰影があるものだ。
「この宝物調査において大切なのは、目の前の絵や建物や仏像が、この国の宝であると知らしめることです。宝物を伝えるために撮って欲しい(フェノロサ)」「(この観音像は)人ならざる者に見えます。怖いですな・・・・・・畏怖とでもいうのでしょうか(小川一眞)」「隆一はこの『美術行政』ができるのは己しかないという強烈な自負があった。何せ、薩長土肥の面々は、文化と芸術というものへの造詣がおよそない・・・・・・。私の矜持はここにある。・・・・・・あの仏の前には、男も女も、上も下も、全てがはぎ取られていく(九鬼隆一)」「推古天皇の勅宗であるこの寺を軽んじて、何が尊皇か。天皇の御名を借りて、己が国を牛耳ることしか考えておらぬ。・・・・・・『開いて、守れ』、国もそうであった(千早定朝)」「千年もの間、閉ざされていた秘仏の扉を、私が開いたんだ。それによって、日本の人々が仏像の真価に気づいたんだ(フェノロサ)」「日本が私を認めてくれないのなら、海の向こうに頼めばいい。----混沌は、あの菩薩像にあったのではない。元より己の内にあったのだ。ただそれから逃げようと彷徨っていたのだが、今、ようやくそれを受け入れることができたのだ(岡倉覚三)」「英国に渡った久成は、その街並みの美しさや技術の発展に大いに驚いた。しかし、それ以上に胸を打たれたのは、大英博物館であった。この国の強さは、軍事力と経済力だけではない。この文化への絶大なる自信と誇りではあるまいか。私は日本に英国のような博物館を造りたい(町田久成)」・・・・・・。
法隆寺の救世観音像――日本の文化と伝統の再興にかけた者たちの葛藤と一筋の志を鮮やかに描いた力作。
 「幸福に衰退する国の20年」が副題。2004年の著作「希望格差社会」から20年――。平成が終わり、令和になった現在、日本社会はどのように展開していくのか。社会の格差は、人々の希望は・・・・・・。
「幸福に衰退する国の20年」が副題。2004年の著作「希望格差社会」から20年――。平成が終わり、令和になった現在、日本社会はどのように展開していくのか。社会の格差は、人々の希望は・・・・・・。
平成日本で起きた「4つの負のトレンド」を指摘する。「経済停滞」「男女共同参画の停滞(女性の活躍の立ち遅れは著しい)」「少子高齢化の進行」「格差社会の進行」だ。一方、ポジティブなトレンドもある。「より安全で安心できる社会へ」「マイノリティーへの理解の拡大――障がい者からLG BTQまで優しい社会へ」だ。平成日本は、経済は成長せず、収入は伸びず、結婚したくてもできない人が増え、格差が広がり、貧困率も上昇したが、驚くべきことに「生活満足度が上昇している」と言う。①衣食住②生きがい③地域の生活環境④人間関係――この4つすべてに満足していると回答した人は、「1988年に36%だったのが2018年には55%。特に若年、中年層で高くなっている」と言うのだ。一体なぜなのか、何が起きているのか。その謎を解くのが本書だ。
戦後の日本の格差の変遷――。戦後の昭和期は格差が縮小し、努力すれば、豊かな生活(中位の生活)を築くことができるという希望を持てた時期。平成期は、格差が拡大し「希望格差」が進行した時期。正規雇用に就けた男性(とその家族)は、努力すれば豊かな生活を築く希望はある。しかし非正規雇用の若者は、いくら努力しても豊かな生活を築く収入を得る見込みが持てない、将来の生活に希望が持てなくなる。これが希望格差社会だ。平成の時代の若者の行動様式は「就活」と「婚活」。これが努力しなくてはできなくなった時代だ。
令和期は「様々な格差が固定化する時代」と懸念する。就職氷河期の青年が30年経って、令和では50歳前後。非正規雇用が不安定なまま続き、パラサイト・シングルが中高年化し、中高年(40〜64歳)の引きこもりは2018年で61万人。50代中高年の独身者も男性276万人、女性239万人と大幅に増加している。一人暮らし独身者の孤立も問題となる。また若者に広がる新たな格差、「親ガチャ――太い親、細い親」や「非経済的教育格差」がある。令和期は「世代内でも世代間でも『格差』が本人の努力ではなかなか縮まらない状況が広がっている」のだ。
この令和の「格差の拡大・固定化」に、若者はどう対処するか? 本書は、「日本人はリアルな世界で格差を乗り越えることを諦めて、『バーチャルな世界』で格差を埋める方向に進んでいる」と考察する。一生懸命働いても認められないし、将来性もない。そこで「パチンコ」「ネットゲーム」「ペット(疑似家族)」「スターやアイドルなどの『推し』(疑似恋愛)」「キャバクラやホストなどの癒し」「『収集』マニアやオタク」・・・・・・。バーチャルな世界で希望を見つけようとする人が増大していると分析する。現実生活に希望を見出せない人が、バーチャルな世界で満足を得ようとしていると言うのだ。バーチャル世界に意識を向けさえすれば、平等で希望に溢れた世界を体験することができる。「ネット空間」「いいね」もそういうことか。経済的に行き詰まりを見せ、格差が固定化しているのに、「格差拡大の被害を最も受けているはずの若者の幸福度が上昇している」という秘密はそこにあると言うのだ。
現状を大きく変えるような変革を望まず、「バーチャル世界」で格差を埋める人々が急増しているわけで、昨年来の選挙もまたそうした「バーチャル世界の楽しみ方」の奔流の中にあると思うと吐息が漏れる。良い悪いではなく、あまりにも生々しい現実を150キロ以上の直球で突きつけられた思いだ。
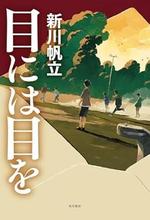 「元彼の遺言状」「倒産続きの彼女」などの痛快謎解きと違って、「少年による犯罪をどう捉えるべきか」「罪を償うとはどういうことか」を問いかける「贖罪と復讐」の本格ミステリーだ。
「元彼の遺言状」「倒産続きの彼女」などの痛快謎解きと違って、「少年による犯罪をどう捉えるべきか」「罪を償うとはどういうことか」を問いかける「贖罪と復讐」の本格ミステリーだ。
殺人など重大な罪を犯して、少年院で出会った6人の少年。更生して社会に復帰した後、そのうちの一人(少年A)が、娘を殺された遺族(母親)に殺害される。少年法によって守られ、氏名や現住所等がわからないはずなのに、どうしてそれを探り当て殺害することができたのか。そもそも少年院の中では互いの名前も、犯罪内容も家庭環境も打ち明けることは禁じられているはずだが、やはり6人の中の一人(少年B)が裏切り密告したのではないか――。1人の女性・仮谷苑子が「密告者探し」の取材を始める。
少年Aを殺したのは、娘を殺された田村美雪。我が子を殺した少年Aに復讐をしたのだ。いくら15歳の少年だからといって、人を殺しておいて、少年院に1年3ヶ月入っただけで、許されるのはおかしい。死には死をもって償ってもらう。被害者遺族が加害者に復讐した稀有な例として「目には目を事件」と呼ばれるようになる。
少年院のこの6人――猟奇殺人や母親の刺殺、集団リンチまがいの少年殺人などに至っているが、いずれも家庭や学校に生きづらさを抱えた少年たちで、「本当は良い子」のよう。「密告者探し」の中で、少年たちの心の傷、苛立ち、渇きが浮かび上がってくる。さらにあまり知られていない少年院の実態が描かれる。そして、最後に驚愕の真相が・・・・・・。
復讐の殺人「目には目を事件」を探る中で、「罪を償うとはどういうことか」「贖罪と復讐」「少年犯罪と少年法」という重いテーマを抉り出す。結論の出ない難問だが、本書の結びには、共感するものがある。
 作家、探検家、極地旅行家、北極圏単独行など著名な角幡唯介さん。易しく語っているが、これは哲学書であり、「生きる」ということ、「生と死」の究極を突き詰めている。通常の評論家ではとても及ばない実践者のみが行き着く境地を覗く思いだ。
作家、探検家、極地旅行家、北極圏単独行など著名な角幡唯介さん。易しく語っているが、これは哲学書であり、「生きる」ということ、「生と死」の究極を突き詰めている。通常の評論家ではとても及ばない実践者のみが行き着く境地を覗く思いだ。
「生が本来接続されていなければならないもの。それはいったい何なのか。この時の私はそれを何か<基盤的なもの>だと感じた。私たちの生を満たす存在の基盤。北極であれば、それは北極を北極たらしめる何かだ。でも北極ではなくても・・・・・・あらゆる土地、あらゆる空間に充ち、私を含めた、あらゆる存在と自然界の間を流れつつ、それらを生かし、結びつける働きをする流動的な何かである。この旅以来、私はこの<基盤的なもの>が何なのか気になり始めた」「そのように10年以上、おのれの行為を真摯に追求していると、時折、事物との距離が喪失し<基盤的なもの>と同化する瞬間が訪れる」「言葉=地図=認識の向こうに流れる<実在の精髄(三島由紀夫)>は、行為をもって初めて届くことができる。それは極めて身体的な感覚だ。三島はそこに到達することを望んだが、しかし、その方法論を死の他に知らなかった」「アマゾン川がアマゾン川たる所以ともいえるその巨大さ、豊饒さ、懐の深さに入り込み、彼はそれと一体化する。・・・・・・この行為と表現の中に開高健とアマゾン川の至高ともいえる調和が実現している」・・・・・・。あるところまで行った人のみが実感できる境地。宗教、哲学の境地が開示され、「実在の精髄に触れ得た瞬間」の喜びとして語られる。
書くことの不純――命がけの探検行のさなかに聞こえるのは、表現者としての悪魔のささやき。「私はこんなことを考えた。もしワイヤーではなく、川を泳いで生きのこったら、そっちの方が話は面白くなったんじゃないか? そして、こんなことを考えている自分にゾッとした」・・・・・・。「行為は純粋で、表現は不純である」と言うが、文章を書く探検家でなくても人間は演技をする不純さを持つ。加藤典洋「日本人の自画像」の「内在と関係」の概念を使う。「本書は基本的に行為(内在)は純粋で、表現(関係)は不純だとの立場に立っている」と言う。
「なぜ山に登るのか」――。役に立つでもなく、有名になりたいでもなく、無意味なことを行う内側からき上がってくる抑え切れない情動がある。「羽生の純粋と栗城の不純」「登山の常道と自分の山」など胡散臭い登山をやっている者を区別する。「<内在>によって生きなければ、人は本物に到達することはできない。<関係>が最初に来るとダメなのだ」。ヴォイテク・クルティカの凄さを「冒険芸術論」で伝えてくれる。感動する。
「生の届かなさをいかに解決するか」――三島由紀夫の考え、「はみ出し理論」を通じて、「実在の精髄」「基盤的なもの」に迫る。
登山、探検の極限を通じて「生きるということ」「行為」の行き着く境地を描く。凄みのある著作。

