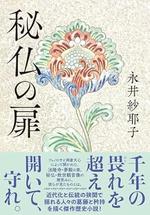 明治政府の発した神仏判然令、廃仏毀釈とは何であったか。天皇制の確立にあることは間違いないが、「寺はかつて、江戸幕府との繋がりが強かった。その故にこそ、その力を削ぐことは新政府の思惑でもあった。そのため、法隆寺のような古刹でさえも、廃寺のように零落れていくのを、手柄顔で語るものも少なくない。だが、町田久成は、それを喜ぶことなどできなかった。それは久成なりの中に、あの夢殿の救世観音像の姿が厳然と立っているからだ。千年以上の歳月を超えるものが、この国にどれだけあるというのだろう。そして、その幾つかが既に壊され、異国へ渡り、失われているのは明白である」・・・・・・。
明治政府の発した神仏判然令、廃仏毀釈とは何であったか。天皇制の確立にあることは間違いないが、「寺はかつて、江戸幕府との繋がりが強かった。その故にこそ、その力を削ぐことは新政府の思惑でもあった。そのため、法隆寺のような古刹でさえも、廃寺のように零落れていくのを、手柄顔で語るものも少なくない。だが、町田久成は、それを喜ぶことなどできなかった。それは久成なりの中に、あの夢殿の救世観音像の姿が厳然と立っているからだ。千年以上の歳月を超えるものが、この国にどれだけあるというのだろう。そして、その幾つかが既に壊され、異国へ渡り、失われているのは明白である」・・・・・・。
飛鳥時代に聖徳太子の姿を模して造られたといわれる法隆寺夢殿の救世観音像。その厨子に納められた仏像は鎌倉時代以降、固く閉ざされ、扉を開けば、ただちに仏罰が下ると信じられていた秘仏であった。それを開けたのは、明治19年、日本の美術研究の第一人者、帝国大学教授アーネスト・フェノロサと岡倉覚三が住職・千早定朝を説得してのもの。2年後の明治21年、「近畿宝物調査」として、宮内省図書頭であり、臨時全国宝物取調局の委員長・九鬼隆一が岡倉覚三、フェノロサと友人の外国人資産家ビゲロー、写真家・小川一眞などを伴って訪れ秘仏を見る。本書はその歴史的ドラマを、そこに参加した各人の思い、そこに至るまでの壮絶な人生から描く。
それこそ一筋の道を求めて戦う男たちの感動的な人生ドラマだ。近代化と伝統の狭間で揺れ呻吟する人々の葛藤と矜持を描いている。さらにそれら男に忍従を強いられ翻弄される波津子(九鬼の妻の立場から逃れ岡倉覚三に走る)など、明治の女性の生々しい姿が加わり、この物語は深みを増す。光にはいい知れぬ陰影があるものだ。
「この宝物調査において大切なのは、目の前の絵や建物や仏像が、この国の宝であると知らしめることです。宝物を伝えるために撮って欲しい(フェノロサ)」「(この観音像は)人ならざる者に見えます。怖いですな・・・・・・畏怖とでもいうのでしょうか(小川一眞)」「隆一はこの『美術行政』ができるのは己しかないという強烈な自負があった。何せ、薩長土肥の面々は、文化と芸術というものへの造詣がおよそない・・・・・・。私の矜持はここにある。・・・・・・あの仏の前には、男も女も、上も下も、全てがはぎ取られていく(九鬼隆一)」「推古天皇の勅宗であるこの寺を軽んじて、何が尊皇か。天皇の御名を借りて、己が国を牛耳ることしか考えておらぬ。・・・・・・『開いて、守れ』、国もそうであった(千早定朝)」「千年もの間、閉ざされていた秘仏の扉を、私が開いたんだ。それによって、日本の人々が仏像の真価に気づいたんだ(フェノロサ)」「日本が私を認めてくれないのなら、海の向こうに頼めばいい。----混沌は、あの菩薩像にあったのではない。元より己の内にあったのだ。ただそれから逃げようと彷徨っていたのだが、今、ようやくそれを受け入れることができたのだ(岡倉覚三)」「英国に渡った久成は、その街並みの美しさや技術の発展に大いに驚いた。しかし、それ以上に胸を打たれたのは、大英博物館であった。この国の強さは、軍事力と経済力だけではない。この文化への絶大なる自信と誇りではあるまいか。私は日本に英国のような博物館を造りたい(町田久成)」・・・・・・。
法隆寺の救世観音像――日本の文化と伝統の再興にかけた者たちの葛藤と一筋の志を鮮やかに描いた力作。

