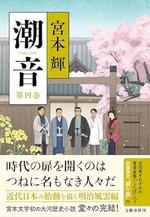 明治となり版籍奉還、廃藩置県、岩倉使節団の派遣、征韓論・・・・・・。不平士族は溢れ世情騒然、すべての人の戸惑いのなか近代化が進んでいく。新貨幣への交換、太陽暦への移行、廃仏毀釈、郵便、鉄道新設、学校・・・・・・。駕籠から人力車を始めとして変わっていかないものなど何ひとつない。北前船が寿命を終え、廻船問屋が時代からこぼれ落ち、越中富山の売薬行商にも新しい時代が来たと弥一らは考え模索する。売薬仲間組から「カンパニー」へ。
明治となり版籍奉還、廃藩置県、岩倉使節団の派遣、征韓論・・・・・・。不平士族は溢れ世情騒然、すべての人の戸惑いのなか近代化が進んでいく。新貨幣への交換、太陽暦への移行、廃仏毀釈、郵便、鉄道新設、学校・・・・・・。駕籠から人力車を始めとして変わっていかないものなど何ひとつない。北前船が寿命を終え、廻船問屋が時代からこぼれ落ち、越中富山の売薬行商にも新しい時代が来たと弥一らは考え模索する。売薬仲間組から「カンパニー」へ。
弥一らは、東京と大阪に分社を出し、大店とはいえない「松葉屋」という廻船問屋を使い、独自に清国との交易に乗り出す。「不平士族」「列強の罠」「密偵警察」「船出(富山の岩瀬浜から約8日で清国・福州へ、2日ぐらい後に富山へ)」「台湾出兵」「朱大老」「青年の自死(弥一の長男・太一郎の悲しい死)」、そして「西南戦争」・・・・・・。
「波の音が聞こえるでしょう? 聞こえるのは波の音なんです。潮の音じゃない。潮の音は海の底の方から聞こえてきて、海の底の動きを教えてくれるんです。岩瀬浜で潮の音を聞き分ける人間は、和泉屋の嘉六と美濃屋の鉄五郎だけですよ」「海が凪いでても、海の底のほうは、とんでもなく大きくうねってるってことだから」「潮の凄まじい音が。凄まじいけど、静かですね。恐ろしいほど静かで、世界の海の底が動いていますよ」・・・・・・。
「越中富山の売薬業者や廻船問屋は、徳川幕府という特殊な政体のなかでは法を犯したかもしれないが、その困難のなかで知恵を絞り、忍耐に忍耐を重ねて密貿易という道を選び、全国の人々に健康を届けるために、貧しい富山の民を食べさせるために、優れた薬を作って販売し続けたのだ」――。その薩摩への片道35日の「冥土の飛脚」。その旧薩摩藩では、若き旧藩士たちが、西郷とともに痛ましい死を遂げていったのだ。
宮本文学初の大河歴史小説。人生哲学をはらみながら、名もなき庶民「富山の薬売り」たちの知恵と勇気、そして幕末・維新の大動乱を新しい角度で濃密に描き切っている。実に読み応えがある力作。

