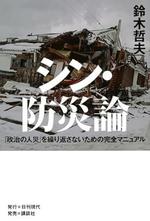 「『政治の人災』を繰り返さないための完全マニュアル」が副題。今年も「大雪」「山火事」に襲われている災害列島日本。水道管の劣化による道路陥没もある。「防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化」は、日本の最重要の柱である。雨の降り方が明らかに変わり、激甚化、集中化、広域化している。
「『政治の人災』を繰り返さないための完全マニュアル」が副題。今年も「大雪」「山火事」に襲われている災害列島日本。水道管の劣化による道路陥没もある。「防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化」は、日本の最重要の柱である。雨の降り方が明らかに変わり、激甚化、集中化、広域化している。
1991年の長崎県雲仙普賢岳の火砕流の現場で、「犠牲者の遺体を目の前にし無力な自分を思い知らされた」というジャーナリストの鈴木哲夫さん。その後、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、そして能登半島地震、豪雨や台風、火山噴火、酷暑など精力的に取材を進めてきた。政府の対応のにぶさや遅さに怒りを感じ、「度重なる自然災害の犠牲や被害は『政治の人災』である」と言い、どうあるべきかを提言する。
「初動の遅れ」は致命的ーー。大災害への司令塔は内閣総理大臣、官邸。参集チームは災害の大小によりランクが決まっているが、私は「政府においても各省庁においても上から集まることが大事」と実行してきた。その上で「災害は現場で起きている」から、トップが「現場に指揮を委ねる」ことが大事。本書でも繰り返しそれが指摘されている通りだ。しかし蛮勇とは全く違い、日本の脆弱国土と日常の管理について、知悉していないと指揮は取れない。
気象庁を始めとする観測体制、河川を始めとする管理体制は日常の積み重ねによって築き上げるものだ。国土のどこが脆弱か、河川のどこが弱点か、科学的知見に基づいていくこと。「日常の管理なくして危機管理なし」ーーそれが危機管理の鉄則だということを多くのリーダーに知ってもらいたいと思う。この10年余、気候の大変化に対して、河川・道路などの強化をし、「流域治水」という考えで、防災減災に取り組み、ソフトとして、タイムライン、ハザードマップ、マイタイムラインを組み上げてきたが、更なる充実が不可欠だ。
「自然災害が起きれば、避難指示の決断など、一気に責任を背負い込むのは、知事や市町村長など、自治体の首長だ。決断を迷い、苦しむ。そこには、首長の権限を担保する仕組みやバックアップ体制が必要」と言っているが、その地域を知っている人しか決断はできない。崖も堤防も地形も知って初めて避難指示などができるが、そのために河川ごとに管理・強化をしている河川事務所などとの強い連携が日頃から行われていなければ決断できない。災害は毎回態様は違う。その動体視力を持つリーダーがいるかいないか。
本書の後半は、石原信雄氏を始めとする多くのリーダーへのインタビュー「危機管理のためのリーダー論」がある。いずれも重圧のなか悪戦苦闘した人の貴重な言葉だ。
脆弱国土日本を誰が守るかーーますます重要の時に差し掛かっている。

