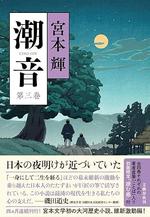 禁門の変の後、幕府は長州残兵隊を追って捕縛、斬殺を続け、エゲレスなど四国連合艦隊は長州を攻撃。次第に「士民の気分を長州への同情、幕府への反感」へと変化させていく。幕府が次第に崩壊していくことを悟った弥一は、薩摩藩の御用商人・満井屋雅右衛門と面会し、富山の薬売りによる清国との直接交易を画策する。満井屋と清国との直接の干し昆布交易だ。「いまの倍の唐薬種が手に入れば、富山の薬は日本の7割を占めることができる」との戦略だ。懸命に工作。川上家の家訓「苦楽が合わさって、ひとつの人生になる」「人の幸不幸にも消長がある。それゆえに何事も時が至るのを静かに焦らずに待て」を思い、「一生涯見ていてあげる。安心していなさい」と、枕崎で月の声を聞く。
禁門の変の後、幕府は長州残兵隊を追って捕縛、斬殺を続け、エゲレスなど四国連合艦隊は長州を攻撃。次第に「士民の気分を長州への同情、幕府への反感」へと変化させていく。幕府が次第に崩壊していくことを悟った弥一は、薩摩藩の御用商人・満井屋雅右衛門と面会し、富山の薬売りによる清国との直接交易を画策する。満井屋と清国との直接の干し昆布交易だ。「いまの倍の唐薬種が手に入れば、富山の薬は日本の7割を占めることができる」との戦略だ。懸命に工作。川上家の家訓「苦楽が合わさって、ひとつの人生になる」「人の幸不幸にも消長がある。それゆえに何事も時が至るのを静かに焦らずに待て」を思い、「一生涯見ていてあげる。安心していなさい」と、枕崎で月の声を聞く。
長州征伐に加わるように命じられた各藩も本音は迷惑で、なかなか腰を上げず、「禁門の変も会津と長州の喧嘩じゃないか」という声もあった。そんななか水戸の天狗党の乱で、三百五十人の尊王攘夷派の浪士が斬首され、「処罰のやり方がひどい。降伏してる者を」の声が上がるなど、幕府の威光は落ちてゆく。「一橋公がいつ将軍後見職を投げ出すかわからないのと同じく、各藩主も佐幕、勤皇、開国、鎖国という旗印をいつ変節させるかわからない」、日本中が右往左往している状況になる。
長州征討軍の引き揚げ、新撰組の台頭、朝廷の勤皇派と反勤皇派の暗闘・・・・・・。そして将軍家茂の死、慶喜が15代将軍に。しかし公武合体、攘夷思想、慶喜を信任する孝明天皇が突然崩御する。「これで何もかもがひっくり返る、と私は思いました」・・・・・・。
大政奉還。「慶喜の大博打」ではある。「薩摩人は理では動かない」「まず朝廷を仰ぐ新政府を樹立して、この国の政体を正しい大義に復し、有力諸藩合議による政事で難局を乗り越えよう。これが安政のころからの倒幕論でございましょう。しかし、西大小(西郷、大久保、小松)の腹の内はそうではない。彼らにとっての勤皇は、徳川幕府をつぶすための方便なのです」・・・・・・。
慶応4年1月3日、鳥羽伏見の戦いが起きる。江戸城無血開城、彰義隊の乱、白河の戦い、長岡の戦い、奥羽越列藩同盟、会津戦争、箱館戦争・・・・・・。明治改元、そして版籍奉還へ。「いったい誰が、この干し昆布を中心とした密貿易によって得た金子が徳川幕府を倒すことになると想像しただろうか」「富山藩がなくなれば、反魂丹役所も消えていくことになる。富山藩が富山県になろうとも、売薬は県の最重要事業であることは変わりはありません。売薬業に関わる者たちの数も四千人を超えようとしております」――。
「越中三人衆」――「それは私どものことでございますか」「そうだ。弥一と長吉と才児だ。あの政変の時代に、町人でありながら京、伏見、大阪、兵庫、摂津と奔走して、薩摩藩に情勢を伝達し続けて、禁裏では『薬隊』を編成して、周辺の町人たちを流れ弾から救った功労者」と富山藩反魂丹役所の緒方喜重郎は言う。
新しい時代、近代化が始まろうとしていた。

