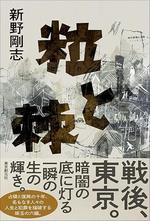 戦後の占領・復興期の東京。暴力や死と向き合う混沌とした時代をもがきながら生きる人々の姿を、6つの短編で切り取る力作。食糧難、浮浪児、パンパン、街を仕切る暴力団、落ちぶれる華族、満州からの引揚げ、捕虜、GHQ、戦犯、街頭紙芝居・・・・・・。昭和20年生まれの私としては見聞きしてきた実感の伴うものばかり。全てを失った東京、想像を絶する苦難のなか生き抜いてきた人々の生命力を改めて突き付けられた。
戦後の占領・復興期の東京。暴力や死と向き合う混沌とした時代をもがきながら生きる人々の姿を、6つの短編で切り取る力作。食糧難、浮浪児、パンパン、街を仕切る暴力団、落ちぶれる華族、満州からの引揚げ、捕虜、GHQ、戦犯、街頭紙芝居・・・・・・。昭和20年生まれの私としては見聞きしてきた実感の伴うものばかり。全てを失った東京、想像を絶する苦難のなか生き抜いてきた人々の生命力を改めて突き付けられた。
「幽霊とダイヤモンド」――上海から空輸されたダイヤモンドの行方をめぐって、追われる飛行士。盧溝橋事件直後の1937年7月末、居留民の多くを殺した通州虐殺事件の幽霊が消えず怯える男。「自分が生きることに葛藤はない。しかし、ただ生きているだけでは、つまらなかった」・・・・・・。極限状況で生きる男の中で弾けるマグマ。
「少年の街」――東京・上野の浮浪児。同じ境遇の浮浪児を集めて、地方の農家に送る少年。それが彼らにとっての幸福に違いないと信じていたが----。狩り込み、浮浪児狩り、そして浮浪児を利用して子供を地方に売る業を大掛かりに展開する大物が介入して----。
「手紙」――GHQのもとで手紙を検閲する元士族。某伯爵家の夫人が売春。女衒と娼婦----「落ちていく女を見て楽しむ。落ちていく金持ちは見世物であり、玩具である。終戦後、貧しき者の思考法をあちこちで学んだ」・・・・・・。
「軍人の娘」――許婚とともに、ソ連に連行された義兄の帰りを待ち続ける紙芝居の出版社で働く女性編集者。「女性の時代が来た」というが、父のいなくなったこの国で自由とは何かを悩む。
「幸運な男」――GHQが接収した洋館で働く叩き上げの料理人。地下に幽閉され、人体実験までされている中国人の捕虜を助けようとする。
「何度でも」――1959年のミッチーブームの時。用賀にある右翼の大物が所有する邸宅で女中となったかつて上野の浮浪児であった若き女性。その主人は元伯爵家の令嬢で、「GHQ高官を虜にした魔性の女」「夫が殺人事件で逮捕された女」と言われた女。その館にはもうひとり"呆れるほど美人"の女性がいた。実はその女、ある国の王の愛人に仕立て上げられようとしていた・・・・・・。
貧困と暴力と死と隣接する不条理充満の時代だが、生き抜くたくましき生命力の輝きがあった。
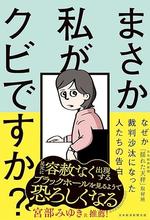 「なぜか裁判沙汰になった人たちの告白」が副題。日本経済新聞電子版の連載「揺れた天秤〜法廷から〜」を書籍化したもの。実際の民事訴訟や刑事事件を題材に「誰もが陥りかねない社会の落とし穴」を浮き彫りにする。各社の「人生相談」は、その回答も含めて人気を博するが、不満が鬱積してつい起こしてしまうトラブル。挽回しようとして泥沼にはまる詐欺まがいの事件。取引を成功させたい社員たちの焦り。近隣・隣人等とのトラブル。学校や会社でのいじめやパワハラなどから起きる事件。昨今のネット、SNS時代から引き起こされる陥穽の数々・・・・・・。この日常には、どこでも取り返しのつかないことになる「落とし穴」「まさか私が」が潜んでいる。手元の身近に置いて、時々読んだ方が現代社会にはいいなと思いつつ、面白く読んだ。
「なぜか裁判沙汰になった人たちの告白」が副題。日本経済新聞電子版の連載「揺れた天秤〜法廷から〜」を書籍化したもの。実際の民事訴訟や刑事事件を題材に「誰もが陥りかねない社会の落とし穴」を浮き彫りにする。各社の「人生相談」は、その回答も含めて人気を博するが、不満が鬱積してつい起こしてしまうトラブル。挽回しようとして泥沼にはまる詐欺まがいの事件。取引を成功させたい社員たちの焦り。近隣・隣人等とのトラブル。学校や会社でのいじめやパワハラなどから起きる事件。昨今のネット、SNS時代から引き起こされる陥穽の数々・・・・・・。この日常には、どこでも取り返しのつかないことになる「落とし穴」「まさか私が」が潜んでいる。手元の身近に置いて、時々読んだ方が現代社会にはいいなと思いつつ、面白く読んだ。
「会社員たちの転落劇。小さな慢心が悲劇を呼ぶ」――。「洗剤『お持ち帰り』で失った銀行副店長のポスト」「入社歓迎会で泥酔からの暴言。失った商社内定の切符」「誠実、勤続30年の教員、たった1度の飲酒運転で退職金1720万円を失う」「会社支給のスマホで集団移籍のグループチャット、引き抜き工作が明るみに」・・・・・・。今更ながら、「酒は飲んでも飲まれるな」。デジタル社会の闇からの声が聞こえる。
「まさか、あの会社で。有名企業のスキャンダル」――。「ソニー生命保険に勤めていた男が、巨額の会社資金に手をつけ、独断で暗号資産(仮想通貨)に交換した。詐欺罪で懲役9年の実刑」「追い込まれたソフトバンク部長、起死回生を狙った副業の投資詐欺(典型的なポンジスキーム)」「近畿日本ツーリストで支店幹部が自治体に業務費過大請求」「営業秘密を持ち出した『かっぱ寿司』元社長」「積水ハウス地面師事件」・・・・・・。
「平穏な家庭が壊れていく。溶けていくお金に、ご近所トラブル」――。「『仕組み債』で1000万円を溶かした母」「マンションでの暴言・乱暴の困った住民」「イブに届かぬピザ。52分遅れで訴訟」・・・・・・。現場で困った事が多いが、それが訴訟にまで発展する。
「会社員はつらいよ。今どき職場の悲喜こもごも」――。「会社で殴った殴られた」「チャットでこぼした愚痴が会社に知られた女性」「上司が強要した偽装請負」「育休から復帰したら部下ゼロ」・・・・・・。ちょっとしたはずみでトラブル・訴訟へ。気をつけなければ・・・・・・。
「パパ活なのか、恋なのか。男女のすれ違いが事件になるとき」――。SNSで知り合った女子高生には本当の彼氏がいた-。当たり前だと思うが・・・・・・。「『隠し子』の認知請求」「遺族年金を争った『2人の妻』・・・・・・。
「秘密資金に粉飾、脱税・・・・・・闇落ちする経営者たち」――。「秘密資金2800億円に騙された外食チェーン会長」。今どきM資金みたいなものが。驚く。脱税事件や粉飾決算、インサイダー取引は相変わらず。
「職場であった本当に怖い話。日常に流れる狂気」――。社内の暴力事件、問題社員の解雇問題、パワハラ、チャットなどによるアクセス権限悪用の恐怖、道の駅でのカスハラ・・・・・・。自分の名前で上司を罵る身に覚えのないチャットが送信されていたというから困った時代になっている。
「SNSの闇。バズリから生まれる誹謗中傷、毀誉褒貶」――。「編み物系ユーチューバーが削除申請を乱用、ライバル動画を次々と封殺」「『バズる』動画で"男気"が売りの社長が暴走」「食べログ訴訟、アルゴリズムの変更の適否」。こういう時代になっている。
「若者たちの心に、司法はどこまで迫れるだろうか」――。「歌舞伎町リンチ死、『トー横』に集まる若者たちの希薄な関係と暴力性」「京大院生が就活WEBテストを替え玉受検」・・・・・・。
イライラ、不満、ネット社会の闇など、世相が浮き彫りにされる。
 赤坂喰違の変(明治7年)岩倉具視暗殺未遂事件、紀尾井坂の変(明治11年)大久保利通暗殺事件、板垣退助岐阜遭難事件(明治15年)、森有礼暗殺事件(明治22年)、大隈重信爆弾遭難事件(明治22年)、星亨暗殺事件(明治34年)等の明治の暗殺事件。大久保利通の暗殺は、不平士族の巨大な怨恨の噴出によるものだが、犯人の島田一郎は小説が刊行されるなど大衆に親しまれ、「憲政功労者」にまでなる。板垣退助の「板垣死すとも自由は死せず」はこれに近いことが言われたことは事実。爆弾を投げられた大隈重信は犯人・来島恒喜の勇気を称賛し、そのことで大隈の人気も上がった。
赤坂喰違の変(明治7年)岩倉具視暗殺未遂事件、紀尾井坂の変(明治11年)大久保利通暗殺事件、板垣退助岐阜遭難事件(明治15年)、森有礼暗殺事件(明治22年)、大隈重信爆弾遭難事件(明治22年)、星亨暗殺事件(明治34年)等の明治の暗殺事件。大久保利通の暗殺は、不平士族の巨大な怨恨の噴出によるものだが、犯人の島田一郎は小説が刊行されるなど大衆に親しまれ、「憲政功労者」にまでなる。板垣退助の「板垣死すとも自由は死せず」はこれに近いことが言われたことは事実。爆弾を投げられた大隈重信は犯人・来島恒喜の勇気を称賛し、そのことで大隈の人気も上がった。
大正に入っての朝日平吾事件(安田善次郎暗殺事件)(大正10年)、同じ大正10年の原敬首相暗殺事件。この2つの事件が構造的に詳しく解説される。
安田善次郎暗殺事件は、朝日平吾が短刀で善次郎を刺殺し、その場で自分も剃刀で咽喉部を切り自殺。「斬奸状」には「奸富安田善次郎 巨富を作すといえども富豪の責任はたさず、国家社会を無視し 貪欲卑吝にして民衆の怨府たるや久し。・・・・・・よって天誅を加え世の警めとなす 朝日平吾」とある。「大久保利通の死、森有礼の死、星亨の死、それぞれの時代色を帯びた死であるが、安田翁の死の如く思想的の深みは無い」「安田翁の死は、明治大正にわたっての深刻な意義ある死である」(読売新聞 1921年9月29日)とあり、吉野作造は「朝日の行動には徹頭徹尾反対だ」とその短見を批判しながらも、「けれどもあの時代に朝日平吾が生まれたと云うその社会的背景に至ては深く我々を考えさせずには置かぬものがある」と言う。明治の暗殺の多くは政治的理由による暗殺であったが、「大正の朝日による暗殺は、対象を貧困な社会的弱者のための救済事業の意義を解しない大富豪としており、暗殺者の動因としては、家庭的不幸ということがあった」と指摘、貧富の差と生い立ちからくる不遇が前面化していると分析している。北一輝、昭和初期の暗殺事件につながるものだ。合わせて「マスメディアをしきりに気にしていて」と言い、マスメディア時代の暗殺の起点となっていると分析している。
一方、原敬暗殺の真因は、犯人中岡艮一の抱えていた個人的行き詰まり、挫折感、゛恋の艮一゛にあり、現代の暗殺にそのままつながるものだと言っている。大正時代の2つの暗殺事件が異なりを見せつつも現在に流れてくることの指摘は納得するものだ。
さらに、暗殺に同情的な日本の庶民文化、意識の背景を分析。「判官びいき」「御霊信仰に由来する非業の死を遂げた若者への鎮魂文化」「仇討ち・報復・復仇的文化」「暗殺による革命・変革・世直し」の4つを挙げている。
安倍元首相襲撃事件から3年が経とうとしている。到底許すことはできない。
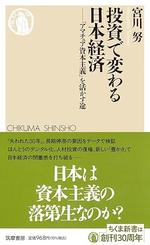 「『アマチュア資本主義』を活かす途」が副題。日本はなぜ30年もの長期停滞から抜け出せないのか。それは時代に合った果敢な「投資」をしてこなかった当然の帰結だ。設備投資額の低迷、人的資本への投資不足、デジタル化の遅れに見られる投資の質の低下。要するに供給サイドの政策不足であり、日本は「開発独裁」から「プロフェッショナル資本主義」への切り替えに失敗したとデータを徹底検証して解き明かす。
「『アマチュア資本主義』を活かす途」が副題。日本はなぜ30年もの長期停滞から抜け出せないのか。それは時代に合った果敢な「投資」をしてこなかった当然の帰結だ。設備投資額の低迷、人的資本への投資不足、デジタル化の遅れに見られる投資の質の低下。要するに供給サイドの政策不足であり、日本は「開発独裁」から「プロフェッショナル資本主義」への切り替えに失敗したとデータを徹底検証して解き明かす。
なぜ日本の投資はここまで増えなくなったのか。「日本企業は需要に合わせて設備投資を行う傾向が強く、バブル崩壊後の低成長期には過剰設備となった」「1997年からの金融システムの崩壊で、日本企業は単独で投資リスクを超えなくなった」「2010年代初頭の円高で、製造業は内需の成長ではなく生産拠点を海外に移した。円安となっても戻ってこない」「デフレが続き、実質金利の高止まりは設備投資を減少させ、収益を実物投資に回すより現預金の蓄積に向かった」とし、最大の要因は「日本企業が収益率の高い投資機会を見出せず、米国のICT革命の時期はリストラの最中。新たなビジネスチャンスとなる技術革新に乗り遅れた」と分析する。日本は新たな分野への挑戦なしに既存設備の削減がダラダラ続いてきた、需要を掘り起こす進取がない。資本蓄積が極端に低下して供給力低下した。その背景には、日本企業の躍進を支えたメインバンク制などの資金面、長期雇用・年功賃金制など労働面の慣行の崩壊がある。日本の個人レベルの行動よりも「ムラ」レベルの意思決定が優先される「アマチュア資本主義(意思決定は遅く、人間関係の協調性が重視され、労働者の満足度も専門的な能力が賃金に反映されず低い)」だと断言する。それが中途半端なデジタル投資に反映してしまっているし、人の配置にも改革が行われていないと言う。
そこで「日本経済の選択肢」を示す。2000年以降、マイルドなデフレ現象が経済の停滞をもたらしたということから「財政金融政策」に関心が集中したが、それは基本的には短期的な政策である。大事なのは真の成長戦略。そのために「デジタル化なくして真の成長なし」と強調する。「ソフト面での遅れが顕著な日本のデジタル化は、ビジネス面だけでなく、安全・安心面での進化にとっても必要である」と言う。
もう一つは「人材への投資」だ。デジタル投資はハードの投資に対して、ソフトウェア投資の比率が高いがゆえに、優秀な人材をいかに集められるかにかかっている。そこでは「少子化が人手不足時代に入った」「キャリアの上昇が図れる労働市場の流動化」「学校教育と企業内外の人材育成システム」の重要性を示す。
そして「市場経済では『プロフェッショナル資本主義』に基づく競争を徹底させ、非市場経済については『アマチュア資本主義』で運営すべきである」「日本では、市場経済でも、アマチュア的な考え方が入り込んでいることが問題」「豊かさで、経済的豊かさ以外の部分がクローズアップされることはあるが、経済的豊かさが維持されなければ、全体の『豊かさ』も低下していく」と述べる。
いずれにしても、幅広い新たな「投資」の重要性を指摘する。金融・財政政策が強調され論議されることが多いが、「投資」「成長」「生産性」「日本企業」にデータを示しながら迫る大事な著作。
 「大規模調査から見えてきた『隠れた多数派』」が副題。リベラルが衰退してると言われる。最近の選挙でも既成の左派政党が伸び悩んでいるのは事実だ。もちろん時代が「デジタル・ポピュリズム」「アウトサイダー・ポリティクス」で多党化時代となっていることはある。では、リベラルと言われた人はどこに行ったのか。人々のあいだで、本当にリベラルな価値観は忘れ去られたのか。そうではない。本書は、従来のリベラルではない「新しいリベラル」という人々が存在している。「社会的投資国家」「人間の成長に希望を見出す」という「新しいリベラル」が日本には存在し、この人たちが実は最多数派を占めていると大規模な社会調査から示している。貴重な実証的研究だ。
「大規模調査から見えてきた『隠れた多数派』」が副題。リベラルが衰退してると言われる。最近の選挙でも既成の左派政党が伸び悩んでいるのは事実だ。もちろん時代が「デジタル・ポピュリズム」「アウトサイダー・ポリティクス」で多党化時代となっていることはある。では、リベラルと言われた人はどこに行ったのか。人々のあいだで、本当にリベラルな価値観は忘れ去られたのか。そうではない。本書は、従来のリベラルではない「新しいリベラル」という人々が存在している。「社会的投資国家」「人間の成長に希望を見出す」という「新しいリベラル」が日本には存在し、この人たちが実は最多数派を占めていると大規模な社会調査から示している。貴重な実証的研究だ。
「従来型の『旧リベラル』は、日米安保反対、憲法9条改正反対、天皇制反対、従軍慰安婦問題への謝罪を根幹としながらも、福祉国家政策の支持や伝統的社会からの解放を枝葉とするイデオロギー」で「私たちの調査では1%に満たなかった」と言う。自衛隊違憲、非武装中立などはかなり遠くなっており、それは姿を変えているものの軸としての「従来型リベラル」は衰退している。
そこで「新しいリベラル」――。「従来型のリベラルは『弱者支援』型の福祉政策を支持するのに対して、新しいリベラルはすべての人を成長させる『成長支援』型の社会福祉政策を支持する」「従来型のリベラルは高齢世代への支援を重視するのに対し、新しいリベラルは子育て世代や次世代への支援を重視する」「従来型のリベラルは、反戦平和や戦後民主主義的な価値観を抱いているのに対し、新しいリベラルは『戦後民主主義』的な論点には強くコミットしていない」ことを調査に基づいて論証する。決して弱者を切り捨てるのではなく、社会的投資を通じて人々の潜在能力を発揮できる環境整備を目指す。救済と言うより成長を促す未来に向けての人への投資である。
この社会調査は、6つのグループ、「新しいリベラル」「従来型リベラル」「福祉型保守」「市場型保守」「成長型中道」「政治的無関心」の6つに分けて分析をしている。そしてこの中で「新しいリベラル」が最多数派を占めると言うのだ。この「新しいリベラル」の特徴は、①子育て世代の割合が高い②女性も多く、大卒・院卒の割合も高く、正規雇用や公務員の割合も高い、安定的に生活を営んでいる人が多く、仕事を通じて成長したいと思っている人③身近な人間関係重視しており、家族や友人と過ごす時間を大切と考えている――ようだ。ちなみに、「従来型リベラル」はやや苦しい生活を送っている高齢女性の割合が高い。「福祉型保守」は、安定した生活を手に入れた高齢者の割合が高い。「政治的無関心」は独身の男性中年層が多いと言う。
「新しいリベラルの政治参加」は注目される。社会的投資型の社会福祉政策を望ましいものと考える意味で、成長論的な自由主義の支持者でもある。戦後民主主義的な価値観とは強くコミットせず、自身の政治的立ち位置についても明確なイメージがなく、子育て世代が担い手となっているが、幅は広い。注目すべきは「新しいリベラルは、自身の政治的価値観に合致する政党を真摯に探しているのだが、そのような政党を見つけられずにいる」「子育て支援や教育政策に力を入れる政党に投票したいと思っているが、現在の日本においてそのような政党は見当たらない」と指摘している。公明党はまさにそうだと思うが、その受け皿になっていないと言う調査となっている。「子育て世代の声」が政治の世界に届いていないということになる。
リベラルは、従来から人権など極端な政策を提起していくようだが、「新しいリベラル」は、LG BTQについても改革的ではあるが極端に神経質ではなく、また平和の問題では戦後民主主義的な反戦平和主義にはコミットしていない。軍事的なリアリズムの立場に理解を示すが、しかし「非核三原則」については堅持が強く出ている。この点の分析もされているが、現場を歩いて多くの人と接しているがわかる気がする。
思想的に論陣を張るのではなく「大規模調査」から「新しいリベラル」「将来への社会的投資重視」「人への投資」を可視化した貴重な研究に敬意を表したい。この未来を志向する「隠れた多数派である新しいリベラル」にはバラマキは通用しないことになる。

