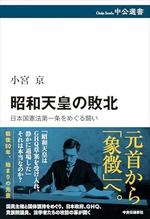 「日本国憲法第一条をめぐる闘い」が副題。大日本帝国憲法における天皇の地位は、「国ノ元首」であり、「統治権ヲ総攬」すると書かれていたが、日本国憲法では「象徴」となる。1946年2月3日の「マッカーサー三原則」の1つ、「天皇は国家の元首の地位にある」は、2月13日のGHQ憲法草案では、「symbol」となる。「昭和天皇は、幣原喜重郎首相の奏上に対し、これを承諾し、自らが統治権の総攬者を降りることを了解した」「陛下親ら『象徴でいいではないか』と仰せられた(吉田茂『回想十年 上』)」という「聖断」があったとされる。著者は「聖断は事実なのだろうか」「戦後の始まりとして信じられてきた"事実"が所詮は物語に過ぎなかったのではないか」と問いかける。憲法制定過程を徹底して調べ上げ、昭和天皇の真意を明らかにするとともに、「象徴天皇」「国民主権と国体護持」をめぐり展開される幣原喜重郎、松本烝治ら日本政府とその官僚、マッカーサー、ケーディスらGHQ、衆議院・貴族院議員、宮沢俊義、佐々木惣一、南原繁ら学者たちの激しい攻防を描いている。
「日本国憲法第一条をめぐる闘い」が副題。大日本帝国憲法における天皇の地位は、「国ノ元首」であり、「統治権ヲ総攬」すると書かれていたが、日本国憲法では「象徴」となる。1946年2月3日の「マッカーサー三原則」の1つ、「天皇は国家の元首の地位にある」は、2月13日のGHQ憲法草案では、「symbol」となる。「昭和天皇は、幣原喜重郎首相の奏上に対し、これを承諾し、自らが統治権の総攬者を降りることを了解した」「陛下親ら『象徴でいいではないか』と仰せられた(吉田茂『回想十年 上』)」という「聖断」があったとされる。著者は「聖断は事実なのだろうか」「戦後の始まりとして信じられてきた"事実"が所詮は物語に過ぎなかったのではないか」と問いかける。憲法制定過程を徹底して調べ上げ、昭和天皇の真意を明らかにするとともに、「象徴天皇」「国民主権と国体護持」をめぐり展開される幣原喜重郎、松本烝治ら日本政府とその官僚、マッカーサー、ケーディスらGHQ、衆議院・貴族院議員、宮沢俊義、佐々木惣一、南原繁ら学者たちの激しい攻防を描いている。
GHQ案に基づいて、日本側が起草した三月ニ日案――「天皇ハ日本国民至高ノ総意ニ基キ日本国ノ象徴及日本国民統合ノ標章タル地位ヲ保有ス」。そして4月17日の憲法改正草案では、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、日本国民の至高の総意に基く」――。そして8月24日の衆議院修正で、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」となる。「象徴」「元首」「君民共治」「国民主権の明示」「国体護持」等をめぐる攻防が、GHQの圧力や公職追放の危機迫るなか展開される。想像を絶する国を負う攻防が伝わってくる。
はたして天皇はどう考えていたのか――。1946年6月7日の第2回両議院有志懇談会。これは衆議院本会議上程に向けての最重要会議だ。「この回は政府の憲法草案により、国体が維持されたか否かで紛糾した」「国体変革という結論に至らない文章にせねばならないと、国体維持が最重要視されていたことがわかる」と言い、馬場恒吾(読売新聞社長)の発言に注視する。
「陛下はKing in Parliamentを希望して居られるから其処へ持って行けば良い」(参議院事務局所蔵の記録)――。「これまで昭和天皇は『第三の聖断』により、第一条の『象徴』を了解したと描かれてきた。しかしながら、馬場が伝えた『昭和天皇の希望』発言は、第一条に関して、昭和天皇が具体的な要求を行ったという驚天動地の内容に他ならない。端的に、馬場発言は聖断神話を真っ向から否定するものであり、これにより、従来の憲法史や昭和天皇像は、根本的な見直しが必要となる」と言う。「希望」があり、それも英国型の「外交使節の接受・条約締結などの外交大権を有する国王の存在を前提とし、君主主権でも国民主権でもない英国型の君民同治」の考えをしていたと言うのだ。「英国憲法では、『強いて言えば"キング・イン・パーラメント"が主権者』であり、『主権は在君か在民かなどという愚問』(猪木正道)」であり、「英国のような立憲君主国がよい」「国民主権を断言しないかたちでの元首型君主」との意向を昭和天皇は持っていたことを徹底した調査分析によって検証しているのだ。「聖断」によって「口をつぐんできた」歴史の闇を、著者は、「天皇自身の心」に迫ることによって剔抉する。凄まじい迫力ある論考に、引きつけられた。
「GHQを恐れ、天皇の宸襟を畏れ」、敗戦日本から立ち上がろうとした先達。それが日本国憲法第一条の文言の変遷に滲んでいる。昭和天皇の「敗北」でもなければ、「加工」「変節」「保身」の政治家・学者たちの「成功・失敗」でもない。この憲法制定から戦後が始まった。昭和天皇にとっても「象徴天皇」を模索する旅が始まり、その現実の行動によって権力ではない「権威」を実感させ、平成から令和の時代を迎えている。本書に出てくる一人一人の「攻防」という以上に「苦衷」に思いを馳せた。
 アグネス・チャン、沢田研二、山下久美子からBUMP OF CHICKENまで手がけた名音楽プロデューサーが、プロデュースの基本、経験から編み出した「法則」を惜しみなく語る。音楽の世界だけでなく、あらゆる世界でためになる素晴らしい著作。面白さと深さと一体感を創造的に作り上げる急所が心に響いてくる。
アグネス・チャン、沢田研二、山下久美子からBUMP OF CHICKENまで手がけた名音楽プロデューサーが、プロデュースの基本、経験から編み出した「法則」を惜しみなく語る。音楽の世界だけでなく、あらゆる世界でためになる素晴らしい著作。面白さと深さと一体感を創造的に作り上げる急所が心に響いてくる。
「いいなと感じて、つくりたいと思ったら、分析して、答えを見つける」――。「なぜ面白いのか、理由を分析する。自分の『好き』を分析する」「自分が好きと思っても伝える上での理屈がないと、より多くの人には理解してもらえない」と言う。そして「天才的な人は、意識しなくても、物事を逆から見ることができる」「もっと良いものを作りたいという視点を常に持つ」・・・・・・。
「『新しいもの』とは、新しい組み合わせのこと」――。「意外な組み合わせが面白さを生む」と言い、例えばアーティスト、歌詞、曲で三角形を作り、距離が離れているほど大きな三角形ができ、そこにたくさんの人=リスナーが入ることができる。セクシーなアーティストには、例えばワイルドで男っぽい詩を作る。ビートルズは存在がハイブリッド、ラーメンに味噌を入れ味噌ラーメンを作り上げる。そして「ストーリーがあると新しい価値が生まれる。ライブにも、ディズニーランドのジェットコースターにもストーリーがあり、コンセプトがしっかりあるから楽しい」と言う。その新しい組み合わせも「切羽詰まっているときに結びつくことが多い気がする」と言う。
「人と仕事するということ」――。「アーティストをまず肯定してあげる。良いところにスポットライトを当てる」と言うが、組織も同じだ。そして、面白い歌詞を書くには、「ものを見る視点を育てるのは、その人自身の積み重ね。言葉の感覚は急に身に付くものではない」と努力と貪欲な吸収力、そして「伝えたい気持ちの強さが大事」だと言う。「クリエイティブな人は、どんな相手も平等に扱う」「正論で人は動かない」とも。
「ヒットをつくるために僕がしていること」――。「そのアーティストの特徴を明確に把握する」「違うと思ったら、逆方向に行ってみる(山下久美子さんは、ブルースを歌っていたがポップスへ)」「アーティストと作品は寄り添わないことが大事(謹慎翌年の沢田研二の『勝手にしやがれ』。阿久悠三さんは僕らが思うのと逆のものを沢田研二にぶつけてきた)」「歌詞と楽曲も合わない方がよい(ギャップが惹きつける)」「基本を共有したら、後は自由に」「歌詞とは、心という見えないものも可視化したもの(ひとつの絵が見えたらそれが歌になる)」・・・・・・。なるほどと思うことばかりだ。「まずはタイトルを」「伝えたい相手を決める」「理知的な部分が先行すると、理路整然となってしまうことがあるが、歌詞は文章でなくていい。メロディーが感情を担う」と言っているが、話でも、演説でも全くその通りだと思う。
「クリエイティブなライフスタイル」――。「アルファ波、すなわちリラックスしている脳波が優位になっている状態の時に、宇宙とつながる感じがある。ゾーンに入ると他のことが無になる。宇宙のリズムとシンクロできる。邪念を振り払って集中していると無になってアルファ波が出てくる。曲が降りてくる」「うまくいっている時ほど何も考えない。リラックスするとアイディアが出る」「目標があればイヤなことも辛くはない」「自分が納得できた仕事だけが糧となる」「渡辺晋という指針」・・・・・・。
木崎さんは、「経験を通じて感じたり、考えたりして出してきた答えたちを整理整頓できて、何かスッキリした」と遠慮がちに言うが、読んだこちらの方がスッキリした。
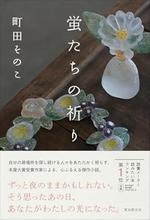 親がいない、虐待を受けている子どもはどう生きる――。蛍が舞う祭りの夜ーー山間の小さな町に暮らす中学生のクラスメイト坂邑幸恵と桐生隆之は、生きるために、互いの重大な秘密を守り合うことを決める。幸恵の両親が火災で焼死、隆之の親父(内縁)の死にそれぞれが関わっていたのだ。共にひどい親だった。・・・・・・それから15年後、同じ蛍が舞う場所で、ニ人は偶然、嘘のような再会をする。「どうしてここに、またこの男がいるの」・・・・・・。
親がいない、虐待を受けている子どもはどう生きる――。蛍が舞う祭りの夜ーー山間の小さな町に暮らす中学生のクラスメイト坂邑幸恵と桐生隆之は、生きるために、互いの重大な秘密を守り合うことを決める。幸恵の両親が火災で焼死、隆之の親父(内縁)の死にそれぞれが関わっていたのだ。共にひどい親だった。・・・・・・それから15年後、同じ蛍が舞う場所で、ニ人は偶然、嘘のような再会をする。「どうしてここに、またこの男がいるの」・・・・・・。
幸恵は涙をこぼす。「お腹の子の父親が・・・・・・いなくなったの。貯金も、金目のものも全部持っていかれた。しかもわたし名義の借金もある」「ここで死のうと思ったんだよ。わたしが知っている中で、一番綺麗な場所でさ」――。励まされて幸恵は子ども(正道)を産むが、自分は出血性ショックで亡くなる。しかも幸恵は去って行こうとする相方を殺害してしまう。
どぎつい、町田そのこの作品と思えないようなサスペンスまがいの導入で引き込まれるが、殺人を犯した親を持つ正道がどう生きたか、その周囲で展開される親子の愛憎が描かれる。息苦しさの中で、ごくありふれた家族の日常の「ありがたさ」「温かさ」そして「居場所の大切さ」が心に染みいる。蛍のような優しい光が人が生きるなかでいかに貴重なものかを思い知る。
正道の養父となって距離を置きながらも育てる隆之。「親に幸せを摘み取られた子ども」「子どもの頃から奪われてしまったものを取り戻すなんて簡単ではない」・・・・・・。隆之の葬儀には本当にお世話になったという人が自然と集まった。
人を救うのは、支える人の温かさ。「ずっと夜のままかもしれない。そう思ったあの日、あなたがわたしの光になった」・・・・・・。
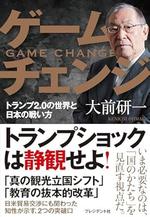 「トランプ2.0の世界と日本の戦い方」が副題。「世界は今後4年、トランプ氏に振り回されることになる」「トランプ氏は一種の『現象』である。現代アメリカの構造的問題と国民性の変化を象徴する存在である」「貿易赤字=悪、関税=自国産業の保護というのは全くの誤り」「アメリカ経済の本質的な強さ、とりわけテクノロジー分野での『マグニフィセント・セブン』の圧倒的な力を理解すべき」「これはアメリカの時代の終焉であり、世界がいよいよ不確実な時代に突入していく幕開け」と言う。
「トランプ2.0の世界と日本の戦い方」が副題。「世界は今後4年、トランプ氏に振り回されることになる」「トランプ氏は一種の『現象』である。現代アメリカの構造的問題と国民性の変化を象徴する存在である」「貿易赤字=悪、関税=自国産業の保護というのは全くの誤り」「アメリカ経済の本質的な強さ、とりわけテクノロジー分野での『マグニフィセント・セブン』の圧倒的な力を理解すべき」「これはアメリカの時代の終焉であり、世界がいよいよ不確実な時代に突入していく幕開け」と言う。
そこで、「日本はトランプショックは静観せよ。柔軟に静かに状況を見守る戦略、『柳に風』戦略を推奨する」「今必要なのは『国のかたち』を見直す視点だ」と指摘する。
大激変する世界情勢――。「インフレ鈍化・利下げ開始により、世界経済は転換局面」「世界経済の成長鈍化の中で、基軸通貨ドルの独歩高が進行」「主要国の不動産市場が問題を抱える中、マネーが日本の不動産市場へ流入」「日本企業は非製造業が好調で製造業は減益に転じた」などを指摘し、主要各国・地域の動向を解説する。
この中で、日本の行うべきソリューションとして、「真の観光立国づくり」と「教育の抜本的改革」の2つを提案する。世界を俯瞰した具体的な迫力ある重要な提言だ。
「観光立国論――インバウンドで50兆円を目指せ」――。「2030年、訪日客6000万人、消費額15兆円というが、観光と富裕層移住で50兆円規模の潜在力があり、地方創生よりも観光立国を優先すべき」と言う。「観光は3つのタイプ『周遊型』『都市型』『滞在型』があり、それぞれブラッシュアップできる」「世界では『歩く旅』や巡礼がトレンド。中東の都市型観光が人気を集め、欧州の田舎にも注目が集まっている」「『江戸時代を歩く旅』が外国人に人気。熊野古道----」「東京の魅力は買い物、食事、治安の良さ、公共交通機関。だが観光コンテンツが乏しい、言語の壁も」「富裕層が宿泊するホテルを誘致せよ」「日本は宿泊施設が圧倒的に弱い」「世界的に富裕層の移住が活発化しており、日本は富裕層を取り込む移住を促進すべき」「観光産業は50兆円に伸ばせる」・・・・・・。世界の具体例を示し、「ここが伸びしろ」と意欲を求める。
「新・教育論――答えなき時代の教育のあり方」――。日本が停滞し続ける最大の要因は工業化時代のままの教育にある。「第4の波の時代、各国はグローバル人材の育成に注力している。活躍するのは海外ルーツを持ち、変化に適応し世界で挑戦する人物だ」「世界で活躍できる人材の教育に挑戦している。台湾やイスラエル、インド(貧困)など危機感の中で凄まじい教育熱心(国も自治体も家庭も)」「知識詰め込み、暗記メインの学習指導要領は時代遅れ」「文系・理系ではなく、世界では人材は理系科目で育て、文系科目は一般教養として学ばせる」「使えない英語を教える間違いだらけの学校教育」「大学は『稼ぐ力』を養う教育機関、無償化のポピュリズムには反対。文科省や政治家の認識はずれている」「社会人の再教育、ITやAI、デジタルスキルは、外部の専門家を講師に呼んでで行うこと」「文科省を『AI教育省』へ改組し、AI時代に対応した人材育成を推進すべき」・・・・・・。
世界が変化する時、今まで通りでなく、チャレンジする日本、日本人へと突破口を示す。




