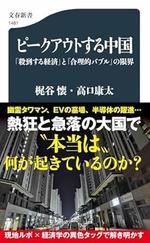 「『殺到する経済』と『合理的バブル』の限界」が副題。不動産バブルが崩壊し変調をきたしているといわれる中国経済。一方で、「新三様(新3大輸出製品)といわれるEV、太陽光パネル、リチウムイオン電池の新興産業の快進撃が語られる中国経済――。中国経済の現状と今後を、経済学者とジャーナリストが解き明かす。
「『殺到する経済』と『合理的バブル』の限界」が副題。不動産バブルが崩壊し変調をきたしているといわれる中国経済。一方で、「新三様(新3大輸出製品)といわれるEV、太陽光パネル、リチウムイオン電池の新興産業の快進撃が語られる中国経済――。中国経済の現状と今後を、経済学者とジャーナリストが解き明かす。
「EVを始めとする新興産業という『光の部分』と、不動産バブルの終焉という『影の部分』の2つの現象は、いずれも『供給能力が過剰で、消費需要が不足している』と言う中国経済が抱える根源的な問題に由来している」「『一帯一路』構想は、貿易を活発化させて経済成長を目指し、国際的地位と軍事的プレゼンスの向上図るものと解釈されるが、実際には生産能力過剰を抱える中国が、国内では消費しきれない過剰な生産物を海外に輸出する経済対策という側面が強かった」「しかし2019年からは融資額より償還額が上回り、発展途上国の債務不履行のリスクが顕在化してきた。加えて、ウクライナ戦争の影響がある。中国の海外向け融資の20%がロシアとウクライナ、ベラルーシの三国が占め回収できなくなるリスクを突きつけられている」「EV等の『新三様』の先進国への輸出は『チャイナショック2.0』への警戒を強めており、新興国への融資も頭打ちだ」「長く続いてきた投資依存型の成長モデル、そこから生じる家計部門における有効需要の低迷こそが、中国経済の宿痾ともいうべき課題なのであり、現在の経済変調はその課題が顕在化したものだ」「過去20年にわたる不動産価格の高騰は、過剰投資の対象が不動産市場となって生まれたがそれが終焉。その過剰投資の是正策としての一帯一路もトーンダウン、新興産業、グリーン産業は過剰投資の最新のターゲットだが、それも生産能力過剰となっている」と言う。過剰生産と消費需要の低迷をいかに克服するかに焦点を当てている。
「中国の不動産市場に何が起きているのか(半減する不動産市場、荒野の巨大幽霊タワマン、チャイニーズドリームの終焉)」。「ポスト、コロナの不動産危機(企業債務の拡大はなぜ生じたのか、控えめだった財政出動、民生部門の保障不足)」。「新型都市化と不動産リスク(不動産危機、西へ)」「中国不動産市場と『合理的バブル』(長く続いた不動産バブルは、住宅価格がファンダメンタルズから発散しそうになると政府が手を打ち、長期にわたって一定の資産価格の上昇が見られる合理的バブルであった)」と指摘する。
「中国社会を覆う悲観論」――。コロナ禍と不動産危機をへて、投資から貯蓄へと時代のムードが変わった。企業から積極性が消えたと言うユニコーン企業も増えていない。成長は続くと言う楽観性が全体に失われてきたと言う。そして「地方は財源不足」「政府は供給サイドの改革に執着し、その14の拡大には消極的」であったと言う。
「殺到する経済」――。EVと車載バッテリー(リチウムイオン電池が用いられる)は世界のシェアの約60%、太陽光パネルは80%超・・・・・・。いかに普及させたかが解かれる。市場の拡大と「ブームに殺到する企業」の組み合わせによって、一気に生産能力が拡大する現象を、中国経済の観察者たちは「殺到する経済」「多産多死」と言う。いかに「殺到する中華EV」となったかを分析している。
世界に大きな影響を与える中国経済の現状と今後を現地ルポを交えて紹介する。

