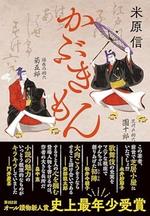 「火事と喧嘩は江戸の華」――江戸の文化文政時代の芝居小屋。庶民文化の沸騰ぶりが、躍動感のなか描かれる。著者はなんと現役東大生。9歳の頃、からくり人形芝居「忠臣蔵」を観たことから歌舞伎にハマっていき、毎月のように群馬県から歌舞伎を見に通ったという。
「火事と喧嘩は江戸の華」――江戸の文化文政時代の芝居小屋。庶民文化の沸騰ぶりが、躍動感のなか描かれる。著者はなんと現役東大生。9歳の頃、からくり人形芝居「忠臣蔵」を観たことから歌舞伎にハマっていき、毎月のように群馬県から歌舞伎を見に通ったという。
芝居町きっての色男、音羽屋の三代目尾上菊五郎、江戸の芝居の現人神とも称される成田屋の七代目市川團十郎、縦横無尽の大作者・鶴屋南北が、ぶつかり合いながら躍動。團菊に心を奪われる大店の娘、やんやの喝采を送る江戸庶民、「金子が大の好物」とちょっかいを出す玉川座、中村座の業突く張りの金主・大久保今助・・・・・・。その次々に起きる騒動が描かれるが、華やかな江戸庶民文化を彷彿させる見事な筆さばきに感心する。
最初の場面は、「助六所縁江戸櫻」の江戸随一のいい男「助六」を当たり役にする市川團十郎に、「俺も助六」と大喧嘩を仕掛けた菊五郎の「助六騒動」。
「ためつすがめつ」――。若君の身代わりに実の子の首を討たせる「菅原伝授手習鑑」の見せ場。「型を守る芝居の天才に立ち戻った」團十郎の新たな工夫。凄まじい世界。
文政6年市村座、春狂言「浮世柄比翼稲妻」初日。ヨリを戻した團菊の共演で大入り御免を叩き出す。團菊がすれ違う拍子に、腰の方の鞘がぶつかって、喧嘩になる場面で、なぜか本身の刀。「あの馬鹿ふたり、舞台で刀抜いちまったよぉ!」----。
「連理松四谷怪談」――。菊五郎がやりたいのは古典の傑作「仮名手本忠臣蔵」。文政8年、夏狂言は「忠臣蔵」と「四谷怪談」を交互にやると、南北は考えた。市川團十郎扮する色悪・民谷伊右衛門、菊五郎を演じるお岩。南北の芝居づくりの才が冴えわたり大入り。
「盟信が大切」――。菊五郎を太宰府に追い払った座元と金主の今助。南北の新作は「忠臣蔵」と「五人切」をないまぜにした陰惨芝居。今助と南北軍団との戦い。「俺ぁ狂言作者だ、それっきゃできねぇ。ここを離れても書き続けるし、芝居をやり続けるさ」「ぼけたかい、南北さん! 小屋がなけりゃ芝居はできないよ、ましてあぁた金も人もいないんだろう?」「銭金で人を動かしゃ遅かれ早かれしっぺ返しよ。まっとうな人間なら金じゃあ動かねえ――人と人との信用は、銭金で買えるもんじゃねえや。・・・・・・這っても、泣いても出ていくぜ?」・・・・・・。
そして、菊五郎が戻ってくる。「耶蘇噂菊猫」――。南北は菊五郎に十役早替わりを当て書きする。文政10年、夏芝居「独道中五十三驛」。菊五郎の化け猫はじめ十役早替わり、一座総出の大仕掛けの夏芝居は衝撃的な大喝采を受ける。
まさに「かぶきもん」。大向こうをうならせる面白さの初陣。

