 2020東京オリンピック・パラリンピックまで1000日を切った。パラリンピックの意義は限りなく大きく、未来に向けて意識を変える大きなチャンスでもある。これこそが、最大のレガシーと言えるかも知れない。本書は、早稲田大学の全学共通プログラムとして、2015年度から「パラリンピック概論」を開講、その講義を中心に編んだもの。生きいきとした内容が伝わってくる。
2020東京オリンピック・パラリンピックまで1000日を切った。パラリンピックの意義は限りなく大きく、未来に向けて意識を変える大きなチャンスでもある。これこそが、最大のレガシーと言えるかも知れない。本書は、早稲田大学の全学共通プログラムとして、2015年度から「パラリンピック概論」を開講、その講義を中心に編んだもの。生きいきとした内容が伝わってくる。
「失われたものを数えるな、残されたものを最大限に生かせ」――。「パラリンピックの父」と呼ばれるルートヴィヒ・グットマン博士の言葉だ。ロンドン郊外のストーク・マンデビル病院でスポーツを通じて生きる喜びや希望や可能性を伝えた博士の言葉で、1948年のストーク・マンデビル大会がパラリンピックの原点となる。
第1回大会は1960年ローマ大会、パラリンピックの名称は1964年東京オリンピックからだ。そして「リハビリの大会」から「競技の大会」へと進展し、2012年ロンドンパラリンピックでは20競技503種目と拡大する。ロンドンオリンピックは26競技302種目で、パラリンピックの競技種目の方が多い。障がいの程度に応じた種目となっているためで、男子100mという種目は13個、車イスバスケットボールでも4クラスある。
課題は山ほどある。「パラリンピックの環境整備」「ボランティアを含めた人、そして物と資金」「注目度を高めるためのメディアの活用」「キメ細かなインフラの整備」「選手の声を聞いて対応する力とスピード(限界は伸びる)」「スポンサー企業を増加させる取り組み」「障がい者が頑張っているのではなく、スポーツに打ち込むアスリートという意識変革(パラリンピックはチャンス)」・・・・・・。
2020年に向けて①スポーツ・健康②街づくり・持続可能性③文化・教育④経済・テクノロジー⑤復興・オールジャパン・世界への発信――。これが5本柱だが、まさに「スポーツには世界と未来を変える力がある」。パラリンピックはチャンスだ。パラリンピックの魅力と凄さを知ることは、心のバリアフリー、共生社会の実現に大きくつながっていく。
 明治150年――。激動の幕末、それぞれの藩に激流が襲いかかった。苦悩し、生き残りを懸命に模索した。迷走もあり、運・不運もあったが、各藩はどう判断したか。幕末を各藩の命運という角度で切り取る。立体的で実に面白く、教訓を示唆する。
明治150年――。激動の幕末、それぞれの藩に激流が襲いかかった。苦悩し、生き残りを懸命に模索した。迷走もあり、運・不運もあったが、各藩はどう判断したか。幕末を各藩の命運という角度で切り取る。立体的で実に面白く、教訓を示唆する。
並べられたのは象徴的な14の藩。薩摩藩(維新回天の偉業を成し遂げた二才(にせ)と呼ばれる薩摩の若者たち)、彦根藩(薩長の走狗となって「生き残った」幕末最大の裏切り者)、仙台藩(東北を戦渦に巻き込む判断ミスを犯した"眠れる獅子")、加賀藩(一方の道を閉ざしてしまったことで、墓穴を掘った不器用な大藩)、佐賀藩(鍋島閑叟の下、一丸となって近代化の魁となった雄藩)、庄内藩(全勝のまま終戦した奇跡の鬼玄蕃(酒井玄蕃))、請西藩(徳川家への忠節を誓い「一寸の虫にも五分の魂」を実践した林忠崇)、土佐藩(無血革命を実現しようとした「鯨海酔候」山内容堂)、長岡藩(義を旗印に苦難が待ち受けていようと筋を通した河井継之助と長岡藩士)、水戸藩(明治維新の礎となった勤王の家譜)、二本松藩(義に殉じて徹底抗戦を貫いた武士の矜持)、長州藩(新時代の扉を開いたリアリストたち)、松前藩(辺境の小藩の必死の戦い)、会津藩(幕末最大の悲劇を招いた白皙の貴公子・松平容保)――。
幕末の激震のなかでの藩としての決断や岐路についての論考。
 新しい画風に挑みながらも、不遇のうちに自らに銃弾を放った画家フィンセント・ファン・ゴッホ。それを献身的に支え続けた弟テオドルス・ファン・ゴッホ(テオ)――。その互いの思いやりが、それぞれの半身ともいうべき深い運命的つながりに起因することが激しく伝わってくる。そしてその同時期1880年代のパリに2人の日本人がいた。花のパリの美術界に東大を中退してまで乗り込み、大ブームとなった浮世絵など日本美術を紹介し売り込んだ林忠正と、その助手・加納重吉。この「史実をもとにしたフィクション」は感動的だ。
新しい画風に挑みながらも、不遇のうちに自らに銃弾を放った画家フィンセント・ファン・ゴッホ。それを献身的に支え続けた弟テオドルス・ファン・ゴッホ(テオ)――。その互いの思いやりが、それぞれの半身ともいうべき深い運命的つながりに起因することが激しく伝わってくる。そしてその同時期1880年代のパリに2人の日本人がいた。花のパリの美術界に東大を中退してまで乗り込み、大ブームとなった浮世絵など日本美術を紹介し売り込んだ林忠正と、その助手・加納重吉。この「史実をもとにしたフィクション」は感動的だ。
19世紀後半のパリの美術界は「アカデミー」全盛から新興の「印象派」台頭のせめぎあいの時。これに、日本の浮世絵が鮮烈な影響を与えた。
「たゆたえども沈まず」――。「パリは、いかなる苦境(洪水等の)に追い込まれようと、たゆたいこそすれ、決して沈まない。まるでセーヌの中心に浮かんでいるシテ島のように」「どんなときであれ、何度でも、流れに逆らわず、激流に身を委ね、決して沈まず、やがて立ち上がる。そんな街。それこそが、パリなのだ」。そして、茶碗の包み紙に過ぎなかった浮世絵も、その光明を受けて夢に突き進んだゴッホも、印象派も、それを支えた人々も、いつか世に認められる陽光の時が来た訳だが、そこは本書にはあえて書かれていない。
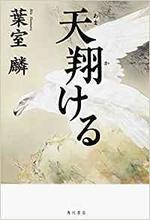 葉室麟の遺作となった。「(国を守ろうと思った西郷・橋本左内の志)それは天を翔けるような志であったに違いない。春嶽もそんな志を持った。・・・・・・しかし西郷は志を捨てぬまま世を去ったのだ。そう思うと春嶽の目から涙があふれた。・・・・・・明治23年、松平春嶽逝去、享年63」・・・・・・。本書はそう締められているが、葉室麟の死を思った。幕末から明治新政府、ずっと要職に就いて苦難を生きてきた松平春嶽。「破私立公」の人であるか否か。救国の思い、大きな志をもった男か「私」に立つ人か。春嶽はその観点から真の友を選び友を得た。見識と謹直と温和、絶妙のバランス感覚をもつ春嶽だからこそ、激震の時代の中枢にいる人の信頼を得た。阿部正弘も、水戸の徳川斉昭も、島津斉彬も、熟友の山内容堂も、そして横井小楠、勝海舟、坂本龍馬、西郷隆盛も春嶽に信頼を寄せたが、彼は徳川慶喜らに危うさを観た。
葉室麟の遺作となった。「(国を守ろうと思った西郷・橋本左内の志)それは天を翔けるような志であったに違いない。春嶽もそんな志を持った。・・・・・・しかし西郷は志を捨てぬまま世を去ったのだ。そう思うと春嶽の目から涙があふれた。・・・・・・明治23年、松平春嶽逝去、享年63」・・・・・・。本書はそう締められているが、葉室麟の死を思った。幕末から明治新政府、ずっと要職に就いて苦難を生きてきた松平春嶽。「破私立公」の人であるか否か。救国の思い、大きな志をもった男か「私」に立つ人か。春嶽はその観点から真の友を選び友を得た。見識と謹直と温和、絶妙のバランス感覚をもつ春嶽だからこそ、激震の時代の中枢にいる人の信頼を得た。阿部正弘も、水戸の徳川斉昭も、島津斉彬も、熟友の山内容堂も、そして横井小楠、勝海舟、坂本龍馬、西郷隆盛も春嶽に信頼を寄せたが、彼は徳川慶喜らに危うさを観た。
春嶽は大政奉還を早くから構想した。「徳川家の私政から脱却させ、公の政を行う」「安政の大獄で冷え切った朝廷との関係を修復し、公武合体によって国難に立ち向かう」「開国派と尊攘派が手を携えて国難にあたる挙国一致体制をつくる」――。常に変わらぬ一念が幕末の混乱のなかでも貫かれた。
しかし、「大政奉還、王政復古にいたる流れでは、実権は島津久光を始めとする春嶽や容堂らいわゆる賢候にあったが、新政府成立後、志士上がりの官僚たちが、すべては自分たちの功績であったかのように主張していく」「いずれにしても明治初年に尊攘派以外の政府要人はしだいに遠ざけられ、その後、明治維新は尊攘派による革命であったかのように喧伝されていく」のである。
激震の幕末を、その中枢にあった松平春嶽から描く思いの込められた歴史小説。幕末の四賢候とは、松平春嶽、山内容堂、島津斉彬と宇和島の伊達宗城。


