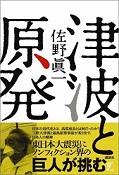 「東京で、偉い人が、くれぐれも復興プランなどつくらないでほしい」「政治家は1か月位、家族ぐるみでここへ来て住んでみたらいい」――3・11以
来、何度も被災地を訪れて聞いた言葉だ。現地では今日も人は生活している。佐野さんは「ここへ来て、悲しそうな牛の目を見てみろ。言いたいのはそれだけ
だ」という言葉を載せているが、この3月、「牛を置いていけといっても牛は俺の家族だ」と泣いた畜産業の人の言葉は私自身、今も深く残っている。先月訪れ
た南相馬市の和牛の悲しそうな、訴えかけるような目も・・・・・・。「原発によってもたらされる物質的要素だけを享受し、原発労働者に思いをいたす想像力
を私たちが忘れてきた・・・・・・。原発のうすら寒い日常の向こうには、私たちの恐るべき知的怠惰が広がっている」と佐野さんは語る。現場の涙と土と汗、
言葉のない絶句の世界。キレイごとどころかキレイごとにもならない東京の政治に、誰も見向きもしなくなった現場。自分が「頑張ります」としか言いようのな
い世界、それが現場。「大衆と共に」だ。
「東京で、偉い人が、くれぐれも復興プランなどつくらないでほしい」「政治家は1か月位、家族ぐるみでここへ来て住んでみたらいい」――3・11以
来、何度も被災地を訪れて聞いた言葉だ。現地では今日も人は生活している。佐野さんは「ここへ来て、悲しそうな牛の目を見てみろ。言いたいのはそれだけ
だ」という言葉を載せているが、この3月、「牛を置いていけといっても牛は俺の家族だ」と泣いた畜産業の人の言葉は私自身、今も深く残っている。先月訪れ
た南相馬市の和牛の悲しそうな、訴えかけるような目も・・・・・・。「原発によってもたらされる物質的要素だけを享受し、原発労働者に思いをいたす想像力
を私たちが忘れてきた・・・・・・。原発のうすら寒い日常の向こうには、私たちの恐るべき知的怠惰が広がっている」と佐野さんは語る。現場の涙と土と汗、
言葉のない絶句の世界。キレイごとどころかキレイごとにもならない東京の政治に、誰も見向きもしなくなった現場。自分が「頑張ります」としか言いようのな
い世界、それが現場。「大衆と共に」だ。
佐 野さんは原発の歴史にふれつつ、「正力松太郎の巨大な掌の上での安穏な暮らし」を問いかけている。プロ野球もテレビも原子力も正力の天才的プロモー ト・・・・・・。戦後とは、繁栄とは・・・・・・。あくまで被災者を思う心の深さがあるかどうか・・・・・・。根本的な問いかけを本書はしている。
 王敏さんの「<意>の文化と<情の文化>」「ほんとうは日本に憧れる中国人――『反日感情』の深層分析」など、日中の比較文化研究はきわめて良い。日中とも人々には同文同種の思い込みがある。姿も容貌も似ているうえ、漢字や儒教の教養も互いにあると思い込む。2000年の交流の歴史もあるが、王敏さんは「文化の相違に関する鈍感」「それがズレとなる」とし、「異文化として認め合う基本の欠落を埋めよ」という。
王敏さんの「<意>の文化と<情の文化>」「ほんとうは日本に憧れる中国人――『反日感情』の深層分析」など、日中の比較文化研究はきわめて良い。日中とも人々には同文同種の思い込みがある。姿も容貌も似ているうえ、漢字や儒教の教養も互いにあると思い込む。2000年の交流の歴史もあるが、王敏さんは「文化の相違に関する鈍感」「それがズレとなる」とし、「異文化として認め合う基本の欠落を埋めよ」という。
日本は1年 ぶりで会った時でも、お世話になったことを感謝する言葉を添えるのが挨拶の基本だが、中国の感謝はその時、その場で行うものであり、後日会った時は謝意は 言わない。繰り返しての感謝は水臭い、親しいからこそ再三の感謝は避ける。しかし、お詫びの言葉は繰り返すことが多い。「前事不忘」の意味はそうしたこと だと、指摘する。
「美 の感性優先の思考」「原理原則のない感性の世界」「無思想、無哲学の国」――そうした真似る日本。「鉄面皮の中国と変節する日本」「西洋化へ雪崩れる、変 わり身のすばやい日本、西洋化を恥とし、敵視した中国」「阿倍仲麻呂に見る望郷・ふるさと(景色・山河)、ふるさとに執着しない中国人(中国人がふるさと で想起するのは人、家族)」「愛国心の差異」――など、丹念に描いている。
 戦後の混乱期に「野球」の夢を追いかけた人たちの物語。日本リーグを立ち上げ、「日本ワールドシリーズ」の開催を考えた藤倉、そしてかつての下手投げ名
投手・矢尾、米国のニグロリーグの大スター・ギブソンとペイジ。日米の戦争のなかで、野球があるゆえの人種を越えた友情。黒人として初の大リーガー、
ジャッキー・ロビンソンのドジャースでのデビュー。
戦後の混乱期に「野球」の夢を追いかけた人たちの物語。日本リーグを立ち上げ、「日本ワールドシリーズ」の開催を考えた藤倉、そしてかつての下手投げ名
投手・矢尾、米国のニグロリーグの大スター・ギブソンとペイジ。日米の戦争のなかで、野球があるゆえの人種を越えた友情。黒人として初の大リーガー、
ジャッキー・ロビンソンのドジャースでのデビュー。
 辛亥革命(1911年)から100年。「君は兵を挙げたまえ。我は財を挙げて支援す」――梅屋庄吉が孫文を生涯、支援した資金は、今でいえばなんと1兆円
とも2兆円とも。辛亥革命後のクーデターで失脚して亡命した孫文と宋慶齢の結婚式も、新宿区百人町の梅屋庄吉の広大な邸宅で行われる。
辛亥革命(1911年)から100年。「君は兵を挙げたまえ。我は財を挙げて支援す」――梅屋庄吉が孫文を生涯、支援した資金は、今でいえばなんと1兆円
とも2兆円とも。辛亥革命後のクーデターで失脚して亡命した孫文と宋慶齢の結婚式も、新宿区百人町の梅屋庄吉の広大な邸宅で行われる。
 時は1500年台前半。北条氏の風摩小太郎、扇谷上杉氏の曽我冬之助。武田氏の山本勘助――この三人が関東の支配権をめぐって鬼神のごとき死闘を繰り広げ
るが、本書はその助走。主人公は早雲庵宗瑞(後の北条早雲)が見出した逸材・小太郎。「人材は見つけるもの」といわれるが、息子・氏綱の子である千代丸の
代になっての軍配者として小太郎を育てる。20年、30年後のことを考えてだ。
時は1500年台前半。北条氏の風摩小太郎、扇谷上杉氏の曽我冬之助。武田氏の山本勘助――この三人が関東の支配権をめぐって鬼神のごとき死闘を繰り広げ
るが、本書はその助走。主人公は早雲庵宗瑞(後の北条早雲)が見出した逸材・小太郎。「人材は見つけるもの」といわれるが、息子・氏綱の子である千代丸の
代になっての軍配者として小太郎を育てる。20年、30年後のことを考えてだ。

