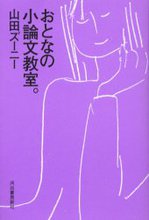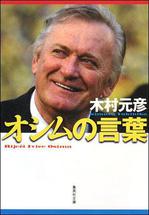 オシムの言葉には、ユーモアがあり、思想があり、したたかな戦略的読みがある。しかし、その底にはスラブの哀愁と多民族共存の良きサラエボが、生死をかけた戦乱の地となった悲しみが沈殿している。監督には孤独がついて回るが、オシムの独特さは、多民族国家ユーゴスラビアの崩壊と民族闘争、そして何十年前から続いている国家紛争で死線を歩いたいわば宗教的境地によってつくられたのではないのか。
オシムの言葉には、ユーモアがあり、思想があり、したたかな戦略的読みがある。しかし、その底にはスラブの哀愁と多民族共存の良きサラエボが、生死をかけた戦乱の地となった悲しみが沈殿している。監督には孤独がついて回るが、オシムの独特さは、多民族国家ユーゴスラビアの崩壊と民族闘争、そして何十年前から続いている国家紛争で死線を歩いたいわば宗教的境地によってつくられたのではないのか。
「他人の評価や、メディアの賞賛に興味がない、反俗的な本質追求の人」というのは、生きてきた世界に当然、関係があろう。
「私のサラエボが戦争にあるのに、サッカーなどやっていられない」「選手を先入観で見ない。すべて平等に扱う」「サッカーの試合とは絶対一人では成立しない。君たちの人生も同じじゃないか」「休みから学ぶものはない」「重要なことはミスをして叱っても使い続けることだ。選手はミスを恐れてリスクを冒さなくなってしまう」――失点を恐れず走り回って攻め続ける「リスクを冒しても攻めろ」というオシムのサッカーは、悲しみを抱きしめて未来を切り開いたオシム氏の生き方なのか。
 日本は安定的な国であったが、なぜ豊かになったのに、景気も回復しているというのに不安や不満が高まっているのだろうか。
日本は安定的な国であったが、なぜ豊かになったのに、景気も回復しているというのに不安や不満が高まっているのだろうか。
本書では人生前半の社会保障と定常型社会が大きなテーマになっている。わが国は、限りない経済成長=生産の拡大が背景となって、完全雇用が達成されていたし、それとあいまって、終身雇用の会社と強固で安定した家族という共同体による"見えない社会保障"があったと広井さんはいう。それが日本の安定を支えたわけだ。
しかし、経済成長に限界があり、雇用の流動化が起き、会社もまた激変・盛衰にさらされ、家族の迷走が起き、しかも、高齢化が加速された時、社会に不安・不満が起きることは必然である。放り出された高齢者は脆弱な存在となり、働くものには不安と不満がうっ積する。
そうすると、事後対応的な福祉政策ではなく、福祉概念を雇用、そして人と人との絆をもつ地域といった創造的かつ広範なものにしなければこの国はもたない。そこで焦点となるのは、人生前半の社会保障ということになる。教育の深さこそが未来の社会を決定づけ、教育の強化こそが失業対策にも、国際競争力の強化にもつながり、高度成長時代の上昇志向の教育ではなく、人間の豊かさの為の教育が大事となる。格差の最大の要因の一つは、教育であり、20代前後の若者にもっともっとチャンスを与える支援が必要だ。
また福祉社会は人と人との関係のあり方にカギがあるとし、「福祉政策と環境政策の統合」などにもふれている。
 「油断」「団塊の世代」「知価社会」・・・・・・。
「油断」「団塊の世代」「知価社会」・・・・・・。
堺屋さんの著作にふれ、読み続けてもう30年になる。国会でも予算委などで論戦し、また、数多くの示唆・指導もいただいた。
世代と時代の構造的分析は見事だが、いよいよ団塊の世代が定年を迎える。暗い少子高齢社会ではなく、「自由な労働力」が、選択と自由にあふれた多様な知価社会にどう挑むか。
「官僚主導・業界協調体制」「核家族・職縁社会」「日本型経営(経営雇用、年功序列、企業内労組)」のエンジンとしての団塊の世代が、武者不用のゼロサム時代に、なげき節(武士)とならない自己革新を果たせるか、そして政治はその受け入れ態勢をつくれるかどうか――知恵があふれた書である。
- 1