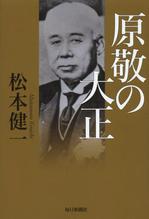 「日本の近代史で最も重要な人物五人を挙げるとすれば、福沢諭吉、西郷隆盛、原敬、北一輝、昭和天皇だろう」と松本健一さんはいう。
「日本の近代史で最も重要な人物五人を挙げるとすれば、福沢諭吉、西郷隆盛、原敬、北一輝、昭和天皇だろう」と松本健一さんはいう。「原敬(たかし)が直面したのは近代民主政治、つまり主権在民の政治と主権が天皇に在る明治憲法との矛盾である」「北一輝という革命的ロマン主義者と原敬という稀有な保守的現実主義者との対立は、大正という時代の矛盾そのものであったかもしれない」「原敬はまさしく、現実をあるがままに見るリアリズムの政治家であった。そして、その現実主義のうえに立って国家統治をプラグマチック(実務的)に処理していこうとした」「国家は伝統(道徳や宗教や慣習)を引き受けつつ、漸進的な改革を行い、そのことによって社会秩序を維持しなければならないというのが、彼の保守主義であった」「大正時代に最初の政党内閣を組織した原敬は、西洋近代文明を議会、民主主義、政党政治で具体化、定着させた。藩閥政治を抑え軍閥政治の危険性を見抜き、軍部が天皇の名を利用し独走するのを防ごうとした」――。
明治維新から明治、そして立憲政体、国会開設運動。大隈重信、伊藤博文、陸奥宗光、山縣有明、西園寺公望、後藤新平、桂太郎・・・・・・。原敬の「政治は力である」は政党に結集する力を源泉とするが、藩閥と戦い、寺内内閣のシベリア出兵と戦いつつも、時には現実主義の欠陥もさらけ出す。激流の時代のなかで、堅固な意思と柔軟性をもって厳と立つ丈夫あってこそ社会の安定は築かれる。そして大正から昭和へ。大衆共存党(永井柳太郎)に現われる無産大衆の生活不安からの解放を志向するファシズム革命思想の流れのなかから大正10年の安田善次郎刺殺、原敬暗殺が生まれたという。凄みを感ずる大作、力作だ。

