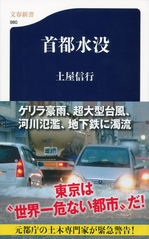
「水は低きに流れる」――。当たり前だが、それゆえに東京は水害には古来より地形的にも脆弱だ。加えて地下水汲み上げ等によってゼロメートル地帯が広がり、かつ多数の地下鉄・地下街がはりめぐらされている。さらに気象変動によって今世紀末には世界平均海面水位は最大82cm上昇(IPCC)、豪雨、スーパータイフーンが予想され、首都直下地震の切迫がある。
問題は河川堤防の決壊による「外水氾濫、大河川氾濫洪水」、台風とともに海の水が襲ってくる「高潮洪水」、降った雨が排水できずに溜まり続ける「内水氾濫」、そして地震によって水門・堤防が破壊される「地震洪水」の4つだ。
家康の利根川の東遷、荒川の西遷に始まり、東京の三大水害という明治43年の「東京大水害」、大正6年の「大海嘯」、昭和22年の「カスリーン台風」に対して、どう対処をしてきたのか。荒川放水路、江戸川放水路から命山としてのスーパー堤防等を詳述する。そして「東京の場合は、大潮の満潮時にゼロメートル地帯の堤防のどこか1か所を破壊するだけで、首都が水没し、地下鉄、共同溝、電力通信の地下連絡網のあらゆる機能が失われる。日本沈没だ」「ゼロメートル地帯の治水対策とは"洪水対策"であり、住民にとって逃げられる"命山"であり、そして日本にとっての"安全保障"なのだ」という。東京都の土木専門家として実際に治水をはじめとして防災を担い続けた現場からの専門家の意義ある書だ。

