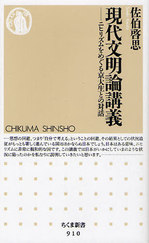 現代文明の病――それはニヒリズムであり、ニヒリズムはヨーロッパの歴史そのものだ、と佐伯氏は言う。
現代文明の病――それはニヒリズムであり、ニヒリズムはヨーロッパの歴史そのものだ、と佐伯氏は言う。それではニヒリズムとは何か。それは至高の諸価値がその価値を剥奪されて無意味となることであり、最高の諸価値の崩落である。ニーチェは、世界の虚構性を暴き、統一の崩落、目的の崩落、真理の崩落の3つをニヒリズムの形態としてあげる。その崩落感を避けようとすれば、意味を問わない、物事の底を問うなということになる。しかし、人は無価値の世界に住むことはできないがゆえに、生命尊重主義、自由平等、個性の尊重など新たなフィクションをつくり出す。
20世紀に入り、近代の超克が、問題となったが、ハイデガーは「存在するもの(存在者)」に意味を与えようとする。死を先取りした現在の意味付け、決断だ。一方、日本の思想は西欧は有、存在の思想に対して無の思想だ。無が存在を支えているがゆえに、我々は深刻なニヒリズムに陥ることはない。佐伯さんは日本思想のもつ可能性を示す。
本書は「ニヒリズムをめぐる京大生との対話」という副題をもち、マイケル・サンデルの白熱授業に類して学生との対話を行なっているが、奥行きは東洋思想にも及ぶだけに深い。
私は、「有と無」で「空」、「存在と時間」で「常住と無常の法」に思考が及ぶ。ニーチェは"客観的真実は存在しない。あるのは1人1人の解釈(どう意味をもたせるか)である"というが、それには意識と無意識、仏法の九識論を考える。

