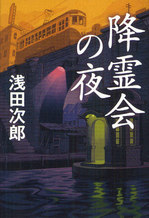 この小説は、人生を考えさせる。人間は、我の世界を生きるとともに、我々の世界を生きるがゆえに仏典では「人間(じんかん=人と人との間)」という。浅田さんは、「人生を生きよ」「生きることに気付け」「高度成長時代というのは生きることに気付かない、慌しさに身を委ねてしまう時代だ」と言っているようだ。問題を正視せず、日常に流され、忙しさに逃避する。
この小説は、人生を考えさせる。人間は、我の世界を生きるとともに、我々の世界を生きるがゆえに仏典では「人間(じんかん=人と人との間)」という。浅田さんは、「人生を生きよ」「生きることに気付け」「高度成長時代というのは生きることに気付かない、慌しさに身を委ねてしまう時代だ」と言っているようだ。問題を正視せず、日常に流され、忙しさに逃避する。人の歩み自体が業を生み出し、業を背負っていく。しかしそんなことに気付くはずがない。業の自覚に鈍感な人間をつくり出し、生のみあって死を正視できないのが高度成長の時代だ。
1951年(昭和26年)、浅田さんは生まれている。まさに戦後だ。小説の設定も昭和26年生まれの男性(ゆうちゃん)が主人公となる。昭和35年、小学生の時、一人の転校生キヨと出会う。あの戦争を背負い続ける父親に"あたり屋"にされ、突き放されてダンプに衝突して死ぬ。貧しい親子。悲しい。高度成長は皆が豊かになっているようで、"たまたま時代に乗れた者"と、"たまたま乗れなかった者"をむごくも浮き彫りにしてしまう。
大学生となった主人公は、高度成長の日常を仲間とともに体現する。仲間である安易さから、主人公に恋する真澄の心を感じられない。彼女は死ぬ。
そして、降霊の儀式ではじめて業に気付き、世間にはけっして見せない人の心に沈潜する悲しみに気付くのだ。死者の言葉を聴いて。高度成長が哲学を不在にするベクトルをもち、「社会の繁栄が個人の幸福を約束する大いなる錯誤の中」で、高度成長の申し子たちは生き、流されてしまったことを。「変容と発展を錯誤したこと」を。そして人の幸福は、人と人との間、人間の中にあることを。同じ高度成長の時代を生きてきた者として、この小説は人生を振り返り、人生を考えさせてくれる。

