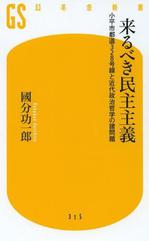
「小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題」と副題にある。「近代の政治理論は主権を立法権として定義している」「そして現代の民主主義において民衆は、ごくたまに、部分的に、立法権に関わっているだけだ」「しかし、より大きな盲点は、実際の政治・政策の決定が、議会という立法機関(国民主権の行使の場)ではなくて、執行機関に過ぎないはずの行政機関においてなされている。議会ではなくて役所でなされているということだ」「行政が全部決めるのに民主主義社会と呼ばれ続けている、ということだ」――。さらにそのうえで、ボダンやホッブスやルソーにおいて、主権が立法権として定義されている事実を示しつつ、「現代の危機は、単に民主主義や人民主権の危機なのではなく、主権の危機である。・・・・・・統治は本質的に、法や主権から分離していく可能性を孕んでいる(大竹弘二氏)」。「主権による立法によって統治を完全に制御することなど不可能であり、行政は行政自身で統治のために判断し、決定を下す」ことを明らかにする。現代議会制民主主義の盲点、欠陥だ。
そして、いくつかの提案がされている。「制度が多いほど、人は自由になる(ドゥルーズ)」「住民投票制度についての4つの提案」「審議会などの諮問機関の改革」「諮問機関の発展形態としての行政・住民参加型のワークショップ」「パブリック・コメントの有効活用」・・・・・・。議会制民主主義に強化パーツを足して補強する。それがジャック・デリダの「来たるべき民主主義――民主主義は実現されてしまってはならない、民主主義は目指されなければならない」が志向の線上にあるとする。
「政治家―官僚―民衆」を議院内閣制のなかで常に考える日々だが、本書は近代政治哲学の重大な欠陥を住民運動の実践と思索のなかで剔抉してくれている。

