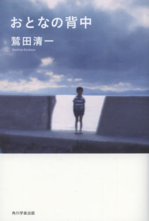
「如実知見」「諸法実相」――本書の哲学者の思考にふれて私の感じたことだ。「哲学は人間学だ」とつくづく思う。大人の人間学、熟練・練達の人間学だ。「教育」「育てる」ということは、教えるのではなく、「伝える」こと。背中で・・・・・・。「期待のされすぎはなぜしんどいのか」「期待のされなさすぎはなぜしんどいのか」――期待の過剰と期待の過小の社会。資格が問われ、選別されてばかりの社会。存在をかき消されてしまう社会。そのなかで人は自分の存在を「できる・できない」の条件を一切つけないで認めてくれる人を求め、溺れているかのようだ。複雑・多様・正解のない現実をどう受け容れるか。独立ではなく自立を、不如意への「耐性」が必要だという。
「文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増す(寺田寅彦)」「この国のほとんどの人は飢餓や戦争をはじめとして、生存が根底から脅かされるような可能性を考えないで生きている」「現代の都市生活はじつはたいへんに脆い基盤のうえに成り立っている。ライフラインが止まれば、人は原始生活どころかそれ以下に突き落とされる」「人は、その生活を"いのちの世話"を確実に代行するプロフェッショナルに委ね、自分たちでやる能力をしだいに失い、とんでもない無能力になっている」――。2007年以降、新聞や雑誌に寄せたエッセー集。いずれもどっしりして、根源的に考えさせられる。

