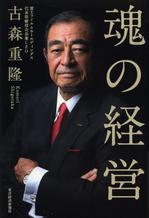
「ミネルバの梟(ふくろう)は黄昏(たそがれ)に飛び立つ」――ヘーゲルの「法の哲学」の言葉だが、私も哲学の、時代総括と次代への備えについて時おり語ってきたものだ。それが富士フイルム先進研究所のシンボルということに心が躍った。その哲学的深さと、勇気ある挑戦があるゆえに、写真感光材料の全盛時代の黄昏から新たな創造を生み出す。デジタルカメラの登場、デジタル化時代の襲来、本業消失の危機を乗り越えたのだと思ったからだ。
「技術志向の富士フイルム」「現実を見る勇気、将来に投資する覚悟」「富士フイルムは写真文化を守る」「富士フイルムが手がける医療、化粧品の理由」「勝ち続ける企業は、変化にすばやく、うまく対応できる企業であり、そこからさらに進んで、変化を先読みし、先取りできる企業でなければいけない」「巨人コダックと富士フイルムを分けたもの」「有事のリーダーシップとそれに伴う責任」「ナンバーツーまでの勝負は竹刀、経営トップの勝負は真剣」「日本の製造業は技術力、人材力、成長ポテンシャルがあり、負けていない。日本人には頑張リズムがある」「PDCAよりSee‐Think‐Plan‐Doだ」――。
日本の課題として、日本企業のSGA費(販売費及び一般管理費)の高さをあげている。それは「ホワイトカラーが多すぎる。管理職も多く、現場で働いている人の数よりも、間接部門の人員が多い企業もある」としている。これはモノづくりをはじめ、日本の遭遇する最も深刻な問題だと私は思っている。日本の労働生産性の低さにもかかわることだ。現場力、業務遂行力の劣化も課題として指摘している。
間違いなく、「勇気」を届けてもらった。勇猛精進(敢(い)さんで為すを勇と曰い、智を竭(つ)くすを猛と曰い、無雑の故に精と曰い、間(たえま)無き故に進と曰う)が本書には貫かれている。

