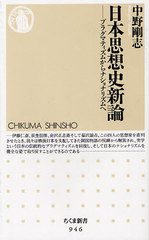
「本書は、戦後日本を支配してきた開国物語を破壊しようという企てである」「本章では、福沢の実学というプラグマティズムもまた、水戸学と同様に、国際問題に応用されることでナショナリズムとして現われたことを示したい。そのためには、福沢諭吉の文明論が尊王攘夷論と対立するものであるという通説を破壊することから始めたい」「伊藤仁斎、荻生徂徠、会沢正志斎そして福沢諭吉。この四人の思想家を直列させたとき、我々は戦後日本を支配してきた開国物語の呪縛から解放され、実学という日本の伝統的なプラグマティズムを回復し、そして日本のナショナリズムを健全な姿で取り戻すことができるのである」――。日本思想の系譜を掘り起こしつつ、剛速球を投げ込んでいる。
明らかに問題意識としてあるのは、戦後日本とは何か。当然のことのように語られる"開国"とは何か。西欧が迫り来る幕末において、「対立軸は『攘夷vs.開国』『鎖国vs.開国』ではなく『避戦vs.攘夷』であった。すなわち事なかれ主義で平和の維持を求めるか、あるいは積極的に国家の独立を維持しようとするかであった(攘夷・開国か避戦・開国か)」など、かなり根源的なものだ。そして「尊王攘夷とは」「攘夷論の源流と古学」「会沢正志斎の『新論』で初めて登場する国体とは」「皇統、政統とは」「水戸学のナショナリズムとは」「福沢の攘夷論と"一身独立して一国独立する"(国の独立は即ち文明なり)」・・・・・・。日本思想、保守思想の水流・水脈を観ずることができる。

