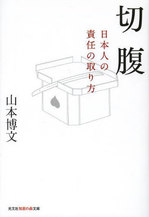
江戸時代特有でもある「切腹」は、「武士の身分的矜持」と、それを支える「主君の絶対性」による。「殿中刃傷事件――大石内蔵助ら46人の切腹など」「宝暦木曽川治水工事 薩摩藩・平田靱負の切腹」「刑罰としての切腹」「御家騒動と切腹」など、具体的実例をあげながら、日本のいわゆる"武士道"といわれるものと、江戸時代を浮き彫りにする。
「武士は失敗があれば腹を切るものという観念があったので、不祥事があれば進んで切腹する者もあり、上から強要された場合でも潔く腹を切った。個々の武士の倫理観は日本人の責任感の強さを示すものとして高く評価できる。しかし、上に立つ者がその倫理観を利用して、自らの責任を逃れようとした事例が目立つ。現在でもそうした傾向はあるが・・・・・・」「江戸時代、切腹に追い込まれた武士を見ていると、本当に悪い事をしている者はそれほど多くない」という。「葉隠」の冒頭「武士道と云(いふ)は死ぬ事と見付けたり」とは、「常住死身」の覚悟、心構えを述べたものだと指摘している。
いわゆる"詰め腹"――現代社会の責任のとり方を再度考えさせてくれる。

