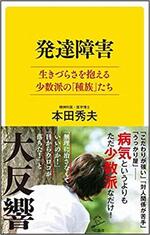 副題は「生きづらさを抱える少数派の『種族』たち」。本田秀夫氏は、信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ診療部部長。東大医学部を卒業、長きにわたって発達障害の臨床と研究に従事し学術論文も多数、日本自閉症スペクトラム学会常任理事。
副題は「生きづらさを抱える少数派の『種族』たち」。本田秀夫氏は、信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ診療部部長。東大医学部を卒業、長きにわたって発達障害の臨床と研究に従事し学術論文も多数、日本自閉症スペクトラム学会常任理事。
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)――。発達障害はこれらなど数種類の障害をまとめた総称だが、じつはそれらの種類のいくつかが重複している人がかなり多い。重複すると複雑な現れ方をして十分に理解されなくなってしまう、という。ASDには「対人関係が苦手」で「こだわりが強い」という特徴があり、ADHDは「うっかりミスが多い」「落ち着きがない」という特徴があるが、「障害(D)」とまではいかず、「AS+ADH」な人たちがかなりいる。「特性は0.5+0.5」「だけど悩みは2以上になる」と理解されないで苦しんでいる人がいるという訳だ。
「発達障害には強弱がある。特性自体は必ずしも障害となるものではないが、生活のさまざまなバランスのなかで支障となったときは、ASDやADHDの特徴として現われてくる」「"オタク"とASはどう違うか。ASの特性がある人は、こだわりと対人関係を天秤にかけた時、こだわりを優先する。オタクの人はこだわりと対人関係を天秤にかけて調整できる(世の中には社交上手なオタクもいる)(映画を見てもケーキを共に食べてもASの人は知識をとことん追究し、内容重視の会話をし、交流重視ではない)」「"うっかり屋"とADHの不注意は違うのか――ミスの多い状態を、本人やまわりの人が『まあいいか』と思える程度であればADHDに該当しない(理解されていくか、"きわめて深刻な問題"として理解されていくか、帳尻が合うかどうか)」・・・・・・。そして自分の「発達の特性」を知っておこうと、11項目を提示する。「ASの①臨機応変の対人関係が苦手②こだわりが強い」「ADHの不注意、多動性・衝動性」「LDの読む、書く、計算が苦手」「DCDの運動、手作業が苦手」「チック、知的発達が遅い」だ。それに対して「生活環境を整える環境調整をする。本人も周りも」「自分の『やりたいこと』を優先する、やりすぎて無理をすることもあるが、"やりたいこと"と"やるべきこと"を分け、調整する」など、11項目についての「環境調整」を具体的に提示している。
更に、「発達の特性を『~が苦手』という形で、なんらかの機能の欠損(病気)としてとらえるのではなく、『~よりも~を優先する』という『選好性の偏り』としてとらえた方が自然」「発達の特性と"ふつう"の間に優劣はない。あるのは多数か少数かという割合だけ」「多数派向けに組み立てられている生活を少数派向けに調整すれば、生きづらさは軽減する」とし、本人や家族や友人・関係者の生活環境の調整を求めている。なにかができない"障害者"というより、独特のスタイルをもつ「種族」のようなものとしての理解を、と結んでいる。

