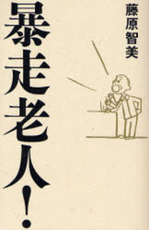 突然、怒鳴り始めた老人に出会った人は確かに多い。老人の暴走というより、若者よりも老人がキレるようになったことをどう解釈するか。まさに藤原さんは「人と人とのかかわり方の根底的な変化」を社会分析する。自分自身ではないかと危機感をもった。
突然、怒鳴り始めた老人に出会った人は確かに多い。老人の暴走というより、若者よりも老人がキレるようになったことをどう解釈するか。まさに藤原さんは「人と人とのかかわり方の根底的な変化」を社会分析する。自分自身ではないかと危機感をもった。1つは「時間」――「待つこと」の耐性に欠ける大人の増加。待つことが苦手、せっかちで先を急ごうとする。待つことのトラブルの増加。待つことが当然だった社会が「待たされることに苛立つ社会」になった。時間帯・スケジュール・帯グラフ人生、どうものんびりと日向ぼっこするおだやかな老人でなくなっている。競争社会を猛烈にスケジュールで来た、しかも指導的立場にあった人がリタイアしてもその感覚は身体に染み込んでいる。自分の時間を奪われることへの怒り。音楽、スポーツ、読書、情報、新しい態度を身につけないと、時代不適性の新老人となる。そしてそれはIT社会から取り残され、焦りと孤独を生む。
2つめは「空間」――地域社会が非地域社会となり、孤独、家自体も個室化する。臭気の攻撃で社会を攻撃するゴミ屋敷、騒音に対するイラダチ、家庭に居場所がない。
3つめは「感情」――社会のマナー、常識のコードが日々更新され、順応できない老人は情動を爆発させる。患者や生徒は「お客様」で医師も教師もサービス業になってしまった。サービス社会では笑いも表情管理、労働となる。クレーム社会だ。

