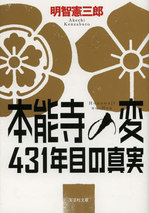
「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」(ビスマルク)――歴史はたしかに勝者が、自分の経験を正当化しがちなものだ。それは真実ではない。明智憲三郎氏は、光秀の子・於寉丸(おづるまる)の子孫。
本書は「本能寺の変」の真実に文献をもって迫るが、その大きな背景として「光秀謀反」「利休切腹」「秀次切腹」は、いずれも信長、秀吉の「唐入り」があるとする。皆が反対するなかでの絶対者の強行姿勢に対して、その阻止のために謀反が企てられた、という。
本能寺の謀反は、光秀の個人的な野望と、残忍な信長への怨みによるものであり、光秀の単独犯行である――こうしたのは秀吉が「惟任退治記」を公式発表してつくり上げたものだ。それを示すとした「時は今あめが下しる五月かな」は、「下なる」が真実で、改竄されていた。光秀は、信長の天下統一と、長期織田政権構想の下では、大名は領地没収と遠国への移封(唐へも)は避けられない。土岐氏としての存続には、迫りくる長宗我部征伐の阻止を何としてもしなくてはならない(信長の長宗我部征伐の発令は5月7日)――こう考えた。突然でも何でもない。同じ5月、信長は家康討ちを計画した。そして光秀は家康と談合して謀反同盟を締結した(5月14日~17日)。その謀略は生きていたが、秀吉軍が予想外の早さで京都に迫り、家康の西陣は遅れた。秀吉は信長の長期政権構想を潰すために、光秀の決起をいわば待っており、事前に本能寺の変を予期していた形跡がある(細川藤孝父子)。勝者のつくった史観は、「太閤記」をはじめとして、どんどん流布していった。明智さんは、文献にあたって裏付けていく。
「利休切腹」も「秀次切腹」も短文だが、「唐入り」問題から解読する。興味深い。

