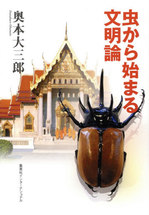
驚嘆すべき本だ。きわめて易しく、目の前がパッと開ける面白い本だが、その思考は、虫の世界から世界各地へ及び、日本の文明から世界の文明へ、日本文化から欧米文化へ及び、微小の生命空間は宇宙生命空間へと広がる。
私も思えば子供の頃、春はつくしんぼを採り、野イチゴを摘み、夏休みは昆虫採集、川で魚をとった。近所の仲間といつも広場で遊んだ。生活は季節のなかに、自然とともにあった。奥本さんは、それが大事なのだ。日本人はそうして小さなものを細かく見る眼、いわば接写レンズの眼を磨いてきたのだという。
「第一部 虫の世界」「第二部 人の世界」を通じ、次から次へと風土と人間と文化(あるいは宗教)が開示され、展開する。ヴェルレーヌ作の詩「落葉」(上田敏訳)について、穏やかで晴天が多く、そぞろに寂しくもある日本の秋と、フランスの厳しい冬を前にしたつかの間の重苦しい凄絶ともいえる秋の違いを示す。虫や自然、詩や絵画を例示しつつ、「日本に風景画はあったのか」「ルイ・ヴィトンはなぜ日本でよく売れるか」などで結ぶ。面白くて心が躍った。

