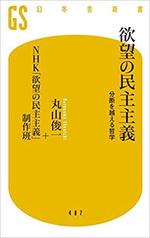 NHK、BS1スペシャル「欲望の民主主義~世界の景色が変わる時~」で、「世界の知性」たちへのインタビューを行った記録。副題は「分断を越える哲学」。問題意識は、英のEU離脱や米のトランプ大統領誕生、そして仏の急進的な右翼の台頭、世界で頻発するテロ・・・・・・。このなかから世界の民主主義に何が起きているかの問いかけだ。民主主義の劣化、熱意の希薄化、破壊衝動、ネット社会の影響、グローバル化、分断の構図、人間の欲望と集合体の社会などを考察する。
NHK、BS1スペシャル「欲望の民主主義~世界の景色が変わる時~」で、「世界の知性」たちへのインタビューを行った記録。副題は「分断を越える哲学」。問題意識は、英のEU離脱や米のトランプ大統領誕生、そして仏の急進的な右翼の台頭、世界で頻発するテロ・・・・・・。このなかから世界の民主主義に何が起きているかの問いかけだ。民主主義の劣化、熱意の希薄化、破壊衝動、ネット社会の影響、グローバル化、分断の構図、人間の欲望と集合体の社会などを考察する。
いずれの「知性」からもホッブス、ルソー、トクヴィル、そして現在が語られる。「万人の万人に対する闘争」を回避するには、自らの欲望を制御し、畏怖する「リヴァイアサン」を打ち立て、国家と契約を結ぶことによって秩序を回復する。ホッブス、ルソーの国家・主権・自由の原始的概念だ。トクヴィルが発見した米の民主主義の良質の部分、中間共同体・市民団体等の活動が、ツイート・ITで崩される現実も語られる。民主主義が衆愚政治や多数者の専制(少数派の抑圧)に陥ることを警戒したベンサムやミルも今、蘇る。
「世界は存在しない。一角獣は存在する」といったマルクス・ガブリエル。「超越した世界」という存在こそが対立を生む。世界を実体化する危険性は、対話のない無数の"正義"の主張の氾濫を生む。ガブリエルは「民主主義とは悪を認識して正す手続き」「倫理観の進歩に照らし合わせて、法律自体を改正すべきです」「民主主義は社会の倫理観の進歩を実践に照らしたもの」「民主主義は、手続きや制度の中で普遍的価値を実現しようとする試み」といい、「民主主義の世界的価値観が崩壊したら、見たこともない規模の戦争(暴力)の世界を目撃する。(民主主義は)今のところ人間がみんなで生き残るための唯一の選択肢」という。民主主義のポテンシャルを引き出せるかどうか、ということだろう。
グローバル化、共同体に参入してくる外国人・移民、格差の拡大、共同体からの孤立化になりかねないIT・AIの時代、代表制民主主義に内包される代表者と有権者のズレ(民主主義の隙間風)、民主主義の主人公でなく阻害されていると感じる者の増大と分極化・・・・・・。「自分たちのことは自分たちの手によって決める。政治参加で世を変える。弱肉強食の世界を避ける」――「自分とは異なる存在を欲望することで自らの欲望を実現する」「民主主義とは自らを問うものだ」との識者の発言は重い。
4月12日、沖縄市に行き、沖縄市長選挙(4月15日告示、22日投開票)に立候補するくわえ朝千夫現市長の総決起大会に出席し、挨拶をしました。
これには、自民党の竹下亘総務会長、公明党の遠山清彦衆院議員のほか、自民、公明、維新の国会議員、県会議員らが駆け付けました。
私は「くわえ市長は沖縄県、沖縄市の大きなエンジンである」「政治は結果。仕事をすることだ。この4年間で幼稚園給食の導入、子ども医療費無料化の小学校3年までに拡充、そして、2023年にFIBA バスケットボールワールドカップの沖縄市に誘致など実績は豊富」「一万人のアリーナ建設は市発展の起爆剤になる」と訴えました。
くわえ朝千夫市長は「東部海浜地区開発や一万人規模アリーナ建設し、市の発展とともに子どもたちに夢と希望を与えたい」と切々と訴えました。
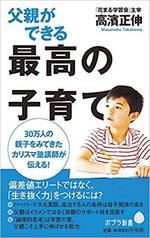 テレビで講演を聞いたこと、さらに「読解力」「意味を考える力」をどう獲得するかを考えていたこともあって、高濱さんの本を読んだ。2050年以降も「生きる」今の子どもが「生き抜く力」を身につけるにはどうしたらよいか。父親の役割は大きいようだ。
テレビで講演を聞いたこと、さらに「読解力」「意味を考える力」をどう獲得するかを考えていたこともあって、高濱さんの本を読んだ。2050年以降も「生きる」今の子どもが「生き抜く力」を身につけるにはどうしたらよいか。父親の役割は大きいようだ。
まずは、「家庭での父親の第一義的仕事はあくまで『妻を笑顔にすること』、そして『母親が安心して育児に取り組めるように支えてあげること』」という。子どもの心身の成長、学力の伸びは、妻の笑顔からということだ。とくに父親は「正しい会話、意味のある会話を日常的に心がけること、論理的思考を伸ばすこと」に努めることだ。言葉の厳密さは学力に比例し、言語感覚は日常会話でしか培われない、という。
妻からの相談ごと、会話には、「解決してあげる」と思わないで「寄り添う」「共感」「聞くこと」にこそ価値がある。そして、「子どもに何かひとつ自信をもたせること」を養うことが大切であり、「子どもの自信、生き抜く力は、親が養ってあげるもの。照れずに本音でぶつかること、取り組むこと」を示す。




