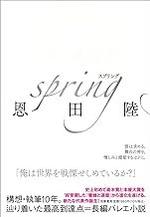 「俺は世界を戦慄せしめているか?」――。構想・執筆10年、著者が「今まで書いた主人公の中で、これほど萌えたのは初めてです」と言った注目のバレエ小説。一人の天才バレエダンサーにして振付家を、関わった周囲の人々の視点から、また本人の心の内から描く。バレエの世界から、宇宙の生命と小宇宙たる人間の生命との共鳴、見えざる世界と「カタチ」ある世界との連続的一体性。そのあわいの世界を身体性を持って表現仕上げる歓喜が伝わってくる。「もはや、身体は反射のみで動いている。ゾーン、来た。・・・・・・まるで、全身が、皮一枚の器になったみたいだ。俺の中心から何かが放射され、どこまでも広がっていくのと同時に、全てが集中線のように集まってくるようにも感じている。なんなのだ、ここにいるのは? 人間でもなく、動物でもなく、なんらかのただの生命体。エネルギー。物理的な運動。事象。現象。摂理。法則。いる、ただ居る、空間を占めている。もはや、何者でもなく、踊りそのものになっている。踊っているという自覚すらなく、俺という人体の輪郭だけがあって・・・・・・」「カタチはあった。そして、なかった。同じものだった。見えるもので、同時に見えないものだった。俺はその一部だった。全部だった。満たされた器は無に見える。光射す闇。死のなかの生。どれも皆、等しく同じもの」・・・・・・。バレエの世界に接していれば、さらに面白かろうと悔やまれるほどの迫力だ。
「俺は世界を戦慄せしめているか?」――。構想・執筆10年、著者が「今まで書いた主人公の中で、これほど萌えたのは初めてです」と言った注目のバレエ小説。一人の天才バレエダンサーにして振付家を、関わった周囲の人々の視点から、また本人の心の内から描く。バレエの世界から、宇宙の生命と小宇宙たる人間の生命との共鳴、見えざる世界と「カタチ」ある世界との連続的一体性。そのあわいの世界を身体性を持って表現仕上げる歓喜が伝わってくる。「もはや、身体は反射のみで動いている。ゾーン、来た。・・・・・・まるで、全身が、皮一枚の器になったみたいだ。俺の中心から何かが放射され、どこまでも広がっていくのと同時に、全てが集中線のように集まってくるようにも感じている。なんなのだ、ここにいるのは? 人間でもなく、動物でもなく、なんらかのただの生命体。エネルギー。物理的な運動。事象。現象。摂理。法則。いる、ただ居る、空間を占めている。もはや、何者でもなく、踊りそのものになっている。踊っているという自覚すらなく、俺という人体の輪郭だけがあって・・・・・・」「カタチはあった。そして、なかった。同じものだった。見えるもので、同時に見えないものだった。俺はその一部だった。全部だった。満たされた器は無に見える。光射す闇。死のなかの生。どれも皆、等しく同じもの」・・・・・・。バレエの世界に接していれば、さらに面白かろうと悔やまれるほどの迫力だ。
八歳でバレエに出会い、才能を見出された少年・萬(よろず)春(はる) は、十五歳でドイツにある世界有数のバレエ学校に入学する。バレエダンサー、そして振付家として、伝統ある厳しいバレエの世界の階段を一気に登っていく。その様子が、共に切磋琢磨する友人ダンサー、暖かく支える叔父、幼なじみの作曲家、そして彼自身の四つの視点から描かれ、さらに春を取り巻く様々な人物が彼を語り、天才の驚きの輪郭がくっきりと浮かぶ。「跳ねる(深津純)」「芽吹く(叔父の稔)」「湧き出す(滝澤七瀬)」「春になる(彼自身)」だ。この世の「カタチ」を表現しようとする凄まじい、そして柔らかな天才・春を、それぞれ接した立場から描き上げる。それらの人も道を極めようとする混じりけのない人々だ。
「Ⅰ 跳ねる」――。深津純は言う。「だが、ヤツは違う。基本、ただじいっと周り全体を見ている」「ヴァネッサといい、ハッサンといい、ヤツが学校時代に振り付けた生徒は大出世した」「ヤツの踊りは、圧倒的な生の歓びに溢れていた。宇宙をつかんでいた」・・・・・・。
「Ⅱ 芽吹く」ーー。彼を見出したバレエ教室の森尾つかさ。叔父の稔は、「彼がほとんど無意識に、イナリ(犬)の動きをつかんで『踊って』いた」「そこに、梅の木が立っていた」・・・・・・。驚くことばかり。
「Ⅲ 湧き出す」――。滝澤姉妹の妹・七瀬は作曲、春は振付けでコンビを組み名作を次々生み出す。バレエの天才であるコンビは、ダンサーにも技術的、身体的極致を要求し、異次元の作品を仕上げていく。「聴いてから踊るのでは遅いのだ。一流のダンサーは、音源を自分の中で鳴らす」「アネクメネの制作が始まった。春ちゃんの中では、いつも目まぐるしく何かが動いていて、すごい勢いで流れている。常に新鮮で、生々しい、精神活動(いや、生命活動か?)としか、呼びようのないものが、どくどくと脈打っている」「『遠野物語』ってバレエになんないかな? 河童にしても、ざしきわらしにしても、かの地の人たちに『見えてた』ものは、無意識に共有してた世界観がビジュアル化されたものなんじゃないかな!」「戦慄せしめよ――柳田國男が『遠野物語』で書いた有名な序文の一説。山の民の精神世界の奥深さに里の民よ驚け、みたいなニュアンスだったはずだ」「『アサシン』という題材をずっと温めていた春ちゃん。この世のカタチ、精神のカタチを踊りにする――春ちゃんのテーマは、いつもブレないし、変わらない」「我々は、表と裏の双方から同じものを見ている。情欲の中の戦慄を。殺戮の中の官能を。それらを併せ持つのが人間の性なのだ、ということを。ついに『アサシン』は完成へと突き進む」・・・・・・。
「Ⅳ 春になる」――。「卓越した音楽家やダンサーとそうでない者の違いは、一音、一動作に込められた情報量の圧倒的な違いだ。彼らの音や動きには、単なる比喩でなく、そのアーティストの内包する哲学や宇宙が凝縮されている」と、ハッサンやヴァネッサ、フランツらと接しながら春は思う。そして春は「春は死の季節」と、西行法師の「願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」の歌に触れ思うのだ。「歳を重ねて、老年の境地に足を踏み入れるようになると、年々、春が恐ろしくなる」と。そして、春たちの「春の祭典」の公演が始まる。
バレエ世界の深淵、宇宙へと広がる生命、突き上げる歓喜が伝わってくる。

