
 人生は「縁」が見えるか否かで深さが決まる。不思議としかいいようのない出来事が現実にある。「運」「縁」「命」「天」「自然」「海」「時」「出会い」・・・・・・。
人生は「縁」が見えるか否かで深さが決まる。不思議としかいいようのない出来事が現実にある。「運」「縁」「命」「天」「自然」「海」「時」「出会い」・・・・・・。
舞台は「光と色と音のるつぼで四六時中翻弄されて、心の堤から泥水が溢れ出ようとしている都会」を離れた「豊かな湧水に恵まれ、海に沈む夕日が、実った稲穂を照らす美しい光」の田園広がる富山。
富山の小さな駅に残された一台の自転車。15年前出張で「九州に行く」と言い残して富山で病死した自転車メーカーの社長である賀川直樹。絵本作家として活躍する「娘」の賀川真帆は、「絵本」を通じてできた意外な出会いをきっかけに、"縁の糸"をたどることになる。富山と京都、東京とそれぞれ誠実に生きている家族の運命が交錯する。
「縁の糸」はもつれることがある。「父」の秘密、それを平静のうちにおさめようとする関係の人々。互いが相手を思い、信じ、守り合う心が、誰からも愛される夏目佑樹(直樹と海歩子の息子)に流れ込む。北田茂生(シゲオちゃん)、平岩壮吉の存在がいい。
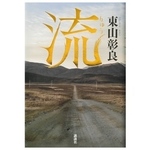 戦争ほど残酷なものはない。戦争ほど悲惨なものはない――「人間革命」の冒頭の言葉を想起した。それも中国本土と台湾を舞台としたこの小説は、戦争というものが取り返しのつかないどころか、殺し合いの連鎖という恐るべき事態を招くことを、浮き彫りにしている。「魚が言いました・・・・・・わたしは水のなかで暮らしているのだから あなたにはわたしの涙が見えません」という言葉は、宿命ともいうべき悲しみを内包する者の沈黙を表わしている。
戦争ほど残酷なものはない。戦争ほど悲惨なものはない――「人間革命」の冒頭の言葉を想起した。それも中国本土と台湾を舞台としたこの小説は、戦争というものが取り返しのつかないどころか、殺し合いの連鎖という恐るべき事態を招くことを、浮き彫りにしている。「魚が言いました・・・・・・わたしは水のなかで暮らしているのだから あなたにはわたしの涙が見えません」という言葉は、宿命ともいうべき悲しみを内包する者の沈黙を表わしている。
衝撃的なプロローグに続いて、1975年、台湾の総統・蒋介石の死と主人公の高校生・葉秋生の祖父が殺害されるところから話は始まる。戦争と戦後の内戦、貧困と暴力の日常のなか、主人公の胸中には「祖父はなぜ、誰に殺されたか」という疑問がことあるごとに噴出する。プロローグで提起されたものは、最後に意外な展開を見せる。あたかも怒涛の寄り身に浴びせ倒されるような迫力があるが、戦争の残酷さや国家の巨大さも、人間の生死を越えうる一念によって砕け散る感がする。それが本書の凄みだ。
 「新たな国際秩序と地政学を読み解く」と副題にあるが、「地政学、文明、歴史から読む新たな国際情勢の地殻変動」だと思った。
「新たな国際秩序と地政学を読み解く」と副題にあるが、「地政学、文明、歴史から読む新たな国際情勢の地殻変動」だと思った。
イスラーム国(IS)、シリア、ギリシャ、ウクライナ、イエメン等をめぐる対立や紛争の構造。そこにある米国、ロシア、イラン、サウジアラビア、トルコ、イスラエル等々の思惑。その背景にあるスンナ派、シーア派等々の宗教と歴史と地政・・・・・・。
緊張する中東、ロシア地域は、日本にとっては、どうしてもその大きな構造変化とその戦略に鈍感になりがちだ。それが怖い。本書はまさにその中東、ロシアの専門家・山内昌之さん、佐藤優さんの対談だが、大胆かつ本質的、鋭角的だ。「イスラーム国、中東の狂った果実」「地政学を抜きにして中東情勢は読み解けない」「地理と民族が彩るロシアの曲折」「欧米史観と虚国ギリシャの悲劇」「中国の理屈なき海外膨張と中東への野望」「情報地政学で理解する未来図、そして戦争」の6章よりなるストレート対談。
「戦争を正面から考える」がテーマで「日本で戦争をすることを決めるのは誰なのか」「国民を兵士として、あるいは戦争支持者として動員するには、人間の精神にどのような働きかけを行うのか」という問いが提示される。とくに後者――。哲学者・田辺元の太平洋戦争開戦前の著書「歴史的現実」と終戦直後の著書「懺悔道としての哲学」にふれ、「死者との連帯」の視点を掘り下げる。そして「国家の歴史、救済・・・・・・このように大きな問題と死者の問題を結びつけると、ルターとなり、田辺元となり、麻原彰晃のような言説を生み、それを信奉し、行動を起こす人間を生む、あるいは異論をとなえられない世間の空気を生むのです」という。そして「愛する人の死を起点にすること」を示す。
そのうえで、「国家は必要悪だが、"悪"がせり出す存在になるゆえに、国家との距離のとり方が大事だ」「中間団体が強くなることで、社会全体を強靭にできる」「自分の愛する人、親しい人――それは亡くなった人も含めて――を起点に人間関係をつなげ、強固にする」ことの重要さを説く。
また「"シーア派のアラブ人"という新しい民族が誕生しつつある」「沖縄人のアイデンティティー」という変化する視点を提示している。



