 あの90年
代前半の政治改革論議。小選挙区制に比重が置かれたのは、「政党中心、政策中心の選挙制度が大切」「政権交代のある二大政党制」「自民党における派閥争
い、カネをめぐっての中選挙区制への忌避」そして「アメリカやイギリスが持つ二大政党制こそがデモクラシーの王道である」などという強力な刷り込みと思い
込みがあったと指摘する。
あの90年
代前半の政治改革論議。小選挙区制に比重が置かれたのは、「政党中心、政策中心の選挙制度が大切」「政権交代のある二大政党制」「自民党における派閥争
い、カネをめぐっての中選挙区制への忌避」そして「アメリカやイギリスが持つ二大政党制こそがデモクラシーの王道である」などという強力な刷り込みと思い
込みがあったと指摘する。
「単 峰型社会では二大政党のイデオロギーや政策は収斂傾向をもつ」「だからこそ、両端の社会層はコストを払うことになり、地域の切実な課題に、政治は応え切れ ない」「選挙は政策論争でなく、政権選択のゲームと化す」「政党は首尾一貫した綱領などイデオロギーに支えられるのではなく、政権奪取ゲームを繰り広げ る。政策も政権政党への批判を軸にして組み立てがちになる。また対立的政策を出す誘惑にかられもする」「政党は人気取りに邁進し、世論調査に振り回され劇 場政治がつくり上げられる」「連立政権は不安定といわれたが、連立政権と内閣の安定性とは関係ない」――。
吉 田さんは、世界の政党と選挙制度を歴史的、現実的に分析しつつ、「多極共存型デモクラシー」や「闘技デモクラシー」を紹介する。「日本政治に欠けているの は"強いリーダーシップ"や"政策本位の政治"などではなく、"政治は自分たちのためにあるもの"という感覚なのではないか」とも言っている。今、選挙制 度のみならず、政治全体の改革が求められる。
時間的にも空間的にも、哲学的にも俯瞰して、寺島さんは、東日本大震災から世界の中の日本を考え、日本の創生を語る。語るというより、熱が感じられる。
小林秀雄は「現代人は鎌倉時代のなまくら女房ほども、無常ということがわかっていない」といったが、生老病死、死に直面しても、どうも「どういう反省」を
し、「どうとらえるか」の意識変革すらない。それが日本創生の熱源とならなければならないのに......。そんな思いが本書からあふれ出ている。
 かつて「暴走老人!待てない、我慢できない、止まらない」(藤原智美著)や「祖母力」(樋口恵子著)なども興味深く読んだが、曽野綾子さんは、年を重ねても自立した老人になっていない、年のとり方を知らない(......してくれないというくれない族)が
増えていることを問題とする。「自立と自律の力」「孤独と付き合い、人生を面白がる力」などが大切。老いの才覚=老いる力を持つことが重要だという。「い
くつになっても話の合う人たちと食事をしたい」「あるか、ないか、わからないものは、あるほうに賭ける」「孤独と絶望こそ、人生の最後に充分味わうべき境
地なのだと思う時がある」、そして最後のブラジルの詩人の「浜辺の足跡」は印象的だ。
かつて「暴走老人!待てない、我慢できない、止まらない」(藤原智美著)や「祖母力」(樋口恵子著)なども興味深く読んだが、曽野綾子さんは、年を重ねても自立した老人になっていない、年のとり方を知らない(......してくれないというくれない族)が
増えていることを問題とする。「自立と自律の力」「孤独と付き合い、人生を面白がる力」などが大切。老いの才覚=老いる力を持つことが重要だという。「い
くつになっても話の合う人たちと食事をしたい」「あるか、ないか、わからないものは、あるほうに賭ける」「孤独と絶望こそ、人生の最後に充分味わうべき境
地なのだと思う時がある」、そして最後のブラジルの詩人の「浜辺の足跡」は印象的だ。
12年前の「中年以後」とあわせ読むと感銘深い。「『老いの才覚』が大変なベストセラーになってしまって......」とか、時代そのものを曽野さんは感じているのかもしれない。両書の微妙な変化もまた「老いの才覚」なのか。
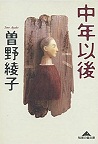 99年
の本だが、「中年以後の人の心をずっと前から書きたいと考えていた。つまり青くない、幼稚ではない人の心を、である」――「ただ人間だけがいる――この世
には神も悪魔もいないことを知る頃」と題する冒頭のエッセイはこの文章から始まる。「若い頃の人間の思考は単反射である」「物の判断については大人にな
れ」「他人のことはわかっていない、という自覚のある人は極めて少ない。......事情がわかると、簡単に、いい人だとか悪い人だとか言えなくなる」
「曖昧さに耐える」「いい年をして正義感だけでものごとを判断していたら、人間になり損ねる」とも。
99年
の本だが、「中年以後の人の心をずっと前から書きたいと考えていた。つまり青くない、幼稚ではない人の心を、である」――「ただ人間だけがいる――この世
には神も悪魔もいないことを知る頃」と題する冒頭のエッセイはこの文章から始まる。「若い頃の人間の思考は単反射である」「物の判断については大人にな
れ」「他人のことはわかっていない、という自覚のある人は極めて少ない。......事情がわかると、簡単に、いい人だとか悪い人だとか言えなくなる」
「曖昧さに耐える」「いい年をして正義感だけでものごとを判断していたら、人間になり損ねる」とも。
こんなエッセイが24も 詰まっている。「かつて自分を傷つける凶器だと感じた運命を、自分を育てる肥料だったとさえ認識できる強さを持つのが、中年以後である」「中年以後にしか 人生は熟さない」「正義など、素朴な人間の幸福の前では何ほどのことか、そう思えるのが中年というものだ」「醜いこと、惨めなこと、にも手応えのある人生 を見出せるのが中年だ」「権力追求病は、主に中年以後にかかる病気らしい。それも女性より男性の罹患率が高い」「中年を過ぎたら、私たちはいつもいつも失 うことに対して準備し続けていなければならないのだ」......。
如 実知見、経験も深さもあり、哲学の背骨も感ずる。何か横にすわって日常の対話をしてくれているようだ。「若い時は自分の思い通りになることに快感がある。 しかし中年以後は自分程度の見方、予測、希望、などが裏切られることもある、と納得し、その成り行きに一種の快感を持つこともできるようになるのであ る」......。
北島康介、福原愛、魁皇、乙武洋匡、さかなクン、山崎直子、ベッキー、広瀬章人、大日方邦子、吉田沙保里......。子どもゆめ基金10周年を記念して、各分野で活躍している30名とのインタビュー。
子どもの頃、個性あるゆえか仲間はずれにされたり、悩んだり......。しかし、「好きなものを見つける努力」「夢をさがす」「もうやめたいと思ってもやり続ける」「厳しい練習を乗り越えてきたことが、自分の自信となった」などと語る。今の若者は伸びる。自由度も大。

