 小学校4年生の6月、福岡県糸島の田舎に都会の団地から引っ越してきた山田加奈子。それはたった1年間の新しい生活だったが、姉や家族、いつも一緒の咲子などとともに"普通の日々"の全てをどんどん吸収していく。そこで出会った「死刑囚の母」のおハルさん。「残酷なところもいっぱいあるの。残酷な時代でしたからね。踏みつけてきたのよ、たくさんの命や、心を」「あなたには、残酷なできごとが起こりませんように」・・・・・・。それは初登校の日、田んぼの畦道でどんどん踏みつけられていく蛙の轢死体に気分が悪くなって保健室で介抱される加奈子が重なる。
小学校4年生の6月、福岡県糸島の田舎に都会の団地から引っ越してきた山田加奈子。それはたった1年間の新しい生活だったが、姉や家族、いつも一緒の咲子などとともに"普通の日々"の全てをどんどん吸収していく。そこで出会った「死刑囚の母」のおハルさん。「残酷なところもいっぱいあるの。残酷な時代でしたからね。踏みつけてきたのよ、たくさんの命や、心を」「あなたには、残酷なできごとが起こりませんように」・・・・・・。それは初登校の日、田んぼの畦道でどんどん踏みつけられていく蛙の轢死体に気分が悪くなって保健室で介抱される加奈子が重なる。
森や田んぼ、豊かな自然のなかで過ごした濃密な1年。命や生老病死の近い所で、子どもの感受性が、より磨かれていく貴重な日々が描かれる。いい。
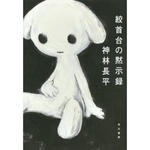 死刑の執行から話が始まる。父の安否を確認するために、新潟の実家に戻ると・・・・・・。「まったく、おかしな話です。実家に帰ったら、自分にそっくりな知らない人間が現れて、自分は昨日死刑を執行された死刑囚だという。わけがわからない」――。
死刑の執行から話が始まる。父の安否を確認するために、新潟の実家に戻ると・・・・・・。「まったく、おかしな話です。実家に帰ったら、自分にそっくりな知らない人間が現れて、自分は昨日死刑を執行された死刑囚だという。わけがわからない」――。
そして次々と出てくる主役が、「俺はいったい誰なのか」「あの人は自分が何者かわからないのでしょうね」「誰が誰だかわからない」という"世にも不思議な世界"に入り込んでいく。カミュの「異邦人」や、コリン・ウイルソンの「アウトサイダー」など、私たちの世代の青春時代の"あの世界"が伏線として提示される。
実在と意識。「意識というのは個人の神経電位や化学反応だけではなく、それらを含めた人体付近の環境全体によって形成されているんだ。そして人体というのは、周囲の環境と情報をやり取りしている発信機であり、受信機なんだ。意識はそれらの情報を総合して形作られている。・・・・・・自分を自分だと思っている<自分>の中には、人体としては別人の、たとえばあなたの意識活動から漏れている信号も含まれている」「死にたくはないが死ななくてはならない。この矛盾状態を破るために、おれは、自分の死を自分で確かめることができないなどというのは我慢ならない、死んでも自分の死体を見届けてやると、そう強く念じたんだ。すると、首にロープを巻かれ、目隠しをされた自分の姿が、見えた」
あまり接したことのない心奥を突き刺してくる長編小説だが、最後まで迫り、ほんろうされる。
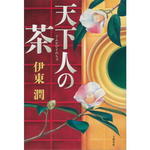 千利休の自害は謎であり、奥深く、多くの解説がある。秀吉と利休の確執を、かなり鋭角的に描いている。そして、1582年の本能寺の変、1600年の関ヶ原とともに、1591年の1、2月、秀吉に直言できることができた羽柴秀長と利休が相次いで死亡したことが、いかに政権を衰退させていったかを感ずる。
千利休の自害は謎であり、奥深く、多くの解説がある。秀吉と利休の確執を、かなり鋭角的に描いている。そして、1582年の本能寺の変、1600年の関ヶ原とともに、1591年の1、2月、秀吉に直言できることができた羽柴秀長と利休が相次いで死亡したことが、いかに政権を衰退させていったかを感ずる。
「殿下は現世の天下人。それがしは心の内を支配する者です。互いの領分に踏み込まぬことこそ、肝要ではありませぬか」「いや、現世をも操ろうとしたのはそなたの方ではないか」「秀吉は、豊臣政権の政治面を弟の秀長に、軍事面を黒田如水に、文化面を利休に託していた。だが利休は謀略面をも担っていたのだ。利休の謀略は(本能寺をはじめ)、次々と功を奏し、秀吉は天下人となった。しかし秀吉は、欲という魔に取り付かれ、己一個に富を集めんとした。民への苛斂誅求は言語を絶するものになった。・・・・・・殿下の関心を大陸に向けさせ・・・・茶の湯によって、戦国の世を終わらせようとしていたのだ」「わしは(秀吉)大陸の王になり、現世と心の内の双方を支配する」「茶の湯の世界には別の秩序があることを、古田織部は世間に知らしめてしまった。現世と精神世界という二重構造が・・・・・・」「利休から精神世界の支配者の座を譲られた時から、こういう結束を迎えると、織部は分かっていた」・・・・・・。
信長において茶の湯は名物唐物を所有するわずかの"本数寄者"だけのものであり、それを政治的に利用しようとした。利休(宗易)はその面白さを民へと拡大しようと"侘数寄"を誕生させた。秀吉はその"侘数寄"を万民の秩序保護に利用した。しかし信長の大陸制覇を踏襲した秀吉と利休の「民の安穏と己の野心」「現世と精神世界」の溝が亀裂となり、補完関係にあった二人はしだいに割れ茶碗のように破局を迎えていく。牧村兵部、瀬田掃部、古田織部、細川忠興を描きつつ、ぐいぐいと利休自害の謎に迫っている。
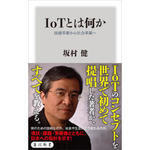 IoT時代が来る。IoT社会が始まっている。技術革新ということの段階を越えて、クローズではなくオープンに。それゆえに技術以外の社会的課題、安全を含めた哲学議論、法的な制度問題が、とくに日本の場合は立ちはだかっている。ドイツの「インダストリー4.0」、米国の「インダストリアル・インターネット・コンソーシアム」の志向するものも同じだが、経済成長の鍵・イノベーションで、日本が遅れをとるわけにはいかない。明確に新段階に突入したIoT社会、IoT時代に、それを引っ張ってきた坂村さんが、IoTの意味するもの、課題(とくに日本の)について述べつつ、総決起を促す書と感じた。それゆえ副題は「技術革新から社会革新へ」だ。
IoT時代が来る。IoT社会が始まっている。技術革新ということの段階を越えて、クローズではなくオープンに。それゆえに技術以外の社会的課題、安全を含めた哲学議論、法的な制度問題が、とくに日本の場合は立ちはだかっている。ドイツの「インダストリー4.0」、米国の「インダストリアル・インターネット・コンソーシアム」の志向するものも同じだが、経済成長の鍵・イノベーションで、日本が遅れをとるわけにはいかない。明確に新段階に突入したIoT社会、IoT時代に、それを引っ張ってきた坂村さんが、IoTの意味するもの、課題(とくに日本の)について述べつつ、総決起を促す書と感じた。それゆえ副題は「技術革新から社会革新へ」だ。
「イノベーションを起こすには、技術だけでなく、制度やものの考え方といった文系的な力もあわせ持つことが重要なのだ。粘り強く議論を続け、ゼロリスクの罠に陥らず、IoT社会に向けた大改革ができるかどうかが問われている。IoTを社会規模で実装して、全体としての高効率化や、安全性向上と個々の利便性の向上の両立という果実を得るのに必要なものは、技術や生産設備よりむしろそういう社会の強靭性だ」「技術的に見ればIoT化が産業機器や家電など、組込みシステムのネットワーク化、高度化の先にある未来にあることは確かだ。しかし、そこには、技術よりもむしろガバナンスチェンジという大きなステップアップが必要で、これについて日本ははなはだ心もとない。・・・・・・ガバナンスも"集中から分散に""クローズからオープンに"する必要があるということだ」「現在の日本は、社会基盤の老朽化やエネルギー危機、災害の脅威、医療体制の懸念、高齢化社会、食の脆弱化・・・・・・。オープンデータにより解決、もしくは緩和される課題は多い・・・・・・。しかし、今までの日本のICT戦略は、技術で始まり技術で終わることが多く、出口戦略がなく、結果として使われないものになっている」。
ロボット、スマートウェルネスシティ、自動運転、ドローン、シェアリングエコノミー、電力自由化・・・・・・。個々がクローズされる中ではなく、あらゆるものが今、クローズからオープン、連携革命の新しい社会への新段階に突入しようとしている。その意識と意欲をもって挑めという。

