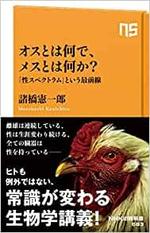 「『性スペクトラム』という最前線」が副題。「性はオスとメスの2つの極として捉えるべきではなく、オスからメスへと連続する表現型として捉えるべきである」という「性スペクトラム」という新たな性の捉え方、性本来の姿を、生物学の最新の知見に基づいて示す。ヒトの脳の性は.「ニつの観点から議論される。一つは自身の性をどのように認識しているかという『性自認』の観点、もう一つがどちらの性を恋愛対象としているかという『性指向』の観点ですが、そのありようは実に多様」と指摘。「性自認ならば、自分を『男性と認識している人』『女性と認識している人』『男性でもあり、女性でもあると認識している人』『男性でもなく女性でもないと認識している人』などがいる。性指向も同様で『男性を恋愛対象とする人』『女性を恋愛対象とする人』『どちらの性も恋愛対象とする人』など多様だ」とし、「スペクトラム状に分布するという考え方によって初めて理解することができる」という。連続してグラデーションの中にあり、赤坂真理氏が「セクシャル・マイノリティーは存在しない。なぜなら、マジョリティーなど存在しないから」と言っていることを思い起こした。
「『性スペクトラム』という最前線」が副題。「性はオスとメスの2つの極として捉えるべきではなく、オスからメスへと連続する表現型として捉えるべきである」という「性スペクトラム」という新たな性の捉え方、性本来の姿を、生物学の最新の知見に基づいて示す。ヒトの脳の性は.「ニつの観点から議論される。一つは自身の性をどのように認識しているかという『性自認』の観点、もう一つがどちらの性を恋愛対象としているかという『性指向』の観点ですが、そのありようは実に多様」と指摘。「性自認ならば、自分を『男性と認識している人』『女性と認識している人』『男性でもあり、女性でもあると認識している人』『男性でもなく女性でもないと認識している人』などがいる。性指向も同様で『男性を恋愛対象とする人』『女性を恋愛対象とする人』『どちらの性も恋愛対象とする人』など多様だ」とし、「スペクトラム状に分布するという考え方によって初めて理解することができる」という。連続してグラデーションの中にあり、赤坂真理氏が「セクシャル・マイノリティーは存在しない。なぜなら、マジョリティーなど存在しないから」と言っていることを思い起こした。
本書はあくまで生物学の研究から生物全体の性を述べている。オスの中には外見上、メスと区別のつかないオス( メス擬態型オス) がいてメスに擬態することで自身の子孫を残すことに成功してきた鳥、魚、昆虫などが多くいる。さらに驚くことに外見だけではなく、生殖機能の性(精子をつくるか卵子をつくるか)でさえ変幻自在という動物も珍しくないという。実例が多数紹介されている。「性スペクトラム上の位置は、オス化の力、メス化の力、脱オス化の力、脱メス化によって、誕生から思春期、性成熟期を経て老年期へと、生涯にわたって変化し続けるし、女性の場合には月経周期に応じて、また妊娠期間を通じても変化する」という。人も生涯にわたって生の状態は変化し続けるわけだ。閉経のある女性と緩やかな曲線で下がっていく男性とは60代以降は違ってくるというのだ。
また「このような性スペクトラム上の位置の決定や移動の力の源泉となっているのが、性決定遺伝子を中心とする遺伝的制御と、性ホルモンを中心とする内分泌制御だ」と指摘する。子育ての時期に卵精巣を発達させ、男性ホルモン濃度を上昇させることで攻撃性を高めるメスモグラや、妊娠期に大幅に上昇した女性ホルモンを糞に混ぜて部下のメス(働きメス)に食べさせることで、養育行動を引き出しているハダカデバネズミの女王など自然界はしたたかで奥深い。さらにまた、「性は細胞に宿っている」「オスの肝臓の細胞とメスの肝臓の細胞は見た目に差は無いものの、両者の間には間違いなく性差が存在する。身体を構成するすべての細胞が性を有しているから、細胞によって作られる骨格筋や血管、皮膚、肝臓などすべての臓器や器官に性が宿るのです」と言っている。これらが遺伝的制御と性ホルモンによる内分泌制御で私たちの身体の性を同調させ、総体として性スペクトラム上の立ち位置を決めているというのだ。
大変刺激的で重要な、「生物学の最前線」「性スペクトラムの最前線」を知ることができた。
 時は町人文化の発展の文化年間(1804~1818年)。江戸木挽町の芝居小屋、森田座の裏通り。雪の降る睦月の晦日の晩、仇討ちが行われた。白装束を纏った年のころ15 、6の若衆。「我こそは伊納清左衛門が一子、菊之助。その方、作兵衛こそわが父の仇。いざ尋常に勝負」――多くの人がいる前で、菊之助は血まみれとなった下男の首を高くかかげたのだった。それから2年後、菊之介の縁者だという若侍が木挽町を訪れ、目撃者から事件の顛末を聞いて回る。
時は町人文化の発展の文化年間(1804~1818年)。江戸木挽町の芝居小屋、森田座の裏通り。雪の降る睦月の晦日の晩、仇討ちが行われた。白装束を纏った年のころ15 、6の若衆。「我こそは伊納清左衛門が一子、菊之助。その方、作兵衛こそわが父の仇。いざ尋常に勝負」――多くの人がいる前で、菊之助は血まみれとなった下男の首を高くかかげたのだった。それから2年後、菊之介の縁者だという若侍が木挽町を訪れ、目撃者から事件の顛末を聞いて回る。
木戸芸者の一ハ、立師の与三郎、衣装部屋のほたる、小道具の久蔵夫婦、戯作者の金治(野々山正ニ)。それぞれの身の上話は、いずれも心を打つものばかり。「(みんな)菊之介、菊之介ってあいつを可愛がっている。俺も含めてこの悪所に集うやつらはみんな、世の理ってやつから見放されて、はじき出されて転がり込んで、ようやっとここに落ち着いた連中だ。それが、まだ武士の理を引きずりながら仇討ちを立てているあいつに、どういうわけか心惹かれていく」・・・・・・。
驚愕の真相が明らかになるが、江戸の町人の陰影を隠して生きる逞しさ、明るさ、知恵、人の情が溢れて心地よい。かっこつけた武士道など簡単にけたぐりにあう。絶妙の構成と筆致に感心する。
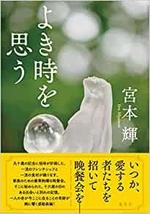 三沢兵馬という老人が、東小金井に所有する中国の伝統的家屋建築の「四合院造り」の家。東西南北のなかの一棟に間借りしている29歳の金井綾乃に、近江八幡市の実家の母から知らせが届く。徳子おばあちゃんが、90歳を迎え、祖母自らが豪華な「晩餐会」を開くと言うのだ。家族全員集合、特別な会場で、超一流のフランス料理で、タキシードやドレスで・・・・・・。徳子おばあちゃん、父陽次郎60歳、母玉枝57歳、長男喜明32歳と妻春菜、長女綾乃29歳、次女鈴香26歳、次男春明24歳の面々だ。
三沢兵馬という老人が、東小金井に所有する中国の伝統的家屋建築の「四合院造り」の家。東西南北のなかの一棟に間借りしている29歳の金井綾乃に、近江八幡市の実家の母から知らせが届く。徳子おばあちゃんが、90歳を迎え、祖母自らが豪華な「晩餐会」を開くと言うのだ。家族全員集合、特別な会場で、超一流のフランス料理で、タキシードやドレスで・・・・・・。徳子おばあちゃん、父陽次郎60歳、母玉枝57歳、長男喜明32歳と妻春菜、長女綾乃29歳、次女鈴香26歳、次男春明24歳の面々だ。
なぜ徳子おばあちゃんは、そんな豪華絢爛な晩餐会を開くことにしたのか。なぜ徳子おばあちゃんは、わずか16歳で出征の決まった青年と結婚したのか。短刀で自刃しようとした後、なぜ数年間も婚家にとどまったのか。なぜ由緒ある端渓の硯と竹細工の花入れを綾乃に、来国俊の懐剣を鈴香に、銀のスプーンを春明に渡したのか。なぜ吃音の教え子に法華経の妙音菩薩品を読ませたのか・・・・・・。綾乃は晩餐会の準備をするなかで、徳子おばあちゃんのキリッと筋の通った人生姿勢と、縁した人に注ぐ慈悲の心を知っていくのだった。
大ドラマやエンターテイメントではない。真摯に丁寧に、人生を生きていくなかに、「人に恵まれる」「心の中から幸せを感じる」こと、そして「人と人との間に幸せが生まれる」ことをしみじみ感じさせる。
「見ていると幸福な気持ちになる。それはやがて『もの』ではなく、幸福そのものになる」「晩餐会は、自分だけでなく、自分の人生に関わった人々すべての生命を褒め称えるためのものだ。・・・・・・わたしはいつか愛する者たちを招いて晩餐会を催そうと思った」「晩餐会への敬意を込めるために最高の正装で臨むそうだ」「まず自分への敬意。同席する妻や家族たちへの敬意。友人知己たちへの敬意。それから料理人や配膳係たちへの敬意。・・・・・・つまり、晩餐会とは、今日生きていることへの敬意。自分の生命への敬意と賛嘆。家族や友人たちへの生への敬意と讃嘆をあらわすためのものだということだ」・・・・・・。
「よき時とは過去の栄光の時ではなく、未来を目指す意志」――。価値創造の意志が、自他共の幸福を築くことをじっくり味わせてくれる素晴らしい作品。
 「自覚ある独裁」が副題。凄まじい時代に戦った凄まじい人物、ドゥ・ゴール。「フランスの偉大さを信じ、フランスと自己を同一視するほど(私はフランスだ)に、フランスのために働いてきた男」「根からの反逆児」であるドゥ・ゴールの戦闘的生涯を描く。第二次世界大戦中、フランスはどう生き抜こうとしたのか、そして戦後――。ドゥ・ゴールなくして語れない。破格の生涯だが、「国の為なら、後悔は無い。あるとするなら私生活のこと。もっと娘といてあげたかった。守るべきアンヌ、愛するべきアンヌ、引退したら妻とふたり・・・・・・」とのエピローグには涙した。
「自覚ある独裁」が副題。凄まじい時代に戦った凄まじい人物、ドゥ・ゴール。「フランスの偉大さを信じ、フランスと自己を同一視するほど(私はフランスだ)に、フランスのために働いてきた男」「根からの反逆児」であるドゥ・ゴールの戦闘的生涯を描く。第二次世界大戦中、フランスはどう生き抜こうとしたのか、そして戦後――。ドゥ・ゴールなくして語れない。破格の生涯だが、「国の為なら、後悔は無い。あるとするなら私生活のこと。もっと娘といてあげたかった。守るべきアンヌ、愛するべきアンヌ、引退したら妻とふたり・・・・・・」とのエピローグには涙した。
1890年に生まれ、1912年にはサン・シール陸軍士官学校を卒業、第一次世界大戦にも参画して戦った。1940年、パリ陥落となるなか、抗戦か停戦かでフランスは揺れに揺れた。軍隊時代にドゥ・ゴールを守ってくれた上官ぺタンは、停戦派を率いてドイツの傀儡ヴィシー政府を作る。歯噛みするドゥ・ゴールはロンドンに渡り、6月18日、BBCからフランス国民に向けてラジオ演説を行い、ナチスへのレジスタンス運動を呼びかける。ドゥ・ゴールは「この世界戦争において、結局フランスだけが降伏し、また降伏したままでいなければならないとすれば、名誉も、独立も終わりになってしまうだろう」「自分は、フランスの命を救うために来た」と考えたのだ。そして「自由フランス」を立ち上げる。ぺタン政府は、反逆者の汚名を着せ、財産没収・死刑を宣告する。チャーチル率いるイギリスの戦略とドゥ・ゴールの戦闘姿勢がぶつかる。チャーチルとの怒鳴り合い、脅しは凄まじい。欧州にとどまらず、アフリカや東南アジアに多数の植民地を抱えたフランス。そこでの体制作りにも奔走するドゥ・ゴール。そこにも上陸してくるイギリス軍の支援を受けたアメリカ軍・連合国軍。ローズヴェルトはドゥ・ ゴールに強い悪感情を持った。英米との関係、欧州戦線の複雑さは、ど真ん中に位置するフランスだけに、パリ陥落を受け入れている傀儡政権がいるだけに、フランス国内の支持が高まっているとは言え、ドゥ・ゴールの苦悩は計り知れないものがあった。しかしドゥ・ゴールは自ら仕掛けていく。次第にドゥ・ゴールなしには抵抗運動は動かず、「フランス国民開放委員会」も立ち上がっていく。「ドイツに協力してきたヴィシー政府が倒されるという意味では、フランスは敗戦国である。しかし、そういう形にならないため、言い換えれば戦勝国になるために払われてきたのが、自由フランス、戦うフランス、フランス国民開放委員会におけるドゥ・ゴールの努力だったのだ」と描かれる。
ノルマンディー上陸作戦、そしてフランス共和国臨時政府樹立。連合国軍による軍政など誰も望まない。1944年8月26日、「パリ解放」を祝い、シャンゼリゼ通りを行進するドゥ・ゴールを300万の市民が歓迎した。「長い長い戦いも、ようやく先が見えてきた。ドイツら枢軸国とのフランスの領土を奪還する戦い、イギリス、アメリカといった連合国とのフランスの主権を守る戦い、ヴィシー政府、ジロー将軍、さらには共産党とフランスの執政をめぐる戦い、その全てに納得できる方向性が現れたのだ」・・・・・・。フランスを戦勝国に押しあげ、国連の安保理常任理事国にも割り込ませた。マジックのような仕事と言うほかない。
大戦が終わっても、復旧は急務であったし、首相になったドゥ・ゴールは政権運営にも苦心した。1946年1月には辞任。これは失敗であった。再び戻ったドゥ・ゴールは第五共和政で憲法改正、大統領権限が拡大され相対的に議会の役割が小さくなった。「消極的な民主主義の成立である」「その憲法は今も受け継がれ、ポンピドゥーやシラク、マクロンに至るドゥ・ゴールの系譜であれ、ミッテラン、オランドに至る社会党系の反ドゥ・ゴールの系譜であれ、強い大統領を改める動きは無い」と言う。世界を巻き込んだアルジェリア問題を収束させ、フランスの植民地帝国も解消していく。敵国ドイツとの連帯、ヨーロッパ共同体からのイギリス閉め出しやNATO脱退などの戦略は、フランスの自主存立に向けての戦略であったが、その成否は今もなお問われ続けている。ドゥ・ゴールの最後の仕事が、あの1968年のフランス学生による五月革命、カルチェ・ラタンであったことは、当時学生であった私としては極めて生々しいものだ。感慨深い。
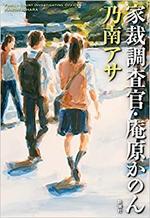 福岡家庭裁判所北九州支部の少年係調査官である庵原かのん。恋人の栗林は東京で動物園に勤めるゴリラ大好きのいい男。家裁で扱う少年少女は主に罪を犯した場合に処罰を下すことができる14歳から19歳の子たちを指す。処罰とはいっても、あくまでも少年の保護更生を目的としたものだ。そこが成人とは違う。将来ある彼らの可能性を信じて、問題の原因を探り、立ち直りへの道筋をつける、それが処罰の目的だ。家庭裁判所調査官は、問題の原因を探るため、何よりも聴くことに徹する。そのために読み、そして報告書を書き、裁判官に提出する。それを資料として裁判官は審判を下す。本書は7 話で構成されるが、かのんの奮闘はすばらしい。少年の心を読み取り、家族関係を知り、家族や学校での友人知人、周りの人々とのもつれを、冷静に熱意を持って解きほぐしていく。乃南さんの力量が、何ともいえない暖かい風を送ってくれ、心の中までほっとする。帯には「令和日本の姿を浮かび上がらせる名作誕生」とあるが、本当にそう思う。
福岡家庭裁判所北九州支部の少年係調査官である庵原かのん。恋人の栗林は東京で動物園に勤めるゴリラ大好きのいい男。家裁で扱う少年少女は主に罪を犯した場合に処罰を下すことができる14歳から19歳の子たちを指す。処罰とはいっても、あくまでも少年の保護更生を目的としたものだ。そこが成人とは違う。将来ある彼らの可能性を信じて、問題の原因を探り、立ち直りへの道筋をつける、それが処罰の目的だ。家庭裁判所調査官は、問題の原因を探るため、何よりも聴くことに徹する。そのために読み、そして報告書を書き、裁判官に提出する。それを資料として裁判官は審判を下す。本書は7 話で構成されるが、かのんの奮闘はすばらしい。少年の心を読み取り、家族関係を知り、家族や学校での友人知人、周りの人々とのもつれを、冷静に熱意を持って解きほぐしていく。乃南さんの力量が、何ともいえない暖かい風を送ってくれ、心の中までほっとする。帯には「令和日本の姿を浮かび上がらせる名作誕生」とあるが、本当にそう思う。
「日本のどこかで様々な人生を背負って悩み、壁にぶち当たり、家庭裁判所まで来なければならなくなった人の話に耳を傾ける」のが家裁調査官だ。逮捕や捜査ではなく、とにかくひたすら「聴く」役柄だが、そこに本当の解決が生まれ、嬉しくなる。
「自転車泥棒」――少年が自転車泥棒をする。母子3人で北九州に来て風俗店に母は働くが、男が家に入り込み乱暴をしていた。また万引きの少年、背景には何でもかまってくる母親がいた。「野良犬」――身柄付補導委託として預けられた猫を可愛がる少年が突然いなくなる。「母さんが、来たんやと思ったんちゃ」・・・・・・。「沈黙」――ごく普通と思われていた少女が売春行為と売春あっせんで捕まるという事件が起きた。聞いてみると、ある時から「父親と急に距離を置き、嫌悪するようになった」という。
「かざぐるま」――中学時代の同級生が少年に囲まれていたとして、助っ人に入りボコボコにした少年。母子の暮らしだが、少年は実父の「川筋もん」に憧れ、叩き込まれてきた。「パパスの祈り」――暴走族として捕まった徳永ミゲル。父はペルー人、母はフィリピン人、日常の家族の会話があまりにも少なかったので。そこでかのんは・・・・・・。「アスパラガス」――帰宅途中の女性に背後から抱きつき陰部を触るなどをした少年。両親も全く気づいていないが、かのんは、コミニュケーションや対人関係が気づけないASDではないかと思う。「おとうと」――「何かを拾ってくるという行為は幼い頃からの、いわば当たり前の習慣だった」という拾い癖の少年の話。
少年少女が、複雑な家庭、家族関係の中で、迷い傷つき暴れる。少年少女や家族と、また周辺と面会を続けるなかで、こんな良い仕事をしている人がいる。それを落ち着いて語っているとても良い小説。

