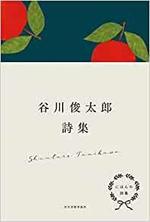 90歳を超えてなお第一線で活躍される谷川俊太郎さんの詩集。戦後すぐの若き時代から今日までの詩が、この4月、詩集として発刊された。昭和、平成、令和の3時代を通しての最新自選詩集。
90歳を超えてなお第一線で活躍される谷川俊太郎さんの詩集。戦後すぐの若き時代から今日までの詩が、この4月、詩集として発刊された。昭和、平成、令和の3時代を通しての最新自選詩集。
自然や宇宙との対話、わたしとあなたの心の対話がススッと心に入ってくる。思索を呼び起こし、こちらの人生自体を思い起こされ、何か心を定置し、心が落ち着く。「是の法 法位に住して 世間の相 常住なり」「海よりも広いものがある、それは大空である、大空よりも広いものがある、それは人間の心である」が浮かぶ。
「僕と神様」「ニ十億光年の孤独」「生きる」「朝のリレー」「さよならは仮のことば」「生まれたよ ぼく」「はにかむ」「おに」「おとなしいおに」「底抜け未来」「十五歳」「宇宙の一隅」「母の日」「ぼく」「あなた」・・・・・・。とても心に響いた。声を出しても読んだ。
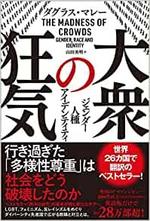 「ジェンダー 人種 アイデンティティ」が副題。「大衆の狂気」と言えば、ファシズム論やオルテガの大衆論を思い浮かべるが、LGBTに焦点を当て、「行き過ぎた多様性尊重の社会の危険性」を、容赦なく暴き出す。「アイデンティティ・ポリティクスの狂気についてよくまとめられた、理路整然とした主張を展開」「社会的公正運動が過激化するこの時代を案内する、洞察力に優れたガイドだ」「差別主義者というレッテル張りで異論を封殺、行き過ぎた多様性尊重がもたらした社会分断と憎悪の実態を暴く」と評される。大変な力作だと思うが、米英の「ジェンダー、人種、アイデンティティ」をめぐる論争は、日本より1周も2周も早いと感じる。
「ジェンダー 人種 アイデンティティ」が副題。「大衆の狂気」と言えば、ファシズム論やオルテガの大衆論を思い浮かべるが、LGBTに焦点を当て、「行き過ぎた多様性尊重の社会の危険性」を、容赦なく暴き出す。「アイデンティティ・ポリティクスの狂気についてよくまとめられた、理路整然とした主張を展開」「社会的公正運動が過激化するこの時代を案内する、洞察力に優れたガイドだ」「差別主義者というレッテル張りで異論を封殺、行き過ぎた多様性尊重がもたらした社会分断と憎悪の実態を暴く」と評される。大変な力作だと思うが、米英の「ジェンダー、人種、アイデンティティ」をめぐる論争は、日本より1周も2周も早いと感じる。
「ゲイ」「女性」「人種」「トランスジェンダー」の各章があり、その間に「間奏」として「マルクス主義的な基盤」「テクノロジーの衝撃」「ゆるしについて」が論述される。「アイデンティティ・ポリティクス(性・人種・性的指向など、社会的不公正の犠牲になっている特定のアイデンティティ集団の社会的地位の向上を目指す政治活動)」が狂気をはらむことについて、マルクス主義的な反権力闘争の基盤や、道徳的中立とは程遠いIT ・テクノロジーの発展が増幅装置となっていることは間違いない。その抑えとして、「インターネット時代が取り組もうとしない問題である『他人をゆるす』こと。誰であれ生きていれば間違いを犯す。そのため、健全な人間や社会には、許す能力がなければならない」を示している。
本書を読むと、トランスジェンダーの問題が、新たな転機をもたらしたことを抉り出している。「ゲイの権利運動は事実上終わった。人種的マイノリティーや女性の地位が概ね向上したことも周知の事実となっている。・・・・・・2015年は、トランスジェンダーの権利、認知、要求が主流化した年である」「LG BTの中のL 、G、Bを不確実なものとするなら、最後のTは、その中でもとりわけ不確実で不安定だ。ゲイやレズビアン、バイセクシャルを不透明なものとするなら、トランスジェンダーは未だ謎に近く、それでいてどれよりも極端な結果をもたらす」と言い、具体例を出しながら本人自体が揺れ動く様を紹介している。そして「社会的公正を推進する活動家の目的は、本書の各章で取り上げたそれぞれの問題(ゲイ、女性、人種、トランスジェンダー)のいずれにおいても、それを人権に対する不満として提示し、大いに怒りをかきたてるような主張をすることにある。彼らが求めているのは、改善ではなく分断だ。鎮めることではなく刺激することを、抑えることではなく燃え上がらせることを望んでいる」と指摘する。「抑圧されたもの」「犠牲者グループ」として、マルクス主義的な下部構造の一端が垣間見えると言うのだ。そして「犠牲者は常に善良で、正しく、賞賛に値するとは限らず、犠牲者でさえないかもしれない」「近年になって被害者意識を主張する人が異常なほど増えている」「人間をそのような行動にかり立ててきた衝動、弱さ、情熱、妬みに翻弄され続ける」と言うのだ。マーティン・ルーサー・キングの言う「『白人に権力を!』と叫ぶ人や、『黒人に権力を!』と叫ぶ人がいなくなり、誰もが神の力や人間の力について話をするようになるその日が来るまで、満足してはいけません。・・・・・・ありとあらゆる討論や議論から人種の要素を取り除き、ますます高まっている人種へのこだわりを追い払い、人種にとらわれない方向へと進むべきである」と言う。さらに「現代の狂気から距離を置く1つの方法は、政治活動への関心を維持しつつも、それを人生に意味を与えるものとして考えないことである。アイデンティティ・ポリティクスや、その表れとしての社会的公正、インターセクショナリティーのために自分を使い果たすのは、人生を無駄にしている」と、私たちの生活から政治的要素を取り除くことを提唱する。LGBと亀裂を生ずるほどのトランスジェンダー問題が勢いを得ている今、「私たちが経験している狂気とは、過去に存在した偏見に対する過剰反応である」と警鐘を鳴らす。
 寛永8年(1631年)、江戸城御座の間。三代将軍家光から、「御伽衆」となっていた立花宗茂は、「神君家康がいかにして『関ヶ原』を勝ち抜いたか、考えを聞かせてほしい」と言われる。「西国無双」と讃えられた名将であり、西軍につき寝返らなかった武将としては唯一、「柳川13万石」を秀忠の時代に復領させた立花宗茂も、下命に不安を募らせる。「その真意は?」「新たな大名取り潰しの意図が潜んでいるのではないか」・・・・・・。時は、ニ代将軍・秀忠の病が篤くなっており、家光は親政に気持ちを昂ぶらせていた。関ヶ原とは何であったのか。「関ヶ原は力と力のぶつかり合いではなかった。内府家康が、艱難辛苦の連続だった人生を賭し、知恵の限りを尽くしての謀略戦だった。しかも、謀りに謀った末の最後の一手を前に、おそらく勝ち戦を確信してはいなかった」「豊臣家の名のもとに集められた軍勢が、豊臣家の城を中心に集まった軍勢と対決するのである。両陣営が美濃路で激突したのが『関ヶ原』であった」「改めて、この天下を分けた決戦の不可解さに、宗茂は思いを致す」・・・・・・。
寛永8年(1631年)、江戸城御座の間。三代将軍家光から、「御伽衆」となっていた立花宗茂は、「神君家康がいかにして『関ヶ原』を勝ち抜いたか、考えを聞かせてほしい」と言われる。「西国無双」と讃えられた名将であり、西軍につき寝返らなかった武将としては唯一、「柳川13万石」を秀忠の時代に復領させた立花宗茂も、下命に不安を募らせる。「その真意は?」「新たな大名取り潰しの意図が潜んでいるのではないか」・・・・・・。時は、ニ代将軍・秀忠の病が篤くなっており、家光は親政に気持ちを昂ぶらせていた。関ヶ原とは何であったのか。「関ヶ原は力と力のぶつかり合いではなかった。内府家康が、艱難辛苦の連続だった人生を賭し、知恵の限りを尽くしての謀略戦だった。しかも、謀りに謀った末の最後の一手を前に、おそらく勝ち戦を確信してはいなかった」「豊臣家の名のもとに集められた軍勢が、豊臣家の城を中心に集まった軍勢と対決するのである。両陣営が美濃路で激突したのが『関ヶ原』であった」「改めて、この天下を分けた決戦の不可解さに、宗茂は思いを致す」・・・・・・。
さらに家光は、「関ヶ原」の毛利についても聞きたいと言う。「関ヶ原」は、徳川と毛利との戦いでもあったのだ。同じく「御伽衆」となっていた毛利秀元が呼び出される。毛利秀元は、「関ヶ原」では毛利一統を率いて南宮山に布陣したものの、戦況を虚しく傍観して、「宰相の空弁当」と揶揄された本人だ。緊張と警戒心のなか、「吉川広家の内通の意味」「毛利秀元と吉川広家の確執」「秀元の動きが封じられた状況」「なぜ大垣決戦ではなく関ヶ原に移動し決戦となったか」「それを促した小早川秀秋の動き」などを話す。凄まじい謀略と各武将の決断・逡巡、間断なくうち続く戦況の変化が、驚嘆すべき重厚さと濃密度で描かれる。これまで描き続けられた「関ヶ原」が、極めてクリーンに立体的に迫ってくる。それをはやる心の家光、天下一の名将の老残の境地。見事に緊張感の中から描いている。
第1章は「関ヶ原の闇」だが、第二章は「鎌倉の雪」――。千姫の名で知られる2代将軍徳川秀忠の長女、家光の姉であり影響力を持つ「天寿院」と立花宗茂の心の通い合いを描く。常軌を逸するほどの経験を積んだニ人が通わすそこはかとないロマンス。これがまた良い。
第3章は、「江戸の火花」――。大御所秀忠が1632年、亡くなる。家光は昂ぶる。旗本を監察する横目に加え、大名家に目を光らせる大横目を設ける。父秀忠からは「代替わりにこそ留意せよ。世にくすぶる輩は再び世が乱れるのを待って息を潜めている。それを恐れよ、それに足元をすくわれぬよう警戒を怠るな」との遺言がある。大名たちの戦々恐々は目に見えるようだ。父母から愛されなかった家光は、父母の寵愛に甘える弟・大納言忠長を許せない。そうしたときに、肥後の加藤忠広の嫡男・光広による謀反の企て「加藤家改易騒動」が起きる。加藤清正以来、関係の深かった宗茂はどうするか・・・・・・。
「誰も、教えてくれぬではないか・・・・・・。眠れぬ夜を、幾度も幾度も重ね――余はようやく、法の徹底しかない、そう思い切ったのだ。徳治ではなく法治、慈悲ではなく処罰、それが余の治世のあり方だ! 偉大なる祖父と父から託されたもの、それを守る道はそこにしかない!」。それに対して宗茂は、「偉大な祖父と父。それに比べて我が身の将軍たる根拠とは――。家光の心中深くにあるこの不安を・・・・・・その心を安んじてあげられぬものか。抜き身のようなその心を、老いの身が鞘となって包んであげられないものか。その思いが、宗茂の胸を貫くことがあった」という。まさに立花宗茂残照。尚、赫赫たれ。
「貴殿の赫赫たる武勲、それを知るものはまず、その居ずまいに驚かされる。誇らず飾らず、あるがままをさらしている。その姿に、人は知らず知らず強く惹かれてしまっている」と語る丹羽長重に、宗茂は「宗茂などはるかに及ばぬほどの辛酸をなめてきた長重。関ヶ原の敗軍も生き延びて今がある。その先にこの柔らかな笑顔がある」「またひとり、畏友を得た思いだった」と語るのだ。いい。
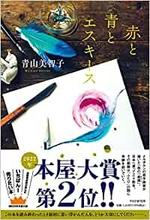 ペインティング・ナイフをすべらせて描いた一枚の「エスキース」(下絵)が紡ぐ連作短編集。
ペインティング・ナイフをすべらせて描いた一枚の「エスキース」(下絵)が紡ぐ連作短編集。
メルボルンに留学した茜は、蒼と出会い恋に落ちる。レッドとブルー。レイとブー。日本に帰るレイを心に留めようとして、ブーは友人の画家・ジャック・ジャクソンに胸から上の人物画を書いて欲しいと頼む。「赤いブラウスと青い鳥のブローチ」「すっと流れるレイの長い髪の毛」――この絵はジャック・ジャクソンにとっても個性を見出し「画家志望ではなく画家のジャック・ジャクソンにしてくれた絵」となった。
メルボルンから帰国するまでの「期間限定の恋」に始まった2人の愛は、日本での展開となる。画廊、絵を飾る額縁工房の物語、漫画家2人の話、輸入雑貨店の店員、猫をめぐっての復縁・・・・・・。様々な困難が当然のように押し寄せるが、収まるところに収まるのは、最初の恋の熱源の大きさあってのことと言えようか。表紙に描かれた爽やかさと美しさが、伝わってくる。
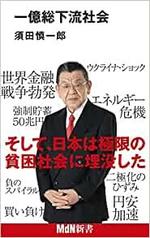 コロナ、ウクライナ危機、円安、慢性デフレ・・・・・・。人口減少・少子高齢社会、AI ・ロボット・ DX などの急進展、レベルの変わった災害、地球環境やエネルギーなどの構造的問題・・・・・・。日本は大変な問題に直面している。腹を決めてこの勝負の10年に挑まなければ日本に未来はない。それを「貧しい国ニツポン」「一億総下流社会」として警鐘を鳴らす。
コロナ、ウクライナ危機、円安、慢性デフレ・・・・・・。人口減少・少子高齢社会、AI ・ロボット・ DX などの急進展、レベルの変わった災害、地球環境やエネルギーなどの構造的問題・・・・・・。日本は大変な問題に直面している。腹を決めてこの勝負の10年に挑まなければ日本に未来はない。それを「貧しい国ニツポン」「一億総下流社会」として警鐘を鳴らす。
「安い日本」を、「ビッグマック指数」の価格比較で見れば、日本390円に対して、物価が高いことで知られるスイスの804円、ノルウェーの737円、アメリカの669円、そしてタイは443円、中国442円、韓国440円。しかもこれが今年年初の1ドル115円の換算というから恐ろしい。本書では、第3章の「金融とエネルギーの問題は表裏一体」、第4章の「世界金融戦争勃発〜知られざる経済制裁」が、ロシアへの経済制裁や経済制裁の最終兵器「 OFA C規制」などを通じて描かれ面白い。いずれにしても「米国の動きをよく見る」ことが重要・不可欠と解説する。日本を、「一億総下流社会」にしてはならないという思いは伝わってくる。

