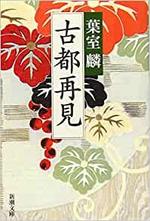 「人生の幕が下りる。近頃、そんなことをよく思う。・・・・・・今年(2015)から京都で暮らしている。何度か取材で訪れた京都だが、もう一度、じっくり見たくなった。古都の闇には生きる縁となる感銘がひそんでいる気がする。幕が下りるその前に見ておくべきものは、やはり見たいのだ(薪能)」「このエッセイの連載は、――幕が下りる、その前にとサブタイトルをつけた。幕が下りる前にしなければならないことがある(義仲寺)」とある。京都の街に潜んでいる人と歴史を探訪する実に味わい深い珠玉のエッセイ68篇。感動的。早く亡くなったことが残念に思われるが、その後出版された本を何冊も読んだゆえに、余計に死が惜しまれる。
「人生の幕が下りる。近頃、そんなことをよく思う。・・・・・・今年(2015)から京都で暮らしている。何度か取材で訪れた京都だが、もう一度、じっくり見たくなった。古都の闇には生きる縁となる感銘がひそんでいる気がする。幕が下りるその前に見ておくべきものは、やはり見たいのだ(薪能)」「このエッセイの連載は、――幕が下りる、その前にとサブタイトルをつけた。幕が下りる前にしなければならないことがある(義仲寺)」とある。京都の街に潜んでいる人と歴史を探訪する実に味わい深い珠玉のエッセイ68篇。感動的。早く亡くなったことが残念に思われるが、その後出版された本を何冊も読んだゆえに、余計に死が惜しまれる。
「ふと、京を逃れて一騎駆けをした武将がいたことを思い出した。源平争乱の時代を切り裂く稲妻のように生きた木曽義仲だ。義仲のどこに魅かれるかと言えば、誰しも最後はひとりだ、という感慨ではないか(薪能)」「ゾシマ長老と法然」「漂泊の俳人尾崎放哉が見た京の空」「最澄と空海(比叡山)」「千利休始め、山上宗二、古田織部など名だたる茶人が非業の死を遂げたのはなぜだろうか(大徳寺)」「漱石の失恋」「龍馬暗殺」に始まる68篇は、いずれも味わい深い。「梶井基次郎の名作『檸檬』の舞台となった京都の書店・丸善、大爆発(檸檬)」「信長が定宿とした本能寺、比叡山と法華宗の戦いの中で本能寺の変を見る(本能寺)」「与謝蕪村の本当の寂しさ(蕪村)」「芹沢は尊攘派が没落した京都に取り残された。・・・・・・この時期まで芹沢が生きていれば、上洛を目指す天狗党に京で呼応しようとしただろう(芹沢鴨)」「山科に隠棲した大石(大石内蔵助の『狐火』)」「高山彦九郎の土下座」「禁門の変の埋火」「京都の島原と島原の乱(島原縁起)」「一休さんが復興した大徳寺(利休の気魄、一休の反骨)」「三条木屋町の『長浜ラーメン』」「西郷が亡くなる瞬間まで肌身離さず持っていた橋本左内の手紙(西郷の舵)」「紫式部の惑い」「庶民世界に根ざした龍馬の手紙」・・・・・・。
京都の街に潜む人間と歴史――7年も京都に住んでいたが何も見なかったなぁ、前ばかり見て走り回っていたなぁとつくづく思う。もったいない。
 28歳にして「終止符のない人生」とは何か、と興味を持ったが、反田恭平さんには確かに終止符はない。その深く、広く、3次元空間を爆走するエネルギーに驚嘆する。尻をぶっ叩かれた思いだ。
28歳にして「終止符のない人生」とは何か、と興味を持ったが、反田恭平さんには確かに終止符はない。その深く、広く、3次元空間を爆走するエネルギーに驚嘆する。尻をぶっ叩かれた思いだ。
ピアニストの世界で、オリンピックやサッカー・ワールドカップのようなすごい大会「ショパン国際ピアノコンクール」で、日本人として51年ぶりの2位の快挙を遂げた反田さん。サッカー少年でもあった反田さんは、骨折を経てピアニストの道に没入する。2012年、高校在学中に日本音楽コンクールで第1位に、2014年にチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院本学科に首席で入学。言葉もわからないロシアでの苦闘が語られる。2015年のイタリアの国際ピアノコンクールで優勝するが、これは無謀とも武勇伝ともいうべき挑戦で、およそ繊細だと思われるピアニストの真逆の行動と生命力に、何か心持よい笑いさえこみ上げる。「いかなる場所でも手を抜くな」「誰がどこで聞いているかわからない。チャンスは目の前にあるといつも思え」――TBS「情熱大陸」でも語っている通りだ。2017年より、ポーランドのフレデリック・ショパン国立音楽大学(ワルシャワ音楽院)に在籍。そして21年10月、第18回ショパン国際ピアノコンクールで第2位に輝く。言語絶する緊張感、一生を賭けた勝負が伝わってくる。かくも戦略性を持って挑むのか、壮絶な格闘技を思わせる。「1分1秒の瞬間瞬間に、永遠が凝縮されているかのような濃密な時間だった」「ああ、自分はなんと幸せ者なのか。ショパンに出会えたおかげで、僕の人生はこんなにも豊かになった。ピアノをやっていて本当によかった」「ステージでピアノを弾きながら、全身の細胞が歓びに打ち震えた。僕の夢のような40分間が終わった」と語る。
その凄まじさは、とどまることを知らない。ピアニストであるとともに、オーケストラを率いる指揮者でもあるのだ。さらに自身のレーベル設立、日本初"株式会社"オーケストラの結成、クラシック界のDX化、コロナ禍におけるオンラインサロンを立ち上げる。バーチャル・リアリティーとメタバースの未来に向け突き進み、アニメ音楽や映画音楽とクラシックの融合、さらには音楽学校設立プロジェクトに意欲的に挑む。文化芸術後進国・日本を覆し、「文化・芸術のソフトパワーによって新しい日本の未来を築く」「奈良を日本のワルシャワへ、いつの日か国際音楽コンクールを音楽の街・奈良で」「ハードパワーによって武力衝突しようとする殺伐とした世界を、僕は音楽の力によって変えていきたい」と言う。圧倒され、嬉しくなる。
 日本経済や政治は重要な局面に立っている。日本を取り巻く環境が変化し、高度成長を支えた諸制度・システムは、根源的な制度疲労を起こしている。それは「人口減少・少子高齢化」「低成長」「貧困化」の3つだという。私が常々言っている3つの構造変化、「人口減少・少子高齢社会」「AI ・IoT・ロボット等の加速」「レベルの変わった気候変動・大災害の頻発」、そして現在の日本の問題である「低成長と格差」と、問題意識は全く同じ。地球環境・エネルギー問題も大きな構造変化で、根源的な対策が必要である。政治が目の前の対応に追われることなく、時間軸を持った政治が展開されることが最重要だ。
日本経済や政治は重要な局面に立っている。日本を取り巻く環境が変化し、高度成長を支えた諸制度・システムは、根源的な制度疲労を起こしている。それは「人口減少・少子高齢化」「低成長」「貧困化」の3つだという。私が常々言っている3つの構造変化、「人口減少・少子高齢社会」「AI ・IoT・ロボット等の加速」「レベルの変わった気候変動・大災害の頻発」、そして現在の日本の問題である「低成長と格差」と、問題意識は全く同じ。地球環境・エネルギー問題も大きな構造変化で、根源的な対策が必要である。政治が目の前の対応に追われることなく、時間軸を持った政治が展開されることが最重要だ。
「改革の哲学」として3つを提起する。「哲学1 まず、リスク分散機能と再分配機能を切り分ける。その上で、真の困窮者に対する再分配を強化し、改革を脱政治化する」「哲学2 透明かつ簡素なデジタル政府を構築し、確実な給付と負担の公平性を実現する」「哲学3 民と官が互いに『公共』を作る」だ。そして25の日本再生への具体的なリストを提示する。さらに重要なことだが、財政赤字解消をはじめ、「打ち出の小槌」は存在しない。財政でも社会保障でも成長戦略でも、一つひとつの制度をきちんと問題を取り除き、効率的に設計し直していくという「地道な方法」しか日本を救う道はないと言う。そしてできる限り迅速に適正なものにしていくことの重要性を指摘する。
25 のTo Doリストは微修正ではない。しかしやれそうなものだ。「マイナンバー利活用の推進と行政手続きのオンライン化」「所得が500万円以下でも、そのサラリーマンの源泉徴収額などの所得情報が集まるよう、源泉徴収制度のルールを改める」「年末調整の簡素化やギグ・ワーカー向け控除」「年金の2階部分について積立方式への移行を検討」「高齢者向けベーシックインカム(10万円)、10年確定年金」「年金ダッシュボードの導入」「医療機関版マクロ経済スライドの導入」「コンパクト+ネットワークで国土づくりをする」「地方財政を圧迫している赤字病院を選択と集中で再編する」「データ金融革命を日本経済の成長分野と捉えいっそうの投資を行う」「デジタル通貨の発行、情報銀行の設立」「データ証券化によってビッグデータ、AI分野の投資を加速させる」「教育格差の縮小のため所得連動型ローンを拡充する」「減価する『デジタル通貨』を活用し、財政赤字の一部を縮減する方策を取る」・・・・・・。考え抜いた具体論を提起している。
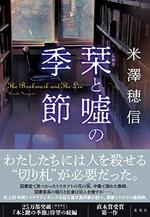 評判を呼んだ連作短編集「本と鍵の季節」に出てきた高校で図書委員をつとめる堀川次郎と松倉詩門のコンビが再び登場する青春ミステリー。今度は長編。ごく普通の高校生活の中で出てきた事件を、友情も絡めて丁寧に解き明かしていく。
評判を呼んだ連作短編集「本と鍵の季節」に出てきた高校で図書委員をつとめる堀川次郎と松倉詩門のコンビが再び登場する青春ミステリー。今度は長編。ごく普通の高校生活の中で出てきた事件を、友情も絡めて丁寧に解き明かしていく。
ある日、図書館の返却された本の中に、猛毒のトリカブトの花の栞を見つける。そして写真コンテストで金賞を撮った写真が保健室の隣に掲示され、その写真モデルはなんとトリカブト持ってジャンプしているものだった。撮影・岡地恵、モデル・和泉乃々花とあり、共に同じ高校に通う生徒だった。堀川と松倉のニ人は、校舎の裏でトリカブトが栽培されているのを見つける。また、瀬野麗が、校舎裏の花壇からトリカブトを抜いて埋める姿を目にする。そしてついに、嫌われていた教師が中毒で救急搬送されてしまう事態が生じ、学校内に不安が広がっていく。堀川と松倉に瀬野が加わり、真相を追っていく。「なぜ猛毒のトリカブトの花が栞に?」・・・・・・。緻密な謎解きが展開される。「わたしたちには人を殺せる"切り札"が必要だった」と言うのだが・・・・・・。
連続殺人事件があるわけでもない。血の臭いもなく淡い日常が続くが、その中に謎や不安の出来事があり、それぞれの人が、全部を晒すわけでもなく、半分は隠し、少しは「嘘」を交えて生きていく。そんなデリケートな「間合い」が、絶妙なタッチで描かれていく。
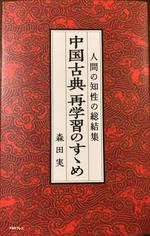 「死刑のハンコ」失言などと言われ、法務大臣が更迭となった。「軽率」などではなく、人間存在の「軽さ」が問題であろう。「綸言汗の如し」だ。本書は今年90歳になった森田先生が、青年時代から学び続けてきた「中国の古典」を「再学習のすゝめ」としてまとめたもの。「中国古典は最も優れた人間の知性の総結集だと私は思っている」「中国の古典は汲めども尽きぬ知恵と知識の黄金の泉である。中国古典を学ぶことによって、われわれは、いかに生きるべきかを学ぶことができる」と言う。選び抜かれた箴言・金言・警句・格言は、あまりにも深く、重く、森羅万象の真実を突く。「軽さ」が指摘される政治家は特に、再学習が不可欠だろう。いやこれまで学んでこなかったが故に、政治世界が軽くなってしまったのではないか。人間哲学不在では、困難をきわめる複雑な社会の変革は成し遂げられない。
「死刑のハンコ」失言などと言われ、法務大臣が更迭となった。「軽率」などではなく、人間存在の「軽さ」が問題であろう。「綸言汗の如し」だ。本書は今年90歳になった森田先生が、青年時代から学び続けてきた「中国の古典」を「再学習のすゝめ」としてまとめたもの。「中国古典は最も優れた人間の知性の総結集だと私は思っている」「中国の古典は汲めども尽きぬ知恵と知識の黄金の泉である。中国古典を学ぶことによって、われわれは、いかに生きるべきかを学ぶことができる」と言う。選び抜かれた箴言・金言・警句・格言は、あまりにも深く、重く、森羅万象の真実を突く。「軽さ」が指摘される政治家は特に、再学習が不可欠だろう。いやこれまで学んでこなかったが故に、政治世界が軽くなってしまったのではないか。人間哲学不在では、困難をきわめる複雑な社会の変革は成し遂げられない。
本書は「論語」「老子」「孟子」に始まり、「荀子」「韓非子」「孫子」「史記」「大学」「中庸」を紹介する。そしてアリストテレスの「ニコマコス倫理学」を挟み東西の哲学・思想が通底していることを示す。再び中国古典の「書経」「礼記」「詩経」「易経」「左伝」「墨子」「管子」「列子」「荘子」「菜根譚」「孝経」「忠経」「小学」を紹介し、再学習をすすめる。最後に私も感動した林大幹著「四十にして志を立つ安岡正篤先生に学ぶ」を紹介する。「政をなすに徳をもってす(徳のない政治は必ず堕落する)」「中庸は最善の道徳だ」「上善は水の若し」「儒教の精神である仁義礼智信――孔子は仁を、孟子は義を、荀子は礼を強調した」「人間関係において最も大切なものは礼節であると私は思う」「政治の目的は最高善の実現にある。今こそ、孔子、釈迦、アリストテレスの中庸・中道思想を現代に生かさなければならない」「荘子はすべての変化を支配する根本原理を『道』と呼んだ」・・・・・・。森田先生の姿に清々しい至誠を感じる。

