 外国人との共生、共に働く日本社会を築くことは、未来を考えてもますます重要なこと。入管の実態や技能実習の現状、難民の受け入れ等について、フォトジャーナリストとして現場で相談を受け、取材したレポートと対談。
外国人との共生、共に働く日本社会を築くことは、未来を考えてもますます重要なこと。入管の実態や技能実習の現状、難民の受け入れ等について、フォトジャーナリストとして現場で相談を受け、取材したレポートと対談。
「そもそも『収容』とはどんな措置なのだろうか。仕事を失ってしまったとか、困難を抱えて学校に通えなくなってしまった、パートナーと離婚した――それは生活していれば誰にでも起こり得る生活の変化のはずだ。けれどもこの変化によって、日本国籍以外の人々は、日本に暮らすための在留資格を失ってしまうことがある」「『収容』とは本来、在留資格を失うなどの理由で、退去強制令を受けた外国人が国籍国に送還されるまでの準備として設けられた措置のはずだった。人を施設に収容するということは、身体を拘束し、その自由を奪うことであり、より慎重な判断が求められるべき措置のはずだ」「ところが実態を見てみると、収容や解放の判断に司法の介在がなく、入管側の一存で、それも不透明な意思決定によって決められていく。しかも収容期間は事実上無期限だ」と厳しく言う。そして「全件収容主義」「外国人は常に管理、監視、取り締まりの対象とされてきた戦前からの見方」を糾弾し、「難民であれ、移民であれ、在留資格を持たない者たちが一様に、犯罪者扱いされるのが日本」と言う。「人権なんてここには全くない」とし、名古屋のウィシュマさんの死亡事件、ベトナム人の女性技能実習生のリンさんが死体遺棄罪に問われた事件など現場の実態を報告する。
「長きにわたり、日本社会は内に差別と偏見を抱えてきた。私たちの社会は、未だ差別を克服していない」と糾弾する。外国人とともに地域で共に生き働く社会へ、現在、大事な時となっている。
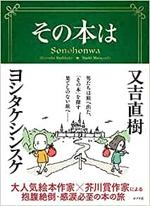 又吉直樹と絵本作家のヨシタケシンスケによる、世にも不思議な本の物語。童話のようでもあり、中身は辛辣な比喩の物語でもあり、泣き笑いも、それぞれにオチがついて、こんな発想があるのかと「本を探す旅」に連れていかれる。本の大好きな王様がいて、もう年寄りで目が見えなくなってきている。「目が悪くなり、もう本を読むことができない。でもわしは本が好きだ。お前たち、世界中をまわって『めずらしい本』について知っている者を探し出し、その本についての話を聞いてきて、わしに教えてほしいのだ」・・・・・・。旅に出たニ人の男はたくさんの本を持ち帰る。
又吉直樹と絵本作家のヨシタケシンスケによる、世にも不思議な本の物語。童話のようでもあり、中身は辛辣な比喩の物語でもあり、泣き笑いも、それぞれにオチがついて、こんな発想があるのかと「本を探す旅」に連れていかれる。本の大好きな王様がいて、もう年寄りで目が見えなくなってきている。「目が悪くなり、もう本を読むことができない。でもわしは本が好きだ。お前たち、世界中をまわって『めずらしい本』について知っている者を探し出し、その本についての話を聞いてきて、わしに教えてほしいのだ」・・・・・・。旅に出たニ人の男はたくさんの本を持ち帰る。
そして王様に毎夜にわたって世にも不思議な物語を語るのだ。よくもこんなに不思議な話が作れるものだと感心する。「第7夜」は、他に比べて長いが、絵本作家になりたいと願う少年・少女のやりとりが、なんとも切なく、また爽やかに心に迫ってくる。全体を通じて「本っていいな」と思わせる。
 「カシの胸が高鳴る。これこそわたしが探していた物語だ。強く優しい母親と率直で健気な男の子。頑迷な夫の父親の気持ちをも変えていく――。ここには、日本の封建的な身分制度に近い環境があり、そんな中、逆境に置かれても子を育てる母の強い愛がある。そしてその母の愛を受け、育てられた子が古い価値観をものともせず、健やかに成長する。求めていた物語が見つかった! その興奮をカシは抑えきれず......。その日から、カシは翻訳に取り組んだ」――。若松賤子が「小公子」と出会った瞬間だ。「この一冊が、子どもたちへ、子を持つ多くの母親たちへ、そして児童文学という新たな道を開く嚆矢となると信じていたに違いない」と語る。
「カシの胸が高鳴る。これこそわたしが探していた物語だ。強く優しい母親と率直で健気な男の子。頑迷な夫の父親の気持ちをも変えていく――。ここには、日本の封建的な身分制度に近い環境があり、そんな中、逆境に置かれても子を育てる母の強い愛がある。そしてその母の愛を受け、育てられた子が古い価値観をものともせず、健やかに成長する。求めていた物語が見つかった! その興奮をカシは抑えきれず......。その日から、カシは翻訳に取り組んだ」――。若松賤子が「小公子」と出会った瞬間だ。「この一冊が、子どもたちへ、子を持つ多くの母親たちへ、そして児童文学という新たな道を開く嚆矢となると信じていたに違いない」と語る。
幕末の1864年、会津で生まれ、戊辰戦争を生き延びた孤独な少女・松川カシ。かぞえ8歳、横浜の大川の養女となる。寄宿学校のフェリス・セミナリーに移り、学び、受洗する。「女性が、自らの意志を持って、羽ばたいていることだ。堂々と大きな翼を広げ、時に雛鳥の私たちを包み込み――それは誰かの強制ではなく、慣習でもない。志を持った、凛としたその姿だ」・・・・・・。カシはキダー先生の姿に、女性の自立と子供の幸せを希求し、女学校フェリス・セミナリーの先生となっていくのだ。そして明治の文学者、翻訳者として歩み出す。肺結核に侵されながらも、翻訳者として、教師として、母として懸命に生きる姿は、美しさを通り越して壮絶だ。療養のために住み、ひと時も休まず仕事をしたのが王子村下十条。なんと私の地元。「命を燃やし尽くした31年の生涯」とあるが、全くその通り。「未だに女性の地位は低く、権利も得ていません。でも、わたしが語りかけたこと、してきたことが、未来につながればと思っています」とあるが、その一筋の道は間違いなく時代を切り開いている。
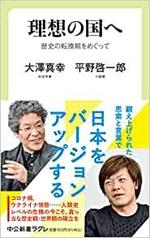 「歴史の転換期をめぐって」が副題。コロナ禍、ロシアのウクライナ侵略、日本社会の極端な凋落・・・・・・。破局への予感を秘めた転換の渦中にある今、「考えに考え抜くことが、今ほど必要な時はない」としてニ人が対談する。「人類史レヴェルの移行期」という時代認識のなか、「平成を経て日本はどう変化したのか」と問いかけ、「自分探し」を続けた平成という時代であり、「虚勢を張った自慢(日本はスゴイ)」「幸福への意識が変化(若い人と高齢者の満足度が高く、30代、40代が不幸を感じている傾向が強い)」「中国への嫌悪が高まる」と、希望が枯渇し希望に飢えている時代となっていると指摘する。そしてアメリカのベースボールに、イチローのやり方で切り込んだように、日本的で特殊な考え方と国際的に通用する普遍性とが直結したことをヒントとすべきだ、という。
「歴史の転換期をめぐって」が副題。コロナ禍、ロシアのウクライナ侵略、日本社会の極端な凋落・・・・・・。破局への予感を秘めた転換の渦中にある今、「考えに考え抜くことが、今ほど必要な時はない」としてニ人が対談する。「人類史レヴェルの移行期」という時代認識のなか、「平成を経て日本はどう変化したのか」と問いかけ、「自分探し」を続けた平成という時代であり、「虚勢を張った自慢(日本はスゴイ)」「幸福への意識が変化(若い人と高齢者の満足度が高く、30代、40代が不幸を感じている傾向が強い)」「中国への嫌悪が高まる」と、希望が枯渇し希望に飢えている時代となっていると指摘する。そしてアメリカのベースボールに、イチローのやり方で切り込んだように、日本的で特殊な考え方と国際的に通用する普遍性とが直結したことをヒントとすべきだ、という。
「世界から取り残される日本」では、三島由紀夫を取り上げ、「あの三島がその三島になった理由」を語り、時代を掘り下げる。さらに「破局を免れるために――環境・コモン・格差」では、斎藤幸平「人新世の資本論」を論じつつ、「分人主義」と「コモン」の関係性と可能性に触れる。また、ロシアのウクライナ侵略をめぐって「国を愛する」を論じる。「手段の正義」と「目的の正義」。普通は愛国主義者と普遍主義者は対立すると考えられるが、「本当に信頼できるのは、愛国主義者であるがゆえに普遍主義者であるような人だと思う」と言う。環境問題、コロナ、ロシアのウクライナ侵略などの世界的課題にさらされている今、国民国家を超えた連帯をどうするか、世界の中で日本がよりよく生きるために、外交努力や相互理解をどうつくるか、「経済的に豊かで、平和を国是としている日本」にどう進むか語り合っている。
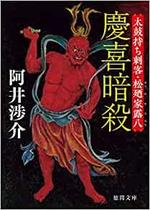 「あなたは、なぜ大阪城から、独り逃げたのか」――。鳥羽伏見の戦いで壮絶・過酷な目にあった元旗本で彰義隊にも加わった土肥庄次郎は、静岡で蟄居する慶喜に怒りをもち、暗殺を企てる。時は版籍奉還前後の明治初頭。政情は定まらず、静岡には江戸から流入する武士や食い扶持を探す人、ひと儲けをもくろむ商人・・・・・・、いずれも時代の激動にさらされ翻弄されて混乱の極みにあった。鳥羽伏見の戦いで生死不明になった友・白戸利一郎と妻の奈緒、慶喜を守ろうとする剣豪・榊原鍵吉、暗殺された坂本竜馬の仇を討とうとする者たちが交差する。また大谷内龍五郎、桐野利秋、西郷隆盛、勝海舟、松浦武四郎、唐人お吉、清水の次郎長、渋沢栄一、榎本武揚などが現われ、接触・交流する。「武士道を貫く」「人は何のために生きるのか」「恨みを晴らすとは何のためなのか」と、急変した日本社会の中で葛藤し、翻弄される姿が浮き彫りにされる。ダイナミックにそれぞれの人の生き様を描いていく。
「あなたは、なぜ大阪城から、独り逃げたのか」――。鳥羽伏見の戦いで壮絶・過酷な目にあった元旗本で彰義隊にも加わった土肥庄次郎は、静岡で蟄居する慶喜に怒りをもち、暗殺を企てる。時は版籍奉還前後の明治初頭。政情は定まらず、静岡には江戸から流入する武士や食い扶持を探す人、ひと儲けをもくろむ商人・・・・・・、いずれも時代の激動にさらされ翻弄されて混乱の極みにあった。鳥羽伏見の戦いで生死不明になった友・白戸利一郎と妻の奈緒、慶喜を守ろうとする剣豪・榊原鍵吉、暗殺された坂本竜馬の仇を討とうとする者たちが交差する。また大谷内龍五郎、桐野利秋、西郷隆盛、勝海舟、松浦武四郎、唐人お吉、清水の次郎長、渋沢栄一、榎本武揚などが現われ、接触・交流する。「武士道を貫く」「人は何のために生きるのか」「恨みを晴らすとは何のためなのか」と、急変した日本社会の中で葛藤し、翻弄される姿が浮き彫りにされる。ダイナミックにそれぞれの人の生き様を描いていく。
「だが、口から出たのは、己にさえ信じられぬ言葉だった。『上様』・・・・・・一体なんだ、これは――」「あなたは、なぜ大阪城から、独り逃げたのか」「そういうものである。慶喜は小さく明確に言った」・・・・・・。「君、君たらずとも、臣、臣たるべし」と武士道を貫こうとした者もいるなかでの慶喜の言葉。それに対峙した庄次郎の反骨精神が、幇間の松廼家露八となっていく。凄まじい世界を垣間見る。

