 「現代の問題を解決しうる名著の知恵」が副題。この20年位を見ても問題が解決できないで、停滞してることが多い。社会の激変に政治・経済が対応できていないのだ。「世界に類を見ない長期にわたる緩やかなデフレ」「構造改革、抜本的な改革の大合唱」「官僚主導を覆せ」「新自由主義の推進と大批判」「ロシアのウクライナ侵略とは何か」「安倍元首相銃撃事件」----。確かに「この問題をどう考えるか」「整理して本質を考える」ということがあまりにも混乱して、情緒的にある方向に持っていかれていることを憂う毎日だ。中野さんは「社会学の古典を読んでおけば、政治や経済において、どんなことをやったらどういう結果になるのか、おおよそ見えてくる」という。
「現代の問題を解決しうる名著の知恵」が副題。この20年位を見ても問題が解決できないで、停滞してることが多い。社会の激変に政治・経済が対応できていないのだ。「世界に類を見ない長期にわたる緩やかなデフレ」「構造改革、抜本的な改革の大合唱」「官僚主導を覆せ」「新自由主義の推進と大批判」「ロシアのウクライナ侵略とは何か」「安倍元首相銃撃事件」----。確かに「この問題をどう考えるか」「整理して本質を考える」ということがあまりにも混乱して、情緒的にある方向に持っていかれていることを憂う毎日だ。中野さんは「社会学の古典を読んでおけば、政治や経済において、どんなことをやったらどういう結果になるのか、おおよそ見えてくる」という。
8人が選ばれている。マックス・ウェーバー。「なぜ組織改革は失敗するのか」「官僚制は、徹底的に効率的で合理的な組織を志向する」「効率性の追求が非効率を生む」「数値だけで測定できない価値。数値による業績評価がもたらす弊害」・・・・・・。
エドマンド・バーク。「急がば回れ。社会は複雑なものであるのに対して、人間の理性には限界がある。そこにエドマンド・バークが革命とか抜本的改革に反対した所以がある」「改革とは、少しずつ改善を積み重ねること。この国の伝統を守りつつ、改革を行う、それが本当の保守」「漸変主義こそ実は近道」・・・・・・。
アレクシス・ド・ トクヴィル。「アメリカの民主政治を見て、多数者の専制に気づいたトクヴィル」「平等が進むほど全体主義化する。平等は人々をバラバラにし、人を結束させる紐帯を引き離す」「人々の絆が社会を豊かにする。平等な民主的社会では、中間団体が必要になる。アメリカ社会には、こうした中間団体がたくさん形成されていた」「日本は構造改革と称して、自国の社会関係資本を破壊して、社会のあちこちに市場原理を持ち込む改革を始めた。日本企業は共同体的な経営を止め地域の共同体は衰退し人間関係が希薄になった」・・・・・・。
カール・ポランニー。「経済人類学者カール・ポランニーが1944年に著した『大転換』。市場が自然環境を破壊し自然や人間を飛んだの商品にしていく。この自然や社会をすりつぶしていく市場メカニズムを『悪魔の碾き臼』と呼んだ」「市場に任せればうまくいくというイデオロギー・新自由主義と、自然・人間・産業組織を守る『社会防衛の原理』」とあり、新自由主義から一刻も早く脱却せよという。
エミール・ デュルケーム。「自殺はどうすれば防げるのか。厳しい宗教は自殺が少なく、個人主義者は自殺に向かいやすい。社会から切り離された個人は、生きる意味を失って、自殺に走る」「人間には、共同体との絆が必要」「突然の社会変化が自殺を減らす。政変や戦争という危機が、社会を結束させる」「宗教社会、家族社会、政治社会の統合の強さに反比例して、自殺は増減する」「そこそこの満足が自殺を抑制する。小泉構造改革で日本の既存の経済社会の構造は破壊され、日本人は生きる意味を失った。自殺を防ぐのは、宗教や家族の機能、職業集団や同業組合の個人を統合した社会の存在。トクヴィルのいう中間団体だ。共同体的な日本的経営は重要ででたらめな改革を日本はやってきたことになる」・・・・・・。
E・H・カー。「危機のニ十年」を取り上げているが、最近、「歴史とは何か」が新版となった。「歴史とは、現在と過去の間の終わりのない対話である」だ。「どうして戦争は起こるのか」「世論は道徳的な社会を望むというユートピアニズム。人間の理性の力を信じる合理主義が基盤だ。しかしユートピアニズムは、理想と現実のギャップという難題にぶつかる。そこに批判的な思考様式としてリアリズムが出る。リアリズムは現実の政治は、力関係や利害関係のみによって決まると考えがちになる。結局のところ、政治とは理想と現実の相互作用の過程である」という。「ユートピアの実現を目指して行動し、リアリティーの壁にぶつかって失敗する。リベラリズムを目指した政治を行って、リベラルではない結果を招く。それを繰り返すのが国際政治というものなのかもしれない」「カーは国際政治における権力には、①軍事力②経済力③意見を支配する力(プロパガンダ)の3つがあると指摘する」が、これらはロシアのウクライナ侵略にぴったり当てはまる。同時にカーは「個人間と同様、国家間にも道義はある」と言っている。
ニコロ・マキアヴェッリ。「政治は、刻々と変化する状況に応じて、臨機応変に対応する技術でなければならない」。リアリストの祖であるマキアヴェッリの哲学だ。
ジョン・メイナード・ケインズ。「市場原理に任せれば、需要と供給は自然に一致するので、政府は市場に介入せず、民間企業の自由放任にゆだねておけば良い」という古典派経済学の思想。その原理を批判するために「お札を詰めた壺を廃坑に埋めて掘り返したほうがまだマシ」との皮肉を言った。不況の時における財政政策の必要性を述べる。「不確かな社会で、どうやって将来に向けて投資を行うのか。資本主義を動かすのは、人々の思い込みや勘違い」との人間洞察に立つ。ケインズは死んではいない。中野さんは「金融市場の活性化によって成長するのは投機であって、必ずしも企業ではない」と言う。
そして「社会科学の教養を踏まえない議論が『失われた30年』を招来した」と警告を発する。貫かれているのは、現実を直視したリアリズム。臨機応変の知恵が政治にとって不可欠ということ。そして共同体。政治イデオロギーも、経済イデオロギーも、イデオロギーとして確立されれば、現実と離れた思考停止に陥るということだろう。
 「ホモ・サピエンスの『信じる心』が生まれたとき」が副題。「私たちホモ・サピエンスが社会を作り始めた出発点、人が人であるようになった時、同時に宗教が生まれた」「本書では、ゴリラやチンパンジーと地続きの人類史を、山極先生の知見に導かれながらたどってきた。歴史の変遷のなかで、とりわけ、近代化・産業化のなかで、人間が失いつつあるものは少なくない。直観や身体性も、そのなかに入っている。宗教は世俗化のなかで、風前の灯火のように見られた時期もありましたが、形を変えつつ、しぶとく生き残っている」「資本主義経済が世界を席巻し、動物が単に消費や娯楽の対象とされる時代のなかで、過剰なほどの人間中心主義に批判的な光を当て、生き方の再考を促すのは、豊穣な生命観を継承してきた伝統宗教の務めであるに違いない」「人間は想像力を駆使し、それによって生み出された知識や物語を共有することによって活動範囲を広げて、集団規模を大きくしてきた。言葉こそが人間とそれ以外の動物を分けたといえる。人間は知覚する現実についての情報交換をするだけでなく、創造した物語を共有できる点が特異です」「山極先生は、人間集団をつなぎとめる力としての宗教の有用性を評価しつつ、同時にそれが、集団外の存在に対し暴力的になることを批判されている。人間に特徴的な集団の結束力を言語や想像力、宗教によって高めた結果、外部集団との軋轢がいっそう大きくなった、共感能力の暴発だ」「西洋の哲学はアリストテレス以来、すべてロゴスの哲学です。だが、その哲学ではやっていけなくなってきた。AIや言葉、情報が扱いきれなくなってきている。そこでもう一度人間の心性、心の領域に戻って、主体と客体を分離しない、合一された地平に戻って考えるべきではないか。・・・・・・生物の動きは人間の直観でしか理解できない。福岡伸一氏の動的平衡だ。生命の形相ではなく、生命の実在を論じる時代に来ている気がする。生命の本質は宗教の根源にも関わる問題です」「家畜が生まれ、栽培植物が生まれて、人間は食料を生産するようになり、人間独自の世界観や環境観が始まる。一番大きなことは未来を予測するようになったこと。過去の事実を言葉によって伝え、時空を超えて未来を予測するようになった。それが宗教の出発点だと思う」「しかし、言葉や情報の性質がだんだん人間の身体性から離れ、自由に一人歩きをし始めた。AIは人間の持っている意識と知能と分けて、知能の領域を特化させたものです。そこでは意識は常に置き去りにされる。人間の直観や身体感覚が非常に重要だ」「人間の身体や心はまだ自然の中にいるのだが、その感覚が人工的な環境とミスマッチを起こしている」などと語り合う。暴力やAI時代の中で、霊長類学者と宗教学者の議論は、極めて根源的であり、人類史における宗教の存在に迫るとともに、AIやデータやシステムに翻弄され、身体性をますます失う現代の本質的課題を突きつける。
「ホモ・サピエンスの『信じる心』が生まれたとき」が副題。「私たちホモ・サピエンスが社会を作り始めた出発点、人が人であるようになった時、同時に宗教が生まれた」「本書では、ゴリラやチンパンジーと地続きの人類史を、山極先生の知見に導かれながらたどってきた。歴史の変遷のなかで、とりわけ、近代化・産業化のなかで、人間が失いつつあるものは少なくない。直観や身体性も、そのなかに入っている。宗教は世俗化のなかで、風前の灯火のように見られた時期もありましたが、形を変えつつ、しぶとく生き残っている」「資本主義経済が世界を席巻し、動物が単に消費や娯楽の対象とされる時代のなかで、過剰なほどの人間中心主義に批判的な光を当て、生き方の再考を促すのは、豊穣な生命観を継承してきた伝統宗教の務めであるに違いない」「人間は想像力を駆使し、それによって生み出された知識や物語を共有することによって活動範囲を広げて、集団規模を大きくしてきた。言葉こそが人間とそれ以外の動物を分けたといえる。人間は知覚する現実についての情報交換をするだけでなく、創造した物語を共有できる点が特異です」「山極先生は、人間集団をつなぎとめる力としての宗教の有用性を評価しつつ、同時にそれが、集団外の存在に対し暴力的になることを批判されている。人間に特徴的な集団の結束力を言語や想像力、宗教によって高めた結果、外部集団との軋轢がいっそう大きくなった、共感能力の暴発だ」「西洋の哲学はアリストテレス以来、すべてロゴスの哲学です。だが、その哲学ではやっていけなくなってきた。AIや言葉、情報が扱いきれなくなってきている。そこでもう一度人間の心性、心の領域に戻って、主体と客体を分離しない、合一された地平に戻って考えるべきではないか。・・・・・・生物の動きは人間の直観でしか理解できない。福岡伸一氏の動的平衡だ。生命の形相ではなく、生命の実在を論じる時代に来ている気がする。生命の本質は宗教の根源にも関わる問題です」「家畜が生まれ、栽培植物が生まれて、人間は食料を生産するようになり、人間独自の世界観や環境観が始まる。一番大きなことは未来を予測するようになったこと。過去の事実を言葉によって伝え、時空を超えて未来を予測するようになった。それが宗教の出発点だと思う」「しかし、言葉や情報の性質がだんだん人間の身体性から離れ、自由に一人歩きをし始めた。AIは人間の持っている意識と知能と分けて、知能の領域を特化させたものです。そこでは意識は常に置き去りにされる。人間の直観や身体感覚が非常に重要だ」「人間の身体や心はまだ自然の中にいるのだが、その感覚が人工的な環境とミスマッチを起こしている」などと語り合う。暴力やAI時代の中で、霊長類学者と宗教学者の議論は、極めて根源的であり、人類史における宗教の存在に迫るとともに、AIやデータやシステムに翻弄され、身体性をますます失う現代の本質的課題を突きつける。
「実は言葉こそが、人間とそれ以外の動物と分けたのだ」「しかし、自然の変化を感じ対応していくのが生きるということであったが、人間は言葉をしゃべり始めてから自然と対話して生きるということからどんどん離れ始めた」――人間、言葉、自然そしてわれわれはどこへ向かうのか、という問題だ。アフリカから脱出したホモ・サピエンスが食べ物を求めて集団で行動範囲を広げて採集して戻ってくる。それを食べる行為は、仲間が持ってきた食物を信じて、つまり仲間を信じて食べると言う行為だ。遠くで食物を獲得しようと活動する仲間の姿を想像し、食物の安全性を説明する――そこに言葉とコミニュケーションが生まれたという。
山極寿一氏は「ゴリラに学べ!」「大学はジャングルだ」という。つまり「我々は今、直観によって生きているのではなくて、情報によって生きつつある。昔は生身の身体で、あるいは生の経験から生じた物語を生きていた。宗教もその一つだと思うが。だから、生の現実にすぐ転換できたわけです。物語がその人の生きる意味になり、その人が他の人間や他の生物たちと付き合う根拠になり得る」「人間は、自分たちの意のままにならない圧倒的な自然の力の前で身体を駆使して生きなければなりませんでした。言い換えれば、人間はリアルな現実に身体的な根を下ろし、そこからバーチャルの世界に飛びたっていたわけです。現代において心配なのは、リアルとバーチャルの間を行ったり来たりする身体バランスを失い・・・・・・」「ゴリラに学べ!とは、自分の行為が他者にどう映っているのかを、常に直感的に判断できるようになる、ということ。自己判断が可能なこと、アイデンティティーを持つこと、危機判断ができること、そして他者を感動させることの4つです」・・・・・・。「宗教にとっても共感は利他性や隣人愛を発揮する上で大切ですが、それが身体性を失って、頭の中だけでバーチャルな形でラジカルな考えと結びつくと、外部への暴力に転じることにもなる」とも語り合う。
ホモ・サピエンスから集団を形成するに至った時、「人々をつないだのは宗教であった」わけだ。それが排他性を持ったり、暴力に転じたり、AI時代のバーチャル世界に人間が持っていかれる危険が目の前にある時、霊長類学者と宗教学者の「宗教の始源」「身体性」をめぐる語らいは有意義で、極めて面白い。
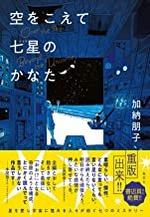 星にまつわる7つの短編。「南の十字に会いに行く」――「七星、南の島へ行くぞ」と、突然、父・寺地北斗に言われて石垣島に行く。中学の合格祝いということだが、去年と違って母がいない。後で謎が明かされるが、母・寺地舞亜は宇宙飛行士としてアメリカに行ったのだ。石垣島でも多くの人と不思議な出会い、縁を結ぶ。「星は、すばる」――同級生の過失で右目を刺された小学4年生の少女の話。星降る夜に「宇宙飛行士になる」と衝撃的な出会いをした「オイラ」は語る。まるで星の王子様みたいな少年の夢を聞き、「私も、宇宙飛行士になりたい」と思う。「箱庭に降る星は」――廃部寸前のオカルト研究会、天文部、文芸部の3つの部。成績抜群でトップ、スポーツ万能で美人の生徒会副会長が奇抜な提案をする。三部合同の「スぺミス部」を作って自らも加わるというのだ。「木星荘のヴィーナス」――お兄ちゃんが大学生になって上京、木星荘で容姿抜群、有名大学に通う頭脳明晰、明るくて親しみやすい金江さんに会う。そして「孤舟よ星の海を征け」「星の子」「リフトオフ」と続く。7つの短編と思いきや、すべての話が合流して、月へ向かう宇宙飛行士・寺地舞亜の壮行会に集まる。もちろん父も私(七星)も。生徒会副会長も金江さんも星の王子様も実は・・・・・・。
星にまつわる7つの短編。「南の十字に会いに行く」――「七星、南の島へ行くぞ」と、突然、父・寺地北斗に言われて石垣島に行く。中学の合格祝いということだが、去年と違って母がいない。後で謎が明かされるが、母・寺地舞亜は宇宙飛行士としてアメリカに行ったのだ。石垣島でも多くの人と不思議な出会い、縁を結ぶ。「星は、すばる」――同級生の過失で右目を刺された小学4年生の少女の話。星降る夜に「宇宙飛行士になる」と衝撃的な出会いをした「オイラ」は語る。まるで星の王子様みたいな少年の夢を聞き、「私も、宇宙飛行士になりたい」と思う。「箱庭に降る星は」――廃部寸前のオカルト研究会、天文部、文芸部の3つの部。成績抜群でトップ、スポーツ万能で美人の生徒会副会長が奇抜な提案をする。三部合同の「スぺミス部」を作って自らも加わるというのだ。「木星荘のヴィーナス」――お兄ちゃんが大学生になって上京、木星荘で容姿抜群、有名大学に通う頭脳明晰、明るくて親しみやすい金江さんに会う。そして「孤舟よ星の海を征け」「星の子」「リフトオフ」と続く。7つの短編と思いきや、すべての話が合流して、月へ向かう宇宙飛行士・寺地舞亜の壮行会に集まる。もちろん父も私(七星)も。生徒会副会長も金江さんも星の王子様も実は・・・・・・。
人生は価値創造。積極的に、決断して、自分を等身大に見ておごらず、たゆまず、まっすぐに、夢を持って。そして愛と涙で包む。周りは振り回されて大変だが、それもエネルギーでうまくいく。北斗七星と宇宙にきらめく星、夢の世界が描かれる。
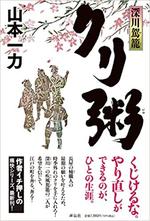 深川の駕籠舁き、江戸を疾駆する疾風駕籠の新太郎と尚平のコンビ。新太郎と同じ木兵衛店の店子である桶職人の鉄蔵が「俺はもうもたねえ」「幾日ももたねえのは、おれが一番わかっている」「おれの蓄えをそっくり遣って、死ぬ前に茶碗半分でもいいからクリ粥を食べたい」という。天明8年11月、もう寒くなっていて、クリの季節はとうに過ぎている。新太郎らは、懸命に走り回る。いろんな嫌がらせにも合うが、まさに「運は人の連鎖」――。まっすぐで、人の頼みとあれば何でもやる。一筋の新太郎らは、次々に助けを得て、ついにクリを獲得する。
深川の駕籠舁き、江戸を疾駆する疾風駕籠の新太郎と尚平のコンビ。新太郎と同じ木兵衛店の店子である桶職人の鉄蔵が「俺はもうもたねえ」「幾日ももたねえのは、おれが一番わかっている」「おれの蓄えをそっくり遣って、死ぬ前に茶碗半分でもいいからクリ粥を食べたい」という。天明8年11月、もう寒くなっていて、クリの季節はとうに過ぎている。新太郎らは、懸命に走り回る。いろんな嫌がらせにも合うが、まさに「運は人の連鎖」――。まっすぐで、人の頼みとあれば何でもやる。一筋の新太郎らは、次々に助けを得て、ついにクリを獲得する。
立派に葬式を終えるが、真面目な仕事ぶり、寡黙ながら人柄の良い鉄蔵は、54両もの慶長小判を残しており、新太郎と尚平に渡すとの遺言を木兵衛に託していた。何に遣うか・・・・・・。木兵衛店の横にある小さな空き地に桜の木を植えようとすることになる。ここでも2つも3つも難関があったが、木兵衛、桜の職人・棟梁の義三、花椿の女将・そめ乃----。多くの人々の腹を決める助力によって実現をみる。
「あの桜は、なおしの桜じゃの。住持のつぶやきに、あの木兵衛が背筋を震わせた。なおし酒を好み、吹上の桜を木兵衛店に呼び込んだ鉄蔵。くじけるな。やり直しができるのが、ひとの生涯」・・・・・・。江戸の街が目の前にあるような、その中での長屋、人情の深いつながりの生活、職人の生真面目さ、何よりも義侠心に厚く頼まれたら断れない(たてひきが強い) ひと、口数は少ないが引き受けた事は命がけでこなし、身体を張ってひとのために尽くせる男。「見て呉れだけの男はこの土地には無用だ」という江戸の世界が、なんとも魅力的に描かれる。貧しくとも良い時代というのが、日本には続いてきたのだろうか。
 「北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語」が副題。メディアでも紹介され話題となった北海道砂川市にある「いわた書店」が、2007年から始めた「一万円選書」――。当初は反響はなかったようだが2014年、テレビで紹介されるや一気にブレイク。放送3日後にはなんと555件の申し込みが来たという。ミソとなるのは「選書カルテ」。「これまで読んで印象に残っている20冊は」「これまでの人生で嬉しかったこと、苦しかったことは?」「一番したいことは何ですか?」などの問いに答えてもらって作るカルテ。それに基づいて一万円、10冊程度を選んで送るという。お客さんとのやりとりは何度も繰り返して行われる。熱意と配慮、想像力、これまでの読書量なくしてできないことだ。
「北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語」が副題。メディアでも紹介され話題となった北海道砂川市にある「いわた書店」が、2007年から始めた「一万円選書」――。当初は反響はなかったようだが2014年、テレビで紹介されるや一気にブレイク。放送3日後にはなんと555件の申し込みが来たという。ミソとなるのは「選書カルテ」。「これまで読んで印象に残っている20冊は」「これまでの人生で嬉しかったこと、苦しかったことは?」「一番したいことは何ですか?」などの問いに答えてもらって作るカルテ。それに基づいて一万円、10冊程度を選んで送るという。お客さんとのやりとりは何度も繰り返して行われる。熱意と配慮、想像力、これまでの読書量なくしてできないことだ。
「最近、面白い本はなんですか」と聞かれることは日常だが、「どんな本を読んだらいいですか」と、かつては多くの人に聞かれた。本を選ぶのは意外と難しいようだ。岩田さんの努力に心からの敬意と拍手を送りたい。
現実に選んで送った本が紹介されている。約90冊。読みたくなった本がいっぱいある。

