 「サイエンスの世界にようこそ」「科学は人の営み」「こんなに楽しい職業はない」「サイエンスは社会的な存在である」――。ノーベル賞等を受賞、基礎科学の第一線を走ってきた研究者の2人が語り合う。
「サイエンスの世界にようこそ」「科学は人の営み」「こんなに楽しい職業はない」「サイエンスは社会的な存在である」――。ノーベル賞等を受賞、基礎科学の第一線を走ってきた研究者の2人が語り合う。
「こんな役に立たない研究をしていていいんでしょうか」「失敗しないためにはどうすればいいですか」――今の社会は、「成果」が求められ、しかも短期で、どの分野でも。この風潮こそ最大の問題と警鐘を鳴らす。「こんなに楽しい職業はない」「研究者の醍醐味――世界で自分だけが知っている」「研究は面白いから、選択は面白い方を」「一番乗りよりも誰もやっていない新しいことを」「効率化し高速化した現代で、待つことが苦手になった私たち」「安全志向の殻を破る」「解くではなく問うを」「科学を文化に」と語り合う。社会も企業経営も大学などの研究も、短期の成果を求めるようになっている。株主資本主義も大学などの研究費削減も、短期の成果をますます求めている。日本の基礎研究が細る所以である。すべてに余裕がなくなっているのだ。「役に立つ」の呪縛から飛び立とう、と様々な角度から強調する。
寺田寅彦は「科学者になるには『あたま』がよくなくてはいけない。しかし一方でまた『科学者はあたまが悪くなくてはいけない』という命題も、ある意味ではやはり本当である」と言ったという。「いわゆる頭のいい人は、いわば足の速い旅人のようなものである。人より先に人のまだ行かない所へ行き着くこともできる代わりに、途中の道端あるいはちょっとした脇道にある肝心なものを見落とす恐れがある。頭の悪いのろい人がずっと後から遅れてきて、わけもなくその大事な宝物を拾っていく場合がある」「頭のいい人は見通しが利くだけに、あらゆる道筋の前途の難関が見渡される。そのためにややもすると前進する勇気を阻喪しやすい。頭の悪い人は前途に霧がかかっているためにかえって楽観的である」「頭の悪い人は、頭の良い人が考えて、だめに決まっているような試みを、一生懸命に続けている・・・・・・」と面白いことを言っている。また永田さんは「よいお友達というより『へンな奴』を友人に持つほうがはるかに面白いと思っている。へンな奴とは、自分にはないものを持っている奴ということでもある」と語る。大隅さんは、鷲田清一氏が紹介している言葉を引き、「ちょっと変わったヤツが必要なんですよ。優等生ばかりを集めていてもいい酒になりません。ブレンドウィスキーはいろいろな原酒を混ぜて造る。その時欠点のない原酒ばかり集めて造っても、『線が細い』ものにしかならないが、変わり者が混じることで初めて、ハッとするいいお酒ができるというのだ。研究者の世界と同じだと思わずうなずいてしまった」と言う。面白い話だ。「科学の価値も、芸術やスポーツ等と同じように、役に立つかという視点ではなく、未知のことが解明されることを人類の共通の資産として純粋に楽しむ社会であって欲しいと思う。私が『科学を文化の一つに』と考える真意である」とも言う。そして繰り返し「『役に立つ』との呪縛を解き放ち、知的好奇心から出てくるものが基礎科学だと思う」と二人は言う。社会の厚み、人間存在の深さが、基礎研究だけでなく試されている。
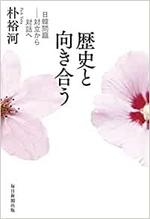 「日韓問題――対立から対話へ」が副題。本書の思いは「なぜ韓国に謝罪が届かないのか」という問いかけだ。その対立の原因や背景を分析し、関係改善を提言する書。「冷戦崩壊と日韓関係」「元徴用工訴訟問題」「慰安婦問題」「日韓併合・日韓協定」「歴史との向き合い方」の5章からなる。
「日韓問題――対立から対話へ」が副題。本書の思いは「なぜ韓国に謝罪が届かないのか」という問いかけだ。その対立の原因や背景を分析し、関係改善を提言する書。「冷戦崩壊と日韓関係」「元徴用工訴訟問題」「慰安婦問題」「日韓併合・日韓協定」「歴史との向き合い方」の5章からなる。
この30年、韓国では「加害者」日本は何ら謝罪も補償もないという声が勢いを増したという。386世代といわれる民主化闘争世代が1980年代、民衆意識で武装した市民として登場する。「民主化闘争は、多くの市民をリベラル化し、革新・進歩的な様々な価値観の植え付けにも寄与した」「慰安婦問題や元徴用工問題など、歴史認識運動に関わった人々が、意見の異なる人を『歴史修正主義者』『反歴史的』として非難。その力が極大化したのが日韓合意をめぐる反対運動だった」「(過去に関して)謝罪も補償もしない責任逃れの日本というイメージが1990年代以降、韓国の人々の間に定着してしまった。・・・・・・様々な研究・認識が生産され、日韓併合不法論などの解釈が、メディアなどを通して拡散・定着してきたことこそが、韓国の現在の対日認識や自己認識を作った」「1965年の日韓基本条約を不十分なものだとする認識も、古くからのものではない。社会全体の認識として広く定着したのはやはり1990年代以降のことといっていい」「そうした1990年代以降の『時代の推移』こそが現在の対立と葛藤を生み出してもいる」と言う。
「2018年のいわゆる元徴用工判決は、1990年代に本格化した日韓併合不法論や日韓基本条約不十分論に基づいている。新日鉄住金に命じているのが未払い賃金ではなく『慰謝料』の支払いである理由も、こうした1990年代の認識にある(すれ違う日韓の意識)」「企業を被告とするものだが、徴用とは明らかに日本『国家』が主導したものである」「危険な炭鉱が朝鮮人徴用者の作業場だった」・・・・・・。日本は「慰安婦問題も含め、日韓間の財産・請求権の問題は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で完全かつ最終的に解決済み」「2015年の日韓合意において『最終的かつ不可逆的な解決』が日韓両政府の間で確認されている」としているが、著者は「日本政府が訴訟自体を相手にしなかったため、韓国の人々には単に韓国を無視した傲慢な行為としてのみ映った。日本は一度も謝罪も補償もしていないと思い込んできた人々に、さらなる悪印象を与えたのである」と言う。そして「慰安婦問題は、事態を正確に把握しないまま、国家責任のみを問い、しかもひたすら『法』に依存して問うたため様々な問題が起きた」「被害者中心主義から代弁者中心主義ヘ、事実よりも運動優先となった」「慰安婦問題の政治化が正しい理解を拒ませ、植民地への理解不足が慰安婦問題理解を遅らせた」と指摘する。
そして「和解を成し遂げるために日韓がなすべきこととは」「事実の背後を見ることの大切さ」「日本は平和国家としての歩みを知ってもらう努力を」などを語る。
 「私が思うに国語力とは、社会と言う荒波に向かって漕ぎ出すのに必要な『心の船』だ。語彙という名の燃料によって、情緒力、想像力、論理的思考力をフル回転させ、適切な方向にコントロールするからこそ大海を渡ることができる。ネットカフェ難民にせよ、ホームレスにせよ、最底辺風俗嬢にせよ、私が取材で出会ったのは、十分な言葉を持たず、自らの心の船を適切に操ることのできない人たちだった。想像し、考え、表現するための言葉を奪われた人々だ」「日本の国力の低下を嘆く声が、国語力の脆弱さと深く関わっているように思えてならないのだ。日本の病理――コミュ障、孤立、炎上、ヘイト、陰謀論など現代を象徴する社会課題は、国語力の弱さなしには説明し得ない」「世界が以前と比べてどれだけ複雑になり、高いコミュニケーション能力が求められるようになっているのか。家庭格差の中で子供たちの内面でどんなことが起きているのか。学校が教育を通して十分な国語力を続けられない原因は何なのか。子供たちを取り巻くネットの言語空間はどのようなものなのか。それらの問題を正確に見つめた上で、家庭での親の接し方、学校のあり方、ネットの使い方を見直す時期に来ているのではないか」――。考える力、感じる力、想像する力、語り合う力、表現する力たる国語力をいかに回復させるか、複雑化しネットなどの情報洪水の中でどう生き抜いていくかのベースになる国語力再生への飽くなき挑戦の迫真のルポだ。
「私が思うに国語力とは、社会と言う荒波に向かって漕ぎ出すのに必要な『心の船』だ。語彙という名の燃料によって、情緒力、想像力、論理的思考力をフル回転させ、適切な方向にコントロールするからこそ大海を渡ることができる。ネットカフェ難民にせよ、ホームレスにせよ、最底辺風俗嬢にせよ、私が取材で出会ったのは、十分な言葉を持たず、自らの心の船を適切に操ることのできない人たちだった。想像し、考え、表現するための言葉を奪われた人々だ」「日本の国力の低下を嘆く声が、国語力の脆弱さと深く関わっているように思えてならないのだ。日本の病理――コミュ障、孤立、炎上、ヘイト、陰謀論など現代を象徴する社会課題は、国語力の弱さなしには説明し得ない」「世界が以前と比べてどれだけ複雑になり、高いコミュニケーション能力が求められるようになっているのか。家庭格差の中で子供たちの内面でどんなことが起きているのか。学校が教育を通して十分な国語力を続けられない原因は何なのか。子供たちを取り巻くネットの言語空間はどのようなものなのか。それらの問題を正確に見つめた上で、家庭での親の接し方、学校のあり方、ネットの使い方を見直す時期に来ているのではないか」――。考える力、感じる力、想像する力、語り合う力、表現する力たる国語力をいかに回復させるか、複雑化しネットなどの情報洪水の中でどう生き抜いていくかのベースになる国語力再生への飽くなき挑戦の迫真のルポだ。
問題となっているのは「家庭環境でのつまずき、家庭格差が言葉の発達を阻害している」「学校が国語力を失わせている。ゆとり教育や社会が求める欲求の肥大化、降り注ぐ新しい指導に翻弄される学校」「ネット、SNS言語の侵略。熊本県インスタいじめ自殺事件で少女を死に追いやった言葉」「19万人の不登校児を救え――フリースクールでの再生」「ゲーム世界から子供を奪還する――ネット依存からの脱却」「非行少年の心に色彩を与える――少年院の言語回復プログラム」「文庫丸ごと一冊の精読で画期的な成果を上げる全人的な教育」「答えのない問いが他者への想像力を鍛える哲学対話」・・・・・・。あきらめることなく挑戦している実例を示す。自然と触れ、ディスカッションをしたり、言葉を使って演じたり、書かせていく。
そしていう。「私は、こうした取り組みは野に芽を出したばかりの植物に、その日の天候に応じて少しずつ水を与えるようなものだと思う。小さな芽が、10年後に樹木となってどんな花を咲かせるのかはわからない。だが、新芽に対してやらなければならないのは、新しい化学肥料を次から次に与えることではなく、将来どんな強い風や激しい雨に襲われても、それに負けない太い根と幹を丹念に育てることだ。そんな木がたくさん根を張る森は決して地滑りを起こしたりはしない」――。丁寧に丁寧に、大事に大事に、樹木や植物を育てるように、それ以上に愛情もって子供を育てる。それはできると石井さんは言う。
 テクノロジーの進歩とともに「人間」はどうなるのか。人間の身体能力、コミュニケーション能力が拡張され、「人間拡張」はどこまで進むのか。そこに現れるのはネオ・サピエンス、そしてユートピアなのかディストピアなのか。人間拡張テクノロジーの第一線で活躍している研究者、AIやロボットそして脳科学、情報科学の専門家、ジャーナリストやミュージシャン、さらに為末大さんのようなパラアスリートと関わり、パラスポーツの義足の開発にも携わっているアスリートなど15人が、きたるべき「人間拡張」の未来について語る。
テクノロジーの進歩とともに「人間」はどうなるのか。人間の身体能力、コミュニケーション能力が拡張され、「人間拡張」はどこまで進むのか。そこに現れるのはネオ・サピエンス、そしてユートピアなのかディストピアなのか。人間拡張テクノロジーの第一線で活躍している研究者、AIやロボットそして脳科学、情報科学の専門家、ジャーナリストやミュージシャン、さらに為末大さんのようなパラアスリートと関わり、パラスポーツの義足の開発にも携わっているアスリートなど15人が、きたるべき「人間拡張」の未来について語る。
「人工的に6本目の指を装着する研究をしている。しばらく使用した後に第6の指を外すと、ちょっとした喪失感を感じるようになる。おそらく脳が身体の一部として理解するようになったのだろう。それは脳さえも拡張できる可能性があるということだ。人類にとってのオプションを用意するのが人間拡張工学の役割でありネガティブな未来だとは思わない(稲見昌彦)」「難病ALSにかかって、自らをサイボーグと呼び、人類で初めて人間と機械の融合という冒険に乗り出した。人間の脳は、見慣れない、よく知らないことを恐れるように神経回路ができている。それは生存のために必要な特性。AIが独立して発展すれば人間は最終的にはAIのペットになるが、AIの飛躍的発展に便乗させてもらって自分を拡張すること、つまりAIとパートナーを組んでいく人間中心のAIで、人間であることの意味を変えることだ(ロボット工学博士、ピーター・スコット・モーガン)」「人間がものに合わせるフェーズから、人間に物を合わせる段階に入ってきた。技術革新と人間の思い、この両輪が限界を拡張させていく構図はこれからも続いていく(為末大)」「制御系を常に自分の中に持つという人間性の拡張を先に完了しない限り、テクノロジーによる人間拡張は必ず人間否定になる。ものすごい能力を持った輝かしい存在が人間本来の姿ではないかと思う。今人間に必要なのは拡張ではなく、デトックス(解毒、体外に吐き出す)です(ミュージシャン平沢進)」・・・・・・。
「人間の意識を機械に移植する。『脳』は神格化されているところがあるが、電気回路に過ぎない。脳と同様の電気回路を作れば『感覚意識体験』は獲得できる。意識の移植が確立し機械の中で第二の人生を送ることが可能になるのはほぼ間違いない(脳科学者、渡辺正峰)」「医療分野における身体に埋め込むタイプのインプランタブルデバイスは進展している。体内の分子ロボットが検査から治療まで行うようになる(木下美香)」「サイボーグ技術とは、身体や生まれた場所によるしがらみから自己の創造性を解き放つ技術、人の可能性を拡張する(粕谷昌宏)」「全能へ向かう者の行く末と愚民の力。有限な地球を『人が住む物理的な球体』以上のものにしてはいけない。人類が滅びるまで宿命に抗ってほしい、これがニュータイプになりたかったおじいちゃんからの遺言です(富野由悠季)」「人間とテクノロジーの理想的な関係。人間がやりたくない、やるべきではない仕事はAIにやらせ、人間がやるべき他のことができるようにする(ケヴィン・ケリー)」「SF作品が夢見た人間拡張。文明の進歩そのものが人間拡張の歴史だったと考えれば未来を恐れることはない(SF作家・大森望)」「人間拡張と言う思想は、身体強化と人間の認識能力の拡大の2つの方向から語ることができる。その思想の現在地は複雑に入り組んでおり、人間拡張の見取り図を常に更新していかなくてはならない(塚越健司)」「コミュニケーションの不完全さを楽しみ、異質なものへの好奇心を(早稲田大学文化構想学部准教授ドミニク・チェン)」・・・・・・。
文筆家・編集者の吉川浩満さんは、人間拡張の4要素として「身体能力の拡張」「知覚の拡張」「認知能力の拡張」「存在の拡張」を示し、義足や眼鏡や顕微鏡、算盤やコンピュータ、リモート会議システム等が古来行われ開発されてきたとし、神学者のラインホールド・ニーバーの言葉を結びとして示す。「神よ、変えることのできない事柄については冷静に受け入れる恵みを、変えるべき事柄については変える勇気を、そして、それらニつを見分ける知恵をわれらに与えたまえ」・・・・・・。「攻殻機動隊は未来を作ることができるか(エッセイスト・さやわか)」・・・・・・。ユートピアでもなければディストピアでもない。しかし大変な時代であることは間違いない。
 「夜回り先生 いのちの講演」――。涙なしには聞けない。感謝なしには聞けない。30年前、全国最大で荒れに荒れていた横浜の公立夜間定時制高校に赴任してからずっと、夜11時過ぎから駅周辺などを歩きまわり、中学生・高校生たちに声をかけ、体を張って戦ってきた水谷先生。「君たちには、まだまだ長い明日があります。幸せないまと明日を作ることができます」「死を怖れず、死から逃げず、生き抜いてほしい」「生きていてくれて、ありがとう。いいもんだよ。生きるって」と言うメッセージを体当たりで伝え、「自らの力で昼の世界に戻った若者」と共に行動する。本当に凄まじく、すごい。
「夜回り先生 いのちの講演」――。涙なしには聞けない。感謝なしには聞けない。30年前、全国最大で荒れに荒れていた横浜の公立夜間定時制高校に赴任してからずっと、夜11時過ぎから駅周辺などを歩きまわり、中学生・高校生たちに声をかけ、体を張って戦ってきた水谷先生。「君たちには、まだまだ長い明日があります。幸せないまと明日を作ることができます」「死を怖れず、死から逃げず、生き抜いてほしい」「生きていてくれて、ありがとう。いいもんだよ。生きるって」と言うメッセージを体当たりで伝え、「自らの力で昼の世界に戻った若者」と共に行動する。本当に凄まじく、すごい。
「人と人との直接の触れ合いを捨ててはならない」「コミニュケーションには4つある。直接会って話す、スマホ・携帯電話で話す、手紙を書く、ネットやSNSでつながる」だ。しかし、「携帯電話やインターネットは、情報を調べたり、伝えたりするために使うべきものに過ぎません。愛や友情や心や思いは通じない。相手の顔が見えないとどんなひどいことも書けてしまう。コミュニケーションは必ず、『直接会って話す』ことだ」と言う。徹底した現場での身体を使っての心の底からの実践。どのページからも、それが痛いほど伝わってくる。公明党の立党精神、「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」は、こういうことだと心の底から思う。

