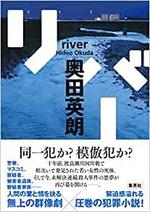 群馬県桐生市、栃木県足利市を流れる渡良瀬川の河川敷で若い女性の遺体が相次いで発見された。いずれも首を絞められ全裸、両手を縛られて殺害される共通点があり、同一犯と思われた。刑事たちのみならず、その地域の人たちは胸がざわつく。というのは、10年前に同じ河川敷で若い女性の全裸遺体が連続して発見されており、しかも未解決事件となっていたのだ。「リバー事案」「渡良瀬川連続殺人事件」と呼ばれ、その手口からも同一犯と推定された。
群馬県桐生市、栃木県足利市を流れる渡良瀬川の河川敷で若い女性の遺体が相次いで発見された。いずれも首を絞められ全裸、両手を縛られて殺害される共通点があり、同一犯と思われた。刑事たちのみならず、その地域の人たちは胸がざわつく。というのは、10年前に同じ河川敷で若い女性の全裸遺体が連続して発見されており、しかも未解決事件となっていたのだ。「リバー事案」「渡良瀬川連続殺人事件」と呼ばれ、その手口からも同一犯と推定された。
隣接する桐生市、太田市の群馬県と足利市の栃木県。多くの人が執念の捜査に乗り出す。群馬県警では、斉藤一馬警部補やベテランの内田警部。加えて10年前に娘を殺された写真館を営む松岡芳邦。彼はこの10年、毎日河川敷に出かけ、「犯人は必ず来る」と写真を取り続けていた。また、栃木県警では平野警部補の班が結成され、足利北署刑事第一課の若手・野島昌宏が担当。加えて、10年前に池田清を犯人として追い詰めながら逮捕できなかった悔しさを持つ元刑事・滝本誠司が動き出す。
捜査線上に3人が絞り出される。まず池田清、暴力団とも、覚せい剤とも関係したサイコパスだが、今回の取り調べでも警察を翻弄する。もう一人は、県会議員の息子で引きこもりの平塚健太郎。調べてみるとこれが普通では全く理解できない多重人格者、違う人格が突然現れてくるのだ。そしてもう一人、太田市の大企業・ゼネラル重機で配送係として働く期間工の刈谷文彦。別件逮捕となるが、全く沈黙して答えない。外国人労働者も多いこの地域の日常が背景として浮かび上がってくるが、なかなか捜査は進まない。そんななか、恐れていた事件が発生する。三人目の被害者が河川敷で発見されたのだ・・・・・。
警察、検察、マスコミ、被害者遺族、容疑者の家族、容疑者を守ろうとする女、犯罪心理学者・・・・・・。648ページの長編、しかも容疑者三人が早々と示されるが、最後まで緊迫した状況に連れていかれる。とにかく容疑者3人も、娘を殺された親や元刑事の10年にわたり執念も、現職の刑事や新聞記者も、凄まじいほどキャラが立つ。ネットによるパパ活、売春の日常化。外国人労働者の多い地域での地域の安定化策。現在社会をも浮き彫りにする卓越した犯罪小説。
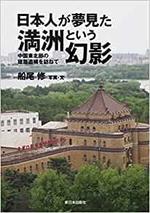 「中国東北部の建築遺構を訪ねて」が副題。満洲国は、13年半ほどしか存在しなかった「国」だが、日露戦争、ポーツマス条約以降を考えれば、日本が約40年、「満洲は日本の生命線」というように投入した熱量はきわめて大きい。多くの歴史書や小説を読んできたが、本書は船尾修氏が、旅順、奉天(瀋陽)、新京(長春)、大連、ハルビン、安東(丹東)などを回り、建築遺構を訪ねて文を書く、写真紀行だ。きわめて面白く、「満洲とは何であったか」が浮き彫りにされる。しかも満洲全域にわたって俯瞰的に時代を見るがゆえに、きわめて有益であった。
「中国東北部の建築遺構を訪ねて」が副題。満洲国は、13年半ほどしか存在しなかった「国」だが、日露戦争、ポーツマス条約以降を考えれば、日本が約40年、「満洲は日本の生命線」というように投入した熱量はきわめて大きい。多くの歴史書や小説を読んできたが、本書は船尾修氏が、旅順、奉天(瀋陽)、新京(長春)、大連、ハルビン、安東(丹東)などを回り、建築遺構を訪ねて文を書く、写真紀行だ。きわめて面白く、「満洲とは何であったか」が浮き彫りにされる。しかも満洲全域にわたって俯瞰的に時代を見るがゆえに、きわめて有益であった。
満洲事変の舞台となった奉天、原野の首都建設計画の新京、満鉄の存在と役割、皇帝・溥儀が信じた偽りの復辟、ハルビンの悪魔の誘惑と731部隊、ロシア系ユダヤ人の受難、炭鉱の都・撫順・・・・・・。地図と事件が結びついてきた。
 吉村昭と津村節子夫妻。それぞれ自立した作家でありながら二人三脚。作家というとてつもなく厳しい世界に身を置き、徹底した取材で透徹した世界を描ききった吉村昭。「3日以上家を空けられない。とにかく書斎に入りたいの。書いているうちにわからないことが出てくればまた行く。だから長崎にも107回も行った。一緒に長崎に行っても、あの人は取材だけなのよ」「ぱっと出かけるのよ。異常な執念よ」「あなたが(大河内昭爾)、司馬さんを史談小説、吉村のは史実小説と区別をしたのはうまいです(吉村昭さんは文明論をやらないで、史実しか書かない)」・・・・・・。凄まじい世界が語られる。小説家として生きる事は至難の業。吉村昭は「絶海の孤島から壜に手紙を入れて流し、拾ってくれる人がいるのを待っている心もとなさだ」と言ったという。吉村昭・津村節子夫妻は、ひたすら同人雑誌に書き続けた。本書を通じて作家として生きる執念を感じる。
吉村昭と津村節子夫妻。それぞれ自立した作家でありながら二人三脚。作家というとてつもなく厳しい世界に身を置き、徹底した取材で透徹した世界を描ききった吉村昭。「3日以上家を空けられない。とにかく書斎に入りたいの。書いているうちにわからないことが出てくればまた行く。だから長崎にも107回も行った。一緒に長崎に行っても、あの人は取材だけなのよ」「ぱっと出かけるのよ。異常な執念よ」「あなたが(大河内昭爾)、司馬さんを史談小説、吉村のは史実小説と区別をしたのはうまいです(吉村昭さんは文明論をやらないで、史実しか書かない)」・・・・・・。凄まじい世界が語られる。小説家として生きる事は至難の業。吉村昭は「絶海の孤島から壜に手紙を入れて流し、拾ってくれる人がいるのを待っている心もとなさだ」と言ったという。吉村昭・津村節子夫妻は、ひたすら同人雑誌に書き続けた。本書を通じて作家として生きる執念を感じる。
「火事明リ」「遊園地」など津村節子の短編にはキレがある。「追悼・吉村昭――ストイックな作家の死」という津村節子と大河内昭爾の対談は、吉村昭の凄さを私生活からも抉り出している。「桜田門外の変」にも「尊厳死の否定」にも触れ生々しい。「ポーツマスの旗」「戦艦武蔵」の俊敏な取材や鋭い歴史感覚に納得する。「夫が『花の好きな女だなあ』と言っていた。・・・・・・私はあじさいが好き」「飛脚の末裔――せっかく散歩しているのに、お前の先祖は飛脚か、といった吉村の声を思い出した」など、とても面白く心に響いてくる。
「観光地のあり方」の中で「かれは桜田門外の変は2.26事件と通じるところがある、と言っていた。維新と敗戦という共に内外の情勢を一変させた原動力で、井伊大老暗殺事件を書いた作品の中に坂本龍馬についての記述はあるが、さして重要な役割を果たしているようには書かれていない」とある。安倍元総理銃撃事件の後だけに、特別な思いにふけってしまう。
 若き哲学研究者として、学校・企業など幅広く哲学対話を行っている。難しい哲学書とは大違い、現代社会の日常の中で感じ、思索した「手のひらサイズの哲学」「あなたと哲学したあの曖昧な時間、水中に深く潜り、頭の中で何度もでんぐり返しをするような心持ち、ぐらぐら揺れる足場の感覚が消えてしまう」瞬間をとらえて示す。哲学は「存在」「生老病死」の意味を問うことであり、答えのない世界を考え続ける人間の営為だ。正解主義の思考停止の誘惑を断ち切ることだ。数千年にわたる人類の「生」への格闘に学び、自らのものへと根を張っていくことだ。
若き哲学研究者として、学校・企業など幅広く哲学対話を行っている。難しい哲学書とは大違い、現代社会の日常の中で感じ、思索した「手のひらサイズの哲学」「あなたと哲学したあの曖昧な時間、水中に深く潜り、頭の中で何度もでんぐり返しをするような心持ち、ぐらぐら揺れる足場の感覚が消えてしまう」瞬間をとらえて示す。哲学は「存在」「生老病死」の意味を問うことであり、答えのない世界を考え続ける人間の営為だ。正解主義の思考停止の誘惑を断ち切ることだ。数千年にわたる人類の「生」への格闘に学び、自らのものへと根を張っていくことだ。
「当たり前のものだった世界が当たり前でなくなる瞬間。そこには哲学の場が立ち上がっている」「哲学をすることは、世界をよく見ることだ。くっきりしたり、ぼやけたり、かたちを変えたりして、少しずつ世界と関係を深めていく」「何かを深く考えることは、深く潜ることに例えられる。哲学対話は、人と一緒に考えるから、みんなで潜る」「哲学対話は共感の共同体でもない。弁証法だ。弁証法は異なる意見を前にして、自暴自棄に自身の意見を捨て去ることではない。ただ単に違いを確かめて、自分の輪郭を浮かび上がらせるのでもない。異なる意見を引き受けて、さらに考えを刷新することだ。中間をとるのでもない。妥協でもない。対立を、高次に向けて引き上げていくことだ」「ヤスパースは、哲学することの根源は、驚異と懐疑と喪失の意識であると言った。驚異から問いと認識が生まれ、認識されたものへの懐疑から批判的吟味と明晰さが生じ、自己喪失の意識から自身に対する問いが生まれる」――。ヤスパースのこの言葉について、永井さんは「ツッコミと不満」を追加する。「総括して申しますと、『哲学すること』の根源は、驚異・懐疑・喪失・不満・ツッコミの意識に存している。・・・・・・バカみたいになってしまった。ヤスパースがボケになってどうする」という軽いノリで言い切ってしまう。なかなかできないことだ。
 「科学の冒険は、紀元前6世紀の古代ギリシャのアナクシマンドロスの革命とともに幕を開けた」「アナクシマンドロスは、高いところに空があり、低いところに地面があるという世界を、大地は虚空に浮かんでいる、大地は宙に浮いている。空間に絶対的な高低は存在せず大地は宙に浮かんでいると洞察した。それは、西洋の思想を何世紀にもわたって特徴づけるであろう世界像の発見であり、宇宙論の誕生であり、最初の偉大な科学革命だった」という。カルロ・ ロヴェッリは、理論物理学の研究者。専門とする「ループ量子重力理論」は、20世紀の物理学が成し遂げた2つの偉大な達成、一般相対性理論と量子力学の統合を目的とした理論だ。最近読んだ著者の「世界は関係でできている」は刺激的であったが、本書は10年ほど前の著作である。「科学とは何か」について、アナクシマンドロスに焦点を当てながら、極めて哲学的に丁寧に論を進めている。この論じ方自体が「科学とは何か」を鮮やかに浮き上がらせている。感動的でさえある。
「科学の冒険は、紀元前6世紀の古代ギリシャのアナクシマンドロスの革命とともに幕を開けた」「アナクシマンドロスは、高いところに空があり、低いところに地面があるという世界を、大地は虚空に浮かんでいる、大地は宙に浮いている。空間に絶対的な高低は存在せず大地は宙に浮かんでいると洞察した。それは、西洋の思想を何世紀にもわたって特徴づけるであろう世界像の発見であり、宇宙論の誕生であり、最初の偉大な科学革命だった」という。カルロ・ ロヴェッリは、理論物理学の研究者。専門とする「ループ量子重力理論」は、20世紀の物理学が成し遂げた2つの偉大な達成、一般相対性理論と量子力学の統合を目的とした理論だ。最近読んだ著者の「世界は関係でできている」は刺激的であったが、本書は10年ほど前の著作である。「科学とは何か」について、アナクシマンドロスに焦点を当てながら、極めて哲学的に丁寧に論を進めている。この論じ方自体が「科学とは何か」を鮮やかに浮き上がらせている。感動的でさえある。
アナクシマンドロス(紀元前610年頃―紀元前546年)は、小さなポリスに分割されたギリシャ世界のミレトスに住み、アナクシメネスとともにイオニア学派の代表とされる。自然哲学について考察し、万物は水であるとしたタレスの後に続いた最初の哲学者ともされる。万物の根源(アルケー)が、「無限なるもの(アペイロン)」であるとしたが、「大地は虚空に浮かんでいる」は単なる発見ではなく、「概念上の跳躍」であり、最初の「科学革命」であったと強調する。「雨を降らすのはゼウスであり、風を吹かすのはアイオロスであるとするような、これら現象を神の意思や決定から切り離し、自然のうちにその原因を見出そうとする試みは当時には皆無であった」。神々を冒涜し、都市の若者を堕落させたとして怒りを買うが、その後ソクラテスがアテネの裁判で死刑に処せられるなど人類の歴史、科学の歴史はガリレオを見るまでもなくこれが続いた。太陽が東に出て西に沈む、蒸発した水が雨になる・・・・・・。アナクシマンドロスは知性と好奇心を組み合わせただけだが、「大地は宙に浮かんでいる」は難問で、それなら「大地が落下しない理由を説明しなければならない」のだ。アナクシマンドロスは「落下する物体は何かに支配されているということ」との思索を巡らせた。アナクシマンドロスは「自然界には法則が存在し、事物が時間の中でどのように変化するかは、この法則が確定している」と自然法則という考え方をもった。同時代にごく近くに住んだピタゴラス、そしてプラトンへと続き、コペルニクス、ガリレオ、ファラデーとマクスウェルの電磁場、アインシュタインの歪んだ時空間、シュレーディンガーの波動力学の関数・・・・・・これらはみな、現象の複雑さを統一的、有機的な仕方で理解するために科学によって提案された、感覚によっては捉えられない「理論的な実体」であり、アナクシマンドロスがアペイロンに託した役割、機能を担っているものだ。見逃してはならないのは、このような自由な知は、ギリシャの都市は王を追放し、創造者、組織者としての神への隷属から解放され、文化の交流がなされていたことによる。
「科学は世界像を構築する役割を担っている」「科学が存在する理由は、我々が限りなく無知であり、抱え切れないほどの誤った先入観にとらわれているからである。好奇心と知っていると思っていた事の問い直し、これこそ科学の探求の源泉である」という。つまり科学の探求とは、概念化された世界像を絶えず修正し、改良する過程である、というのだ。加えて大事な事は、科学の革命は単なるひらめきや先達の否定によるものではない。「事情はその反対である。既存の理論、すなわち蓄積された知に立脚する力こそ、科学が前進するための原動力である」ということだ。「科学とは、世界について考えるための方法を探求し、私たちが大切にしているいかなる確かさをも転覆させて倦むことのない.どこまでも人間的な冒険である」という。
最後に、カルロ・ロヴェッリは前ー科学的な思考について述べている。「神々に頼らずに世界を理解せよ、というアナクシマンドロスの提起。自然主義的な思考と神話・宗教的な思考の本質的な違いはどこにあるのか」を問いかける。「ベルクソンは宗教を、知の解体的な力から社会を防衛する存在として認識していた。だが、無知の解体的な力からは、一体誰が私たちを守ってくれるのだろう」と問いかけるのだ。そして、私たちの社会が理解の及ぶレベルをはるかに超えて複雑化している現在、「空虚な確かさに閉じこもるのか、あるいは、知の不確かさを受け入れるのか、選択を迫られている」と語り、カルロ・ ロヴェッリは、後者を選び、神話・宗教的思想から世界の理解を解放すること、世界を理解する方法を模索することに真摯に挑みたいと言う。

