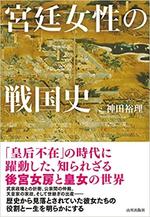 天皇の権威が低下したと捉えられがちな戦国時代――。後宮女房・皇女達は何をしていたのか、どういう役割を果たしていたのか。戦国時代のみならず、日本の歴史は男性の歴史であったと思われるが、本書は天皇・朝廷を取り巻く、これら女性の実像に学問的に迫っている。すばらしい研究だ。
天皇の権威が低下したと捉えられがちな戦国時代――。後宮女房・皇女達は何をしていたのか、どういう役割を果たしていたのか。戦国時代のみならず、日本の歴史は男性の歴史であったと思われるが、本書は天皇・朝廷を取り巻く、これら女性の実像に学問的に迫っている。すばらしい研究だ。
後宮女房は、天皇の日常生活を支える「侍女」の役割を担うとともに、後宮と外部を結ぶ「伝達者」「使者」の役割も果たしていた。さらに戦国時代は、天皇の正妻(嫡妻)たる皇后や中宮が立てられなかったようで、天皇との間に、世嗣ぎの皇子をはじめ、多くの皇子・皇女をもうけていた。そうなると生母となって重きをなすことになる。
「後宮女房が記した執務日記」「武家政権との間を取り次ぐ女房たち(足利将軍・三好氏、織田信長時代の多彩な活躍、活躍の機会が減った豊臣政権時代)」「朝廷内を揺るがす大スキャンダル事件(猪熊事件など)」「戦国期の後宮女房のはたらきと収入」「将軍側近に勝るとも劣らぬ役割を果たしていた女房たち」「後宮女房の一生と様々な人生」「娘の出仕をはたらきかける実父」「周防の大内義隆に嫁いだ二人の娘、京の文化を取り入れることに熱心であった大内義隆」「その多くが出家した、皇女たちの行方」らが詳述される。大変興味深い著作。
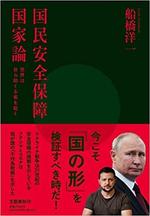 「世界は自ら助くる者を助く」が副題。フクシマでもコロナでも、ウクライナ危機を考えても、日本は危機と有事に対する備えがあまりにも乏しいことが明白になっている。気候変動に伴うエネルギー危機もきわどい。安全保障の枠組みが根底から揺さぶられている今、「国の形」と「戦後の形」を検証し、国民が参画する危機管理という観点から新たな国家安全保障、経済安全保障、国民が危機管理に参画する国民安全保障国家を築かねばならない。ウクライナの状況を見ても、「自分の国は自分で守らねばならない」という意思が大事だ。「日本は、平時において、その法制度と規制とインテリジェンスと人的資源、つまりは国家統治を安全保障の観点から見直し、有事の体制を構築するべきである。安全保障とは、国民の生命と財産の安全及び国家としての価値の保全を保障することである」という。
「世界は自ら助くる者を助く」が副題。フクシマでもコロナでも、ウクライナ危機を考えても、日本は危機と有事に対する備えがあまりにも乏しいことが明白になっている。気候変動に伴うエネルギー危機もきわどい。安全保障の枠組みが根底から揺さぶられている今、「国の形」と「戦後の形」を検証し、国民が参画する危機管理という観点から新たな国家安全保障、経済安全保障、国民が危機管理に参画する国民安全保障国家を築かねばならない。ウクライナの状況を見ても、「自分の国は自分で守らねばならない」という意思が大事だ。「日本は、平時において、その法制度と規制とインテリジェンスと人的資源、つまりは国家統治を安全保障の観点から見直し、有事の体制を構築するべきである。安全保障とは、国民の生命と財産の安全及び国家としての価値の保全を保障することである」という。
本書は2020年春のコロナ危機から2022年のウクライナ危機までの2年間の論考をまとめている。各誌に発表したものだが、ウクライナ危機後の論考は書き下ろしで新しい。その「国家安全保障、レアルポリティーク時代の幕開け――ウクライナの悲劇、米中新冷戦と日本の選択」「経済安全保障、経済相互依存とネットワークの武器化――グリーン大動乱とエネルギー危機」は、ウクライナ危機以降の論考で、深く広く安全保障 の 重要性をえぐり出している。「ウクライナ 戦争 が 日本 に 問い かけて いる 最大 の 教訓 にして 最大 の クエスチョンは、自らを守ることができる国を世界を助ける、というその点にある」「これからの時代、最も恐ろしい『日米中の罠』は、米中対決の中で日本が選択肢を失う罠である。中国に日本の自国防衛の意思と能力、日米同盟の抑止力の有効性、科学技術力とイノベーションの力を常に理解させるべきである。同時に、日米が中国を全面的な敵性国と決めつけ、それが中国の排他的民族主義を煽り、双方とも後戻りができなくなる状況を避けるべきである。互いに相手の意図を正確に把握、不断の対話をすることが必要である」「そのためには、日本がより自立し、自らの安全保障に責任を持ち、日米同盟を相互依存的な責任共有の体制に進化させるべきであり、有事に国民を保護できる国の体制を作らなければならない。日本の抑止力を高めなければならない・・・・・・」といい、戦略的思考、外交力、統治力を求めている。またウクライナ問題が、エネルギー危機の始まりになることを指摘し、エネルギーの経済安全保障上の脆弱性に論及。かつサイバー攻撃力、監視力、情報統率力、諜報力の全てが脆弱であることを指摘する。さらに「国家的危機には、大きな政府と大きなビジネスが必要だ」という。
コロナでは「デジタル敗戦」「ワクチン暗黒国家」を指摘するが、「不確実性のシナリオの前に、政治家も官僚も『作為のリスク』を恐れ、結果として『不作為のリスク』を生じさせることになった」という。コロナで「泥沼だったが結果オーライ」との言葉を再三にわたって述べている。その場しのぎの"泥縄貧乏"が、構造的に日本を危機に弱い国にしているという指摘を噛み締めなくてはならない。
 14歳のイギリスの少女ミアは、酒と薬に依存する母親と貧しい人々が暮らす団地で暮らし、弟のチャーリーの世話をしている。母親は働かず、子供はほったらかし。食事も衣服もままならず、チャーリーはいじめに遭っている。生活保護のお金まで母親の薬に消えてしまう有様だ。そんなミアの楽しみは図書館などで本を読むこと。ある日、100年前の日本の「金子文子」の伝記に出会う。戸籍にも入っていない無籍者、同じような薄幸の少女・フミコに惹かれ、自分の人生を重ねて読み進めていく。フミコは大逆罪で有罪、獄死したアナキスト。獄中で本を書いたという。
14歳のイギリスの少女ミアは、酒と薬に依存する母親と貧しい人々が暮らす団地で暮らし、弟のチャーリーの世話をしている。母親は働かず、子供はほったらかし。食事も衣服もままならず、チャーリーはいじめに遭っている。生活保護のお金まで母親の薬に消えてしまう有様だ。そんなミアの楽しみは図書館などで本を読むこと。ある日、100年前の日本の「金子文子」の伝記に出会う。戸籍にも入っていない無籍者、同じような薄幸の少女・フミコに惹かれ、自分の人生を重ねて読み進めていく。フミコは大逆罪で有罪、獄死したアナキスト。獄中で本を書いたという。
イギリスの階級社会では、言葉まで違ってミドルクラスにはなれない壁があまりにも大きい。重苦しい閉鎖された誰にも理解されない世界。男なしでは生きられない母親。貧困、性暴力、ネグレクト、虐待、薬物依存・・・・・・。最後のセーフティーネットのソーシャルに連れていかれても、ミアとチャーリーはバラバラにされることを極度に恐れる。広い世界の中で身を寄せ合い2人がひとつになっての孤立だ。フミコはついに自殺を図ろうとする。ミアらは逃げようとする。残酷な世界からの逃走だ。
フミコは自殺の寸前――。「あたりを見回し、私はぎょっとして立ちすくんだ。私を囲んでいる世界が、あまりにも美しかったからだ。いま飛べば折檻や空腹からは逃れられる。だけど、それでも世界にはまだ美しいものがたくさんある・・・・・・私は死ぬわけにはいかない。・・・・・・ここじゃない世界は今ここにあり、ここから広がっている。別の世界は存在する」と思い覚醒する。逃避行の果てに駅で倒れたミアは、分け隔てすることなく、ミアの素敵なリリックに感動し曲をつけてくれたウィルの「両手にトカレフ クリスマス・ヴァージョン」を病床で聴く。「ここじゃない世界に行きたいと思っていたのに、世界はまだここで続いている。でも、それは前とは違っている。多分世界はここから、私たちがいるこの場所から変わって、こことは違う世界になるのかもしれないね」「それは驚くべきことだった。そこにあるのはNOではなく、YESだったからだ。ここにあった世界には存在しなかった言葉が、ここにある世界には存在し始めている。私の、私たちの、世界はここにある」・・・・・・。どん底の生死を超え、宇宙のリズム、宇宙生命に触れた幸福感を見出した瞬間といえようか。
 「満洲は日本の生命線」――。日露戦争前夜から第二次世界大戦までの約半世紀。満洲の名もない都市、奉天の東に位置する李家鎮で繰り広げられる攻防。ロシアの南下を防ぎ、「燃える土」である石炭を発掘、一大拠点・仙桃城を建設しようとする日本。それに抗した地元軍閥、国民党、八路軍。知力と殺戮と謀略の半世紀を、満洲の一都市にこだわって見ると、従来の時間軸からの線で見る歴史とは違う定点からの歴史が浮かび上がる。「国家とはすなわち地図である。その街の歴史を地図ほど雄弁に語るものは他に存在しない」「なぜこの国から、そして世界から『拳』はなくならないのでしょうか。答えは『地図』にあります。世界地図を見ればすぐにわかるが、世界は狭すぎるのです」と、白紙から地図を作り暴力たる拳で地図を書き換える力業ともいうべきテーマを設定する。満洲から見たあの昭和の戦争、満洲になぜこだわったのか、なぜ南下政策に突入したのか、白紙の地図に築いた満洲がどのようにして消えていったのか・・・・・・。大変な力作だ。
「満洲は日本の生命線」――。日露戦争前夜から第二次世界大戦までの約半世紀。満洲の名もない都市、奉天の東に位置する李家鎮で繰り広げられる攻防。ロシアの南下を防ぎ、「燃える土」である石炭を発掘、一大拠点・仙桃城を建設しようとする日本。それに抗した地元軍閥、国民党、八路軍。知力と殺戮と謀略の半世紀を、満洲の一都市にこだわって見ると、従来の時間軸からの線で見る歴史とは違う定点からの歴史が浮かび上がる。「国家とはすなわち地図である。その街の歴史を地図ほど雄弁に語るものは他に存在しない」「なぜこの国から、そして世界から『拳』はなくならないのでしょうか。答えは『地図』にあります。世界地図を見ればすぐにわかるが、世界は狭すぎるのです」と、白紙から地図を作り暴力たる拳で地図を書き換える力業ともいうべきテーマを設定する。満洲から見たあの昭和の戦争、満洲になぜこだわったのか、なぜ南下政策に突入したのか、白紙の地図に築いた満洲がどのようにして消えていったのか・・・・・・。大変な力作だ。
序章は1899年夏、続いて1901年、1905年、1909年、1923年、1928年、1932年、1934年、1937年、1938年、1939年、1941年、1944年、1945年、そして終章が1955年。その年々に世界に、中国と日本に激震が走る。張作霖の爆殺、関東軍による満州事変、リットン調査団、国際連盟脱退、盧溝橋事件、泥沼化する日中戦争・・・・・・。その都度、この満洲の人工の一都市は激震に見舞われ、人が死に、その果てに街も人心もボロボロになる。
日露戦争で満洲に使命を与えられた第ニ軍歩兵第六連隊中隊長の高木大尉とその死。その地に通訳として踏み入り、次第にその力を増していく知略ともにもつ存在・細川。ロシアの鉄道網拡大のために派遣され、いきなり義和団の乱に遭遇し、ずっと人道的役割を果たそうとする神父クラスニコフ。叔父に騙されて不毛の地へ移住し新たな王となり都市開発を進めた馬賊の孫悟空。東京帝国大学で気象学を研究し、満鉄で地図を作り満洲国建設の使命を与えられた須野、そしてその息子・明男。
「三日で終わる」と高をくくった戦争が、日中泥沼化の15年戦争になる。ヨーロッパではナチス・ドイツが各国を侵略、やがて敗れる。時代は石炭の時代から石油の時代へと突き進む。泥沼化し戦線拡大するなか南下政策を余儀なくされ、日本は孤立し追い込まれる。「満洲は生命線」どころか軍人を始めとして人が去っていく。真珠湾攻撃より前、「戦争は始まっていなかったが、始まる前から終わっていたのである」と、満洲で地図を作り拳を腹の中に収めてきた細川らは思うのだった。なんと細川は敗戦後の日本のために何ができるかを考え、密かに動いていたのだ。関東軍も石原莞爾も出てこない満洲の一都市から描き出される誠にドラマチック、残酷・悲惨な戦争史だ。
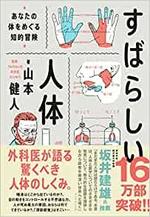 「あなたの体をめぐる知的冒険」が副題。「脚は片方だけでも10キログラム以上、腕でも4〜5キログラムもあって重い」「頭を激しく動かしても文字が読める」「おならが出ても、気体だけで固体が出ない(すごい肛門)」「細菌が病気の原因となることを発見したコッホ、細菌を殺せる化学物質で梅毒の治療薬サルバルサンを発見したパウル・エールリヒ」「偶然がもたらした抗生物質ペニシリン」「ウィルスとの戦いとワクチン」「唾液は1日1~2リットル出る」「心臓の拍動の仕組み」「肺はどのように空気の出し入れをするか」「肝臓は人体の『物流基地』」「免疫は『自己』と『非自己』を見分ける」「DNAという暗号文」「B型肝炎もC型肝炎も治療できるようになった」「糖尿病は細い血管が蝕まれて恐ろしい」「痛み止めの効用」「全身麻酔とは(麻酔と鎮静は異なる)」「レントゲンとCTとMRI」「パルスオキシメーターを生んだ日本人・青柳卓雄」「血液の赤色と透明な輸血」・・・・・・。
「あなたの体をめぐる知的冒険」が副題。「脚は片方だけでも10キログラム以上、腕でも4〜5キログラムもあって重い」「頭を激しく動かしても文字が読める」「おならが出ても、気体だけで固体が出ない(すごい肛門)」「細菌が病気の原因となることを発見したコッホ、細菌を殺せる化学物質で梅毒の治療薬サルバルサンを発見したパウル・エールリヒ」「偶然がもたらした抗生物質ペニシリン」「ウィルスとの戦いとワクチン」「唾液は1日1~2リットル出る」「心臓の拍動の仕組み」「肺はどのように空気の出し入れをするか」「肝臓は人体の『物流基地』」「免疫は『自己』と『非自己』を見分ける」「DNAという暗号文」「B型肝炎もC型肝炎も治療できるようになった」「糖尿病は細い血管が蝕まれて恐ろしい」「痛み止めの効用」「全身麻酔とは(麻酔と鎮静は異なる)」「レントゲンとCTとMRI」「パルスオキシメーターを生んだ日本人・青柳卓雄」「血液の赤色と透明な輸血」・・・・・・。
知らないことばかり。考えたことがないものがいかに多いか。いかに人体は奇跡的なものか。そして人類がいかに戦い、病気を克服してきたか。まさに格闘の歴史が、誰にでもわかるように図入りで語られる。極めて面白い。確かに「すばらしい人体」だ。

