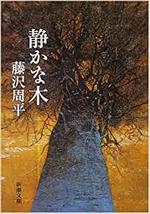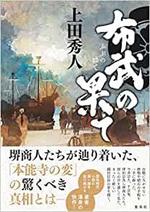 堺の商人――今井彦八郎(今井宗久)、魚屋與四郎(千宗易)、天王寺家助五郎(津田宗及) の三人は、貿易による富で自治を貫く堺の納屋衆のなかでも時代の動向を見抜くしたたかな眼を持っていた。永禄11年、織田信長は足利義昭を奉じて上洛する。納屋衆のなかでは、これまでの経緯から三好三人衆につくべきだとの意見も強く、新興勢力であった信長に賭けることに反対も強かった。そのなかで今井宗久ら三人は、信長の勢いと人物に未来をかけることにした。信長の勢いは続き、その実力が認められていき、今井宗久らは信長から茶道衆に任じられ、その内に入る。「堺を手放せば鉄砲も硝石も入らない」「茶の湯で名高い三人は、茶の湯の振興、茶の席で語られる武将との会話・情報の収集の重要な役割を担う」との信長の考えを今井宗久らは察知していた。鉄砲が重要視されるようになり、鉄砲や硝石、ロジスティックスの手配を一手に握ることになっていく。したたかな堺商人の面目躍如、戦乱の情報戦の機密情報を手に入れていく。
堺の商人――今井彦八郎(今井宗久)、魚屋與四郎(千宗易)、天王寺家助五郎(津田宗及) の三人は、貿易による富で自治を貫く堺の納屋衆のなかでも時代の動向を見抜くしたたかな眼を持っていた。永禄11年、織田信長は足利義昭を奉じて上洛する。納屋衆のなかでは、これまでの経緯から三好三人衆につくべきだとの意見も強く、新興勢力であった信長に賭けることに反対も強かった。そのなかで今井宗久ら三人は、信長の勢いと人物に未来をかけることにした。信長の勢いは続き、その実力が認められていき、今井宗久らは信長から茶道衆に任じられ、その内に入る。「堺を手放せば鉄砲も硝石も入らない」「茶の湯で名高い三人は、茶の湯の振興、茶の席で語られる武将との会話・情報の収集の重要な役割を担う」との信長の考えを今井宗久らは察知していた。鉄砲が重要視されるようになり、鉄砲や硝石、ロジスティックスの手配を一手に握ることになっていく。したたかな堺商人の面目躍如、戦乱の情報戦の機密情報を手に入れていく。
しかし、信長の天下布武の戦いは容易ではなく、浅井長政の裏切りにあって朝倉義景との戦いに敗北、窮地に陥る。足利義昭の反信長の動きも信長を追い詰めていく。一向一揆との戦いは10年にも及んだ。西から三好三人衆と石山本願寺、北から浅井、朝倉、比叡山延暦寺、南から伊勢長島一向一揆衆が信長を攻めていた。松永弾正や荒木村重らの動きにも手を焼く。しかし、信長は一気呵成に天下への道を強引に駆け上って行く。
戦国武将の側からの眼ではなく、今井宗久・千宗易・津田宗及ら堺商人の目から見た戦国史。きわめて面白く、全体の動きがよくわかる。そして本能寺の変ヘ。徳川家康、明智光秀の本心。家康の腹心で一向宗徒の本多弥八郎(正信)の怪しい姿・暗躍が「布武の果て」をもたらすことを匂わせる。「茶室を舞台に繰り広げられる、圧巻の戦国交渉小説」と帯にある。「あほやなぁ」「怖いなぁ」という声が響いてくる小説だが、したたかな堺商人や徳川家康が勝つということか。武田や上杉、毛利などは出てくるが、秀吉は出てこない。
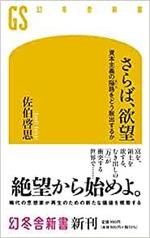 「資本主義の隘路をどう脱出するか」が副題。「グローバリズムの矛盾が露呈し、新型コロナに襲われ、プーチンによる戦争が始まった。一体何が、この悪夢のような世界を見出したのか」「我々が今、生きている世界は、もはやそれほど安閑な場所ではない。超克されることなく妄信されてきた『西欧近代思想』が、なし崩しの禍々しい死を迎えそうな気配さえも漂う。まずは悲観的なビジョンの極限に身をおきたい。現在文明の隘路から脱出する都合の良い正解などない、と覚悟を決めるほかない」といい、直面する課題の根源を剔抉する。2018年の秋から今年3月にかけて連載したコラムや論考を収録している。
「資本主義の隘路をどう脱出するか」が副題。「グローバリズムの矛盾が露呈し、新型コロナに襲われ、プーチンによる戦争が始まった。一体何が、この悪夢のような世界を見出したのか」「我々が今、生きている世界は、もはやそれほど安閑な場所ではない。超克されることなく妄信されてきた『西欧近代思想』が、なし崩しの禍々しい死を迎えそうな気配さえも漂う。まずは悲観的なビジョンの極限に身をおきたい。現在文明の隘路から脱出する都合の良い正解などない、と覚悟を決めるほかない」といい、直面する課題の根源を剔抉する。2018年の秋から今年3月にかけて連載したコラムや論考を収録している。
「空間、技術、欲望のフロンティアを拡張して成長を生み出してきた資本主義は臨界点に近づいていると言わざるを得ない。無限の拡張、無限の進歩への渇望を適合させた資本主義は限界に突き当たっている。我々に突きつけられた問題は、資本主義の限界というより、富と自由の無限の拡張を求め続けた近代人の果てしない欲望の方にあるのだろう」・・・・・・。
「日本近代、ふたつのディレンマ」――。一つは「近代化の大成功が生んだ列強との対立(西洋文明の急速な導入による近代化を図る以外に、日本は列強の属領化、分割統治を免れることは難しかった。しかし近代化に成功すれば、西洋列強の地位を脅かし、列強との決定的な対立を引き起こす。列強との対立という大いなる危機に陥る)」ことだ。ふたつ目は、「文明化が進むほど失われる独立の精神(外形的な文明化が進展すればするほど、日本人の精神的な空虚感は増幅し、その結果、日本は文明から遠ざかる)」と述べる。今再び、グローバル世界で再演される「日本近代のディレンマ」を指摘する。
また「民意が間違い続けた結果の失われた30年」「『民意』亡国論(民意の便利使いをするメディア、民意にすり寄る政治家)」「主権者を抑制するものがなくなった時、主権者の暴走、民意の暴走が始まる。吉野作造は『民主主義』とは言わずに『民本主義』と言った。彼にとって政治とは『民衆が行うもの』ではなく『民衆のために行うもの』であり、それが『民本主義』であった。民衆の直接的な関与、世論の無条件の反映の危険を彼はよく知っていたのである」・・・・・・。
「ロシア的価値と侵略」「黒か白か、敵か味方か、正義を振りかざし急激に不寛容になった社会」「民主主義こそが独裁者を生み出す」「壮大な『ごっこ』と化した世界。現在の『現実主義』は本当の現実(リアリティ)に直面しているだろうか」「不要不急と必要の間」・・・・・・。一つ一つの論考は極めて根源的、本質的だ。
「岡安家の犬」――。岡安家の当主・甚之丞。親友の野地金之助から犬鍋を食おうと誘われる。ところがなんと自分の家で飼っていたアカという犬が捕まって食べさせられる。怒りのあまり決闘となり、妹の縁組みもなくなろうとする。隠居の祖父・十左衛門が動き出す。
「静かな木」――。隠居の布施孫左衛門が川釣りから帰ると、大変なことが起きていた。息子の邦之助が果たし合いをするという。相手は鳥飼郡兵衛の息子で、許しがたい侮りを受けたからだという。孫左衛門は立ち上がる決心をする。隠居となった成熟した男の知恵と決然とした胆力が静かに描かれる。
「偉丈夫」――。大変な役割を仰せつかった片桐権兵衛。「6尺近い巨躯、鼻はしっかりとあぐらをかき、口は常にしっかりと結ばれている。そして寡黙」のこの男。その体躯に蚤の心臓を備えた小心者だけに、困難な仕事をやり遂げる。
いずれも静謐なる藤沢周平の世界。
 今の政治家の存在感のなさと言葉の軽さ。今、テレヴィジョンに出てくる芸人さんたちの恥を知らない、目立ちたいだけ、馬鹿げた装い、笑いの強要のなんと醜いことか。今の聴くに堪えない言葉、日本語の乱れ――。リーダー不在、インテリ不信の時代に「言葉の力」と「教養の本質」を問う。
今の政治家の存在感のなさと言葉の軽さ。今、テレヴィジョンに出てくる芸人さんたちの恥を知らない、目立ちたいだけ、馬鹿げた装い、笑いの強要のなんと醜いことか。今の聴くに堪えない言葉、日本語の乱れ――。リーダー不在、インテリ不信の時代に「言葉の力」と「教養の本質」を問う。
「自分」から、自分が引き受けている社会的役割を、一つ一つ引き剥がしていったとして、最後に何が残るか。「その最後に残るべきものを、自分のなかに見付け、それを耕し、それを育てる、それを自分が生きた証としようと努力を重ねる。そこに『平等』を超えた一人一人の人間の姿があり、その努力をこそ『教養』と呼ぶのではないでしょうか。人と人との繋がりは、こうした人間の『芯』同士の繋がりであってこそ、『人間』つまり『人と人との間』を作り上げるものではないでしょうか」と語る。「エリート」とは「大衆よりも自分が優れていると自任するような輩ではなく、大衆よりも自分に対してより重い義務を課す人間である」とオルテガの言った言葉を述べる。
「欲望の過剰な発揮を抑制する方途として道徳、倫理があり、長らく宗教に依存してきた」「カントは道徳の基盤を宗教から切り離し、それを人間の理性に求めることとした」「教養の概念の一部は『理性の戒め』を実行するための根源として働く。理性が命ずる道徳律をも遵守するための原動力としての教養。何事にも『慎みがある』ことだ。『慎み』はある社会で生きていく際に求められる作法、行動習慣にかなっていることであり、社会がどのような行動習慣を求めているかを『弁えている』ことだ」「こうした点から派生する、教養の大切な局面の一つはコミニュケーション能力だ」「日本の政治の現状を見ると、政治家の発言にユーモアも、巧みなレトリックも遠き慮リも何もなく、何も言っていないのに等しい」「政治家よ、教養人たれ。ウィットやユーモアも、心の余裕、あるいは自由度から生まれる『教養ある』存在に許された能力である」「教養を深めることには、自分自身の個を築きあげることが中心となるのは言うまでもないが、他人が同じ過程をたどっているはずであることを否応なく悟らされることになる。そこに初めて、自分が、自分の個から離れてみる志向性が生まれる」と深く掘る。コミニュケーションの重要性と世阿弥のいう離見の見、山崎正和さんの社交する人間だ。
さらに教養について、「エリートと教養」「日本語と教養」「音楽と教養」「生命と教養」などを詳述する。「ポストコロナの日本考」が副題だが、「教養」の本質を浮き彫りにする。静かに考える、深く考え行動する、そうしたなかでの人間の豊かさと社会の豊かさを考える。
 ハンガリーに生まれ、RNA研究を続け、新型コロナ感染症を抑えるワクチンを開発したカタリン・カリコ。ロシアによるウクライナ侵攻という蛮行が続いているだけに、ハンガリー事件で大変苦労したカリコ氏の粘り強い戦いが、より鮮明に浮き彫りにされる。RNA研究を続けるために、30歳の時に娘のテディベアにお金を忍ばせて一家で渡米する。職場で見向きもされなかったり、大学で降格されたり、研究費が出ないなど、とにかく大変な状況が次々と襲ってきた。そのなかでも粘り強く一筋の道を歩み続ける彼女を応援する家族、恩師、同志ともいうべき研究仲間。40年間、あきらめず続けたワクチン開発の裏側にあるカリコ氏の真摯な姿勢を描く。「世紀の.発見は逆境から生まれた」とあるが、本当に感動的だ。
ハンガリーに生まれ、RNA研究を続け、新型コロナ感染症を抑えるワクチンを開発したカタリン・カリコ。ロシアによるウクライナ侵攻という蛮行が続いているだけに、ハンガリー事件で大変苦労したカリコ氏の粘り強い戦いが、より鮮明に浮き彫りにされる。RNA研究を続けるために、30歳の時に娘のテディベアにお金を忍ばせて一家で渡米する。職場で見向きもされなかったり、大学で降格されたり、研究費が出ないなど、とにかく大変な状況が次々と襲ってきた。そのなかでも粘り強く一筋の道を歩み続ける彼女を応援する家族、恩師、同志ともいうべき研究仲間。40年間、あきらめず続けたワクチン開発の裏側にあるカリコ氏の真摯な姿勢を描く。「世紀の.発見は逆境から生まれた」とあるが、本当に感動的だ。
「生涯の師匠となる高校の教師アルベルト・トート博士」「多大な影響与えたハンス・ セリエ博士、ビタミンCを発見しノーベル賞を受賞したセント・ジュルジ・アルベルト博士」「一人娘のスーザン・フランシアさんはアメリカを代表するボートのオリンピック金メダリスト」「mRNAの研究で新しいタンパク質の生成に成功(mRNAに特定のタンパク質を作る指令を出させるという新しい発見)」「mRNAを使えばタンパク質を作らせることができるが、大きな欠点は体内に注入すると激しい炎症反応を引き起こすことだった。これをついにカリコ氏とワイズマン氏の共同研究で克服」・・・・・・。
本書の末尾で山中伸弥教授へのインタビューがあるが、最大の問題は日本でのワクチン開発でも明らかなように、それを薬品として提供できること、「死の谷」の克服だ。カリコ氏は、ドイツの製薬会社「ビオンテック」に2013年に移籍する。そして2020年の世界的な新型コロナウィルスの流行に際し、ファイザー・ビオンテックとモデルナがワクチンの治験・製造を行い、世界各国で使用される。わずか一年足らずという短い期間でワクチンが製造できたのは奇跡的。カリコ氏のような長い年月をかけてmRNAの研究に取り組んできた存在があったからだ。その研究姿勢について、山中伸弥教授は「私自身、人生のモットーを『VW』と言っている。ビジョンとワークハード。自分のぶれない研究テーマを持って、それを達成するために困難にも負けずに打ち勝っていく。まさにお手本です」と言っている。そして研究心を駆り立てるものは「ワクワクドキドキする好奇心です。特に基礎研究者は、朝起きて、今日は何が起こるか分からないという仕事なんですね」と言う。二人とも静かでありながら強い意志を貫く。凄さが伝わってくる。