 「学問、功利主義、ジェンダー、幸福を考える」が副題。ポリティカル・コレクトネス、差別、格差、ジェンダー、動物の権利、仕事の辛さと幸福・・・・・・。直面するこれら課題について「幸福」「道徳」を古典的な思想と哲学の議論を踏まえつつ最新の学問の知見に触れつつ考える。「学問の意義」「功利主義」「ジェンダー論」「幸福論」の4つのカテゴリーで構成する、進化論を軸にしたこれからの倫理学を語る。
「学問、功利主義、ジェンダー、幸福を考える」が副題。ポリティカル・コレクトネス、差別、格差、ジェンダー、動物の権利、仕事の辛さと幸福・・・・・・。直面するこれら課題について「幸福」「道徳」を古典的な思想と哲学の議論を踏まえつつ最新の学問の知見に触れつつ考える。「学問の意義」「功利主義」「ジェンダー論」「幸福論」の4つのカテゴリーで構成する、進化論を軸にしたこれからの倫理学を語る。
最終章は「黄金律と『輪の拡大』、道徳的フリン効果と物語的想像力」で締めくくる。「人間の利他的行動をめぐる論争」だ。利他的行動は生物学だけでは説明がつけられない。「道徳の黄金律は、自分が他人から知ってもらいたいと思うような行為を、他人に対して行え。自分が他人からされたくないと思うような行為は、他人に対して行うな」――この黄金律が普遍的な道徳と呼ばれる。「本来は生存や繁殖を有利にするために進化したはずの理性が、生存や繁殖を不利にしても他人を助ける考え方を選択するようになる。『輪の拡大』」だ。人類の歴史において道徳的配慮の輪が拡大してきた。その道徳的配慮の輪を広げるためには「他人の立場に立つこと、他人の視点を取得すること」が必要とされる。さらに「知識と論理だけでは黄金律を実践することはできない」「他人の立場に身を置くためには物語的想像力が必要だ。そのためには人文学や芸術が不可欠である」と言う。そして「他者に対する関心を広げるきっかけとなるのは愛情である。相手のことを真剣に考えるようになるものだ」と言い、「抽象的な思考と物語的想像力のどちらも不可欠」と結論付ける。
論点を長い歴史の中から考える。「人文学は何の役に立つのか」「なぜ動物を傷つける事は差別であるのか」「トロッコ問題を考える。オートモードの感情とマニュアルモードの理性。トロッコ問題は、まさに特殊な状況であり、道徳感情に従うべきではなく、理性に基づいて考えることだ」「マザー・テレサの名言。大切な事は遠くにある人や大きなことではなく、目の前にある人に対して愛を持って接することだ。他の国の人間を助ける事は他人によく思われたいだけの偽善者である。偽善者なのか慈善者なのか」「かわいそうランキングについては、感情ではなく、マニュアルモードの理性に基づかせるべきである」「フェミニズムは男性問題を語れるか(男性の対物志向と女性の対人志向) (男性のシステム化思考と女性の共感思考)」「ケアや共感を道徳の基盤とすることができるのか」「ストア哲学の幸福論は現代にも通じるのか(ストア哲学の欲求コントロール)」「マズローの欲求のピラミッド。生理的欲求から社会的欲求、そして自己実現への欲求」「心の平静を求めるストア哲学、それを超えて他者がいないと満たされない欲求もある」「快楽だけでは幸福にたどり着けない理由、子供を育てたり仕事での達成感や没頭感」「仕事は禍いの根源なのか、それとも幸福の源泉なのか」・・・・・・。
「哲学と言えば、答えの出ない問いに悩み続けることだ、と言われることがあるが、私はそうは思わない]といい、「哲学的思考は難しい問題に何らかの形で正解を出すことができる考え方」と言う。言い方を変えれば、難しい問題から目をそらさずに考え続けることが哲学であり、その真摯な姿勢が「21世紀の道徳」となるのではないかと思う。
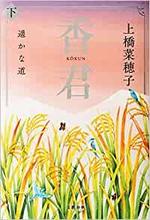 「この世に、香りで万象を知る香君は存在しない。初代の香君さま以外はすべて偽物だ」「私にとって香りは言葉より雄弁です。絶えず香の声が聞こえ、人の声と違って止む事はありません。それを聞き続けていることが、幸君の徴であるというのであれば、私は多分、香君なのでしょう」――。
「この世に、香りで万象を知る香君は存在しない。初代の香君さま以外はすべて偽物だ」「私にとって香りは言葉より雄弁です。絶えず香の声が聞こえ、人の声と違って止む事はありません。それを聞き続けていることが、幸君の徴であるというのであれば、私は多分、香君なのでしょう」――。
いったん下限を下げることによって、危機を乗り越えたかに見えたが、「駆除の方法が見つからない以上、本当の危機脱出にはならない」との恐れは払拭できないでいた。そして香君オリエ、アイシャは、マシュウの母の故郷でもある「幽谷ノ民」の地へ向かう。しかし「救いの稲」による希望は無残にも打ち砕かれる。それ以上の凄まじい災厄、バッタの大群に襲われるのだ。稲だけでなく、牧草も野菜も食い尽くすという自然の摂理の無情さだ。全焼却すべきだが、国は果たして維持していけるのか。政治的にも帝国は保持できるかどうか――大変な決断を迫られる。オードセン新皇帝、香君オリエ、マシュウ、アイシャ・・・・・・。
オードセンを前にしてのアイシャの発言、マシュウの発言――まさに立正安国、国主諫暁のごとしだ。
「私は、天と地と人々の前に、何の掛け値もない自分として、たたねばならない」――。壮大なファンタジーであるが、人間と自然、自然界の連鎖、国家の危機管理、神と幻想、文明の進歩と逆襲など、根源的問題を提起し、コロナ禍をも想起させる類例の」ない作品。
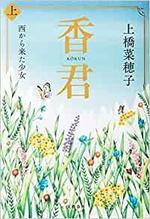 植物は香りを使って他の動植物や昆虫・生物などと会話をしている。その香りで森羅万象を知る「香君」という女性がいた。権力とは別の権威たる"神"的存在だ。ウマール帝国を舞台にしての「香君」の壮大な物語。この巨大な帝国が作られたのは、遥か昔、神郷からもたらされた奇跡の稲・オアレ稲によって飢えから解放されたことによるものであり、「香君」がそれを庇護してきたからだった。「父上は、オアレ稲を喜びと悲嘆の稲、と呼んでいた」「オアレ稲は豊かさだけでなく、従属ももたらした(帝国は種籾を独占した)」「オアレ稲は化け物でもある。こいつは、自分だけを頼るように、人と、大地を変えてしまった」――。豊かさを保障するものであるとともに、支配の道具でもあり、さらに他の生物の生存をもなぎ倒す側面をもっていたのだ。そしてついに恐れた事態が発生した。その奇跡の稲にオオヨマがたかる虫害に襲われたのだ。「飢えの雲、天を覆い、地は枯れ果て、人の口に入るものなし、ああ、香君よ、風に万象を読み、衆生を救いたまえ」・・・・・・。
植物は香りを使って他の動植物や昆虫・生物などと会話をしている。その香りで森羅万象を知る「香君」という女性がいた。権力とは別の権威たる"神"的存在だ。ウマール帝国を舞台にしての「香君」の壮大な物語。この巨大な帝国が作られたのは、遥か昔、神郷からもたらされた奇跡の稲・オアレ稲によって飢えから解放されたことによるものであり、「香君」がそれを庇護してきたからだった。「父上は、オアレ稲を喜びと悲嘆の稲、と呼んでいた」「オアレ稲は豊かさだけでなく、従属ももたらした(帝国は種籾を独占した)」「オアレ稲は化け物でもある。こいつは、自分だけを頼るように、人と、大地を変えてしまった」――。豊かさを保障するものであるとともに、支配の道具でもあり、さらに他の生物の生存をもなぎ倒す側面をもっていたのだ。そしてついに恐れた事態が発生した。その奇跡の稲にオオヨマがたかる虫害に襲われたのだ。「飢えの雲、天を覆い、地は枯れ果て、人の口に入るものなし、ああ、香君よ、風に万象を読み、衆生を救いたまえ」・・・・・・。
主人公はアイシャという少女。西カンタル藩王の孫で、人並み外れた抜群の嗅覚をもち、植物の世界を読み取る力をもっていた。しかしアイシャは、オアレ稲の栽培に危惧を唱える一族の末裔でもあり、帝国から追討を受けていた。捕縛され殺される寸前、マシュウ・カシュガに助けられ、現在の香君オリエのもと、菜園で働くことになる。
そこに恐るべき虫害が国を襲い、土地を焼き払うしか術はなかった。オアレ稲に秘められた謎、宿命づけられた抜群の嗅覚を持つ自らの出生。自然をコントロールしようとする人間の業、そして自然からの逆襲・・・・・・。その戦いと煩悶、自然との対話が、「下」で展開されようとする。
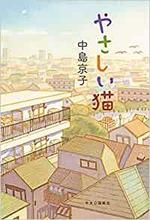 スリランカ人男性・クマラと結婚した日本人女性・ミユキとその娘・マヤが、日本の厳しい出入国管理制度に翻弄されていく様子を描く。入管制度の仕組みが、言葉も十分わからない彼らにとっていかに過酷なものか。そのことが息苦しくなるほど日本の私たちにとって迫ってくる。「偽装結婚ではないか」が焦点となるが、外国人労働者として入国し、失業した場合にいかに大変か。立場が不安定である上に、オーバーステイの問題、「審判」「退去強制、強制送還、5年間の入国禁止の恐怖」「収容所の厳しい環境」「在留特別許可の激減」「出生主義と血統主義、日本で生まれても日本人ではない問題」「収容所での電話の不許可、病気になっても十分医療が受けられないこと」「難民を保護することと外国人を管理するという同じ入管の抱える問題(入管から独立した難民認定機関の必要性)」「非正規滞在の仮放免では働けない問題」「非正規滞在では健康保険が使えない、入れない」・・・・・・。次から次へと難問が「小さな家族」におそいかかる。「強制送還されるか、死ぬか、どちらかを選べと言われている気がする」と追い込まれる。「出会って好きになった人と、ずっと一緒に暮らしたいだけなのに」・・・・・・。
スリランカ人男性・クマラと結婚した日本人女性・ミユキとその娘・マヤが、日本の厳しい出入国管理制度に翻弄されていく様子を描く。入管制度の仕組みが、言葉も十分わからない彼らにとっていかに過酷なものか。そのことが息苦しくなるほど日本の私たちにとって迫ってくる。「偽装結婚ではないか」が焦点となるが、外国人労働者として入国し、失業した場合にいかに大変か。立場が不安定である上に、オーバーステイの問題、「審判」「退去強制、強制送還、5年間の入国禁止の恐怖」「収容所の厳しい環境」「在留特別許可の激減」「出生主義と血統主義、日本で生まれても日本人ではない問題」「収容所での電話の不許可、病気になっても十分医療が受けられないこと」「難民を保護することと外国人を管理するという同じ入管の抱える問題(入管から独立した難民認定機関の必要性)」「非正規滞在の仮放免では働けない問題」「非正規滞在では健康保険が使えない、入れない」・・・・・・。次から次へと難問が「小さな家族」におそいかかる。「強制送還されるか、死ぬか、どちらかを選べと言われている気がする」と追い込まれる。「出会って好きになった人と、ずっと一緒に暮らしたいだけなのに」・・・・・・。
スリランカの民話の話に「優しい猫」がある。クマラがマヤに語る。「親を猫に殺された子ネズミが、猫に窮状を訴える。それを聞いた猫は後悔する。そして自分にも子供がいるからと、一緒に育てる」という話。この話はマジョリティーとマイノリティーの話に思えるという。強い者、大きい者たちが、ネズミの真摯な訴えに耳を傾けて気づくということ。「猫の気づき、猫の覚醒」と指摘する。外国人との共生社会に向けて、外国人労働者問題は最も重要なものだ。この3年で大きく変わってきたと思うが、より本格的に具体的に急速度に対応しなければならないと思う。
 「構造的問題と僕らの未来」が副題。「社会学は社会の複雑な現象・変容をどう捉えるか。『構造的問題』として理解することが重要だ」「社会の『底』が抜けてしまっている」「『安全、快適、便利』なのになぜ生きづらいのか」との認識がある。そして「汎システム化とヒューマニズムの持続可能性の危機にいかにして対峙すべきなのか」という問題意識がある。
「構造的問題と僕らの未来」が副題。「社会学は社会の複雑な現象・変容をどう捉えるか。『構造的問題』として理解することが重要だ」「社会の『底』が抜けてしまっている」「『安全、快適、便利』なのになぜ生きづらいのか」との認識がある。そして「汎システム化とヒューマニズムの持続可能性の危機にいかにして対峙すべきなのか」という問題意識がある。
「生活世界」と「システム世界」――。人間らしい情の交いあう顔見知り同士の「生活世界」が、匿名性とマニュアルに従う「システム世界」に侵食されて、やがて完全に取って代わる汎システム化、システム世界の全域化になっていく。そこでは、流動的な労働市場で、社員や店員は「過剰流動性」と「入れ替え可能性」にさらされる。大企業のエリート社員、エリート官僚も同じで、「自分は一体何者であるのか」との「人間存在をめぐる不安」「孤独」から逃れられなくなっている。「安全、快適、便利」の一人ひとりの欲望の行き着く先が、この「システム世界の全域化」であり、「感情の劣化」「不安・孤独の暴発」という人間存在の変容をもたらしている。孤独に耐えられないことから無差別殺人事件などの悲惨な事件が起きる。
それに加えて、テクノロジーの進化、ネット社会の加速が、本来DNAに刻まれてきた人間性をも押し潰し、「仲間としての人間関係」「われわれ意識」を遮断し、人間関係は「損得化」に堕していく。さらに社会には秩序が必要であり、そのための統治が必要だが、「『まとも』に生きようとするより、『うまく』生きようとする『あさましい』『損得野郎』が溢れてくる。社会と人間の劣化がとめどもなく進む」と指摘し、嘆き、弾劾する。まさに「社会の『底』が抜けてしまっている」わけだ。国民=仲間から始まった国民国家は希薄化し、個人の主体性を頽落させて、民主政を世界中で機能不全に陥れさせ、社会の統治をいっそう困難にしているのだ。
それでは「システム世界の全域化と共同体の空洞化にどう向き合うか」――。ヨーロッパの知識人たちは伝統的にシステムを警戒し、スローフード運動などを通じてシステム世界の全域化に抗ってきたが、濁流に飲まれて挫折してきた。対称的アプローチをしたのがアメリカで、成員が「快・不快」で動く動物であっても社会が回るような統治のあり方を追求した。マクドナルド化をディズニーランド化によって埋め合わせるマッチポンプ的発想だ。これをさらに進めようとしているのが、新反動主義者や加速主義者だが、ともに我々の望むところではない。同感だ。「快・不快」の動物的性質を利用した統治よりも、人々の善意と主体性を基礎に置く統治を望む。「うまく」生きる人よりも、「まとも」に生きる人が溢れる社会こそ、「よりよい社会」だ。「テクノロジーやシステムを全否定はしない」「小さなユニットから再出発し、食やエネルギーの地産地消をテコにテックやシステム社会と共存する形で、(疑似)共同体自治を確立せんとする」といい、その波及を展開したいという。政府や市場を否定することなく、中間集団の(再)構築、小さいユニットから「われわれ意識」を取り戻すという提案だ。これには当然、人々をエンパワーするリーダー、利他的・倫理的で信頼されるリーダーが必要だが、「ミメーシスを起こす人間たれ」と講義を受講する人に呼びかける。社会と人間の変容にどう立ち向かうか。指摘しているのは考えているうえでのリアルである。

