 文章も書き、演説もし、会話も人一倍してきたと思うが、「接続詞」を意識して考えたことはなかった。本書を読んで、改めて「接続詞」を考えてみると、確かに「文章は接続詞で決まる」ことが浮かび上がる。「プロの作家は接続詞から考えます。接続詞が、読者の理解や印象に特に強い影響を及ぼすことを経験的に知っているからです」と言う。名人芸というか、魔法というか、本書で示された夏目漱石の「坊ちゃん」「それから」、アガサ・クリスティーの「そして誰もいなくなった」、梶井基次郎の「檸檬」、谷川俊太郎の「そして」等を見ても鮮やかさに喝采したくなる。
文章も書き、演説もし、会話も人一倍してきたと思うが、「接続詞」を意識して考えたことはなかった。本書を読んで、改めて「接続詞」を考えてみると、確かに「文章は接続詞で決まる」ことが浮かび上がる。「プロの作家は接続詞から考えます。接続詞が、読者の理解や印象に特に強い影響を及ぼすことを経験的に知っているからです」と言う。名人芸というか、魔法というか、本書で示された夏目漱石の「坊ちゃん」「それから」、アガサ・クリスティーの「そして誰もいなくなった」、梶井基次郎の「檸檬」、谷川俊太郎の「そして」等を見ても鮮やかさに喝采したくなる。
「接続詞が良いと文章が映える」「4種10類に分ける――論理の接続詞(順接、逆接)、整理の接続詞(並列、対比、列挙)、理解の接続詞(換言、例示、補足)、展開の接続詞(転換、結論)」「文末の接続詞」「話し言葉の接続詞」「接続詞のさじ加減」「接続詞の戦略的使用」などが、丁寧に解説される。
「話し言葉の接続詞」は文章とは違うが、演説と会話はまた違う。演説は接続詞が多かったりするとテンポが狂う。会話は主語がなくても通じる。演説も会話もライブだから、場面転換を突然行っても相手は話に必ずついてくる。しかし、「文章は接続詞で決まる」は納得した。
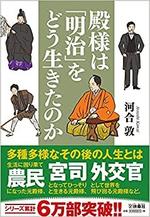 幕末から明治初期、各大名がいかに苦闘したか。江戸三百藩は攘夷と開国、佐幕と倒幕、公武合体政策と大政奉還と王政復古の大号令(新政府樹立宣言)、戊辰戦争での各藩の決断、そして明治に入っての版籍奉還、廃藩置県などで揺れに揺れた。藩が一瞬のうちに消滅して、「殿様」はどう明治を生きたか。
幕末から明治初期、各大名がいかに苦闘したか。江戸三百藩は攘夷と開国、佐幕と倒幕、公武合体政策と大政奉還と王政復古の大号令(新政府樹立宣言)、戊辰戦争での各藩の決断、そして明治に入っての版籍奉還、廃藩置県などで揺れに揺れた。藩が一瞬のうちに消滅して、「殿様」はどう明治を生きたか。
「維新の波に抗った若き藩主たち」――。会津藩主・松平容保(朝敵にされた悲劇の大名、不幸の始まりは松平春嶽に要請されて京都守護職を引き受けたこと)、桑名藩主・松平定敬(松平容保と行動を共にした実の弟)、請西(じょうざい)藩主・林忠崇(藩主自らが率先して薩長と戦う。一時は農民になった)、紀州藩主・徳川茂承(敗走した旧幕府軍兵をかくまい、新政府から敵のような扱いを受けた。陸奥宗光に助力を求める)・・・・・・。
「徳川慶喜に翻弄された殿様」――。水戸藩主・徳川昭武(兄徳川慶喜の身を案じた仲の良い16歳も年下の弟。趣味に生きた晩年)、福井藩主・松平春嶽(徳川家存続のために奔走するが徳川慶喜に裏切られ続けた。坂本龍馬の理解者)、土佐藩主・山内容堂(戊辰戦争の勝者だが、新政府のやり方に不満、酒浸りの晩年)、尾張藩主・徳川慶勝(実の弟が松平容保と松平定敬。弟たちと敵味方で刃を交えるが、後に弟たちの助命活動。倒幕に動き、諸藩を新政府の味方につけたが故に、新政府が苦もなく江戸に到達できた。趣味の写真を残した)、静岡藩主・徳川家達(幼くして徳川宗家を継いだ16代目当主。徳川慶喜を嫌い、明治では大いに政治的手腕を発揮し、天皇から組閣を命じられたほどの大政治家。貴族院議長を31年間)・・・・・・。
「育ちの良さを生かして明治に活躍」――。徳島藩主・蜂須賀茂韶(祖先の不名誉な噂を払拭するために外交官や官僚として活躍)、広島藩主・浅野長勲(3人の天皇と心を通わせた最後の大名。財政を確保するために製紙会社を設立)、岸和田藩主・岡部長職(長年の欧米生活、外交官として活躍、東京府知事)、米沢藩主・上杉茂憲(沖縄の近代化に尽くそうとした名門藩主)、津和野藩主・亀井茲監(国づくりは教育にありを実践)・・・・・・。
どの人も波瀾万丈の人生。大変な決断と心労だったと思う。
 生老病死のなかでも身近にある「病」。「病」に対処しようとした時、文学や哲学はどう役割を果たしたのか。また文学と哲学はいかに「病」の影響を受けてきたのか。「病と宗教」「病と哲学」「疾病と世界文学」、そして「医学と文学」が描かれる。ギリシャから今日に至るまで、まさに古今東西、全てと言っていいほど内容豊かに書き上げる。
生老病死のなかでも身近にある「病」。「病」に対処しようとした時、文学や哲学はどう役割を果たしたのか。また文学と哲学はいかに「病」の影響を受けてきたのか。「病と宗教」「病と哲学」「疾病と世界文学」、そして「医学と文学」が描かれる。ギリシャから今日に至るまで、まさに古今東西、全てと言っていいほど内容豊かに書き上げる。
「序章 パンデミックには日付がない(地震のように一撃ではない。長期にわたって危険)」「第一章 治癒・宗教・健康」――。「神罰としての病に抗する接触する治癒神イエス」「免疫システムとしての仏教」「哲学に対して賎業の医術だった」・・・・・・。「第ニ章 哲学における病」――。「徳には適切なエトス=習慣こそがエチカ、つまり倫理と一致する」「医学は占いや魔術から発したが、ヒポクラテスらは医術を魔術から区別しようとした」「ヒポクラテスらは臨床的な立場から哲学という『気まぐれな思弁』を撃退しようとした」「16世紀のヴェサリウスの解剖学とハーヴィの生理学。17世紀のデカルトの哲学には、これらの研究が取り入れられている」「ベーコンの最上の善としての健康」「18世紀、カントは哲学と医学との分業を強調、インフルエンザは従来と異なる奇妙で不思議な流行病とした。ジェンナーの種痘をヴォルテールは評価したが、カントは自分の身体を恣意的に危険にさらすとして批判した」「哲学VS医学、唯心論VS唯物論、神学VS人間学が起きる」「ヘーゲルはコレラで死亡」――。そして細菌学のコッホ、免疫学のジェンナーにフロイトの精神分析が加わって大転換がなされていく。病因論のインパクトは大きく、フロイトも病因を特定しようと野心を持ったという。そして20世紀に入り、「哲学者は人体の究明からも感染症の課題からも遠ざかっていく」のが根本的変化と結論づける。
「第三章 疫病と世界文学」――。「デフォーのペストはロンドンの惨状を克明に描いた。疾病そのものよりも、錯乱とパニックに陥った集団の自己破壊、信用の崩壊、人間の愚かさを描く。しかもロビンソン・クルーソーと共通するロックダウンの閉鎖空間・監禁と別離のテーマ」「カミュのぺストは日付のないパンデミックの単調さと遮断と追放の感情」「罪と罰で描かれるコレラの悪夢」「コレラの恐怖を反映したドラキュラ」「ぺスト文学は共同体の閉鎖性に対し、コレラ文学はユダヤやアジアからの浸食という外部性の違いがある」「日本では結核文学が多くある。梶井基次郎と堀辰雄」・・・・・・。そして平成文学は、結核ではなく、心の病、多重人格、自閉症、LG BT、AIと人間が描かれていく。
「第四章 文学は医学をいかに描いたか」――。「終章 ソラリスとしての新型コロナウィルス」――。そして「病のイメージに多くの仕事を任せてきた哲学と文学、その2つの歴史を新しいやり方で交流させ、お互いに感染させることが私の狙いとなりました。思うに、哲学や文学はそこにどれだけひどい世界が書かれていても、いつかは良いこともあるだろうという無根拠な希望を呼び覚ます力を持っています。本書がこの慎ましい希望の力の一端を読者に伝えることができれば著者としては本望です」と語る。
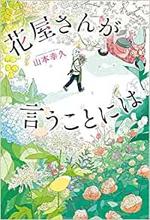 ブラック企業に勤め、心身ともに疲れ果てていた君名紀久子、24歳。復帰を求められて困っていたところ、紀久子をカッコよく助けてくれたのは、外島季多という女性で、駅前で「川原崎花店」を営んでいた。グラフィックデザイナーになるという夢を持っていた美大出身の紀久子だが、この花屋でアルバイトをすることになる。花を求めてくる様々な客、バラエティーに富んだ従業員やその友人。美しい花や花言葉に囲まれ、紀久子は自分を取り戻し、未来に向けて進もうとする。
ブラック企業に勤め、心身ともに疲れ果てていた君名紀久子、24歳。復帰を求められて困っていたところ、紀久子をカッコよく助けてくれたのは、外島季多という女性で、駅前で「川原崎花店」を営んでいた。グラフィックデザイナーになるという夢を持っていた美大出身の紀久子だが、この花屋でアルバイトをすることになる。花を求めてくる様々な客、バラエティーに富んだ従業員やその友人。美しい花や花言葉に囲まれ、紀久子は自分を取り戻し、未来に向けて進もうとする。
「泰山木」――「昨日、泰山木の花をくださいましたね。・・・・・・花言葉は前途洋々」。「向日葵」――「列車にて遠く見ている向日葵は少年のふる帽子のごとし(寺山修司)、ひまわりは本数で花言葉が違う。3本は『愛の告白』だ」。「菊」――「重陽の節句に現れた幽霊。まるで菊花の約。菊の英語の花言葉は『あなたはとても素晴らしい友達』」・・・・・・。
「クリスマスローズ」――「(結婚詐欺師に騙され)泣きじゃくる百花に千尋が抱きついた。さらに馬淵先生が百花の背中に寄り添う。そんな母子三代を見て、紀久子はクリスマスローズの花言葉を思い出していた。『私の不安を和らげて』」。
「ミモザ」――「深作ミモザ園を出て20分ほど経ち、陽が沈み、辺りはすっかり暗くなっている。・・・・・・ミモザ(アカシア)の花言葉は優雅、友情、そして秘密の恋」――。「桜」――「桜並木の写真をSNSにあげる際、紀久子は桜の花言葉を毎日、添えていた。桜全般でも精神美、優美な女性、純潔とあリ、桜の種類によってもちがう。フランスの桜の花言葉は『私を忘れないで』」・・・・・・。
「スズラン」――「スズランって見れば見るほど、鈴にそっくりなんですねぇ。すずらんのリリリリリリと風に在リ。・・・・・・若いうちに自分のやりたいことに取り組まなくっちゃって・・・・・・。スズランの花言葉は『再び幸せが訪れる』」。「カーネーション」――「赤いカーネーションの花言葉は母への愛、純粋な愛、そして真実の愛」・・・・・・。
花屋さんで働くことになった紀久子の周りに爽やかな薫風が吹き渡る。
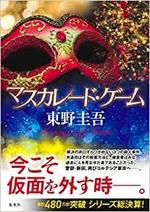 3つの連続殺人事件が起きる。共通点は、胸をナイフで刺されるという殺害方法と、被害者はいずれも過去に人を死なせたものであるということだ。刑事・新田浩介らが捜査に入り、ローテーション殺人事件ではないかと目星をつける。少年の暴力によって植物状態にされ、ついには失った「無念の母」の神谷良美、母親を強盗殺人犯に奪われた森本雅司、リベンジポルノによって娘が自殺に追い込まれた前島隆明の3人だ。いずれも「日本は罪の大きさに比べて罰が小さすぎる」という恨みを持っていると思われた。人を殺したのに刑期が20年以下とか、犯人が少年だと刑務所にさえ入らないとか、心神喪失等で刑事責任能力がないなどで、罰せられないということに対する苛立ちと怒りだ。そしてなぜか、その3人がクリスマスの夜、ホテル・コルテシア東京に集結することがわかる。ホテル側からも協力を得て、細やかな観察眼をもつフロントクラーク・山岸尚美が急遽、アメリカから呼び寄せられる。潜入捜査に入る新田浩介と山岸尚美の名コンビが復活する。4番目の事件とそれに苦しむ家族も現われ、緊迫したクリスマスの夜、事件は思わぬ展開を見せるのだが・・・・・・。
3つの連続殺人事件が起きる。共通点は、胸をナイフで刺されるという殺害方法と、被害者はいずれも過去に人を死なせたものであるということだ。刑事・新田浩介らが捜査に入り、ローテーション殺人事件ではないかと目星をつける。少年の暴力によって植物状態にされ、ついには失った「無念の母」の神谷良美、母親を強盗殺人犯に奪われた森本雅司、リベンジポルノによって娘が自殺に追い込まれた前島隆明の3人だ。いずれも「日本は罪の大きさに比べて罰が小さすぎる」という恨みを持っていると思われた。人を殺したのに刑期が20年以下とか、犯人が少年だと刑務所にさえ入らないとか、心神喪失等で刑事責任能力がないなどで、罰せられないということに対する苛立ちと怒りだ。そしてなぜか、その3人がクリスマスの夜、ホテル・コルテシア東京に集結することがわかる。ホテル側からも協力を得て、細やかな観察眼をもつフロントクラーク・山岸尚美が急遽、アメリカから呼び寄せられる。潜入捜査に入る新田浩介と山岸尚美の名コンビが復活する。4番目の事件とそれに苦しむ家族も現われ、緊迫したクリスマスの夜、事件は思わぬ展開を見せるのだが・・・・・・。
罪と罰。被害者の家族の苦しみと葛藤。「軽い刑罰」で生きる加害者側にもある苦しみ。業火に焼かれる人間の生と死のはざまで、「憎しみ」と「許す」との相克。「憎しみなんかは人生にとってただの重たい荷物だけど、それをおろす方法は一つしかない。ところがそれも失ってしまって」という重い言葉がのしかかるが・・・・・・。その答えも重いものであった。東野圭吾さんの「マスカレード」シリーズ、本書もぐっと胸に迫る。確かにホテルは仮面をかぶった人が集まるマスカレードだ。悲喜こもごもの人が日常からちょっと離れて仮面をかぶって集まるが、この社会がそもそも仮面舞踏会かもしれない。「仮面を剥ぐ」のは、ミステリーの根幹。マスカレード・ホテルはそれゆえに面白い。このシリーズ、続けて欲しいものだ。

