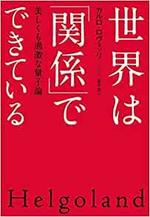 「美しくも過激な量子論」が副題。著者は「時間は存在しない」の著書でも名高い理論物理学者で「ループ量子重力理論」の提唱者の一人。竹内薫氏の解説がついている。単なる量子物理学の解説書、難解な数式を駆使しての書ではない。「科学とは世界を概念化する新しい方法を探ること」であり、物理学もそのルーツをたどれば「自然哲学」であり、この世界をひもとく思想である。コペルニクスの地動説、ニュートン力学、ダーウィンの進化論、アインシュタインの相対性理論を経て、古典力学では捉え切れない一見奇異な量子現象をとらえる「量子論」が、いかに人類の世界観にインパクトを与えたか、量子物理学の真髄を解き明かそうとしたのが本書だ。したがってロヴェッリの思索の旅は物理学にとどまらず、あらゆる思想・哲学に及ぶ。ハイゼンベルクのみならずボグダーノフ、レーニンの政治まで及ぶが、特に「量子理論」がナーガールジュナ(龍樹)の「空」の哲学にまで結びついていく。「びっくり仰天した」とロヴェッリはその衝撃を語るが、圧巻であり、興奮を私自身、共にする思いだ。
「美しくも過激な量子論」が副題。著者は「時間は存在しない」の著書でも名高い理論物理学者で「ループ量子重力理論」の提唱者の一人。竹内薫氏の解説がついている。単なる量子物理学の解説書、難解な数式を駆使しての書ではない。「科学とは世界を概念化する新しい方法を探ること」であり、物理学もそのルーツをたどれば「自然哲学」であり、この世界をひもとく思想である。コペルニクスの地動説、ニュートン力学、ダーウィンの進化論、アインシュタインの相対性理論を経て、古典力学では捉え切れない一見奇異な量子現象をとらえる「量子論」が、いかに人類の世界観にインパクトを与えたか、量子物理学の真髄を解き明かそうとしたのが本書だ。したがってロヴェッリの思索の旅は物理学にとどまらず、あらゆる思想・哲学に及ぶ。ハイゼンベルクのみならずボグダーノフ、レーニンの政治まで及ぶが、特に「量子理論」がナーガールジュナ(龍樹)の「空」の哲学にまで結びついていく。「びっくり仰天した」とロヴェッリはその衝撃を語るが、圧巻であり、興奮を私自身、共にする思いだ。
科学界最大の発見である量子論の核心とは何か。時は1925年夏、物質粒子を追い求めてきた世界に、量子論を着想したドイツの青年、ハイゼンベルクが登場する。そして本書は、ハイゼンベルクやシュレーディンガーらの戦いをドラマチックに表現する。ミクロの世界の深淵に迫れば、「物理学は長い時間をかけて、物質から分子、原子、場、素粒子・・・・・・というふうに『究極の実体』追い求めてきた。そのあげく、量子場の理論と一般相対論のややこしい関係に乗り上げて、にっちもさっちもいかなくなった」、そして「この世界は実体ではなく、関係に基づいて構成されている」「あくまでも相互依存と偶発的な出来事の世界であって、『絶対的な存在』を引き出そうとするべきではない。根源的な確かさの不在こそ、知の探求を育む」「私たちが観察しているこの世界は、絶えず相互に作用しあっている。それは濃密な相互作用の網なのだ」「『シュレーディンガーの猫』の思考実験が示すように、量子は確率的で重ね合わせされた状態にある」・・・・・・。
量子力学は「粒子と波の二重性(本質は波)」「観測するまで実在しないという非実在性」「位置と速度は同時に決まらないという不確定性(古典力学では確定)」「エネルギーの壁をすり抜けるトンネル効果」などの特徴をもつが、本書はその歴史的な数々の論争をドラマチックに再現する。そして宇宙とは何か、世界とは何かの命題に、物理・科学者だけでなく哲学者・宗教者等がいかに迫ったか、そして今も挑戦しているかを生きいきと描く。
 「ベーシックアセットの福祉国家へ」が副題。日本における貧困、介護、育児の政治について、これまでの対立構図、その中で達成されてきた制度、そして現在の日本の生活保障の状況とその課題、そして提起される「ベーシックインカム」「ベーシックサービス」「ベーシックアセット」の中身とあるべき方向性を示す。この世界を、政府・自治体の政策論議に現実に関わってきた宮本さんが、俯瞰的に思想の系譜を掘り下げつつ解読・提起する。次の段階の社会保障のあるべき姿、あるべき社会を示す重厚な書。
「ベーシックアセットの福祉国家へ」が副題。日本における貧困、介護、育児の政治について、これまでの対立構図、その中で達成されてきた制度、そして現在の日本の生活保障の状況とその課題、そして提起される「ベーシックインカム」「ベーシックサービス」「ベーシックアセット」の中身とあるべき方向性を示す。この世界を、政府・自治体の政策論議に現実に関わってきた宮本さんが、俯瞰的に思想の系譜を掘り下げつつ解読・提起する。次の段階の社会保障のあるべき姿、あるべき社会を示す重厚な書。
日本の社会保障は、「男性稼ぎ主の雇用保障に特段の力点を置き、家族が扶養される条件を確保する」という仕組みにあった。男性稼ぎ主の雇用を確保し、行政指導や業界保護で企業を安定させ、家族賃金によって安定を確保する「行政・会社・家族の三層がつながった三重構造」だ。しかし、雇用も家族も変容し、共働き、非正規化、業界保護も財政的に難しく、子育ての直面する問題も複雑化し、貧困・格差、高齢社会での医療・介護の課題等、制度は新しい課題に揺さぶられてきた。
そうしたなか焦点となるのは「新しい生活困難層」だ。従来の縦割り的制度の中で、どの恩恵にも外れてしまう人々だ。ひとり親世帯、低年金の高齢者、引きこもり、軽度の知的障害者など複合的な困難を抱えて、世帯内では相互依存にあり、雇用と社会保障の狭間にはまる人々だ。安定就労で社会保険制度の給付を受ける人や福祉受給者でもなく、非正規雇用で縦割りの社会保障の狭間に陥る層だ。
その上で本書は「貧困政治(生活保障の揺らぎと分断、対抗軸の形成、社会保障と税の一体改革、ベーシックインカムの台頭)」「介護政治(介護保険制度という刷新、分権多元型と市場志向型と家族主義型の新たな対立構図)」「育児政治(待機児童対策を超えて、児童手当をめぐる政治、保育サービスと政治とマタイ効果)」などを詳細に語る。財政の制約や新自由主義の潮流がいかに影響したかが明らかとなる。またその中で、生活困窮者自立支援制度、介護保険制度、子ども・子育て支援新制度等が制度化されてきた意義と課題を論述する。
そして「ベーシックインカム」「ベーシックサービス」「ベーシックアセット」だ。ベーシックインカムは、給付つき税額控除やAIで仕事を奪われる不安、コロナ禍の救済策などで論者も増えている。ベーシックインカムは現金給付、ベーシックサービスは公共サービス(医療・教育・住宅・デジタル情報アクセス)だが、それぞれのなかでも規模も思想も異なる。ベーシックアセットは「全ての市民に基本的なアセット(資源)を」という思想だ。現金給付も公共サービスも当然だが、こうした私的・公共的アセットに加えて、コモンズのアセットを重視する。コミュニティー、自然環境、デジタルネットワークなどが入る。新たな視野を入れる理念だが、これによって介護保険制度や子ども・子育て支援新制度、生活困窮者自立支援制度も本来の趣旨に沿って息を吹き返すという。困っている人を縦割り、一律に助けることではなく、その人が必要としているコモンズという財を柔軟に届けることでもある。本書は、人間と幸福の哲学・思想が読み取れる。
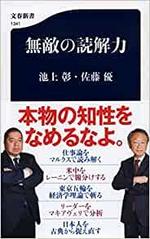 「このところ日本社会には反知性主義が蔓延しているのではないか。与野党問わず数多くの政治家の発言から、知性の煌きが感じ取れません。教養という言葉は、どこに消えたのか」「日本の政治家や実業家の話は、・・・・・・エピソードの羅列で、これらのエピソードに通底する普遍的規則を導き出そうとしていない。・・・・・・このような本の読み方をやめなくては日本の知力も国力も弱っていく」と、池上さんと佐藤さんは嘆く。現在、眼前にある諸問題について、その本質を見抜く「読解力」を具体的に示す。
「このところ日本社会には反知性主義が蔓延しているのではないか。与野党問わず数多くの政治家の発言から、知性の煌きが感じ取れません。教養という言葉は、どこに消えたのか」「日本の政治家や実業家の話は、・・・・・・エピソードの羅列で、これらのエピソードに通底する普遍的規則を導き出そうとしていない。・・・・・・このような本の読み方をやめなくては日本の知力も国力も弱っていく」と、池上さんと佐藤さんは嘆く。現在、眼前にある諸問題について、その本質を見抜く「読解力」を具体的に示す。
ベルクソンは「問題は正しく提起されたときそれ自体が解決である」と言ったが、問題提起それ自体に、すでに「読解力」の蓄積が現れるということだろう。毎日毎日、「これはどういうことなのか」と不断に問い続ける姿勢、日頃から「学ぶ」姿勢を続けなければ、本質が見えてこないと痛感する。ましてや政治家は常にポピュリズムへの誘惑と権力の魔性にどう耐え得るかが試されている。だからこそ、鍛えられた知性、教養、国家観や人生観など哲学が大事だ。かつ、思考停止に堕しかねないイデオロギーに、吸収されない現場主義が重要だと思う。
本書で扱う問題は、現在ある重要課題だ。「人新世から見た仕事論」――。そこでは「前資本主義の方が、コモンズ(公共財)に結びついており、豊かで無償で潤沢だった」「エネルギー問題をどうするか。清貧の思想の再確認に陥るか」「ブルシット・ジョブはマルクスの疎外論の大前提」などが語られる。「米中対立 新冷戦か帝国主義抗争か」ーー。「ミアシャイマーの米中対立・限定的な核戦争の懸念も」「帝国と帝国主義の違い、ネットワーク支配とネイションステート」「中国は文明の受容はうまいが、文化の受容の難しさが皮膚感覚でわかっていないかも」「クレバーなオバマの対中封じ込めと、バイデンの稚拙な体制間戦争意識」「すでにものづくりの世界の中心は中国、ユーラシア・サプライチェーンの形成」「勇ましい人は例外なく難しい交渉を経験したことのない人だ」「中国とは挨拶はするけど握手はしない。柔軟な日中関係」・・・・・・。
「オリンピックはなぜやめられなかったか」――。「オリンピックとガダルカナル、戦術変更に伴う高い埋没コストで後戻りできないという感覚」「複数の部分合理性を知ることの重要性」・・・・・・。「日本人論の名著を再読する」――。「『菊と刀』の影響と間違い。日本人は恥だけを規範にして生きていない」「大きな役割を果たしたライシャワー大使」・・・・・・。
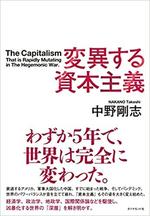 日本を含めた欧米先進諸国の経済・社会は長期停滞と格差に襲われている。そのなかで、米国のバイデン政権は、過去40年にわたって支配的であった新自由主義から訣別しようとインフラ投資、研究開発投資、製造業支援、これら画期的な大型経済対策に乗り出した。その布陣を見ても財務長官をウォール街から選んできたことを変え、労働経済学者のイエレンを起用し、ウォール街の権力に批判的な人物を各要職に付けた。この「経済政策の静かなる革命」を可能にした背景には、中国のハイブリッド軍国主義という地政学的な脅威がある。経済の長期停滞、バイデン政権の「経済政策の静かなる革命」、中国のハイブリッド軍国主義の深層を洞察すると、今の「残酷な世界」が見えてくる。資本主義は時間とともに「変異」しており、その劇的な変異の実相を構造的に、かつ時間軸をもって描き出している。「富国と強兵」「世界を戦争に導くグローバリズム」「日本経済学新論」「奇跡の経済教室」などの論考を踏まえ、「変異」する世界を構造的に解き明かす。
日本を含めた欧米先進諸国の経済・社会は長期停滞と格差に襲われている。そのなかで、米国のバイデン政権は、過去40年にわたって支配的であった新自由主義から訣別しようとインフラ投資、研究開発投資、製造業支援、これら画期的な大型経済対策に乗り出した。その布陣を見ても財務長官をウォール街から選んできたことを変え、労働経済学者のイエレンを起用し、ウォール街の権力に批判的な人物を各要職に付けた。この「経済政策の静かなる革命」を可能にした背景には、中国のハイブリッド軍国主義という地政学的な脅威がある。経済の長期停滞、バイデン政権の「経済政策の静かなる革命」、中国のハイブリッド軍国主義の深層を洞察すると、今の「残酷な世界」が見えてくる。資本主義は時間とともに「変異」しており、その劇的な変異の実相を構造的に、かつ時間軸をもって描き出している。「富国と強兵」「世界を戦争に導くグローバリズム」「日本経済学新論」「奇跡の経済教室」などの論考を踏まえ、「変異」する世界を構造的に解き明かす。
「新自由主義に基づく経済政策(小さな政府、均衡財政・・・・・・)やグローバリゼーションが、米国の長期停滞と格差の拡大を招いた」「21世紀の戦争はハイブリッド戦(正規軍のみならず非正規軍、無差別テロ、シャープパワー、エコノミック・ステイトクラフト) (米国のリベラルな国際秩序への楽観・錯覚と中国の戦略)」「政府の積極的な財政政策、金融市場の規制等を阻止しようとする資本家階級。それに対する国家能力の強化や労働者階級の社会的パワーの増大が重要」「コロナのパンデミックと中国のハイブリッド軍国主義の台頭の構造変化によって、世界はシュンペーターのいう社会主義化(政府の経済社会への関与の強化と積極財政、公的な経済運営や経済計画の役割の相対的増大)へと変異を遂げる」「その方向を考えると、国家が高度な統治能力を有することが必要不可欠」「構造改革、規制緩和、競争の活発化、生産性向上という新自由主義的政策が長期停滞をもたらした。供給力の高まりではなく、今は需要の増大が同時に行われることが大切。デフレ脱却の時」「金融資本主義こそが長期停滞の根本要因。金融政策以上に財政政策が重要で、民間投資を減殺しないで、ばらまきではなくインフラ、技術、公共投資、医療、教育、観光などが大切」「持続可能性を欠いた金融資本主義」「失敗に終わったリベラル覇権戦略(リベラリズムの楽観論)、既に崩壊した東アジアの米中パワーバランス」・・・・・・。
世界の政治家・経済学者・国際政治学者等の論争と実践を駆使した力業の著作。
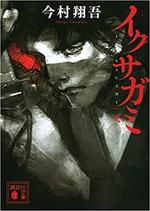 西南戦争が終わった後の明治11年。「武技ニ優レタル者。本年5月5日、午前零時。京都天龍寺境内ニ参集セヨ。金十万円ヲ得ル機会を与フ」なる怪文書が全国に出回る。巡査の初任給が4円、年間で48円の時代で、途方もない金額だ。そこに集まった強者292人、いずれも「コロリ(コレラ)の妻子を救いたい」「幕末・維新での汚名を雪ぎたい」「武士のあらぶる心を発散させたい」と大金を求めていた。そこで発せられたのは心技体の全てを競う「こどく(蠱毒)」というゲーム。1人の持ち点が「1点」。互いを殺し合いながら点数を稼ぎ、東京(江戸)に着くときに30点の者のみが生き残るという「殺戮の旅」のゲームだ。嵯峨愁ニ郎、共に動くことになった12歳の少女・香月双葉、伊賀者の柘植響陣、京八流の愁二郎の義兄弟・四蔵や彩八(いろは)、狂人的な乱斬リの貫地谷無骨・・・・・・。
西南戦争が終わった後の明治11年。「武技ニ優レタル者。本年5月5日、午前零時。京都天龍寺境内ニ参集セヨ。金十万円ヲ得ル機会を与フ」なる怪文書が全国に出回る。巡査の初任給が4円、年間で48円の時代で、途方もない金額だ。そこに集まった強者292人、いずれも「コロリ(コレラ)の妻子を救いたい」「幕末・維新での汚名を雪ぎたい」「武士のあらぶる心を発散させたい」と大金を求めていた。そこで発せられたのは心技体の全てを競う「こどく(蠱毒)」というゲーム。1人の持ち点が「1点」。互いを殺し合いながら点数を稼ぎ、東京(江戸)に着くときに30点の者のみが生き残るという「殺戮の旅」のゲームだ。嵯峨愁ニ郎、共に動くことになった12歳の少女・香月双葉、伊賀者の柘植響陣、京八流の愁二郎の義兄弟・四蔵や彩八(いろは)、狂人的な乱斬リの貫地谷無骨・・・・・・。
なぜこんなひどいゲームが。あたかも韓国映画の「イカゲーム」。本書の場合、仕掛けた黒幕は、士族の不満が充満し、維新の要人が次々に「暗殺」されたこの時代。前時代の亡霊の反乱を早めに鎮圧するために、「暗殺を実行し得る武に長けた者だけを、同士討ちさせて消し去る」策謀のゲームを目論んだようだが・・・・・・。殺戮のゲームの旅は始まったばかり。本書は三河の手前・宮宿あたりまで描く。東京(江戸)はまだまだ遠い。

