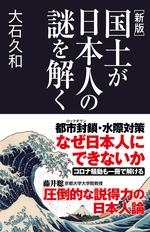 「コロナ禍で日本人は強制的な都市封鎖がなぜできないのか」「なぜ日本人は権力を嫌うのか」「なぜ日本人には長期戦略がないと言われるのか」――。それは長い歴史の中で、国土の自然条件から得た経験が日本人の生命に連綿と刻まれているからだ。それが共同体にも、社会全体にも刻まれている。日本人は欧米、中国、中東、アフリカ等々の人々とも違う。「ハンチントンは日本を独自の文明を持った国と位置づけている」「松本健一氏は泥の文明、石の文明、砂の文明の違いを鮮やかに描いた」「国旗を見ても、太陽を表す国と、太陽は忌むべき存在で月や星を描く国がある」「国歌においても敵を倒せという勇ましい歌と日本のような生命・自然の永久を歌う国もある」・・・・・・。「論語と算盤」の企業経営は、新自由主義の米型資本主義とは違うはず。大石さんは、西欧の「紛争死史観」と日本の「災害死史観」を詳説し、「国土」の視点から日本人の強みと弱さを解きあかし、「日本人の底力」「日本人の結束した時の集団の強さ」から、未来を再構築しようと訴える。
「コロナ禍で日本人は強制的な都市封鎖がなぜできないのか」「なぜ日本人は権力を嫌うのか」「なぜ日本人には長期戦略がないと言われるのか」――。それは長い歴史の中で、国土の自然条件から得た経験が日本人の生命に連綿と刻まれているからだ。それが共同体にも、社会全体にも刻まれている。日本人は欧米、中国、中東、アフリカ等々の人々とも違う。「ハンチントンは日本を独自の文明を持った国と位置づけている」「松本健一氏は泥の文明、石の文明、砂の文明の違いを鮮やかに描いた」「国旗を見ても、太陽を表す国と、太陽は忌むべき存在で月や星を描く国がある」「国歌においても敵を倒せという勇ましい歌と日本のような生命・自然の永久を歌う国もある」・・・・・・。「論語と算盤」の企業経営は、新自由主義の米型資本主義とは違うはず。大石さんは、西欧の「紛争死史観」と日本の「災害死史観」を詳説し、「国土」の視点から日本人の強みと弱さを解きあかし、「日本人の底力」「日本人の結束した時の集団の強さ」から、未来を再構築しようと訴える。
日本にはなぜかその災害が集中する時期がある。鎌倉時代の1200年代――正嘉の大地震、寛喜の大飢饉、疫病の蔓延、そして蒙古襲来。幕末は安政の頃を中心に東海と南海大地震、江戸大風水害、ペリー来航等がある。1945年前後には、東南海、三河、福井地震があり、枕崎やカスリーン台風などの風水害、そして第二次世界大戦の敗戦がある。私はコロナが2年続いている今、本当に首都直下地震、南海トラフ地震等を心配している。
歴史を動かした国土と災害・飢饉」「なぜ『日本人』は生まれたか(日本の脆弱国土の10項目)」「なぜ日本人は世界の残酷さを理解できないのか(世界の紛争・ 大虐殺と都市城壁)(フランスのカルカソンヌはなぜ5年間籠城できたのか)」「なぜ日本人は権力を嫌うのか(日本の分散した平野の小さな共同体と中国の中原を争う広域支配の大きな権力)(江戸は人口を100万抱えたが『江戸市民』はいなくて『木戸内住民』だった)」「なぜ日本人は中国人とここまで違うのか(中国人が生き延びるための血脈の団結、共同で結束する日本人)(侵略・殺戮から『考える』中国人と、災害から無常を『感じる』日本人) (理性・論理の民と情緒・感情の民)」「なぜ日本人はグローバル化の中で彷徨っているか(日本人に合わない企業統治制度)(対話ができない日本人と江藤淳の『閉ざされた言語空間』)」・・・・・・。
コロナ禍の今、大災害頻発の今、再読すべき極めて有益な書。
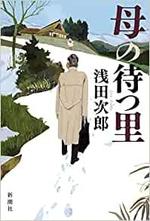 「素晴らしい里帰りを」――。家庭も故郷も持たない3人の還暦の男女に舞い込んだ招待。大企業の社長で独身の松永徹、会社からの退職金の振り込みがあったその日、妻から離婚届を突きつけられた室田精一、母に死なれて娘という安逸な立場が失われた60歳の医師・古賀夏生。それぞれが、この魅力的な誘いに乗り、向かったのは、岩手県の過疎の集落。そこには「ちよ」と名乗る「母」がいた。「ちよ」は、松永ちよとして、室田ちよとして、古賀ちよとして、それぞれの痛んだ心を癒し、都会の喧騒の中で忘れていた「ふるさと」「母子」「自然」の空洞を埋めてくれる。「ちよ」は「何があっても、母はお前の味方だがらの」とまでいうのだ。
「素晴らしい里帰りを」――。家庭も故郷も持たない3人の還暦の男女に舞い込んだ招待。大企業の社長で独身の松永徹、会社からの退職金の振り込みがあったその日、妻から離婚届を突きつけられた室田精一、母に死なれて娘という安逸な立場が失われた60歳の医師・古賀夏生。それぞれが、この魅力的な誘いに乗り、向かったのは、岩手県の過疎の集落。そこには「ちよ」と名乗る「母」がいた。「ちよ」は、松永ちよとして、室田ちよとして、古賀ちよとして、それぞれの痛んだ心を癒し、都会の喧騒の中で忘れていた「ふるさと」「母子」「自然」の空洞を埋めてくれる。「ちよ」は「何があっても、母はお前の味方だがらの」とまでいうのだ。
目標のなくなった還暦後の人生、便利ではあっても無機質な都会の生活、心許せる者を次々と失っていく孤独、真心に触れられない寂寥感、期待されない崩落感、繁栄と幸福との乖離・・・・・・。「ちよ」の無限の愛と村人と自然に、3人それぞれが魅せられ、引き込まれていく。
「母がかくも愛された理由は、自然であったから。そして子らがかくも母を愛した理由は、それぞれが不自然であるから」「人口の偏在や地域格差などという社会問題とはさほどかかわりなく.繁栄すなわち幸福と規定した原理的な過誤によって、多くの人々が自然を失い、不自然な生活をしなければならなくなった。そういう話だったのだと古賀夏生は得心した」・・・・・・。還暦後の人生と心に宿る原風景を問いかける。心奥に迫る。
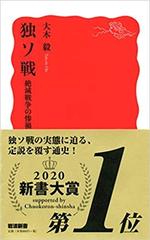 1941年6月22日、第二次世界大戦の独ソ戦が開始される。ナチス・ドイツとその同盟軍は、独ソ不可侵条約を破ってソ連に侵攻した。数百万の大軍が激突したこの戦争は、第二次世界大戦の主戦場(東部戦線)であり、北はバルト海から南は黒海、バルカン半島、コーカサスに至るまでの実に数千キロにわたるスケールといい、非戦闘員を巻き込んだ死者数といい空前絶後。数字自体が不明だが、現在では第二次世界大戦でのソ連の死者数は2700万人、ドイツは830万人にも及ぶという。とくにそれが戦闘して和平に至るという通常戦争ではなく、収奪戦争となり、根本は絶滅戦争であった。人種的に優れたゲルマン民族が、「劣等人種」スラヴ人を奴隷化するための戦争、ナチズムと「ユダヤ的ボルシェヴィズム」との闘争と位置づけた「世界観戦争」「絶滅戦争」とし、一方でスターリンのソ連は、ファシストの侵略者を撃退し、ロシアを守るための「大祖国戦争」と規定したのだ。結果は当然、仮借なき残酷な絶滅戦争となる。本書は戦後の独ソそれぞれの総括(ドイツはヒトラーに全ての悪を押し付けようとし、ソ連は祖国を守り抜く戦争だとし、双方に展開されたジェノサイド、収奪、捕虜虐殺の惨劇、戦略・戦術の誤りを歪曲した歴史修正主義に立った)を正し、その戦いの本質を剔抉している。2020年、評判を呼んだ新書大賞だが、今回、「同志少女よ、敵を撃て(逢坂冬馬著)」に刺激されて、改めて読んだ。戦争の構図が鮮やかに描き出されていて、目が覚めるようだ。
1941年6月22日、第二次世界大戦の独ソ戦が開始される。ナチス・ドイツとその同盟軍は、独ソ不可侵条約を破ってソ連に侵攻した。数百万の大軍が激突したこの戦争は、第二次世界大戦の主戦場(東部戦線)であり、北はバルト海から南は黒海、バルカン半島、コーカサスに至るまでの実に数千キロにわたるスケールといい、非戦闘員を巻き込んだ死者数といい空前絶後。数字自体が不明だが、現在では第二次世界大戦でのソ連の死者数は2700万人、ドイツは830万人にも及ぶという。とくにそれが戦闘して和平に至るという通常戦争ではなく、収奪戦争となり、根本は絶滅戦争であった。人種的に優れたゲルマン民族が、「劣等人種」スラヴ人を奴隷化するための戦争、ナチズムと「ユダヤ的ボルシェヴィズム」との闘争と位置づけた「世界観戦争」「絶滅戦争」とし、一方でスターリンのソ連は、ファシストの侵略者を撃退し、ロシアを守るための「大祖国戦争」と規定したのだ。結果は当然、仮借なき残酷な絶滅戦争となる。本書は戦後の独ソそれぞれの総括(ドイツはヒトラーに全ての悪を押し付けようとし、ソ連は祖国を守り抜く戦争だとし、双方に展開されたジェノサイド、収奪、捕虜虐殺の惨劇、戦略・戦術の誤りを歪曲した歴史修正主義に立った)を正し、その戦いの本質を剔抉している。2020年、評判を呼んだ新書大賞だが、今回、「同志少女よ、敵を撃て(逢坂冬馬著)」に刺激されて、改めて読んだ。戦争の構図が鮮やかに描き出されていて、目が覚めるようだ。
ナチ・イデオロギーの人種主義と軍備拡張と不況・財政危機は領土拡張政策となり、戦争へと突き進む。「ナチス・ドイツは独裁者ヒトラーの『プログラム』とナチズムの理念のもと、主導的に戦争に向かうと同時に、内政面からも資源や労働力の収奪を目的とする帝国主義的侵略を行わざるを得ない状態に追い詰められていた」「ヒトラーは東方植民地帝国の建設を戦争目的に据えていた」「ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅は、ヒトラーの人種イデオロギーが動因といわれるが、最初からユダヤ人の絶滅を企図していたのではなく、国外追放が失敗した結果、政策をエスカレートさせていった」「スターリンは開戦当時、全く警戒措置をとっておらず、ソ連軍はスターリンの将校大粛清によって弱体化していた」「ヒトラーは、弱体化しているソ連軍など鎧袖一触で撃滅できると考え、当初はそのとおり進んだが、バルバロッサ作戦直後から頑強に戦うソ連兵に消耗し、補給端末との距離も遠ざかるばかりとなった」「スモレンスクの戦いは、モスクワ会戦やスターリングラード攻防戦、クルスク戦車戦に並ぶほど重要性をもつターニング・ポイントとなった」「南部ロシアの工業・資源地帯、コーカサスの油田といった経済目標を重視するヒトラーと、政治的・戦略的な目標である首都モスクワの奪取こそ勝敗を決すると信ずる陸軍の対立があった」「真珠湾攻撃の知らせを聞いたヒトラーは、1941年12月11日、米国に宣戦布告。ヨーロッパの紛争から世界大戦となった」「ソ連には当初、スターリンへの嫌悪が激しかったが、『ドイツの占領者どもに死を』とのナショナリズムと共産主義の擁護が融合し、民衆も反撃に立ち上がった。それが独ソ戦を凄惨なものとした」「スターリングラードの敗北、ドイツ軍は戦略的攻撃能力を失った」「ムッソリーニもソ連との和平をヒトラーに訴え、日本も他の同盟国も和平交渉を働きかけ、リッぺントロップも戦争継続と和平とのあいだで動揺したが、絶対戦争を貫くヒトラーは変わらなかった」「戦後を睨んだスターリンは、ドイツを徹底的に打倒することを前提として、中・ 東欧の支配を米英に認めさせようと勢力圏を西に拡大しようとした」・・・・・・。
そして、ドイツ国防軍は、1944年6月6日のノルマンディーで敗れ、呼応したソ連軍の大攻勢が行われ、1945年1月12日、ドイツへの侵攻作戦が開始された。ヒトラーは4月30日、自殺する。本書は終章として、今もなお独ソのみならず、この独ソ戦の悲惨な歴史が「『絶滅戦争』の長い影」となっていることを語り、結ぶ。
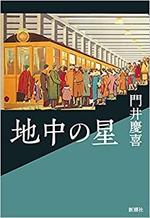 「土木工学はシビルエンジニアリングといって、市民、公共の為に働き構造物を造る。誰が造ったとかいう名は残らない」と京大土木に入った時に恩師が言った。「俺はあの工事に携わった」という誇りが胸の中にあれば、最高ではないか、と思う。本書の主人公・早川徳治は東京に地下鉄を誕生させた男だ。「地下鉄の父」と呼ばれるが、知る人は少ない。
「土木工学はシビルエンジニアリングといって、市民、公共の為に働き構造物を造る。誰が造ったとかいう名は残らない」と京大土木に入った時に恩師が言った。「俺はあの工事に携わった」という誇りが胸の中にあれば、最高ではないか、と思う。本書の主人公・早川徳治は東京に地下鉄を誕生させた男だ。「地下鉄の父」と呼ばれるが、知る人は少ない。
1881年、山梨県に生まれた早川徳治は早稲田大法学科を卒業し、南満州鉄道株式会社に就職、その後転職もするが、鉄道畑を歩んだ。ロンドンで地下鉄を見て、「これを東京にぶち込んでやる」と決意する。資金も経験もない、徒手空拳。大隈重信にも渋沢栄一にも頼み込み、熱き闘いが始まり、工事着工にこぎつける。そこで闘いは現場に移る。まずは浅草―上野間の2.1キロ。土留めおよび杭打ちの坪谷栄、覆工担当の木本胴八、掘削担当の奈良山勝治や西中常吉、コンクリート施工担当の松浦半助、電気設備の与原吉太郎。大倉土木の現場総監督・道賀竹五郎率いる各部門の腹心だ。事故あり、資金難あり、路面電車をはじめ通行激しき地下工事でもあり、神田川をくぐる技術的困難さとの闘いもあり、数々の苦難が押し寄せるなか、昭和2年、開業にこぎつける。そして新橋までの延線(昭和9年)。技術者たちの名は"土木屋"らしく大して残っていない。その間の五島慶太との熱い心の交流や時流に翻弄されるがゆえの確執などが描かれる。そして営団地下鉄となる昭和16年・・・・・・。
帯には「家康、江戸を建てる」の著者による昭和2年のプロジェクトX物語とある。壮大な熱き闘いに感動するとともに、私はこの同時期に荒川放水路(現在の荒川)の大工事が並行して行われていたことに思いをはせる。
 気候変動の影響拡大が止まらない今、地球最大の氷である南極の氷に何が起きているか。またこの先何が起きるのか。南極氷床の面積は日本の約40倍、氷の厚さは平均2000メートル、場所によっては4000メートルを超える。もし全てが溶けて海に流れ込めば、地球の海水準(陸地に対する海面の高さ) は約60メートル上昇すると言う。極寒の南極の氷床が急激に溶け始める事はないと言われていたが、近年の研究で急速に氷が失われつつある事実が明らかになった。南極越冬隊の話は子供の頃から知っていたが、南極そのものを知らなかったことを改めて感じた。南極に何度も行き、科学的調査をしている杉山慎さんが、現在の状況を冷静に解説する。今もなお、わからないことばかりの南極の氷床と地球環境問題。副題は「気候変動と氷床の科学」。
気候変動の影響拡大が止まらない今、地球最大の氷である南極の氷に何が起きているか。またこの先何が起きるのか。南極氷床の面積は日本の約40倍、氷の厚さは平均2000メートル、場所によっては4000メートルを超える。もし全てが溶けて海に流れ込めば、地球の海水準(陸地に対する海面の高さ) は約60メートル上昇すると言う。極寒の南極の氷床が急激に溶け始める事はないと言われていたが、近年の研究で急速に氷が失われつつある事実が明らかになった。南極越冬隊の話は子供の頃から知っていたが、南極そのものを知らなかったことを改めて感じた。南極に何度も行き、科学的調査をしている杉山慎さんが、現在の状況を冷静に解説する。今もなお、わからないことばかりの南極の氷床と地球環境問題。副題は「気候変動と氷床の科学」。
「IP CC第6次評価報告では、21世紀末までに海水準が2メートル近く上昇する可能性を否定できない。21世紀に入って氷床が氷を失いつつある」「「氷河の流動と氷床。南極氷床は地球の氷河の9割、残りのほとんどはグリーンランド氷床。淡水」「明らかになった氷床の危機。崩壊する棚氷、加速する氷河」「氷床は温暖化でじわじわ溶けているのではない。海へと流れる氷河に起きた加速と言う異変によって海へ排出される氷が増加しているのだ。そこには棚氷の縮小がある。底面融解が増加し、薄くなり、場合によっては崩壊し、接地線が後退している。南極氷床は現在、まだグリーンランド氷床の半分程度に過ぎないが・・・・・・」「12万年前には今とほぼ同じ水準にあった海水準は、その後に低下し、直近の2万年間では100メートル以上上昇している。これは今は存在しないローレンタイド氷床の融解によるものだ」「今は間氷期で1万年を超えて続いており、過去の周期を見ると気温が下がる氷期になってもいい頃だが、そうなっていない。地球が人間の活動でおかしくなっているからか。研究者の間でも議論は様々だ」「海水準の上昇は、氷床の縮小。各研究者も縮小方向は共通しているが、大きさは2100年までに10センチもあれば、1.5メートルもある」「急激な氷床変動の要因は、①海洋性氷床の不安定性②海洋性氷崖の不安定性」「南極の未来を考えて不確定なのは、①温室効果ガスの排出量②降雪量や海水温などの気候モデル③氷の流動・氷床モデル」「2021年のIPCC報告書では、最悪2100年までに2メートル、2150年までに5メートルの海水準の上昇を否定できないと言う」――。
そして現在の気候変動がいかに異常かを示し、ブレーキをかける真剣な対策を、と言う。

