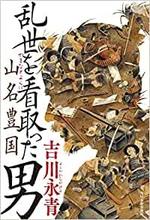 「何ゆえ山名家は没落の途を余儀なくされたのか。幕府の累代管領、栄達と権勢を渇望した者たちの私欲に巻き込まれ、振り回されてきたからだ」「信長には天下布武の大志があった。天下に静謐をもたらし、武王の徳政を布く。・・・・・・翻って羽柴はどうだ。立身出世も結構だろう。では何を志すがゆえの栄達なのか。それに対する答えを、恐らく羽柴は持たない」――。
「何ゆえ山名家は没落の途を余儀なくされたのか。幕府の累代管領、栄達と権勢を渇望した者たちの私欲に巻き込まれ、振り回されてきたからだ」「信長には天下布武の大志があった。天下に静謐をもたらし、武王の徳政を布く。・・・・・・翻って羽柴はどうだ。立身出世も結構だろう。では何を志すがゆえの栄達なのか。それに対する答えを、恐らく羽柴は持たない」――。
足利幕府の名門と崇められた山名家。12代目・山名宗全が応仁の乱を起こし凋落を始める。その90年後、時は戦国時代間近。かつて治めていた分国も次々失われ、今となっては但馬と西隣の因幡を家領に残すのみとなっていた。この苦境を撥ね退け、中興との願いを当主・伯父の裕豊の下で育った山名豊国は託せられる。
しかし、織田と毛利の二大勢力に挟まれ、どちらにつくかで、裏切りを繰り返す。但馬衆や因幡衆の手前勝手な不平・不満・反発を戒められず、国はますます混乱していく。尼子の残党(山名鹿之助ら)の生き残り戦略、秀吉の策謀等々、ついに山名家は潰れる。まさに東西の攻防激しき地、因幡、但馬、播磨、摂津の武将はいずれも苦難の歴史をたどることになる。
そして秀吉に"名門"であることで身を寄せることになった山名豊国だったが、家康から声をかけられ、将棋相手となるなど心を打ち明けるほど昵懇となる。秀吉の死、関ヶ原、二度の大坂城攻めによる豊臣滅亡、家康の死・・・・・・。禅高入道・山名豊国は乱世の終わりを見届ける"役目"(我が生、定数あり)を終え、寛永3年(1626年)齢79の生涯に別れを告げた。
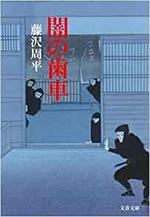 テレビの犯罪ドラマを観ているかのように、映像が立ち上がってくる。しかも登場人物はきわめて少なく、人生の陰翳が浮き彫りにされて面白い。盗賊、押し込みが描かれるが、これもまた藤沢周平の世界か。
テレビの犯罪ドラマを観ているかのように、映像が立ち上がってくる。しかも登場人物はきわめて少なく、人生の陰翳が浮き彫りにされて面白い。盗賊、押し込みが描かれるが、これもまた藤沢周平の世界か。
それぞれが問題を抱えている四人の男は、酒亭「おかめ」の常連。重い病を患っている妻をもつ脱藩浪人・伊黒清十郎。かつて人を刺して江戸払いとなり、今は娘夫婦の家に住む飲んだくれの白髪の年寄り弥十。許嫁がいながら年上の女と深い仲となっている商家・兵庫屋の若旦那・仙太郎。同居していた女にも逃げられ長屋に住んで悪事を働いている佐之助。この四人が"押し込み強盗"に誘われる。誘ったのは盗っ人を本業とする伊兵衛。決行は夜ではなく、人足が途絶える"逢魔が刻"で、"鬼平"が狙い定める"強盗"ではなく、あえて"素人"による"押し込み"だ。南町奉行所の定町廻り同心・新関多仲は、伊兵衛を怪しいと見て探りを入れる。"押し込み"は成功したのだが・・・・・・。
「五人の男たちが、人の知らない闇の中で回しつづけてきた歯車が、これでぴったりと止まったのだ。歯車は俺ひとりでは動かない。佐之助は沈黙したが次に不意に腹の底から笑いが衝きあげてくるのを感じた。なんという運のない、情ない連中なのだと・・・・・・」「笑いながら、佐之助はろくに言葉をかわしたこともないその男たちを、自分がひどく好いていたのを感じていた。連中は間違いなく仲間だったのだ。・・・・・・笑いの一皮下に、険悪な怒りが動いていた。彼らをそうさせた運命といったようなものに、佐之助の怒りはむけられている」・・・・・・。
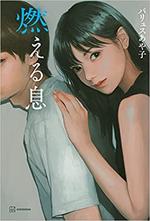 喧騒の現代社会には鬱積が満ちている。心の中にこもり積もった感情と衝動が、間欠泉のように吹き上げる。不安定なデリケートでセンシティブな社会の進展とともに、「止められない衝動」「何かへの依存、依存症?」が生まれる。それを6編としてまとめている。
喧騒の現代社会には鬱積が満ちている。心の中にこもり積もった感情と衝動が、間欠泉のように吹き上げる。不安定なデリケートでセンシティブな社会の進展とともに、「止められない衝動」「何かへの依存、依存症?」が生まれる。それを6編としてまとめている。
「呼ぶ骨」――置き引きをしたくてしたくてたまらない。突き上げるように震える手が、そのモノに「呼ばれる」ように感じ、動いてしまう。ある時は、それがお骨だった。「燃える息」――物心ついた頃からガソリンの匂いに魅せられた。あのツンとした刺激臭に出会うと不思議と心が落ち着く苅田灯馬。ある時、同類のガソリン女・須賀ほのかに出会う。「ジューンブライド・バナナパフェ」―― 結婚式でエレガントなウェディングドレスを着たいとダイエットを決意した守口芙美香。運動していると脳内麻薬物質でも生まれるのか、苦しい恍惚感が肉体の変化という確かな結果に裏打ちされて更に増幅していく。「疲れる以上に快感」と思っているが、身体は悲鳴をあげる。
「鈴木さんのこだわり」――交通事故で夫の保険金が相当入った母親が、異様なほどに高級化粧品等を買い続ける。整形を繰り返していた息子・善太は、「善太の友人」と嘘をついて毎週、母親の下に通う。化粧品にハマる母、整形にハマる息子。
「21周6日」――電車通学で痴漢にあった後、とにかく「搔きたい。掻きむしりたい」と無意識に手が動き皮膚を剥がしていく垣内江麻。心配してくれた間宮千春は、妊娠していた。痴漢にあい苦しみを隠している高校生と妊娠を隠している高校生の二人の葛藤。 「ファントム・バイブレーション」・・・・・・スマホ依存。震えてないのにスマホの振動を感じたり、鳴ってない着信音が聞こえるファントム・バイブレーション・シンドローム。1日中、SNS。「いいね」が欲しい。「人生を無駄にしているのではないか」「スマホ生活を仕切り直すチャンスをどうつかむか」。大変な時代となっている。
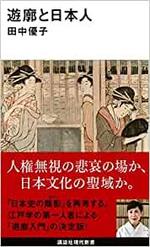 吉原を中心として「遊郭とは何であったか」「遊郭の歴史」を語る。庶民の厳しい暮らしと夢・歓びが同居した遊郭の生々しい姿が、解説される。
吉原を中心として「遊郭とは何であったか」「遊郭の歴史」を語る。庶民の厳しい暮らしと夢・歓びが同居した遊郭の生々しい姿が、解説される。
「遊郭は、家族が生き残るために、女性を『前借金』として誰も選びたくない仕事に差し出す制度だった」。しかし、「大正・昭和の吉原のイメージから、単なる娼婦の集まる場所と考えるのは誤解です。遊郭は日本文化の集積地でした。書、和歌、俳句、三味線、唄、踊り、琴、茶の湯、生け花、漢詩、着物、日本髪、櫛かんざし、香、草履や駒下駄、年中行事の実施、日本料理、日本酒、日本語の文章による巻紙の手紙の文化、そして遊郭言葉の創出など、平安時代以来続いてきた日本文化を新たに、いくぶん極端に様式化された空間」という二面性をもつ。その両面を、遊廓という空間に抱え込んだ非日常の夢・歓びの空間に仕上げたのだ。それを踏まえたうえで「遊郭は二度とこの世に出現すべきではなく、造ることができない場所であり制度である」という。
「遊郭より遊女の存在は古く、遊女は芸能者であり、昼に美声を聞かせ、夜には呼ばれて床入りする」「女かぶきの禁止と吉原遊郭の誕生(1617年、幕府公認の元吉原)」「遊女とはどんな人たちか?――なぜ"心中もの"が流行したのか?」「男女の『色道』と吉原文化――江戸のいい男といい女、出版文化が演出した遊郭・遊女」「吉原遊郭の365日――吉原は演出された劇場都市」「近代以降の吉原遊廓――マリア・ルス号事件と芸娼妓解放令(明治5年)、にごりえとたけくらべ、遊郭社会の拡大と吉原の凋落(江戸文化の消滅)」・・・・・・。
「ジェンダーの問題とは、女性そのものの問題ではなく、『女性を道具とみなす』『女性を性対象としてしか見ない』という男性たちの問題。戦争時に極端に現れるが、平常時でも同様、今日まで続いている」とし、「家族の多様性」「追い詰められない家族」「正月も桜の祭り、諸行事も、茶の湯や着物、踊りも歌舞伎ももう一度生活に取り戻す」・・・・・・。大変意義深い書。
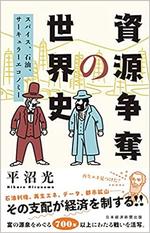 「資源争奪の世界史」が表題だが、「世界は資源争奪の歴史であった」ことが鮮やかにわかる。最初の資源はスパイス。コロンブス、バスコ・ダ・ガマ、マゼラン。それがポルトガル、スペイン、オランダ、それにイギリスが加わり、東インド会社設立を始めとする植民地争奪戦となり、勢い本国の戦いとなっていく。「石炭の登場」は森林破壊を防ぎ、イギリスの産業革命を起こす。石炭は蒸気船、蒸気機関車を生み日本にはペリーが来航する。そして19世紀後半から一攫千金のオイルラッシュだ。ロックフェラーが石油に目をつけ、いよいよガソリン車の登場。石油争奪は第一次、第二次世界大戦を左右した。2000年代はシェールガス革命だ。そして地球温暖化問題、SDGsの登場。蒸気機関、電気、コンピュータ、それに続くICT活用のインダストリー4.0は、エネルギー、資源の角度で見れば、まさに今新しい世界史に突入する歴史的な分岐点に立っているということがよくわかる。それを鮮やかに浮き彫りにしているのが本書である。
「資源争奪の世界史」が表題だが、「世界は資源争奪の歴史であった」ことが鮮やかにわかる。最初の資源はスパイス。コロンブス、バスコ・ダ・ガマ、マゼラン。それがポルトガル、スペイン、オランダ、それにイギリスが加わり、東インド会社設立を始めとする植民地争奪戦となり、勢い本国の戦いとなっていく。「石炭の登場」は森林破壊を防ぎ、イギリスの産業革命を起こす。石炭は蒸気船、蒸気機関車を生み日本にはペリーが来航する。そして19世紀後半から一攫千金のオイルラッシュだ。ロックフェラーが石油に目をつけ、いよいよガソリン車の登場。石油争奪は第一次、第二次世界大戦を左右した。2000年代はシェールガス革命だ。そして地球温暖化問題、SDGsの登場。蒸気機関、電気、コンピュータ、それに続くICT活用のインダストリー4.0は、エネルギー、資源の角度で見れば、まさに今新しい世界史に突入する歴史的な分岐点に立っているということがよくわかる。それを鮮やかに浮き彫りにしているのが本書である。
COP26のグラスゴ一合意を見ても、脱石炭・脱化石燃料、再生エネルギーへの加速、EV・自動運転への大転換は「大戦争」といってよい。世界は激震の中にあり、「エネルギー転換とサーキュラーエコノミーの構築が目指すものは、化石燃料依存から再生可能エネルギー利用に転換し、天然資源ではなく再生資源を循環させる経済モデルを構築するステージに突入している」「明確なゲームチェンジであり、チャンスだ」「日本には世界一の都市鉱山がある。日本は太陽光発電産業を牽引してきた歴史があり、高いエネルギー変換率の太陽光パネルを製造するなど再生可能エネルギー分野の高度な技術を持っている」「IoEの重要な要素となるV2Gでは、日本のチャデモが唯一実用化されているEVの急速充電設備だ(エネルギーシステムの一部となるEV)」「中国の台頭著しいリチウムイオン電池だが、そもそもリチウムイオン電池を開発したのは日本であり、注目の全固定リチウムイオン電池の開発でも特許保有など先んじている」「レアアースの一種であるジスプロシウムを一切使わないネオジム磁石をホンダが開発している」「水素の燃料電池車(FC V)のミライを送り出したのも日本だ」「浮体式洋上風力発電は世界6位の海洋面積に囲まれた日本には有力な再生エネルギーだ(ブルーエコノミー)」・・・・・・。
本書は、世界全体の熾烈な「生き残り戦争」がデータを示しつつ語られている。危機感を募らせながらも、エールを送ってくれている。頑張らねばならない。

