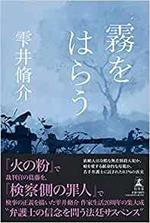 病院で入院中の4人の子どもたちが死傷(2人死亡)する点滴死傷事件が起きる。点滴にインスリンが混入されたという。305号室は4人部屋。急性系球体腎炎で入院していた小南紗奈の母親・野々花が逮捕される。野々花はいったん犯行を自白するが、その後無罪を主張。人権派の有名な弁護士・貴島義郎が弁護を担当。その下にいた同期の桝田から若手弁護士の伊豆原は、弁護団に加わることを誘われる。調べを進めるうちに伊豆原は弁護の中心となっていく。
病院で入院中の4人の子どもたちが死傷(2人死亡)する点滴死傷事件が起きる。点滴にインスリンが混入されたという。305号室は4人部屋。急性系球体腎炎で入院していた小南紗奈の母親・野々花が逮捕される。野々花はいったん犯行を自白するが、その後無罪を主張。人権派の有名な弁護士・貴島義郎が弁護を担当。その下にいた同期の桝田から若手弁護士の伊豆原は、弁護団に加わることを誘われる。調べを進めるうちに伊豆原は弁護の中心となっていく。
「野々花が無罪であると、100%信じているか。今の自分はまだ、野々花の周りにある霧を払い切れてない」「弁護人が100%信じていないなら、無罪判決など到底勝ち取れない」・・・・・・。そして検事から「もし万が一、冤罪が生まれるとするなら、それはほかでもない、君ら弁護人に100%その責がある。君ら弁護人だけが被告人を守る役目を促されているからだ」とまでいわれるのだ。
野々花と入院中の他の親との感情の衝突や、看護師の間での人間関係のもつれ、点滴にインスリンを混入される時間はあったのか。野々花は自分の娘を被害者とすることで自分が疑われることから逃れようとしたのか。野々花は検察が持ち出した代理ミュンヒハウゼン症候群なのか。警部補の尋問に強引さがあったのではないか・・・・・・。伊豆原は丁寧に丁寧に調べ続け、野々花の娘・由惟や紗奈にも暖かな目を注いでいく。そして霧をはらい、「無罪」を確信していくのだった。
事件の解明という表層の底で、弁護士はどう感情をつかみ、戦略を組み上げていくか。公判での弁護士の姿を扱う通常のドラマではなく、公判前手続などがいかに行われていくか。調査がいかに大変な作業か。弁護士の信念とゆらぎ、さらに生活にまでキメ細かく描いた法廷サスペンス。霧は濃霧を突き抜けて晴れるようだ。
 「失踪60年――伝説の作戦参謀の謎を追う」が副題。私が小学校低学年の頃、親父から「潜行三千里」の辻政信の話をよく聞いた。そして参院選全国区で上位当選をして話題になったこと、さらに昭和36年、謎の失踪をしたことをよく覚えている。多くの調査・書籍があるが、改めて今、辻政信の真実に迫る本書は、なぜか新鮮。かつ、あの昭和の戦争の現場が、辻政信の生きざまを通じて蘇える。
「失踪60年――伝説の作戦参謀の謎を追う」が副題。私が小学校低学年の頃、親父から「潜行三千里」の辻政信の話をよく聞いた。そして参院選全国区で上位当選をして話題になったこと、さらに昭和36年、謎の失踪をしたことをよく覚えている。多くの調査・書籍があるが、改めて今、辻政信の真実に迫る本書は、なぜか新鮮。かつ、あの昭和の戦争の現場が、辻政信の生きざまを通じて蘇える。
「作戦の神様」とも「悪魔の参謀」ともいわれ善悪評価が二分される辻政信。ノモンハン事件やマレー作戦などを主導した伝説の作戦参謀・辻政信は1902年(明治35年)、石川県江沼郡東谷奥村今立という寒村に生まれる。山中温泉に近い、今の加賀市今立地区だ。貧しい炭焼きの子だった。優秀さと頑強な身体をもったが、何よりも真面目、真剣、反骨、貧しさを乗り越える家族の期待を一身に担っての精神的骨格、負けじ魂が備わったようだ。1917年、名古屋陸軍地方幼年学校に入学、1920年に首席で卒業、陸軍士官学校本科も首席で卒業。1924年には陸軍少尉となる。1939年、ノモンハン事件を作戦参謀として主導、1941年、太平洋戦争開戦時のマレー作戦を参謀として主導、フィリピン戦線、ガダルカナル奪還にも常に砲弾をくぐり抜ける前線に立つ。1945年終戦、バンコクを脱出し、まさに潜行三千里。1950年戦犯指定解除後、1952年には衆院選石川一区で当選。4期当選し、1959年参院全国区で3位当選。1961年、東南アジアへ視察旅行、ラオスで消息を絶つ。
「超人的な気力と体力と研鑽」「兵士たちをいたわり、その尊敬は絶大」「石原莞爾の日満漢蒙鮮の五族協和、道義思想、東亜連盟思想に感銘」「それに反して好戦的姿勢で、ノモンハンで独断専行」「関東軍を引っ張る最年少参謀」「タムスク爆撃でも最前線」「マレー作戦で作戦の神様」「フィリピン戦線、ガダルカナルの死闘」「ビルマ戦線」「終戦、一人で大陸にもぐり、アジアの中に民族の再建を図ろうと、大陸に潜ろうと決意」「政界という戦場――。兼六園での3万人講演会」「兄ともいう存在の服部卓四郎の死」「理想は妥協してはいけないが、手段は妥協しろ」「池田首相の訪米のための情報収集――。ラオスの内線が米ソの代理戦争であり、世界戦争に拡大することが懸念され、ラオスの中立化や南北ベトナム統一の可能性を探るため、ホー・チ・ミン大統領との会談をめざす。説得することを目的とする」「東南アジアで戦没した将兵の回向も」「戦いは敗けたと感じたものが、敗けたのである」「危険が来たら、それを避けずに、逃げないで死神に体当たりする。それが信念だ」・・・・・・。死を覚悟しての「冥土の旅」であったのか。
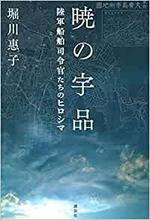 「陸軍船舶司令官たちのヒロシマ」が副題。広島市の宇品には、かつて「暁部隊」と呼ばれた陸軍船舶司令部が置かれ、軍事で最も重要である兵站を担った。歴史上でも大本営の発する戦略や陸海軍の戦闘は目立つが、この最重要の兵站が日本では軽視されていた。戦う陸軍兵の海上輸送ができなければ「戦い」にはならない。その黙々たる「隠れた力」を支えようとした輸送基地・宇品港、そして現場の苦悩を、奥歯をかみしめつつも諫言した司令官や結束する宇品の男たちの懊悩する魂を描く。司令官の田尻昌次、佐伯文郎、篠原優、そして技師・市原健造らの魂の決断と行動を膨大な文献を丹念に調べ上げた傑作。無謀な太平洋戦争の悲惨をドスンと心奥に叩き込まれる。ゆえに宇品は海軍ではなく陸軍、そして軍都・広島は8.6に原爆を落とされる。重い。
「陸軍船舶司令官たちのヒロシマ」が副題。広島市の宇品には、かつて「暁部隊」と呼ばれた陸軍船舶司令部が置かれ、軍事で最も重要である兵站を担った。歴史上でも大本営の発する戦略や陸海軍の戦闘は目立つが、この最重要の兵站が日本では軽視されていた。戦う陸軍兵の海上輸送ができなければ「戦い」にはならない。その黙々たる「隠れた力」を支えようとした輸送基地・宇品港、そして現場の苦悩を、奥歯をかみしめつつも諫言した司令官や結束する宇品の男たちの懊悩する魂を描く。司令官の田尻昌次、佐伯文郎、篠原優、そして技師・市原健造らの魂の決断と行動を膨大な文献を丹念に調べ上げた傑作。無謀な太平洋戦争の悲惨をドスンと心奥に叩き込まれる。ゆえに宇品は海軍ではなく陸軍、そして軍都・広島は8.6に原爆を落とされる。重い。
あの戦争で日本は「ナントカナル」で突き進んだ。満洲事変、日中戦争、その泥沼化、資源を求め打開しようとした南進、真珠湾。そしてミッドウェー、ガダルカナル、フィリピン、硫黄島、沖縄と次々に打ち砕かれ、本土へと追い込まれる。その現実をまざまざと真っ先に突き付けられたのが、兵站を担う宇品の陸軍船舶司令部であった。上海上陸を果たそうとする死を賭けた「七了口奇襲戦」。ガ島の"飢死"、生きるため善悪を越える極限状況に追い詰められる兵士。船が撃沈されても新しい船の建造ができない国内の物資不足・鉄鋼不足。最後には輸送からベニヤの船での特攻へと突き進む。大本営の精神論、楽観論と、現場の悲劇的現実。そして8.6――。宇品の男たちは、救出に死に物狂いで働いたという。しかも直言した田尻らは更迭されたという事実。
胸が締め付けられるが、常に立ち上がる重い課題に、リーダーはどう決断し、行動するかを、重く考えさせられる。常に、そして今も歴史を踏まえて考えることを忘れてはならない。
 1990年代以降の日本。進む少子高齢・人口減少社会、成長率の低下、雇用の悪化、非正規社員の増加、生活保護の増大、ワーキングプアの厳しい現実、子どもの貧困の連鎖、中間層の脱落・・・・・・。格差が広がっていることが指摘される。しかし、「日本型格差社会」と岩田さんが言うように、その根源は日本のデフレである。「こうした経済環境の悪化をもたらしたのは、90年代以降、アベノミクスが始まるまでの日銀の金融政策がもたらした長期にわたるデフレと、デフレ脱却に本格的に取り組み始めて、1年しかたっていない時期に実施した消費増税を筆頭とする緊縮財政である」「格差を縮小し、少子化を止める正攻法の政策は、財政政策と金融政策が協調して、デフレから脱却することである」という。そのうえで、「デフレから完全に脱却し、生産性が向上するように、供給者保護政策から公正な競争政策に転換し、規制と税制を改革して、一人当たりの成長率を高めることである」と言い、具体的改革案を提示する。
1990年代以降の日本。進む少子高齢・人口減少社会、成長率の低下、雇用の悪化、非正規社員の増加、生活保護の増大、ワーキングプアの厳しい現実、子どもの貧困の連鎖、中間層の脱落・・・・・・。格差が広がっていることが指摘される。しかし、「日本型格差社会」と岩田さんが言うように、その根源は日本のデフレである。「こうした経済環境の悪化をもたらしたのは、90年代以降、アベノミクスが始まるまでの日銀の金融政策がもたらした長期にわたるデフレと、デフレ脱却に本格的に取り組み始めて、1年しかたっていない時期に実施した消費増税を筆頭とする緊縮財政である」「格差を縮小し、少子化を止める正攻法の政策は、財政政策と金融政策が協調して、デフレから脱却することである」という。そのうえで、「デフレから完全に脱却し、生産性が向上するように、供給者保護政策から公正な競争政策に転換し、規制と税制を改革して、一人当たりの成長率を高めることである」と言い、具体的改革案を提示する。
「90年代以降、日本の生産性はなぜ低下したか――人手不足経済が成長の土台となる。OECDやアトキンソン氏が"日本の労働生産性は国際的に見て極めて低い"などといっているのは、労働生産性の分子の実質GDPは総供給と総需要で決まり、景気の変動でコロコロ変わることを認識していない。景気という鏡に映った数字上の労働生産性は景気の良し悪しによる実質GDPを比較しているにすぎない。真の労働生産性に最も影響する要因は技術進歩であり、全要素生産性(TFP)だ。アトキンソン氏が経営者を"無能"呼ばわりするのは過ちで、デフレでもたらされた最悪の経済環境こそ直すべきだ。日本のデフレは人口減少や高齢化の上昇によってでなく、日銀の金融引き締めによるマネーストック増加率の急低下である」・・・・・・。デフレ基調を変え、人手不足経済にならないと、「GDPは資本、生産性、労働力」といっても働かない。デフレ脱却政策を進めつつ、ミクロ政策による生産性向上策をとるということだ。
そして「一人当たりの生産性、GDPを引き上げるには、公正な競争政策を導入し、女性の労働参加率を引き上げる」「日本の所得再分配政策は、社会保障による高齢者への再分配に偏っており、税による所得再分配が弱い。資本所得課税に累進性を」「正規、非正規の区別をなくし、労働市場の流動化を」「職業訓練制度や就業支援制度を取り入れた積極的労働市場政策に転換を」「所得再分配政策を中小企業や農業などの特定の集団を保護するのではなく個人単位の所得再分配に」「切れ目のないセーフティネット整備のために、負の所得税方式の給付付き累進課税制度の導入を」「年金は修正賦課方式から積立方式に」などを提唱している。
デフレ脱却をめざし、アベノミクスを進め、金融政策とともに、財政政策。インフラのストック効果を強く進めた私として、この数年を改めて想起した。
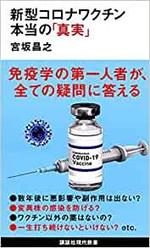 「2020年末に登場したファイザー製とモデルナ製のmRNAワクチンは、感染流行の反復という悪い流れを断ち切る、いわばゲームチェンジャーとなりつつある。ともに約95%という発症予防効果を持ち、重症化予防効果、感染予防効果という、いわゆる『三本の矢』が揃った、見事なワクチンだ。これによってワクチン接種で集団免疫を達成できる見込みが出てきた」「感染抑制は、①人流の抑制②ワクチン③治療薬の3つが大切だが、ワクチンと効率的に重症化や死亡を防ぐモノクローナル抗体という2つの『武器』を手に入れた。収束の方向に持っていける。不安材料は未知の変異株。その発生を防ぐためにも2回のワクチン接種を」という。免疫学者・宮坂昌之氏が、ワクチンに関する最新の知見を科学論文誌や研究機関のデータ、50年の臨床研究を踏まえて示し、本やメディアを通じての"嫌ワクチン"発言を切る。
「2020年末に登場したファイザー製とモデルナ製のmRNAワクチンは、感染流行の反復という悪い流れを断ち切る、いわばゲームチェンジャーとなりつつある。ともに約95%という発症予防効果を持ち、重症化予防効果、感染予防効果という、いわゆる『三本の矢』が揃った、見事なワクチンだ。これによってワクチン接種で集団免疫を達成できる見込みが出てきた」「感染抑制は、①人流の抑制②ワクチン③治療薬の3つが大切だが、ワクチンと効率的に重症化や死亡を防ぐモノクローナル抗体という2つの『武器』を手に入れた。収束の方向に持っていける。不安材料は未知の変異株。その発生を防ぐためにも2回のワクチン接種を」という。免疫学者・宮坂昌之氏が、ワクチンに関する最新の知見を科学論文誌や研究機関のデータ、50年の臨床研究を踏まえて示し、本やメディアを通じての"嫌ワクチン"発言を切る。
「新型コロナワクチンは本当に効くのか、安全か」――「2つのワクチンは驚異的な有効率とスピード開発」「2回接種で、B細胞が作る中和抗体だけでなく、NK細胞、T細胞などが活性化され、変異株に対しても効果を発揮する」「副反応は感染ではない。自然免疫機能を強化したり、感染阻害の抗体をつくる免疫応答を誘導するため発生する。副反応と有害事象を区別せよ。副反応は深刻なものではない」「1回と2回が違う会社でも良いか――データがまだない。IgA抗体量、IgG抗体量、B細胞の数でも、組み合わせた方が良いという結果もある」・・・・・・。
「ワクチンの効く仕組み」――。「免疫機構は自然免疫と獲得免疫の二段構えで、順番に働く」「病原体には多数の『抗原』があり、私たちの免疫系は『抗体』を使って自己と非自己を区別する。目印(抗原)に対して作られるのが抗体」「ワクチン接種は自らの免疫系に『免疫記憶』を植え付ける。ワクチンでは、獲得免疫ばかりに焦点が当てられるが、免疫力は自然免疫と獲得免疫の総合力。だから変異株でワクチンが全く効かなくなることはない」。子どもは自然免疫が強く、ウイルス侵入に粘膜面で自然免疫が強く働く。インフルエンザは子どもの方がかかりやすいが、毎年流行するので大人の方がウイルスにさらされた回数(経験)が多く、獲得免疫ができているからかも知れない」「ワクチンは生ワクチン、不活化ワクチンがあるが、mRNAは遺伝情報を与え、ウイルスタンパク質を私たちの細胞に作り出す"新世代ワクチン"」「mRNAワクチンが免疫反応を起こす仕組み」「アストラゼネカ製ワクチンはウイルスベクターワクチン」「イスラエル、英国の今の感染はデルタ株によるもの」「感染放置による集団免疫獲得アプローチは惨憺たる結果(英国、スウェーデン)」・・・・・・。
「コロナの情報リテラシー」――。「マスクは有効。鼻出しは鼻からウイルスを吸い込んでしまう。不織布マスクは最も良い」「ファイザー製、モデルナ製は血中にIgG抗体(体内に侵入したウイルスの排除)とIgA抗体(粘膜表面に分布して、粘膜の局所でのウイルスの防御)の両方が増加する」「コロナコメンテーターには悲観的、負の側面強調、間違い、査読前論文の使用、恣意的解釈など、理解に誤りがある。嫌ワクチン本に注意」「行動制限がなくなるのは2023年以降?」「ゼロから始まった治療薬の開発」「変異株の中には抗体が効きにくい株が出てきているが、複数の抗体をカクテル化していることが功を奏している(ウイルス感染を中和できる)」・・・・・・。

